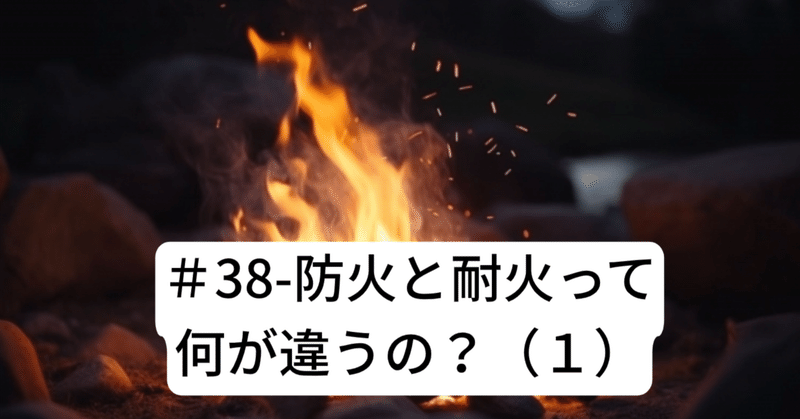
#38-防火と耐火って何が違うの?(1)
建築基準法には防火性能と耐火性能が区別されています。
皆さんも覚えるのが大変ですよ。
まずは、防火と耐火の違いをしっかりと理解しましょう。
防火と耐火の違い
「防火」は延焼から自分の家を守ることです。
防火は周りの火から守る能力のことです。
燃え移るのを防ぐことです。
これに対して「耐火」は自分の家が燃えた時に避難するまでに家が燃え崩れないようにすることです。
耐火は火災による家の倒壊を守る能力のことで、家の燃えにくさになります。
さらに家は燃えにくければ、他の家に火を移す(延焼)ことも防ぐことになります。
と言っても火に強い、弱いとは材料なのでしょうか。
それとも構造的なことなのでしょうか。
そこで建物の構造を考えることにしましょう。
建物の主要構造と耐火の関係
建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義していますが、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されています。

建物の主要構造部分の6項目は建築基準法の基本です。
必ず覚えてください。
主要な構造と耐火構造、防火設備の関係は次のようになります。

6項目が耐火構造であれば良いことになります。
耐火構造って何?
耐火構造とは、主要構造となる壁・柱・床・梁(はり)・屋根・階段が不燃材料を使用した構造であることです。
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄骨造(S造)の両面を耐火被覆した構造、コンクリートブロック造などが主な構造方法となります。
最近では木材に加工を施すことで木造でも耐火構造の建物が認められています。
不燃物とは一定時間火炎の中でも燃えないこと、変形、破損をしない性能をもつ材料のことです。
不燃物にはそれぞれ耐火時間があり、建築基準法では建物の高さ毎に次のように定めてあります。

上記表を覚えるのは大変ですが、絵にすることで簡単に暗記ができます。

避難に必要な階段は30分、4階以下では1時間、5階以上は2時間、15階から2~3時間の耐火性能が求められ、その性能を主要構造にもつ建物のが耐火構造であり耐火建築物です。
高い階が脆いと下階に被害がでます。
そのため、高層階ほど高い耐火性のが求められます。
もう一度、復習ですが耐火は消火作業が完了するまで建物が倒壊することが目的です。
火による構造物の燃焼、破損が起きない不燃性能が求められます。
準耐火構造は何?
耐火構造ほどの不燃性はなく、「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」とされています。
低層で延床面性が小さな建物などで採用されます。
耐火構造との性能差は、4階以下で比較すると判ります。
準耐火は最長1時間、火災で崩壊、ほかに火災が広がらないことが求められ、具体的には間仕切り壁、外壁、柱、床、梁は45分間、軒裏を除く屋根や階段は30分間の不燃性が求められます。
不燃物の性能を覚える
むずかしくはありません。
次の表を覚えるだけです。

耐燃焼性能で覚えることは次の3つ。

次回は防火性能です。
耐火とはまったく違います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
