
さあ、新年度!4月からの保育の指導計画を作りましょう!
新クラスへの心構えと指導計画づくりはこの1冊で大丈夫!
新年度に向けて、書店にもたくさん「指導計画」の本が並んでいますね。4月から担当する新クラスの指導計画の準備は進んでいますか?
今日は、手軽に指導計画づくりに取り組める、おすすめの書籍、『保育の質が高まる!0歳児(~5歳児まであり)の指導計画 子ども理解と書き方のポイント』(阿部和子先生・山王堂惠偉子先生編著)のシリーズをご紹介します。





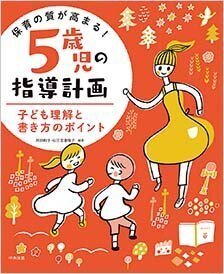
年齢に応じた子ども理解をふまえて
0歳児~5歳児まで、年齢ごとに1冊、書籍があります。そのため、各年齢での発達や生活の中での姿、その時期に大切にしたいことをしっかり押さえることができます。
各巻の章構成は共通しており、以下のようになっています。
第1章 保育において大切にしたいこと
…年齢・月齢ごとのよりよい生活、発達の姿、大切にしたいこと、保育の基本
第2章 指導計画
…年間指導計画、月案(4月~翌年3月まで毎月、季節や発達に応じた計画)
…0~2歳は個別の計画(前月の振り返り、高月齢・低月例別)
…3~5歳は月案、配慮が必要な子の保育、異年齢児とのかかわり、おたより
第3章 乳・幼児保育の基本と展開
…生涯発達におけるその時期の意義、保育の基本(保育所保育指針などをベースに)、保育内容の発展
4月から、初めて担当する年齢のクラスに当たっている保育者も、基本や知っておきたいことをしっかり踏まえてから、新年度を迎えられますね。
このシリーズの特徴
指導計画を書く・作るとなると、「何を書いたらいいの?」「文章を考えるのが大変」という方は多いと思いますが、本シリーズでは、まず「子どもの姿」をとらえることに取り組みます。すると、今の発達の状況、次へのステップ、かかわり方など、キャッチできる情報も増えていきます。そのことが保育のねらいや目標となり、指導計画の作成(書くこと)にもつながります。本シリーズは単純な文例集ではありませんので、ひと手間はかかりますが、本書を活用すれば一人ひとりの子どもの姿に立脚した指導計画づくりが自然とできるようになります。
そして、やみくもに保育のねらいや目標をたてるのではなく、保育所保育指針など、よりどころとなる考え方、望ましい保育の進め方について、年間を通して意識できるよう、大切な情報も3章にまとめられています。
3歳以上児の書籍の中には、配慮が必要な子どもの保育、毎月のおたより文例など、保育業務の中で避けて通れない部分についてもしっかりフォローしています。
月案のPDFダウンロードもできます
本シリーズをご購入いただくと、お買い上げいただいた年齢児の月案(12か月分)をPDFファイルでダウンロードすることができます。文章のまとめ方、表現の仕方などを参照しながら、オリジナルの計画づくりにお役立てください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
