元カノに逢いに行った
2010年9月12日
前回の「奈良の絵日記 東大寺」からの続きです。
大和西大寺駅から秋篠寺まで歩いた。
競輪場が周辺の雰囲気を壊しているけれど、これも仕方のないことなのか。
ため息が漏れる。

相変わらず人が多い。
折しも今日は日曜日。
人が途切れたところで、
やっと一枚撮った。
以前は車で来て楽だったが、駐車場は満車で、寺までの細道は大渋滞。
もっとも、駐車場のスペース自体が狭いから無理もない。
ここまでは徒歩で来るべし。

境内に入る。
どこもかしこも人、人、人。

スケッチはいい。
余計な哺乳類を排除して描いた。
話題は飛ぶが、立原正秋は、最初に影響を受けた作家。
初読は中二の時だった。
実家にいる頃、読む本がなかったので、何気なく手に取った。
母か叔母の蔵書だったのだろう。
読み始めると、それはいわゆる不倫小説だった。
それでも横須賀や鵠沼から始まり、鎌倉を終の棲家とした作家らしく、鎌倉や湘南を舞台にした作品を多く発表していた。
私は次第に立原にのめり込んで行った。
登場人物は、すべて類型的だが、独特の簡潔な文体がすっきりと心地よく、立て続けにすべての作品を読破した。
まだヴェルヌやドイル、たまにリルケやハイネの詩集などを読んでいた時期で、言葉には表現できない無意識のバランス感覚のようなものが働いたのだろう。
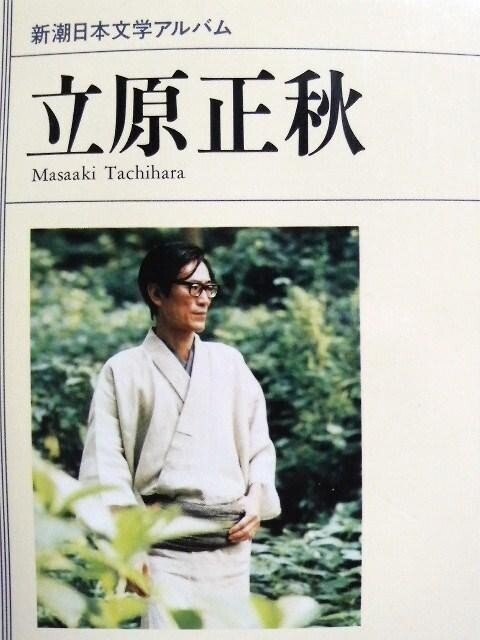
朝鮮半島出身でありながら、研ぎ澄まされた美的感覚は、日本人の美意識を凌駕するものだった。
金胤奎(キム・イュンキュウ)として大正十五年に生れ、昭和十二年、十一歳の時に渡日した。
昭和十五年には「創氏改名令」により金井正秋と名乗り、やがて結婚を機に日本国籍を得て帰化する。
昭和二十二年のことだった。
立原は臨済禅や世阿弥の風姿花伝などから深い影響を受け、その作品は次第に円熟味を増していく。
特に顕著なのがエッセイや評論で、「日本の庭」は今でもたびたび読み返す名著だと信じている。
寺の池で鯉を飼うのは生臭坊主だとか、銀閣寺の銀沙灘は坊主の醜悪な手慰みであると断じ、
「乱世にひたすら美を追うのは滅亡を視ていると同じことになる」
と、室町文化の儚さに想いを馳せている。
話が脱線した。
立原が秋篠寺を訪れた時の歌がある。
みゆきふる秋篠の里にそのかみも
なやみをいだきてこの道を行きし
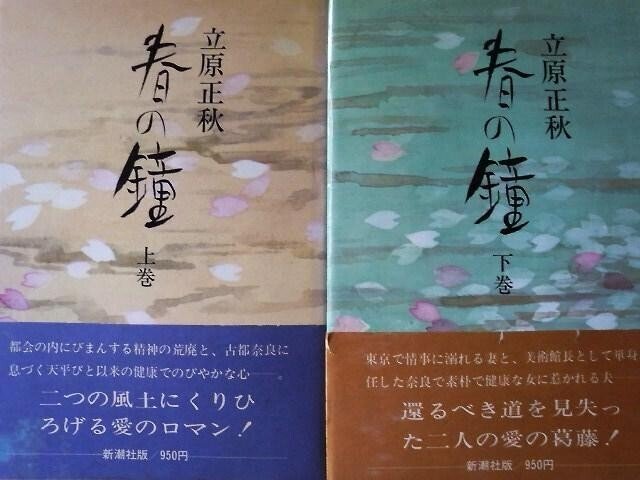
立原は1980年(昭和55年)8月12日、食道癌のため、国立がんセンターにて死去。
まだまだ創作意欲の衰えぬ、わずか54年の生涯だった。
ショックのあまり、数日、食事が喉を通らなかったことを覚えている。
「春の鐘」は、昭和五十二年に日本経済新聞に連載されたもの。
奈良を舞台にしたこの小説に、秋篠寺が登場する。
「ずいぶんやさしい御堂ですのね」
「それがわかればたいしたものだ。藤原時代の末に、ここは講堂だけを残して焼けてしまってね、その講堂を改築したのがこの金堂だ。優しいみどうに相応しく、堂内に、優しいみほとけさまがいらっしゃるよ」
金堂の西側に白い木蓮が咲いていた。金堂の入口はこの西側にあった。
堂内はうす暗かった。前面の戸はあかりをいれる程度にしか開いていない。薬師三尊と地蔵菩薩立像があり、伎芸天は西側の入口をはいってすぐのところにあった。
「まあ、美しいほとけさまだこと」
「色っぽいだろう」
「そうですわね」
「目もとが涼しい。色っぽいが、しかしよくみると、天平末期の幽愁を秘めている。若い頃、僕はこのほとけさまに恋をしたことがあった」
「まあ……」
「その頃、このほとけさまは僕より年上だった。ところがいまは僕よりはるかに若い。こちらがだんだんとしをとって行くにつれ、見えてくるものがあった。移ろわぬ美というやつだ。そんなときに実になにげなく歴史も見えてくるのだな。するとね、生あれば死がある、という実相も見えてくる」
< 立原正秋著 「春の鐘」 新潮社より抜粋 >
この作品は映画化された。
主演は北大路欣也と古手川祐子。
北大路の妻役の、三田佳子さんの妖艶な美しさが際立った作品だった。




立原の長女で、エッセイストの立原幹さんが「春の鐘によせて」と、パンフレットに寄稿している。
家から山をひとつ越えた所にあるお寺から、明け方、梵鐘の音が聴こえてくる。
それは、季節やその日の天気によって、様々に聴こえる。それは聴く者のその時の心持ちによっても、変わって聴こえるのだった。朝のまだ覚めきらぬ頭に響く鐘の音で、逆にその時の心持ちをわからせてくれる時もある。
ことに、季節の色がついて聴こえてくるようだった。
今回映画にしていただいた父の「春の鐘」は、日本経済新聞に、十ヶ月間にわたり連載した新聞小説でした。
新聞小説は、書き始める前に、すでに題名が決まっていなくてはならず、父にとり、いつも大変なことのひとつだったと思う。
この「春の鐘」も、父の他の新聞小説と同じように、ずいぶんと迷ってつけた題名で、最初は、「朝の鐘」とするように父は考えていたようだった。「朝の鐘」では、健康小説のようで、父の小説には似合わないと私が口にすると、父は、他のいくつかの題のなかから、「春の鐘」を選んだ。
新聞の連載は四月からで、まさに「春の鐘」だった。山桜が咲く山や谷や谷間(たにあい)を通りぬけてくる鐘の音は、いくつもの衣をまとって響いてくる感じがした。
夜中に仕事をしていた父が、朝の梵鐘を聴いてから眠ることもあれば、鐘の音よりも、前に眠ることもあった。
父がいなくなった現在(いま)も、鐘の音は、毎朝聴こえてくる。
朝のよどみのない天空を伝わってくる鐘の音に、父が何を思い、仕事をしていたのかと、私の考えが及ばない分だけ想像するのも、今の私には、哀しくて楽しい。
鎌倉の山の上を終の棲家として建てた家だから、立原が聴いた鐘の音は、小説や映画の舞台、西の京ではなく、鎌倉のいくつかのお寺の梵鐘だった。
その鐘の音から想を得たのだろうし、愛蔵の「いびつな白磁」にヒロインの性格を重ね、また見立てながら幾つかの小説を書き、この「春の鐘」もそのようにして生れたのだろう。
ひとり、静かな酒を酌み、白磁と対峙しながら小説の構想を固めていく立原の後姿が見えるようだ。

東南隅から描く。
ホモサピエンスは抹殺。
女身仏に春剥落のつづきをり 細見綾子
俳人、細見綾子さん、昭和四十五年の句である。
この句への自註で、「見事な永遠なものの前での時間の流れを切実に感じた」と記している。
伎芸天は実にすばらしかった。外は春雪の舞い降る冷え冷えとした堂内でこの像を仰ぎ見たのだが、その立ち姿に脈うてるごときものを感じた。黒い乾漆がはげて下地の赫い色が出ている。遠いいつからか剥落しつづけ現在も今目の前にも剥落しつづけていることの生ま生ましさ、もろさ、生きた流転の時間、それ等はすべて新鮮そのものだった。
美の永遠を信じるに足る、的確な表現だと思う。
春の昼伎芸天女のくの字腰 藤井艸眉子
以前、一人で訪ねた時、「春の鐘」の文庫本を片手に、人の少ない境内を歩く、若い女性を見掛けたことがある。
顔や衣服などの記憶はまったくないが、あの女性なら共通の話題も多そうに思えて、かなり気になった存在だ。
あれは、ワンレン、ボディコンのお姉ちゃんが増殖し続けていた頃だった。
そんな風俗とはまったく別世界に棲む女性に見えた。
年を経て、今もどこかのお寺を巡っているのだろうか。
そして私の駄句。
秋晴れやかはらずおはす伎芸天
立原の作中人物同様に、実は、私も伎芸天に恋をしていた時期があった。
ふくよかなお姿は、かつてのまま。
私の元カノは、永遠に美しい。
歳を取らないのは仏様だけだ。
駅に戻る道すがら、人生の長さ短さを考えた。
會津八一の歌が浮かぶ。
あきしののみてらをいでてかへりみる
いこまがたけにひはおちむとす
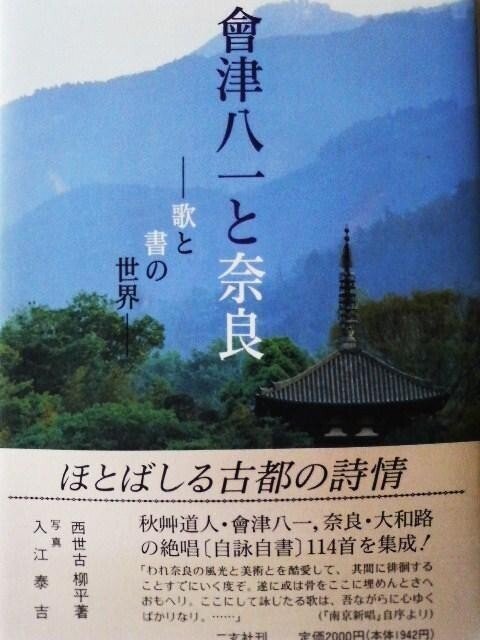
寺や仏像を詠まずに生駒山を詠んだのは、山家集の中にある西行の歌が頭にあったからだろう。
秋しのや外山の里や時雨るらむ
生駒のたけに雲のかかれる


続いて薬師寺へ行った。
少しめまいがする。
暑さは相変わらず。
素早く仕上げて終わりにした。
東塔は泣きそうなほど美しい。
唐招提寺へ向かうつもりだったが、近くの店で遅い昼食にした。
ところが体調がいまひとつすぐれない。
今年の残暑が恨めしい。
どうにかならぬものか。
秋暑しうらみつらみの箸を置く
白日夢また貧血か秋暑中
食事の大半を残し、唐招提寺をあきらめて、タクシーで宿に戻った。
再び伎芸天に逢えただけでも、大きな収穫だった。
夜になってもまだ、胸の鼓動が弾んでいる。
春 の 鐘
寂しい人よ
ぼくらのいのちは 蒼い冬の空に溶けて
いま 秋篠の風に 二人 身をゆだねている
千二百年の過去に届け
千二百年をさかのぼれ
みほとけの前にひざまずき 心の声を聴く
菩提樹の枝の下 天平びとの影がよぎる
寂しい人よ
陽だまりの小径を 長い影を見つめて歩いた
遠いあこがれの果ての 極楽浄土に近づく
千二百年の過去に届け
千二百年をさかのぼれ
めぐる季節に背を向けて 息をひそめている
如月の空の下 現身のはかなさを知る
寂しい人よ
この旅の終わりに 春の鐘はいまだ響かず
忘れられたいにしえの光に 手を合わせている
続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
