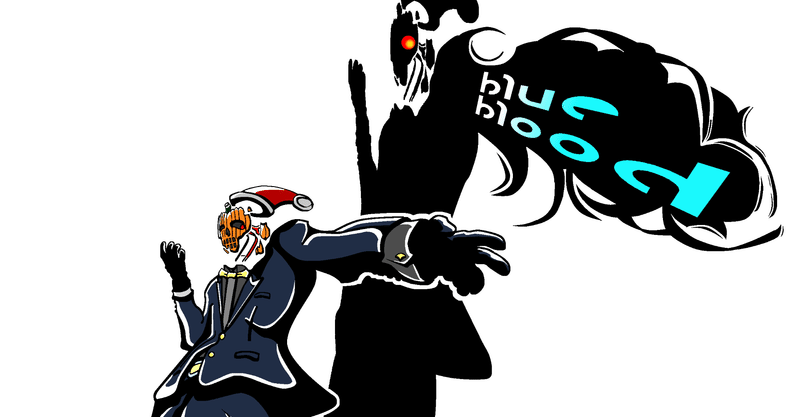
【二次創作 C97】blueblood sensation sanctuary
概要
※昨年のコミックマーケット97にて寄稿させていただいたショートショートです。原作者から許可を頂いたため、note化いたします。
ちょっと加筆修正してます。
有料記事ですがあくまで投げ銭用のため全文無料(なってなかったらミスですTwitterに連絡ください)
原作↓
参加告知記事↓
あとがき、解説はこちら↓
本文
「sensation sanctuary」
この仕事は、引き受けるのではなかった。いや、いつかこんな目に遇うのなら、はじめから運び屋など──
いや違う。はじめって、何時だよ───
*
悪ガキの俺が、怖いもの見たさや成り行きでこの仕事を始め、ワルの世界に足を踏み入れたつもりになって■年。今日も俺が『支店長』と呼ばされている上司のオッサンと、いつもの地味な現場仕事だった。本当である。こんな郊外の廃ビルなんかで取引先と待ち合わせ、とっとと鞄を渡して帰るだけ。後日捨て口座から現金で報酬を受け取る。
よくわからない。怪しいとしか言いようのない内容。こんな話を見聞きしただけで、誰だって裏社会の使い捨てがやる仕事だとわかる。しかしながら、流石裏バイト。内容のわりに高給であること、競争率に対して穴場でもあり、この職にありつける人が少ないことを、支店長がぼやいていた。それを聞くなり、俺は「勝った」と思った。
安泰だ。たったこれだけで今月も遊び放題、それに、俺たちが運んでいるものを知れば、仲間達も俺を一目置くに違いない。ワルとしてのメンツも保たれるというもの。“上”なんて得体の知れないものを目指すつもりもない。ここでいい。闇の世界の端っこで、細々とやっていけばいい。それが願いだった。
誰に言っても信じてもらえないだろう。今日の取引相手は、およそ人間と呼べるものではなかった。姿だけではない。その感覚、価値観すら、遠く及ばないものに違いなく、俺が一生をかけたとしても、奴を理解することなど到底できない───
高そうな外車に乗り、高そうなスーツを着た体格のいい男。フロントガラス越しに見た時は、ただの仮面でも被っているのかと思った。顔を隠した相手とのやりとりに立ち会ったことは何度かあるが、そうではない。ちらと見えた横顔は、ない…頭を構成するパーツが何一つ。
本来人の顔があるはずの位置に、仮面のようなものがポカンと浮いて見える。つまりソイツの頭部そのものが仮面とも言うべきだった。
ハロウィンのカボチャを髑髏の形に切り出した、ふざけたデサイン。つけっ放しになったハザードランプがそれを照らし、規則正しいリズムでやわらかな光を返す。
まさかそうではあるまいな、と思うことに限って、そうなのだ──
不安を覚えつつある俺の背中を支店長がポンと叩き、耳打ちする。
「舐められるのが一番マズイ」
普段のやさぐれた様子とは違う。彼も最大限警戒しているのだ。交渉の場。待ち伏せ、略奪。戦闘もあり得る。もちろん相手がつまらない真似をしようものなら、こちらも制圧できるだけの装備は持っているし、行使するつもりである。これまでもそんなことは幾度かあった。
しかしそれも、相手が常識は通じずとも、姿形だけは常識的な生き物の場合。
──人間なのか?
初仕事の時を思い出す…未知に対する恐怖。その発信源が、じりじりと歩み寄ってくる…ズボンのベルトに差してある拳銃に意識を向ける。
「やあ、脅かしてすまない。クリスマスの準備で忙しくてね。今回は助力に感謝するよ」
人気のない深夜の立体駐車場でコンクリートの床を鳴らさずに歩いてきた仮面男は、そんな不気味さはさておきといった趣で、気さくにそう発した。
ほらと頭に手をかざすと、手品のようにサンタクロースの帽子が現れ、それを頭に浮かばせた。俺は呆気に取られて、両手に持った鞄を危うく爪先に落としそうになる。
───得体が知れなさすぎる。なんなのだコイツは…一見友好的だが、真意はまだわからない。
俺が荷物の入った重いアタッシュケースを相手の前にふたつ置くなり、一瞥もくれず、音もなく消す。
いや、消えたのだ。そんなことは俺たちにできるはずがない。ならば、目前の相手のせいとしか説明がつかない。
「確かに受け取った、ご苦労様」
──コイツは、自分が非常識なものであることを疑問に思っていないのだろうか?いくら本人が気にせずとも、周りは決してそうではないのに。
コイツの価値観なるものが、少し気になってきた。
すっかり相手に調子を狂わされてしまった俺は、つい好奇心で「なあ、あんた、視界とかどう見えてるんだ…?音とかさ」
と、口を利いてみた。無論仕事柄、詮索は歓迎されない。支店長は俺に注意するも、当の仮面男は子どもに答えづらい質問をされた大人のように少しだけ唸る。その仕草は、どこか人間臭く感じた。
やがて仮面のある方向から声が届く。「どうと言うとそうだな…とても鮮明だが、しかしどこか妙な夢を見ているようでもある。君たちもそういうことはないか?」
それは詩的で、この場においてはナンセンスな回答だと感じる一方、嫌に心当たりがあった。
ここ最近、記憶や景色に違和感を覚えていたのだ。古い廃墟が点在しているこの地区が栄えていた記憶。知らない人と面識があること、知っていた人が自分を知らないこと。おおよそ人ではない目前の男へ順応できる自分…疑わしい物事が増えた──そもそも、いつから俺は運び屋なんだっけ?どうしてこんなことを───?
「それと、君達の名誉のため訊いておくが」
不気味なカボチャ仮面が防犯カメラのようにグルリと支店長のほうを向くと、目の前で仮面の裏側までがはっきりと見えた。首の中から枝分かれにゆらゆらと伸びる、薄気味悪い黒煙のようなもの。それが顔の位置にある仮面に橋を渡し、首の上では大きな渦がギロリと浮かんでいた。ブラックホールに星が吸い込まれていくイメージで輝くそれと、「目が合った」ような気がした。
「君たちをつけている“自警団(ビジル)”のことは気付いているのかな?」そんな言葉が思考を遮り、我に返った。
つけられている─!?
『全員そこで止まれ!』
柱の影から怒号を発して現れる者。駐車場の白線の上に突如姿を見せる者。天井を突き破って落ちてくる者。俺達三人(?)はいつのまにか、数人の男女に囲まれていた。
──なんだ、こいつら。“ビジル”ってなんだよ──!?
「君たちでは逃れられまいよ」
顔色の伺えない仮面が、360度を水平に回りながら、当然のようにそう放つ。
「ふむ…遅かれ早かれ全員“うちに来る”のだろうし、彼らの手柄にするのも面白くない…」
しかし、意味の解らない言葉の意味に紛れた、心なしか楽しそうに感じる声色だけが辛うじて、俺に危険だということを知らせた。
「“調整者(レギュレイター)”か!?まずい、伏せろ!」
支店長が俺の頭を近くの柱に押さえつけ、懐から手榴弾のようなものを取り出して、その場で炸裂させる。
途端、体感時間が急激に遅くなり、身体を猛烈な倦怠感が襲う。あたりを見渡すと、現れた者たちも頭を抱えたり、鼻血を垂らしたりしている。
…目の前の仮面男に至っては、その場にべちゃりと倒れ、体をブルブルと震わせる。
頭の中をミキサーでかき回されるような最低最悪な不快感。俺は思わずその場で嘔吐し、意識を失う。
なぜ咄嗟に対応をしてみせた?この人は何か知っているのか──?
俺を守る体制で倒れ込んだ支店長の感覚。その重みが、ある時を境に無くなった。それが最後の感覚だった。
鐘の中に閉じ込められて轟音を聴かされるような、毒沼を飲み干したような感覚。
どれくらい経ったのだろう。意識が混濁していた。気がつくと俺の身体はコンクリートの柱を背もたれにして伸びていた。
視界にあるのは抉れた床と、背後から隣へ倒れ込む剥き出しの鉄筋コンクリート、散らかる人のパーツ、男の車の窓に突き刺さった人の骨。ハザードランプがチカチカと照らす真っ赤な柱…
地獄の有様。そうとしか表現できない。唯一残った、最も人の形にわずか近いものが、仮面の顎のあたりをさすり、それを傾げながら近づいてくる。片方の腕や脚は人のモノではなくなっており、頭部に在ったものと似た黒煙のようなもので触手構成し、そのままグズグズとムカデのように這いながら、不細工に、不恰好に。
「調整者同士の争いに巻き込まれるとは気の毒に。君たち“一般人格存在(オルドナ)”も上層から都合よく扱われているのだろう…」
「彼の“特殊素子塊榴弾(クラッカー)”の効果…なかなかだった。君たちにもいざという時、ああいった手段が講じられているのだね…侮れない」
「しかし、そのお陰で君に“カーネルパニック”の症状があるとは予想外だ。常人が感知できないレベルの情報圧力に適性があるほど効果的なはずだ。君はいい調整者になれたかもしれない」
「ああ、ペラペラとすまない。懐かしくてね、君たちとの交流が…“悪戯”が過ぎたと反省している……」
水の中で聴いた音のように、何を言っているのか、はっきりとは聴こえなかった。
腰も曲げず、俺の前でフォークリフトを下ろすように姿勢をヌルリと下げた仮面男は、俺の足元にあるひしゃげたアタッシュケースを触手で拾い、隙間からそれを這わせてこじ開ける。
パンパンに膨らんだビニールの袋から、ボロボロとこぼれてくる派手な色の洋菓子。そこそこの数を運んできたが、中身を見るのは今回が初めてだった。
「君達が運ばされているこれは、劣化コピーを重ねられた贋作のようだ」
「これは人という個体の構成情報を強制的に書き換える力を持っている。『ベルナールの遺産』とは大層な名前だ。解析をすれば使い道があると踏んだが、これでは大した使い道もない…そうだ…!君にあげよう。大分早いが、一足先にプレゼントだ」
熊を象ったひときわファンシーな個体が取り出され、俺の喉に押し込まれる。
「さあ、もう行こうか。しばし、おやすみ」仮面男がそう言った気がした。
床があったはずの足元は瞬く間に暗闇とすり替えられ、吸い込まれてゆく。果てしない虚空に自分の存在だけが放り込まれ、その中を落ちているのか、流されているのかも、わからなくなるほど感覚が霞んでゆく。
──足元といっても、もう俺には足が無いのが、先ほど見えたばかりなのだが。
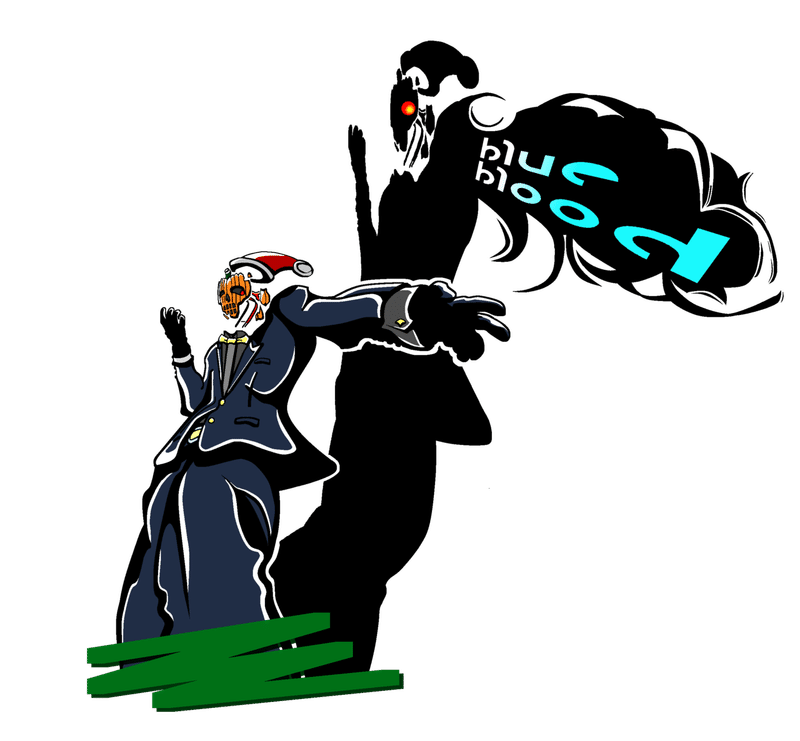
*
自分の姿を、少し遠くから眺めているような気がする。悪い癖だ。自分を動かしているのは俺自身なのに、どこか諦めたもう一人の自分がその景色を冷たく俯瞰している。自分がこの世界の住人ではないとか、全てがマヤカシならいいとか、そう思っている。ほどけそうになる意識が凧のように背後へ細長く伸びていくイメージ。必死に少しずつ巻き取るよう己に言い聞かせようとするも、糸は切れ、それは外に取り残されていった。徐々に五感は失われ、残された脳内の情報に向き合うくらいしか、出来ることがなかった。
仮面男の話す内容には意味の解らない言葉がたくさんあったが、ひとつだけ聞き覚えのあるものがあった。
ベルナール。裏社会では知らぬ者は居ない、麻薬王の名。 俺達が運んだ薬は、界隈ではハッピーなんたらとの渾名で呼ばれていた。麻薬王の最高傑作のうちひとつと謳われる人気が高いものだと聞いていたが──よもや贋作だとは。
そんな大物を運んでいるわけで、騙し討ちに遭い、1度だけ戦闘と呼べるものを経験したことがあった。日の当たる場所での仕事ではお目にかかれないはずの銃だって見たし、見様見真似で使った。初めて人を撃ち殺した時、ようやく『あちら側の人間になれた』高揚感があったというのが正直な感想だ。それ以来支店長に覚悟を買われ、今日まであの拳銃をベルトに挟み仕事をしてきた。しかし、あれが如何にたまたま運が良かっただけであったか。
今日会った奴らは超能力としか言いようのない行動。そもそも人間ですらない存在。そしてこんな下っ端で働いている支店長ですら対抗策らしき選択肢を持っていたこと。俺に内緒で、俺のようなガキがこれっぽっちも知らない向こうの世界から守っていてくれたかもしれないこと。悔しさとやるせなさで頭が潰れそうだった。
俺はすっかり浸かったつもりでいた闇の、ほんの波打ち際で遊んでいただけだったのだろう。その先がどんな景色をしているのか。彼らの感覚、価値観すら、遠く及ばないものに違いなく、俺が一生をかけたとしても、奴等を理解することなど到底できない───
他の誰にも感知できない自分だけの懺悔の世界で、ときどき薬の症状と思われるでたらめな快感がたびたび身体を襲った。
潤う肉の中に全身を閉じ込められるような、あらゆる嬌声を飲み干したような感覚。快感の概念を注射されたよう─快感が直接インストールされたような気味の悪い絶頂。懺悔や後悔とそれが徐々に精神の領域を飲み込んでいき、「俺が終わる」まで交互に続いた。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
