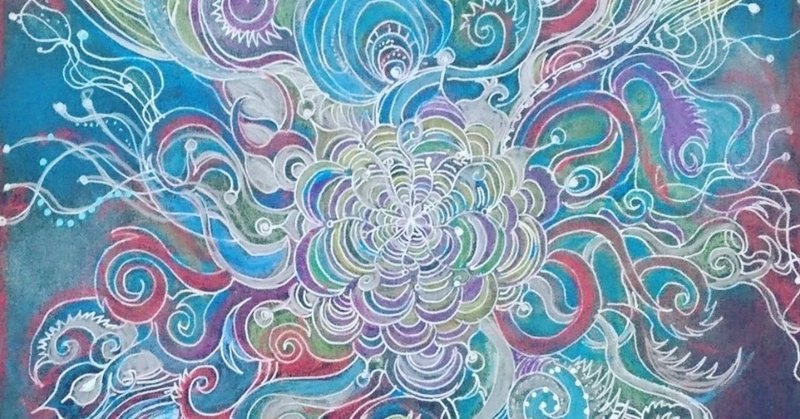
『色・いろ・イロな見方、感じ方、考え方〜性的マイノリティーの視点から〜』
西宮市若竹公民館では「人権を考える市民の集い」が毎年開催されています。今年は「性的マイノリティってなに?」という演題で弁護士の仲岡しゅんさんが登壇されました。
※【文章はあくまで筆者の受けた印象であり、実際の仲岡さんの話の内容とは違う場合があります。】

「最初に演題の訂正があります。〝正しく学ぶジェンダー、セクシャリティ〟とありますが、〝正しく〟は間違いです。何をもって正しいのか、そのハテナマークを共に考えていくことが今日のような集いの醍醐味だと私は思うからです。」
と初めに仲岡さんの言葉があった。
弁護士として日々、民事・刑事事件やLGBT、刑務所での性的少数者への処遇改善などに奔走している仲岡さんの口調はとても力強く、どんな小さな嘘も見透かされてしまうような鋭い眼光だ。その鋭さに加えて、美しい容姿と声、ユーモアたっぷりの大阪弁には噛みつかれそうな勢いがありながらも、一層親近感が増し、どんどん仲岡さんワールドに引き込まれていく。壇上で一歩足を前に出すたびに、腰まで伸びた長い髪が揺れ、いい香りが漂ってくる。
そんな仲岡さんワールドの前半は、性的マイノリティについての用語などの知識理解が主であったが、後半は仲岡さんの幼少の頃にさかのぼり、生きづらさを実体験を交えてお話して下さった。
中でも職業差別のリアルなお話に何度も胸が締め付けられる思いがした。
大学生で自分の性について直視するきっかけともなった当事者の会。そこで出会った友人から「トランスしたらどう?」と提案された瞬間、必死で開かないように鍵をかけて守ってきた心の蓋が開いてしまったという。少しずつ自分の心に正直に生きてみようと、女性の姿になっていった。
就職活動の際、男性として履歴書を提出するたびに、雇用者が決まって口にする言葉が
「うちはいいのですがね、派遣先が何というかね。」
だった。
何度もアイデンティティを傷つけられ、激しく憤りながらも漸く就いた職が学童保育の指導員だった。
戸籍は男性だが、女性として働く仲岡さんの姿に同僚は最初は戸惑っていたが、数日ですぐに慣れていった。
子ども達の心はまっさらで何の先入観もない。
女性、男性という性別以前に仲岡先生という人格に信頼し、たっぷり甘え、真っ向から飛び込んでくる。子ども達にとって仲岡先生は紛れもなく仲岡先生だった。
仲岡さんが学童保育の指導員をやめられる3日前、自身のトランスについて子ども達に打ち明けたいと同僚に申し立てた。
「私たちはかまわないけれど、子どもから聞いた保護者がなんというか。それは言わないでおきましょう。」
胸が締め付けられる思いだった。
今までチームとなって子どもを育ててきたのだ。
認めている風に装い、大切なところを直視しない。ただひたむきに、自分の性に、自分のアイデンティティに向き合っているだけなのに、信じては裏切られ、虐げられる。
「では、〝トランス〟という言葉を使わずに子ども達に説明させてください。」
そう上司に申し立てをした次の日、
仲岡さんは子ども達に語りかけた。
「仲岡先生な、どうしてもみんなに知ってもらいたいことあるねん。」
子どもの顔を思い浮かべながら話す仲岡さんは弁護士というよりは、学童の先生の表情だった。
仲岡さん「性別ってみんな何やと思う?」
子ども達「男と女、、、やろ?」
仲岡さん「実はなぁ、それ以外にもあるねんで?」
子ども達「…。」
「わかったで!」
「子ども!」
「宇宙人!」
「中学生!」
仲岡さん「そうかぁ。それも、〝子ども〟も性別かぁ ^_^」
まだ生まれて6年7年しかたっていない低学年の子どもたちの柔軟な発想。何の固定観念も先入観もないからこそ、大好きな仲岡先生に質問をぶつける子ども達。仲岡さんはこう優しく答えた。
「世の中にはね、男の気持ちも女の気持ちももってる人たちがいるねん。その人たちをね、〝ちゅうせい〟っていうねん。」
子ども達は目をまあるくして驚いて、しばらく考えてから、そうなんや、とうなづいた。そして、子どもたちなりに一生懸命に知っている言葉で表現しようとしている。
「大切なのは〝性同一性障害〟とか〝トランスジェンダー〟とか難しい用語を覚えて唱えることではなく、子どものように感覚的に捉えること。心に湧いてきたハテナマークが一体何であるか、もてる言葉で一生懸命に表現することなんだと私は思うのです。」
性についての問題提起。
性は人生の根幹。
そのことを子ども達の中に点として残したかった。子ども達へ送る話はクライマックスを迎えた。
「ほうら、金色と銀色の折り紙はなぁ、めっちゃ枚数が少ないけど、みんないつも取り合いっこなるなぁ。大好きやんなぁ。それだけ貴重な色なんやなぁ。人も一緒でなぁ、数が少ないってことは、おかしいことじゃない。ヘンテコなんかじゃない。それだけ貴重ってことなんや。」
多様な性を色とりどりの折り紙に例えられた仲岡さんの眼差しは子ども達への愛で溢れていた。
「子ども達が大人になっていく過程で、どんな壁にぶちあたっても、〝人と違う。〟
と言われても、紛れもなく君は貴重な存在。
大切な存在なんだ。と語り続けたい。
そしてここにおられる教職員の方、お父さん、お母さん、子どもを育てる全ての方に、当事者の、特に思春期の子どもたちの自尊感情を、どうか守ってほしい。マイナスになったものをせめてゼロへ、そこから徐々にプラスへと私は上げていきたいのです。」
何度も何度も傷ついてきたからこそ、
同じ思いを抱えた子どもたちを守りたいと願う仲岡さんの想いが伝わってきた。筆者が最初に仲岡さんから感じた力強さの正体。
それは、「子どもらを守らなあかん!」という命がけの愛。
マイノリティから考える人の性と生。
どちらも感性なくしては見出せないもの。
感性が押しつぶされてしまっては
多様な見方、感じ方、考え方を培うことはできない。
やはりここまで書いて気づく。
多様な見方、感じ方、考え方を育み、感性を育てる図工美術が担う役割は大きいと。
今日新たな気づきを与えてくださった仲岡しゅんさんに心から感謝を込めて。
大人の図工塾管理人 米光智恵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
