
キリスト教の封印を解く
【宗教の封印】
どんな宗教であれ、ある宗教を信じている人といったら、その教団と同じ考えを持っていて、教団に従っている人だということになる。これまではそれが当たり前の普通のことだと思えていた。ところが、この間、宮島のエネルギーを解放したことと関係があるのか、あるいは地球全体で次元が変わっているからなのか、それがもう当たり前のこととは思えなくなっている。
昔のある賢い人が言ったことに感銘して、それに従って生きるというのは、ごく自然なことだと思う。でも、それが宗教というものになったとき、教団と教団に従う信者というヒエラルキーができあがる。信者は教団に奉仕したり寄進をしたりする義務があり、そしてそれによって宗教的に報いがあるということになっている。魂の救いというものを、教団が独占してしまって、その会員だけが利用できるようにし、会員になるためには、教団の定める通りのことを信じる義務があるというわけだ。
3年前に奇妙なパンデミックが始まってから、メディアによる大衆操作のことが表に出てきて、支配者たちが100年以上も前から人の心を操作する術を研究してきたということがわかってきた。そのためにイギリスのタビストック心理研究所などに投資してきて、人をまるで操り人形のようにしてしまう洗脳方法や、メディアや音楽、あらゆる娯楽を使って、視聴する不特定多数の人々に一定の同じ印象、同じメッセージを潜在意識に植えつける方法などを使っていたことがわかってきた。そうやって、大勢の人々が同時に同じように考え、同じように反応するようにしてしまうことができ、たとえそれが自分や家族を犠牲にするようなことであっても、自分から従うようにしてしまうことができるというのだ。
ところで、宗教はまさにそれと同じことを、100年以上も前からずっとやっていたようだ。魂の救いというものを、教団が上から与えることができるようなものにしてしまい、それを教団の教義や掟を守ることと引き換えにしている。それで、魂の救いを求める人々は、教団に依存することになり、自分で考えて結論を出すのをやめて、教団の解釈を信じて教団に従い、奉仕したり寄付したりすることになる。しかし、人間は何かに依存すればするほど、自分から自由を売り渡してしまうことになるわけなので、魂の救いからはますます離れていくことになる。
実に皮肉なことに、魂の救いは宗教や教団とは関係なく誰にでも得られるのだということを示したナザレのイエスの教えが、その後しばらくして、世界最大の宗教に仕立て上げられてしまったのだ。魂の救いを宗教から解放してしまったがゆえにイエスは憎まれて、処刑されることになったわけなのだけれど、その処刑の姿が教団のシンボルにさえされてしまった。
一体何だって、処刑の姿などが最高のシンボルになったのだろう? 教団は、イエスは自ら十字架にかかることによって世界を救ったのだと主張しているのだけれど、それはもちろんイエス本人が言ったことではない。それは、イエスのあとに出てきた十字架を信仰する人々の宗教だとも言える。それを信じるのもまた自由なのだけれど、しかし十字架の信仰を前面に出すことによって、イエスの自由と解放の教えが、自己犠牲的な愛の奉仕の宗教に変えられてしまったというのもまた事実だ。
ナザレのイエスの教えを信じる人たちは、ユダヤ教会やローマ帝国など既存の支配に組みさなかったので、最初は迫害された。ユダヤ教徒もローマ帝国も、イエスを信じる人たちを迫害して、反逆者として処刑した。それがあるときから、ローマ帝国はキリスト教に改宗して、この教えを支配に利用し始めるのだ。しかしそれは、教団の主である法王だけが神と繋がることができ、人々は教団に従うことによってのみ魂の救いを得られるという、ナザレのイエスの教えとは似ても似つかぬものだった。
ナザレのイエスの物語を書いた4つの福音書は、この教団が編纂して改ざんもしているのだけれど、それでもちゃんと読めば、イエスの教えがそれとは真逆のものであったことは、はっきりとわかる。
福音書は、政治支配に利用する目的で、ナザレのイエスを特別な人物として神格化しているので、実はアブラハムの末裔だったとか、母親が処女懐胎して生まれた子供なので神の子だとか、そういう神話的な要素がたくさん入れ込んである。ユダヤの預言によれば救世主はベツレヘムで生まれたはずだからというので、両親が住民登録のためにベツレヘムに行っていて、厩に宿を取ったときに生まれたのだという話が作られたりもした。
福音書は、イエスを見てきた人が書いた書ではなく、言い伝えを編集してまとめたものだ。言い伝えというものは、語り伝えられていくうちに、尾ひれがついていくことになっている。特別な人物だということを示すために、実は貴い血筋なのだとか、生まれたときから不思議なところがあったとか、そういう話がつけられていく。他の誰かの物語が混同されて伝えられたりもする。それで4つの福音書は、それぞれに別々な尾ひれがついた物語になっていて、一つが正しければ他は正しくないはずだというくらいに違っている。それなのに、教団では何故だかすべてが正しいものとして扱われている。
厩で生まれて飼い葉桶に寝かされたという有名なエピソードも、実は四つの福音書のうちのたった一つにしか書いてないということは、意外と知られていない。もう一つの福音書では、ベツレヘムではあるけれど、生まれたのは厩ではなく普通の家だ。そしてあとの二つでは、生誕物語についてはまったく書かれていなくて、ヨハネのところで洗礼を受けた話から始まっている。そのことからして、生誕にまつわるさまざまな神話的エピソードは、語り伝えられていくうちにつけられていった尾ひれなのだろう。事実はおそらく、田舎の職人の家に生まれた息子で、ヨハネのところで洗礼を受けて啓示を受けるまでは、普通の人と特に変わるところがなかったのだと思う。
神さまとは、無条件で子供を愛し大事にする父親のようなものなのだということを、ナザレのイエスは繰り返し語っている。子供が何をしでかそうが、親にとっては子供が無事でいるかどうかだけが一番大事なことなので、何でもしてやるものだと言っている。誰にでも父親がいるように、誰にでもそういう神さまがついていて、無条件に愛し、すべてを与えようとしているのだと言っている。
イエスが「神を信じる」と言っているのは、まさしくこのような存在としての神がいるのだということを信頼して生きることを言っている。そして、こうした信仰が、パン種を入れたパン生地のように、あるいは辛子の種のように、自ずと何倍にも膨れていくのだと言っているのだ。
イエスはそれを示すために、障害を持つ人たちを目の前で治してみせたりもしたし、弟子たちを杖一本だけ持たせて旅に出したりもした。わずかなパンを大勢の人に分けて増やしたりもした。世界にはそれほどの大きな可能性があり、そのすべてを私たちの神は与えてくれているのだということを示すためにだ。そのことを彼は「福音」(幸福のメッセージ)といい、それを伝えるようにと言っていたのだ。そして、それが誰にでもできるのだということを示すために、弟子たちに人を癒すやり方も教えて、やらせたりもしていた。このこともまた、どの福音書にも書いてあるのにもかかわらず、知らない人が多い。いや、知ってはいても、意識が向かないようになっているのかもしれない。教会では、イエスだけが神の子で特別だから、奇蹟を起こすことができたのだと強調しているからだ。
イエスだけが神の子だというのも、明らかに矛盾している話なのだけれど、これも教会の中では誰も疑わないことになっている。教会の人たちは、神に祈るときに「天にまします我らが父よ」と言っている。我らが父なのだったら、私たちは誰もが神の子だということになる。イエスはまた、「私の父」「私を地上に遣わした方」とも言っているけれど、それは彼だけが神の息子だということではなくて、一人一人に父なる存在である神がいるということを言っている。そうでなかったら、「私の父」とか「私たちの父」とか「あなたがたの父」とか言えるはずがない。だけど教会は、彼だけが神の子であったという風に言っていて、それを多くの人はそのまま信じている。
キリスト教会では、私たち人間が神をそのように身近な存在として考えること自体を、とんでもない冒涜だとしている。父親であるはずの神は、子供の行動をすべて監視して、容赦なく罰するような存在であるかのようなイメージを植えつけられている。まるで、すべてを犠牲にして神に奉仕しなければ、神の国に入れてもらえないかのように思わされている。そして、そこに十字架のイメージが重なるのだ。ナザレのイエスは自分の命を神のために犠牲にしたために、神の心にかなう者になれたのだと。神はそこまでの犠牲を要求しているのだというように。かくして教会は、イエスが伝えようとした「福音」とはまさに真逆なものを人に信じさせることに成功したわけだ。
福音書だけからしても、まるきり矛盾しているのだけれど、信仰している人たちは、その矛盾に気づかないようだ。意図的に情報操作されていると、明らかに筋が通っていないことでも、人は信じ込んでしまうことになる。矛盾していることに気づくのは、タブーなのだ。見ても意識を向けてはいけないことになっている。それで、その点を指摘すると、相手は一瞬目が大きくなり、それから思考停止するようにボーッとした空虚な顔になり、それから話を逸らそうとする。こういう反応と同じものを、私たちはこの3年間何度も見てきたから、それが何なのかはもうわかる。
初めてキリスト教を支配に利用したのは、ローマ帝国だ。そしてローマ帝国は、無条件に従って命を犠牲にする兵士たちを養成して、帝国支配に利用していた。キリスト教化以前には、ローマ帝国はローマの神々を信仰することを属州に強制していたのだ。そして、それを今度はキリスト教に変えた。十字軍では、神のためにといって多くの若い騎士たちが率先して命を犠牲にし、多くの「異教徒」たちを殺したのだ。愛の教えであるはずのキリスト教でも、信じる人に殺戮を行わせることができる。それは、ナザレのイエスの無条件の愛の教えを付け替えて、無条件の服従の教えにしてしまったからだ。
宮島のエネルギーを解放した頃から、何だかそうした構造が透けて見えるように見えてきてしまったようだ。支配構造というものは、中に取り込まれている間は意識に上ってこないけれど、意識がその構造から解放されると、見えてくるようになる。それが今、起こり始めているのかもしれない。2000年もの間、封じ込められ続けてきた、ナザレのイエスの解放の教えが、ついに本当に世界に解放されるときが来ているのかもしれない。
宗教にされているすべての教えは、もともとは解放の教えだったのだ。私たち人間に何がすべて可能なのかを示すものだった。それがすべて支配のための意識操作に使われてしまい、これまで封じ込められてきた。
本当にもう、神の力とかそういう超自然的な力にでも頼らなければ、どうにもなりそうにないというところまで、私たちは追い詰められているのだけれど、そんなことでもなければ、私たちはそこに意識を向けさえしなかったかもしれない。この支配構造を乗り越えていくために、何千年というこの封印がついに解けようとしているのだとしたら、今のこの状況にもまた意味があるということになる。
2022年11月18日

***
【受難の道を行かない方法】
2007年の頃、私はいろいろな存在と意識でコンタクトしていた。その半年前くらいに、私はとつぜん目に見えない存在の声を聞くという体験をしていた。そして、神さまと言われる存在だとか、大天使と言われる存在だとか、あるいは歴史上の人物とかが次々とやってきては、いろいろな会話をしていった。
それまでの私は、そういう世界はないものだと思っていた。だから、最初、神さまの声が聞こえたりしたときは、これは妄想なんじゃないかとずいぶん悩んだ。いや、本当は、悩んだのは、妄想かどうかということではなかった。妄想でないのは、はっきりとわかっていた。そうではなくて、他の人たちが妄想だと思うんじゃないかということだったと思う。同様のことを経験した人ならばわかると思うけれど、真実が見えてきたときには、たとえそれが世間の常識とはどれだけ違っていようが、それは妄想ではないということが、かなりはっきりとわかる。世間であれこれ言われている人に自分で会ってみたとか、あれこれ取り沙汰されている事件の現場に実際に行ってみたとかいうとき、なるほど現実はこうだなとわかるようなものだ。リアリティの度合いがぜんぜん違う。解像度が高い映像を見たときのようなもので、すべての部分が鮮明に見えて、全体としてどうなっていたのかがわかる。すべてに筋が通っているのを感じて、すっきりと晴れ渡るような感覚がある。だから、これは妄想ではなくて、真実なのだということは、かなりはっきりとわかる。
あれから15年以上が経って、意識の領域では、誰でもどんな存在とでもコンタクトできることが、まったく現実的なこととして、わかるようになった。こうしたことは、実のところ、特殊能力というようなものでさえない。2年前からは、オンラインセミナーで、いろいろな存在とコンタクトしたり、遠隔でいろいろな場所のエネルギーとアクセスしたりすることを教えてもいるけれど、そんなことは妄想だという思い込みさえ捨てることができれば、誰でも繋がることができることもわかった。受け取ったものをイメージ化したり言語化したりすることには、人によって得意不得意はあるけれど、アクセスすること自体は、やってみれば誰でもできるというようなことなのだ。
結局のところ、そうした意識の世界を封じ込めていたのは、私たちの中にある思い込みにすぎなかったのだ。そんな世界は存在していなくて、妄想にすぎないのだという思い込み。それが、まるでバリアのようになっていて、そこから出ていったら、まともな人ではなくなってしまうという恐れが湧いてくるようになっている。まさにその恐れが、封じ込めを作っている。
2007年の頃、私は新たに開かれた意識の世界の途方もない大きさ、多彩さに圧倒されながらも、好奇心に駆り立てられた冒険者のように、見知らぬ領域を次々と探索していた。探索していたというより、向こうから次々とやってきた。どこからともなく、ある存在が現れて、コンタクトすることになる。あの頃は、世間的な世界からどんどん引き離されてしまうという恐怖で、緊張でガチガチになりながらも、そのたびに現れてくる真実の世界に、私はすっかり魅了されていた。それは、描き割りのようなペラペラの世界を現実としてさんざん見せられたあとで、本物の生きた感触のある世界にやってきたようなものだった。それで私は、それまでの人生が何故あんなに渇いた味気のないものだったのかを、ようやく理解したのだ。それは、ものの物理的な表面しか見ないような、実に薄っぺらい現実認識で生きていたからだったのだということが。
あの頃のいろいろなコンタクトの中でも、最も強いタブー感があったのは、ナザレのイエスとのコンタクトだった。どうして彼と繋がることになったのかは、よくわからない。あるとき、向こうから私の意識の中に現れたのだ。あのとき私は、卵の形をした陶芸オブジェを作っていた。あの頃私はよく、何なのかもわからないままに、浮かんできたイメージの形から始めて、作品を作っていた。作っていくうちに、細かい部分が見えてきて、最終的には何だったのかがわかる。あれがつまりは、造形を通したチャネリングだったのだけれど、当時はそうと意識してやっていたわけではなかった。それはまるで、陶土の塊の中から、新しい命が生まれてくるかのようだった。そうやって、目に見えない存在たちは、目に見える姿を得るのだと思っていた。
あのとき、卵のような形のオブジェを作っていたときに、私はピーター・ガブリエルの「パッション」を聞いていた。あれは、ナザレのイエスの受難の物語を映画化した「最後の誘惑」のサウンドトラックで、確か南仏で知り合ったミシェルという名前のアーティストがコピーしてくれたものだった。曲が「成就 It’s accomplished」に変わったときに、身体の中を稲妻が走ったような感覚がした。そして、私が今作っているものが何だったのかがわかったと思った。「これはイエスの目だ」と私は思った。自分が作っている卵の形をしたものが、イエスの目だったのだと。
その日の夜、寝ているときに、部屋の中に彼の魂が来ていることに気がついた。意識のアクセスには、空間というものがあるわけではないのだけれど、あの頃の私はまだそういうことを知らなかったので、彼の魂が部屋の中にいると思ったのだ。ナザレのイエスとコンタクトしてしまったら、いよいよ精神疾患か狂信者の仲間になると思ったから、早く消えてくれますようにと私は祈っていた。しかし、彼は消えてはいかなかった。朝までずっと、そこにいるのがわかった。それは、とても澄んだ白く強い光で、わずかにピンクがかっているのが、人間的な温かみを感じさせた。彼は何を言うわけでもなく、それ以上近づいてくるわけでもなく、ずっと部屋の隅に居続けていた。
それで、一晩明けたところで、私は彼に話しかけてみることにした。私は彼が間違えて来ているんじゃないかと思っていたので、「あの、私はいわゆるキリスト者というものではないんですけれど、それをご存知でいらしたんですか?」と恐る恐る聞いてみた。すると、返答は即座に返ってきた。「だからさ。。。」そう言って彼は、人が土下座して崇めている様子を真似してみせた。それを見て、ああそういうことかと私は思った。キリスト者だと、平伏してしまうから、対等に話してもらえない、ということらしい。だから、対等に話ができる人のところに来ているというのだ。
それを見て、私はこの人は思ったほど堅苦しい人じゃないなと思った。どちらかというと、ふざけたお兄ちゃんという感じで、実に気さくな感じだった。もともと型破りな人だったから、ものにこだわらない人なのだろう。それに、この人は30歳代前半で地上を去っているから、若い人の感覚のままなのだ。リチャード・バックが「イリュージョン」という、ナザレのイエスの生まれ変わりのような若い救世主に出会うという小説を書いているけれど、あそこに出てくる男のような感じだと思った。あれはおそらく、リチャード・バックが実際にナザレのイエスとコンタクトした体験から来る話なのだろう。
あそこに出てくる救世主は、型破りな風来坊といった男だった。救世主として、人を癒やしたり、説教をしたりして、群衆に囲まれながら暮らしていたけれど、もともと自動車整備工だったので、あるときモーターオイルのにおいが懐かしくなり、救世主をやめることにした。それで、山の頂上で神さまと話して、救世主をやめさせてもらう。その後、旧式の小型飛行機に乗って、飛行機ジプシーとしてアメリカのあちこちを飛び回っているときに、リチャード・バックと知り合った、という話だ。あれは、ナザレのイエスがもし、オリーブ山で神さまに祈ったあとで、受難を逃れることができていたら、という話でもある。福音書では、イエスはオリーブ山の上で神さまに祈るのだけれど、受難を逃れることはできないとわかって、自ら引き渡されるような行動に出る。しかし、リチャード・バックの話では、救世主はもう群衆に追いかけられているのは嫌だから、元いた整備工場に戻して欲しいと神に祈るのだ。すると神は、あなたのことを思っているのだから、あなたの思う通りにしなさいと言う。そして、救世主は群衆のところに戻ると、「神さまはあなたたちに幸せになりなさい、と命じました。だからあなたたちも、もう私を頼りにしないで、自分で幸せになりなさい」と言って、去っていく。そのときには、彼は他の人と同じようになっていて、誰も止めようとはしなかった、という話になっている。
意識のコンタクトでは、本心を隠すということは一切できない。取り繕おうとしても、まったく無駄なのだ。意識と意識が開かれて繋がっているのだから、隠そうとしていることが相手に丸見えの状態になる。それまでのいろいろな存在とのコンタクトで、私はすでにそのことをよく知っていた。それで、ナザレのイエスに出会ったときに、一番気になっていたことを、まず言うことにした。そして私は、あまりに唐突だと思いながら、一番言いにくいことを言った。
「何で受難の道を行くようなことをしたの? あなたがそんなことをしたおかげで、世界は自己犠牲に取り憑かれてしまったじゃない」このときも、返答は即座に返ってきた。彼は何だか恥ずかしそうな顔をして、笑いながら言ったのだ。「若かったからね」
彼の返事は、とても短いけれど、その言葉は鮮烈な光のようなイメージとともにやってくる。それはまるで、稲妻の光のように私の意識の中に入ってくる。ピカッと光って、それと同時に、ああそういうことか!とすべてを理解するような感じでだ。それを言葉として解読するのは、それからまだ時間がかかるのだけれど、とにかく一瞬で受け取ってはいる。それは、雷に打たれて一気に目覚めたといったような、とても強烈な印象がある。
ナザレのイエスは、エルサレムに行ったら保守的な人たちを挑発するようなものなのだとわかっていたのに、どうしてもエルサレムに行こうとしたのだ。しかも、エルサレム大聖堂に勝手に入っていって説教したり、聖堂前でものを売っている商売人たちを追い払ったりした。彼は「若かった」のだ。
人間は保身で生きているわけではない。ときに、自分を犠牲にするような無謀さに身を任せる行動にも出る。そこにどんな意味があるのかは、世界全体の大きな時間の流れの中で、初めて意味がわかるようなこともある。あのときから2000年の間、宗教による支配と戦いの時代が続いてきた。そして、愛と解放の教えであったはずのナザレのイエスの教えは、自己犠牲の強制による支配へと利用されていく。その激しく対立する二つの軸を、あの受難は作り出してしまったのだ。時代が大きく転換しようとしている今、その本当の意味が、初めて見えてこようとしているのかもしれない。
「私は受難の道は行かないよ。あなたはあれでよかったのかもしれないけれど、私はそうじゃないんだから」これははっきり言っておかないとと思って、私はナザレのイエスに言った。するとまた、返答は即座に返ってきた。「君は受難の道を行っちゃいけないよ。僕は君が好きだからね」その言葉は、とても暖かいピンク色のまぶしい光のようだった。それで私はまた、ああそういうことだったのかと、そのまぶしい光に貫かれるように思ったのだ。
無条件の愛を学ぶには、神の無条件の愛を受け取ることを知らなければならない。それを知らないで、無条件の愛を生きようとしたら、それは無条件の愛ではなく、自己犠牲になる。自己犠牲から無条件の愛へといたるのは、私には長い道のりだった。まさしくそれこそは、この2000年の封印だったのだ。自己犠牲から、自分への無条件の愛にいたること。それは、他人に犠牲を強いるのをやめて、無条件に愛することでもある。15年経った今、そのことがようやく私の中で言葉になろうとしているようだ。
2023年10月26日

***
【十字架を背負えといったのは誰なのか?】
キリスト教を信じる人たちが、自己犠牲に取り憑かれてしまうのには、ナザレのイエスが「誰でも私に従おうとする者は、自分の十字架を背負ってついてきなさい」と言ったということがある。あるときから、イエスは昔の預言者が言っていたように、自分は見捨てられて処刑され、3日ののちに蘇るのだということを言うようになった。おそらく彼は、自分の運命を予見していたのだ。一番弟子のペトロが、イエスがそういうことを言い始めたのを見て、そんなことを言うべきではないとたしなめた。それでイエスは怒って、皆、自分の十字架を背負ってついてこいと言った、とマルコ書には書いてある。
その場のやり取りで、そんなことも実際に言ったのかもしれないけれど、どういうつもりで言ったのか、どうも腑に落ちないものがある。聖書の記述は、公会議で何度も書き換えられているから、どこでどう事実から離れているともかぎらない。そういうときには、私は本人にコンタクトして、直接聞いてみることにしている。これは、やってみるとわかると思うけれど、かなり筋の通ったメッセージが受け取れる。もちろん、それだけで事実を確定できるというようなものではないけれど、他の情報と突き合わせて、パズルがピタリとはまるような答えが出てきたりするのだ。
それで私は、ナザレのイエスにコンタクトして、十字架を背負ってついてこいと本当に言ったのかと聞いてみた。すると、「言ってない」という答えが、何度聞いても即座に返ってくる。そんなことはまったく論外だ、といった調子で、それ以上何の答えも返ってこない。それで私は質問を変えてみた。そうでないなら、何を伝えようとしたのか、と。彼自身が、磔刑にかけられる未来があることは知っていて、それは避けられないこともなかったのだろうけど、彼は積極的に避けようとはしていなかった。おそらくは、そこに何かしら絶対的な確信があったのだ。これが正しい道なのだと。しかし、彼の弟子たちがどうすべきなのかについては、彼はどう考えていたのか、だ。もし彼が、皆にそれぞれ自分の十字架を背負ってついてこいと本当に言ってないのだとしたら。
「十字架じゃないだろ?」と彼は言った。「十字架は背負うものじゃない」
彼が言おうとしたのは、どうも磔刑になるための十字架ではないようだ。それは、神と繋がる内なる軸のようなものだ。下から上へと並ぶチャクラの軸のようなもの。天と地を身体で結ぶ軸。それを内に持つということが、つまり神とともに生きるとか、神に従って生きる、というようなことになるようだ。背負うものではなく、内に持つもの。十字架をそのように考えたとき、まるきり違うエネルギーが流れ始めるのがわかる。背負ったら、身体の軸が前に倒れて、力がなくなる。しかし、内に持ったとき、体の軸が通って、内側から輝き始める。
ナザレのイエスは、これから世界に「艱難」が起こるということを言っていた。戦争なのか災害なのか、何なのかわからないけれど、とにかく大きな災害が起こるということをだ。そして、それに対処するためには、彼はただ「目覚めていろ」「神を信じていろ」ということを言っていた。その目覚めていること、神を信じていることこそは、つまりその内なる十字架を持つということなのだろう。自分軸をしっかり立てて、ブレないでいること、天と地とにしっかり繋がっていることだ。
チャクラを開くワークとかをやったことがある人ならわかると思うけれど、天と地としっかり繋がっているときは、自然に背筋が伸びて、頭から尾てい骨まで、すっと一本軸が通っているような感じになる。そして、背骨がしっくりと安定するので、筋肉の力が心地よく抜けて、身体が緩む。合気道なんかで、どんな攻撃もかわせる状態というのも、こういう風に力が抜けて、軸が通っているときだそうだ。だから、この状態になっていたら、実際、どんな災害が起きても、守られていくのだろうと思う。ナザレのイエスが言っていたのはそのことなので、十字架を背負えなんてナンセンスなことは言ってない、と言っているようだ。
ところが、キリスト教会を信じている人たちは、イエスがすべての人に自分の十字架を背負うことを要求したと思っているのだ。信仰のために自分を犠牲にしろと。それが多くの人々にとって、幸せになることに対する罪の意識になっていたり、虐待のような扱われ方をすることを受け入れなければいけないという強制になっていたりする。キリストの神は、人々に自己犠牲を求めている、というのだ。自己犠牲を進んで行う者だけが、神から認めてもらえるのだと。
これは、ナザレのイエスが言っている、神の無限の愛という教えと、まったく正反対のものだ。神は子供の幸せを何よりも思っている親のような存在で、子供がどんな放蕩者であろうと、それとはまったく関係なく、持っているものすべてを与えて、大事にしようとするものだと、イエスは言っている。それが、自己犠牲を進んでするような人でなければ、認められないなど、それは究極の条件づけだとさえ言える。不可能なことを条件にするのは、洗脳操作に使われるやり方だ。キリスト教会は、まさにそうしたロジックで、神のためだと言われれば、どんなことでもする人々を作り出してきたのだ。これは、神の教えではなくて、洗脳支配だ。全体主義とも言えるものだ。
イエスが処刑されたあとで、ローマの兵士だったパウロがローマ・カトリック教会の元になる組織を作って、十字架の奇蹟を中心とするキリスト教を作り上げたのだ。その後、ローマ帝国はキリスト教を国教にして、支配権力に利用していく。ローマ帝国は、ナザレのイエスの教えを、愛の教えではなく、自己犠牲を崇拝する教えに変えてしまったとも言える。それで実際、神の望みだと言えば、無条件に自分を犠牲にして従う集団を作り出してしまったわけだ。
ナザレのイエスは、彼が早々に磔刑になってしまったために、こんな事態になることを予測していたのだろうか? それでも、エルサレムへ行って、保守的な人たちを挑発し、磔刑になるような状況を引き寄せたのだろうか? 彼はこれが、2000年もかかるような大きなプロセスになることを知っていたのだろうか? そうしたことをイエスの魂に問いかけていると、ただ、あのまぶしいほどの強い光が見えるばかりだ。2000年もかかるような大きなプロセス、それを行うことが、地球の、宇宙の、大きな意志だったのかもしれない。それによって、ついに支配の世界を乗り越え、多極的な調和に移行するために。そのまぶしいほどの強い光の中にあるのは、言葉にならないような、概念さえも越えたような、宇宙的な大きさの意志だ。
ナザレのイエスは、「人の子は引き渡され、殺されるだろう」と言っているけれど、そこではどういう殺され方をするのかについては言っていない。それで、「十字架を背負ってついてこい」と言うのは、確かにどうもおかしいようだ。実際、それ以外のところでは、十字架で死ぬという話は出てこない。石でも投げられて死ぬような感じに聞こえる。だからあるいは、この「十字架を背負って」というのは、あとでつけ加えられた話なのかもしれない。パウロが十字架の奇蹟を中心にしたキリスト教を作り出したあとに、作られた話である可能性がある。
キリスト教がどうなっていったにしても、それはこの世界の人間の闇の深さを表しているのにすぎないのだろう。それだけ深い闇があるからこそ、ナザレのイエスの教えがそれほど真逆のものを抱えた、矛盾に満ちたものにもなったのだ。それはまるで、深い闇と強いまぶしい光とが一緒になったかのようだ。
そのすさまじいばかりの支配と戦いの時代を経験して、人類はついに、自分自身を信じること、自分自身を愛することを学ぶのかもしれない。誰かの言葉を信じるのではなくて、自分の内に軸をしっかりと立てて、自分で神と宇宙と繋がること。まさしくそれこそは、ナザレのイエスが、「目覚めていろ」「神を信じていろ」と言ったことなのだろう。外の何かを神だと思いこむのではなくて、自分の内に聞こえてくる神の声に従うことをだ。
2023年10月27日
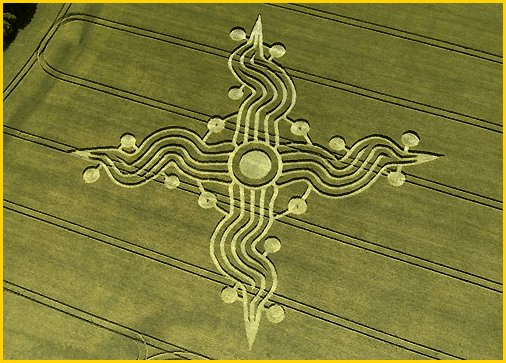
***
【人の子なのか、神の子なのか?】
ナザレのイエスは、神の子だから、普通の人間とは違って特別なのだという風に、キリスト教会では信じられているけれど、神の子だから特別だというのは、王族の支配権を正当化するために、昔から使われてきたやり方でもある。普通の人間とは違っていて、特別な血統だから、国を支配するべきで、人々はそれに無条件に従うべきだというような話は、昔から世界中で作られてきた。
ローマ・カトリック教会は、何が正統なのかを決める公会議で、イエスの人間性を否定していった。人間として表現している記述を、聖書からことごとく排除していき、彼を神の子であるとした。イエスは人間だったとする説は異端だとして、弾圧されさえした。そうやって、ナザレのイエスはキリスト教会の中で、神格化されていった。
ナザレの田舎の大工の息子では、キリストとして認められないというので、マタイ書には、実は父のヨセフがアブラハムの息子のダビデの末裔だとして、長い系図が書いてある。ここでは、婚約者のマリアが処女で神の聖霊が宿って、ベツレヘムでイエスを産んだということになっている。ルカ書では、やはりヨセフの婚約者マリアが処女懐胎したことになっているけれど、ダビデの血統だったので、ナザレからベツレヘムに人口登録のために出かけていて、そこでイエスが生まれたという話になっている。メシアはベツレヘムで生まれることになっているから、何とかしてベツレヘムで生まれたことにしようというので、作られた話のようだ。父親をわざわざダビデの血統にしておきながら、母親のマリアが処女懐胎したのなら、ダビデの血統を受けていないことになるわけだけれど、そこは突っ込んではいけないところなのだろう。
マルコ書とヨハネ書には、イエスの生誕については何も書いていなくて、イエスが洗礼者ヨハネのところに洗礼を受けに来たところから始まっている。おそらくは、これが事実なのだろう。イエスは、洗礼者ヨハネのところに現れるまでは、特別な人間だと思われてはいなかったのだ。彼が人を癒やしたり説教をしたりするようになって、群衆がついて回るようになっても、生まれ故郷のナザレの町に戻ってきたら、イエスの家族を知っている人たちは、彼を信用しなかったということが、マタイ書とマルコ書には書いてある。そこで、「預言者は、自分の郷里や自分の家以外では、どこでも敬われないことはない」という有名なセリフを言っている。つまり、生まれ故郷の町では、イエスは敬われなかったのだ。生まれにしても育ちにしても、特別なところがないと思われていたからだ。ただの田舎の大工の息子以外のものではないと思われていたからなのだと思う。
2007年に私が初めてナザレのイエスとコンタクトしたとき、彼が神の子だと言われているのは本当なのかと、神さまに尋ねてみたことがある。イエスにではなくて、神さまに聞いたのだ。彼は本当に神の子なのかと。すると、即座に答えが返ってきた。「え? 誰が神の子じゃないの?」と神さまは言ったのだ。驚いているようでもあったし、おかしがっているようでもあった。言葉だけだとわかりにくいけれど、神さまが何を言おうとしているのかは、すぐにわかった。もちろんイエスは神の子だ。だけど、神の子でない人間なんてどこにいるのか、と神さまは言ったのだ。
そのことに気づいたとき、私は、あっと思った。いくつもの概念がいっぺんに意識の中に入ってきた。キリスト教のお祈りでは、「天にまします我らが父よ」と神に語りかけている。我らが父、と言っているのだから、皆、神さまの子だということになる。それに、イエスはいろいろな場面で、神はあなたがたの父なのだということを言っている。
「でも、キリスト教の人たちは、イエスが神の子だからどうこうって、特別な人間みたいに言ってるけど? 彼が十字架にかかることが、神の望みだったとか」と私はさらに神さまに尋ねた。すると神さまは、何だかしみじみと懐かしそうな顔になって言った。「私は何も望んでいないよ。だけどあれは、なかなか独創的だった」
この頃では、神さまはハイヤーセルフと言って、自分自身の高次元意識に他ならないということを言っている。それは、普通に「自分の意識」だと思っている顕在意識の領域を超えて、宇宙意識とも一緒になっている意識なので、まるで自分から離れた上の方からやってくるメッセージのようにも思える。しかし、それは自分の外にある意識ではなくて、内なる意識だ。しかし、その次元の意識になると、地球全体の意識、宇宙全体の意識をも共有しているので、内なる意識という言葉で想像するような狭いものではない。テレパシー的なコミュニケーションやアカシックレコードへのアクセスなども可能になる意識の領域だ。
ナザレのイエスが、神はあなたがたの父のようなものだと言っているのは、一人ひとりがその意識に守られて、導かれているという意味なのだろう。親が、子供一人ひとりに必要なものをすべてそろえてやって、やりたいことができるようにしてやるように、私たちの高次元の意識は、必要なものがすべて整うように、ちゃんとはからってくれている。これは、波乱な人生を歩んできて、いろいろなシンクロを経験した人は、よく知っていると思う。何のあてもなくても、いつもちゃんとどこからともなく助けが現れて、思ってもみないようなところへ導かれていったりするものなのだ。それはまるで、宇宙のお父さんみたいな存在がちゃんと見ていて、助けてくれているように思える。
彼は、人を癒やす方法を弟子たちに伝授してから、杖だけ持たせて旅に出したりもした。人々のために働いていれば、生活に必要なものは、必ず与えられるはずだからと、お金も食糧も着替えの服も何も持たないで行かせたのだ。弟子たちは飢えもせず渇きもせず、いつも住むところも食べるものも十分に得られて、無事に帰ってきた。彼自身、行きあたりばったりで生きてきたから、必要なものが必ず現れるのを知っていたのだろうけれど、それが誰にでもできることを示そうとして、弟子たちをそんな旅に出したのだと思う。
ナザレのイエスは、どこかで古代ユダヤの神秘主義に触れて、そこでヒーリングの技などを覚えたのではないかとも言われている。イスラエルの失われた支族がその知を持って、世界中に散ったのではないかという説があり、ハワイのフナ(ホオポノポノ)と呼ばれるシャーマニズムは、古代ユダヤ神秘主義が根底にあるようだと、イギリスの言語学者のマックス・フリーダム・ロングは言っている。言語学的に見て、明らかに古代ユダヤの言語と関係があるというのだ。
フナでは、私たちの意識は、クー、ロノ、カネの3つに分かれていると言っている。クーは潜在意識や感情、ロノは顕在意識や理性、カネは宇宙意識や高次元意識、つまりハイヤーセルフのようなものとしての神の意識だ。そしてフナでは、この3つを統合させることにより、現実を望むように変えていくことを教えている。
ナザレのイエスが説いていた「無条件に愛する父のような神」は、まさしくこのカネのようなものだ。自分自身の意識だから、自分のことは親のようにすべて知り尽くしていて、理解しているし、それで、私たちが見えていない領域をちゃんと見ていて、必要なものが整うようにはからってくれている。彼はまさに、その「父なる神」の力を信じることで、不可能に思えるようなことも、可能にすることができるということを、人々に教えていたのだ。
まさにそれゆえに、ナザレのイエスはユダヤの宗教権威に憎まれたのだと思う。誰もが神と話して、その力を使うことができるということになれば、人々は宗教権威に従わなくなってしまうからだ。それで、ナザレのイエスが反乱を起こしてユダヤの王になろうとしていると言って、捕らえてしまった。
その後、ローマ帝国の国教となったキリスト教は、イエスを普通の人間とは違う特別なものとして権威づけるために、「神の子」だとしたのだ。そして、イエスの受難を神格化することによって、ケルトやゲルマンの土地で、キリスト教を強制して、支配していった。神が望むなら、自分から処刑されたりもするような人間だけが、天国にいけるというような話に書き換えて、内なる宇宙意識の力を封じ込めてしまったわけだ。
キリスト教会では、普通の人は神とコンタクトすることなどできないし、そんなことができると思うのは、神に対する冒涜だみたいに言われているらしい。ナザレのイエスと初めてコンタクトした頃、そのことをドイツ人のカトリックの友達に話したら、彼は青くなってブルブル震えながら、「こんなことを教会の人たちが聞いたら!」と言った。彼はスピリチュアルな人でもあったのだけれど、カトリックで育っているので、反射的にそういう反応になったようだ。
アーティスト仲間だった修道女の友達に、「あなたたちは神さまを信じているから、恐いものなんて何もないんでしょうね」と言ったときにも、やはり同じような反応が返ってきた。彼女もブルブル震え始めたのだ。私は、修道院に入るような人は、神さまが守っているということを本当に信じているのだと思っていたので、かなりびっくりした。「いえ、信仰を保つことは簡単なことではありません」と彼女はブルブル震えたまま言った。
サードアイが開いている感じのオーラを出しているプロテスタントの牧師さんに、「神さまと話す経験をした方なんでしょうね」と言ったときも、やはり同じだった。その牧師さんも同じ感じでブルブル震え出したのだ。私が思った通り、神とコンタクトする経験をして、牧師になったという人だったけれど、教会に入ると、神と話せると思うなんて、高慢だとか言われるらしい。神さまというのは、ずーっと遠い高いところにいるのだから、自分が話せるとかいうのは違う、と彼は困ったように言っていた。
ブルブル震え出すのは、タブーに触れたからなのだろう。キリスト教会は、まさに神の意識と繋がることを封じ込めるものになっていたのだ。ナザレのイエスが解放しようとした神の意識を。彼は、私たち人間が、実はどれだけの大きさを持っているのかということを伝えようとしたのに、キリスト教会は、人間を神の威光の下に押しつぶされているような小さな存在にしてしまったらしい。
さんざん書き換えられた福音書でも、読み取ろうと思えば、やはり真実のイエスの姿を読み取ることはできる。そして、そこから読み取れる彼の姿は、人間の持つかぎりない大きさと可能性とを示している。この2000年の歴史は、ナザレのイエスをめぐって、人間の可能性を解放しようとする力と、それを封じ込めようとする力とが、せめぎ合って、戦い続けていたのかもしれない。もしそれが、イエスが予言していた黙示録的な「艱難」であるとするならば、今、この戦いが解放で終わるときが、もう来ているような気がする。
2023年10月28日
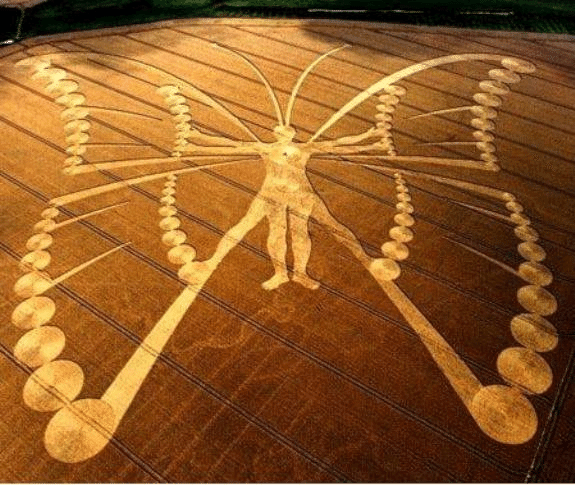
***
【神の次元と人の次元】
キリスト教がわかりにくいものになっているのには、ナザレのイエスの受難が難解にされているということがあると思う。キリスト教会の解釈では、ナザレのイエスは人類の罪をあがなうために自ら犠牲になったのだと言っている。いったい何の罪だというのだろう? いったいどうしてイエスが処刑されることで、その罪が赦されたことになるのだろう?
そもそもナザレのイエスが逮捕され、処刑されることになったのは、彼がユダヤ教会の嘘を暴いていたからだった。神とはどういうものなのか、祈りの力で何がすべてできるのか、ということを人々に示していたからだった。彼が悪霊祓いをして、普通治らないと言われている病気をその場で治してしまったりしたので、信心深い人たちがイエスを殺そうとした、とある。そして、イエスが悪魔の力を使って人を癒やしているとか、そういう噂を流されたりした。
そうしたことは彼だけではなく、誰もができるのだということを、彼は示していた。12人の弟子たちに、人を癒やす方法を伝授して、人々を癒やす旅に出したりした。レイキとか遠隔ヒーリングとかを習ったことがある人ならわかると思うけれど、実際、こうしたことは誰でもできる。もともとあった力を思い出すだけで、誰でもできるようになってしまうのだ。もちろん、上手い下手はある。だけど、誰でもできることはできる。
支配権力というものは、人々が自分の本当の力に気づくことを嫌う。彼らにとっては、人々が強くなり、自立してしまうのは、脅威なのだ。支配権を奪われるような気がする。権威に従わなくなってしまうんじゃないかと思う。だから、多くの人々の注目を集める人物が現れると、取り込もうとしたり、つぶそうとしたりする。イエスを取り囲む群衆が何千人というものになったとき、支配者たちは、イエスが反乱を起こしてユダヤの王になるつもりなのではないかと思って、警戒した。それに、イエスが率いる人々が、律法を守らないで自由にやっているので、ユダヤ教の権威は脅威を感じていた。
ものの本質を知っている人ほど、形式通りにやるのではなく、自由なやり方をする。形式などは、あるとき誰かがこれでうまくいくというやり方を決めただけなので、他のやり方でもできたりするし、それよりうまくいくやり方があったりもする。形式にこだわる人は、誰かが違うやり方をしていると、それは間違っていると批判するけれど、それはその人がものの本質をわかっていないからなのだ。イエスのまわりの人たちが、自由なやり方をやってうまくいっているのは、形式を守ることで権威を保っていた人たちに、脅威を感じさせたはずだ。
4年前に、奇妙なパンデミックが始まってから、政府のやり方に反対して真実を言う人々が、どんな弾圧のされ方をしているのかを見てきた。真実を暴露する人がどれだけ憎まれ、妨害されるものなのかを。悪魔だとか頭がおかしいとか、極右だとかナチだとか、あるいは左翼だとかテロリストだとか、筋が通っていようがいまいが、何でもかんでも言われた。それで、家宅捜索を受けたり逮捕されて拘留されたり、医師免許剥奪されたり、銀行口座を閉められたり、あるいは暗殺されたりもした。
ナザレのイエスはあの当時、支配者たちのそうした憎悪にさらされていたのだ。支配者たちは、何とかしてイエスを消してしまおうとしていた。だから、群衆を引き連れてエルサレムに出かけていったのは、敵の陣営に飛び込んでいくようなことでもあった。エルサレムの支配者たちは、イエスが反乱を起こして乗っ取ろうとしているのだと思ったし、イエスを迎えた人々は、イエスがエルサレムをローマ帝国の支配から解放してくれるのだと思った。弟子たちは、イエスが革命を起こして、新しい支配者になるのだと思っていたようだ。
しかしイエスは、エルサレムに行けば、教会権威の人々に見捨てられ、殺されるということを予知していた。それでも、わざわざエルサレムに出かけていこうとしたのだ。彼は捕まって殺されるだろうけれど、3日のうちに復活するからと言っていた。
そういうことを、彼が公に人々に言い始めたので、弟子のペトロは、そんなことを言うものではないとたしなめた、とマタイ書とマルコ書には書いてある。マタイ書では、「神はそんなことをさせないでしょう」と言ったとされている。それからイエスは、ペトロに向かって、「サタンよ、引き下がれ。あなたは神が望んでいることではなく、人が望んでいることを考えている」と言った。この言葉は、マタイとマルコにだけ書いてあって、他の二つの福音書には書いていない。
ところで、イエスにとって、神とはかぎりなく慈愛深い父親のようなものであり、すべてを知っていて、すべてが可能な力だ。だから、神が望んでいることというのは、そのかぎりない力を持った存在としての自分が望んでいることだということになる。つまり、宇宙意識としての自分の意志だ。
イエスが捕らえられて殺されたりしないようにと望むのは、人間的な次元の思考だ。イエスは、エルサレムに行って支配者たちを挑発するようなことをしないで、目立たないようにしていれば、殺されたりはしなかったかもしれない。しかしイエスは、たとえ殺されても、エルサレムに出かけていって、言うことを言い、やることをやるのを選んだわけだ。それは、神の次元での思考だ。
実際、命を狙われながらも、真実を言い続けている人たちはたくさんいる。そういう人たちにとっては、安全に生きるために、言わないでいるなんていうことは、あり得ない選択だ。真実と愛を捨てて、生きながらえても、そんな人生で幸福でいられるはずがない。嘘の人生を歩むくらいなら、どんな危険があろうと、真実に生きた方がいい。そこまで覚悟を決めて真実を報道し続けている人たちを、4年前からよく見るようになった。
パンデミック対策の嘘を暴いて、ロンドンのスピーカーズ・コーナーで逮捕されたドイツ人医師のハイコ・シェーニング博士。ドンバスの真実を報道し続けて、ウクライナ諜報部に命を狙われているジャーナリストたち。彼らは、真実に生きると覚悟を決めた結果、まるで王者のような輝かしいオーラを放っている。
たとえ命の危険にさらされても、真実に生きると肚をくくってしまった人は、神の次元の意識と人の次元の意識とが、一つに統合してしまうのだ。この意識の状態になっている人は、実際、まるで神がかっているかのように、不思議と守られたりする。いろいろと困難に遭いながらも、すべてうまくいくように導かれていったりもする。これは、波乱な人生を歩んできた人なら、経験して知っていると思う。肚をくくって危険に身をさらすような生き方を選ぶとき、神の次元が味方しているかのように、すべてが不思議な力で運んでいくようなことがある。
この状態を知っている人は、危険な状況が差し迫っているときに、人の次元で保身を考えたりすることの方が、実は危険だということを本能的に知っている。真実と愛に生きているとき、人は背筋を伸ばして堂々としていられる。その状態になれている人は、無敵なのだ。恐れて防御姿勢になったり、攻撃姿勢になったりすると、重心の軸がずれるから、倒されてしまう、と合気道では言っている。恐れず堂々として、背筋を伸ばしていると、重心が安定しているから、倒すことができない。それと同じで、覚悟を決めて堂々としている人を、攻撃することはできないのだ。攻撃した力は、すべて元のところへ跳ね返されていってしまう。
「自分の命を救おうと思う者はそれを失い、わたしのため、福音のために、自分の命を失う者は、それを救うだろう」と、イエスは言っている。エルサレムに行って、捕まって殺され、3日のうちに復活する、と言い、弟子たちに自分についてこいと言ったときにだ。イエスとともにエルサレムに行くということは、反逆者として一緒に逮捕される危険もあるということになる。そういうときに、命を救おうとすることの方が、危険なのだ。命を賭けてしまって、堂々としていた方がいい。そうすれば、神的な力によって守られていく。
ナザレのイエスは、人間には本当にはどれだけの力があるのか、どれだけ大きな存在なのかということを示すことで、人々を支配から解放しようとしたのだと思う。保身のために支配に従わなくても、神の意識とともに自由に生きていけることを、示そうとした。それでエルサレムに行って、禁止されていた塩作りをしに海へ行ったガンジーのように、勝手に聖堂に入って説教したりしていた。
彼を殺そうとする情念があまりに大きいので、大人しく殺されて、復活すればいいと、彼は思ったのかもしれない。柔道の受け身みたいにだ。抵抗するより、すんなり投げられた方が、身を守ることができる。実際、亡くなった人とコンタクトしてみたことがある人はわかると思うけれど、死んだ人は消えてなくなってしまうわけではない。霊的な意識体としては、逆に生きていた頃より存在感が強くなることさえある。それを知っている人にとっては、肉体を持っているかどうかは、あまり重要ではないのかもしれない。もちろん、肉体を持っているからこそできることもあるけれど、純粋な霊体になったときに、だからこそできることもまたある。
とにかくイエスは、磔刑に遭って葬られてから、マグダラのマリアと11人の弟子たちのところに、肉体的な存在として現れてから、天に行ったと伝えられている。あれから2000年経って、今でも彼の魂とコンタクトする人はたくさんいるけれど、そういう人はかなり鮮烈でパワフルなエネルギー体を感じている。それを考えると、あの衝撃的な死に方のおかげで、彼の魂はある意味、永遠に復活したと言えるような状態になったのかもしれない。つまり、そういう形で、彼は人間の解放のために働き続けているとも言えるわけだ。
だからこそ、この2000年は、イエスが解放したこの力を封じ込める力とのせめぎ合いが続いていたとも言える。キリスト教会は、まさにその封じ込めの中心となっていた。神の意識と繋がることを、特別なことにしてしまって、イエスの受難を人類の原罪をあがなうためだというような、わかりにくい話にしてしまった。それによって、イエスがいったい何のために迫害されたのかが、見えなくなってしまったわけだ。まさにキリスト教会が、イエスが戦っていた律法学者たちに入れ換わったようなものだった。
しかし、この4年ほどの流れを見ていると、この2000年のプロセスが、ついに完了するときが来ているように思える。イエスが解放しようとしていた力を、普通に使っている人たちが増えているし、実際、そんな力でも使わなければ乗り切っていけないような状況に、私たちは追い詰められている。こんな風に追い詰められているということは、その力を使ってみろということなのだ。それでこの4年ほど、いろいろな人たちがそのために動かされているようにも思える。
2023年10月29日


***
【敵は愛するものじゃない】
ナザレのイエスは、「汝の敵を愛せよ」と言ったとされている。本当にそんなことを言ったのだろうか? この言葉に私が反射的に疑問を持ったのは、この言葉を聞くと、身体の軸が歪む感覚がするからなのだ。特に胃のあたりがギュッと縮む感じになって、吐き気がしそうになる。イエスは、本物のヒーラーだったようだから、人のエネルギーが透けて見えていたはずだ。あれだけのヒーリングは、そうでなかったら、とてもできるものではない。その彼が、こんな身体に悪い影響のある言葉を言ったりしたのだろうか? 人のエネルギーが読める人ならば、その言葉を聞いた人々のオーラが、一気に力をなくすのがわかるのじゃないかと思う。
福音書は、ローマ帝国が国教にして、支配のためにさんざん改ざんしていたから、別な内容に書き換えられている可能性もある。まったくの作り話である可能性もある。こういうときは、4つの福音書を読み比べてみると、かなり見えてくるものがある。事実を確定するときに、複数の証人の証言が一致するかどうかを調べるようにだ。4つの福音書の間に相違がある場合は、どれかが虚偽である可能性がある。
それで調べてみると、汝の敵を愛せよと言ったということが書いてあるのは、マタイ書とルカ書だけだった。マルコ書には書いていない。4つの福音書の中で、一番現実に忠実だと思われるのは、一番古くに書かれたと言われるマルコ書だ。マルコ書に書いていないということは、後の時代に作られた話である可能性も高くなる。
それで、マルコ書を最初から最後まで読んでみて、それに類することをどこかで言っているかどうか調べてみた。すると、イエスは敵を愛するどころか、敵に怒りを顕にしている場面がたくさんある。彼は、つねづね敵に囲まれていたのだ。彼が人を癒やしたり、説教をしていたりすると、パリサイ派の律法学者だとか、ヘロデ派の人たちというのがやってきて、やれ律法に従ってないだの、そんなことをする権威がどうしてあるのかだの、絡んでくる。そういう人たちをかわすのに、イエスは天才的な知性を示すのだけれど、それでますます怨みを買うことになり、彼に殺意を抱く人々は増えていった。
こうした敵に、彼が愛するような素振りを見せていた記述は、マルコ書にはない。彼は、パリサイ派の律法学者たちに対して怒りを示しており、あの連中には警戒しろと言っている。弟子たちがてんかんの子供を治せないで、律法学者たちと議論していたときには、「何という不信仰な時代だろう。いつまであなたたちに我慢していられるだろう」と言っていて、あからさまにブチ切れている様子だ。
いちじくの実を食べようとして、実がなかったのでがっかりして、「これから後、誰もお前の実を食べるものがないように」と言ったら、いちじくの木が枯れてしまったといったこともあった。エルサレム大聖堂に来たときは、人々がそのまわりで商売をしているのに腹を立て、屋台をメチャメチャにして、人々を追い出してしまったりもした。家族が会いに来たときに、肉体の親兄弟などは本当の親兄弟ではないと言って、会わないで帰してしまったこともある。
マルコ書の中で、唯一、敵に寛容であれという意味のことを言っているのは、第11章で、「立って祈るとき、誰かに対して、何か恨み言があるならば、ゆるしてやりなさい。そうすれば、天にいるあなたたちの父もあなたたちのあやまちをゆるしてくれるだろう」と言っている部分だけだった。ところで、これは、彼が呪ったいちじくが、枯れてしまったときのことだった。そこで彼は、本当に信じるなら、山をも動かすことができる、というあの有名なセリフを言っている。そのあとで、このセリフを言っているのだ。つまり、これは望んだことは本当に実現するのだということを言っている。本当に望んだら、木を枯らしてしまうこともできる。だから、もし誰かに恨みがあったら、ゆるしてやるように、と言っている。
そのことからすると、このゆるしてやるべきだというのは、通常理解されているような、とにかく争いはいけないというような意味ではないようだ。そうではなくて、力がある人間は、加減を知らなければいけない、というような意味で言っているのだと思う。素手で人が殺せるほどの武術を身に着けてしまったら、寛容さを覚えなければ、身を滅ぼすことになる。そしてまた、それだけの力があると知っていたら、他人の攻撃を恐れる必要もないわけだから、相手に対して寛容になることもできる。イエスは、そうしたことを言っているように思える。
そもそも、イエスは人々には喩えでしか語らなかった、とマルコ書にはある。そして実際、彼が人々に対して、ああしろこうしろ、こうするべきだ、ということを言っている箇所は、マルコ書には一つもない。「神の国とは、ひと粒の辛子の種のように、一番小さくてもものすごく大きくなる」とか、「外から入ってきたものは、人を汚すことはない。人の内から出るものが、人を汚すのだ」とかそういうことを語っているだけだ。あとは、絡んでくる律法学者に、「お供え物をしていれば、あとは何もしなくても父母を敬ったことになるのか」とか、「お金はローマ皇帝のものなのだから、ローマ皇帝に返せばいいだろう」とか言って、返し技を食らわせている場面がある。それ以外は、あちこちでいろんな奇蹟を起こしたことが、書いてあるだけだ。
ところで、「汝の敵を愛せよ」と言ったというマタイ書の部分を見てみると、イエスがガリラヤで説法を始めた頃に、群衆に囲まれたので、山の上から説教をした、という場面で、このセリフを言ったことになっている。ルカ書では、イエスが山に行って、12人の弟子を選んで使徒にしたあとで、山から降りてきて、人々に語ったことになっており、記述が一致していない。そして、マルコ書には、この説教の話は一切出てこない。
この説教は、「貧しい人たちはさいわいだ。飢えている人たちはさいわいだ」という話で始まっていて、何故さいわいなのかと言うと、あとで報いが受けられるからだ、というのだ。だから、苦しみを喜べ、と言っている。罵られたら喜べ、迫害されたら喜べ、と。
これは、マルコ書から読み取れるナザレのイエスの教えとは、まるきり違うものだ。心から望めば、山だって動かせると彼は言っていて、弟子たちが人を治せなかったり、パンが足りないとか心配しているのを見て、何で悟らないのだとイライラしている。彼は、何千人もの群衆にパンを分けたりもした。それを見ていながら、どうしてパンが足りないとか心配しているのか、と言っている。その同じ人物が、一方で貧しいのを喜べ、と言っているのは、どう考えてもおかしいように思える。何かが足りないのなら、信じることで得られるようにすればいい。イエスはまさに、そのことを教えていたのだから。
この山の上の説教では、律法を守れということも言っていて、これもイエスが律法学者たちとやり取りしていたことと食い違う。彼はその説教で、律法を一つでも破ったら、天国で小さい者と呼ばれる、と言ったことになっている。しかし彼は、あれやこれやの律法を守っていないというので、律法学者にいちいち絡まれていたのだ。律法を守ることではなくて、内容が大事だろう、というのが、彼の考えだ。その彼が、律法を一つでも破ってはいけないというようなことを言うのは、どう見てもおかしい。
そして、「敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈れ。頬を打つ者には、他の頬も差し出せ」と続くのだ。こうなると、もう胃がムカムカしてくる。胃のあたりがギュッと縮んで、痛くなってくる。これは、第3チャクラがやられている徴だ。第3チャクラ。それは、自我意識がある場所で、自分が自分を守る力のセンターになっている場所だ。
敵を愛せ、というのは、つまり自分を守るのを放棄しろということなのだ。自分が自分であることを放棄して、自分の自由を侵そうとする相手に従えと。これは、本当の自分を発見し、人間の可能性を解放しようとするのとは、正反対の方向だと言える。しかし、人々を支配者に従わせるには、最適の教えだ。一発で、人々から自分軸を失わせ、自分の自由を守る力を萎えさせてしまうことができる。罪の意識を与えて、自己イメージを下げることで、意識エネルギーを一気に落としてしまえるはずだ。キネシオロジーとかで、ネガティブな言葉とポジティブな言葉を言ったときに、人のエネルギーが変わるというのをやっているけれど、あれで見てみたら、「汝の敵を愛せ」という言葉は、エネルギーの下がり方がハンパじゃないんじゃないかと思う。
2007年に、ナザレのイエスとコンタクトしていたとき、福音書をどう思うかと、彼に聞いてみたことがある。彼は、まったく興味がないといった様子で、「こんな古くさいもの」とつぶやいて、炎の中に投げ込んでいるイメージが表れた。あのときの私は、いくら何でもそれはないんじゃないかと思ったけれど、こうして見ていくと、あれもそれほど大げさな反応ではなかったように思えてくる。数年前には、テレビも新聞も全部嘘だから、あんなものは捨ててしまえと誰かが言っていたら、まさかそこまではと思ったけれど、今は、テレビも新聞も本当にほとんどすべてが嘘だったことがよくわかった。あれと似ているようだ。
それを考えれば、福音書も、あるいは本当にほとんどの部分が、あとから入れ込まれたフェイク情報だったりするのかもしれない。フェイク情報によくあるように、おそらくは一部は真実で、残りの部分は作り話だったり、歪曲されていたりするのかもしれない。ローマ帝国が、弁論術で大衆操作することに長けていたことを思えば、これはかなりあり得る話のような気がする。
マルコ書を読むかぎりでは、イエスが言っている「神の国」というものは、高次元の意識にシフトしたときに、現れてくる意識の領域のようだ。そこでは、望んだことは現実化するし、健康上の問題を変えることもできるし、物質に作用することもできる。しかし、他の福音書では、神の国とは、生きている間に我慢して従っていれば、死んだ後に行けるかもしれないようなところになっているようだ。
キリスト教の歴史とは、まさにこの封じ込めの歴史だったのかもしれない。それが2000年経って、ようやく封じ込めが解け始めているような気がする。2000年を超えたあたりから、ハイヤーセルフにアクセスする人が、飛躍的に増えていった。遠隔ヒーリングも普通のことになったし、テレパシーやチャネリング、過去生にアクセスするのも、多くの人が普通にやるようになった。
そうなったとき、イエスが譬えで語っていた謎めいた言葉が、何のことなのかがリアルにわかるようになったのだ。イエスのまわりにいた同時代の人たちは、彼とともにさまざまな奇蹟を体験していたからこそ、彼が何を伝えようとしているのかがわかったのかもしれない。高次元領域の現象は、理屈で説明しようとすると、ものすごい難しくなるけれど、体験すれば一発でわかったりするものだから。
今、ナザレのイエスにコンタクトして、「敵を愛せよ」なんて言ったのかと聞いてみると、やっぱり福音書を炎の中に投げ込んでいるイメージが見える。それから、「敵は愛するものじゃないだろ」という声がした。そのあとで、彼がうれしそうに目を輝かせながら、敵をガンガンやっつけているイメージが現れた。「敵とは、遊ぶもんだ」
それを見ていると、彼はやっぱり敵を愛しているようだ。敵とは、やっつける喜びを味わえるからこそ、愛すべき存在なのだ。そのために彼は、言葉の芸当を駆使して、後世に残るようなやり取りを交わしもしたのだから。
2023年10月30日

***
【金持ちは天国に入れないのか?】
ナザレのイエスは、「金持ちが神の国に入るのは、ラクダが針の穴を通るのよりも難しい」と言ったと言われている。カトリックの教育を受けて育ったドイツ人の友達は、そのおかげでお金のブロックが外れないのだとよく嘆いていた。
この話は、お金を持っていることがいけないみたいに解釈されていることが多いけれど、本当はそういうことではないと私は思う。実際、イエスのまわりには富裕な人もたくさんいたようだし、お金があるということ自体が問題だということではないように思える。
この話は、マルコ書にもマタイ書にもルカ書にも、ほとんど同じ言葉で、同じことが書いてある。これはつまり、すべての証人の証言が一致したということで、事実はまず、書いてあるその通りに現実に起こったのだろうと考えることができる。
イエスが道を歩いていると、一人の男が走ってきて、彼の前に膝まずいて、「よき師よ、永遠の生命を受けるためにはどうしたらよいですか?」と聞いたとある。それに対してイエスは、どうして「よき師」なんて呼ぶんだとか、誰でも知っている戒律を言って、それを守ればいいだろう、とか答えている。この答え方からして、イエスはこの男がこういう質問をしに来たのを、ウザいやつだと思っているように見える。
この男は、たくさんの資産を持っている人だとある。ということは、それが見てわかるくらい、豪奢な服装をしていたのだろう。いかにも大金持ち、というかっこうをした人だったのだ。そういう人が、永遠の生命を受ける方法を教えてくれと言ってきた。「よき師」とイエスに呼びかけたりしたのも、何だかおべんちゃらを言っているような感じだったんじゃないかと思う。だから、何でそんな呼び方をするのかと、イエスが突っ込んだわけだ。この人は大金持ちだから、永遠の生命でも何でも、お金で買えるみたいに思って、イエスのところに来たのかもしれない。何十万円もするような高額セミナーを受講して、それで悟れると思っている人たちみたいにだ。
それで、永遠の生命を受けるには、十戒を守ればいい、みたいな話でかわそうとしたんだと思う。高額セミナーに来るような大金持ちは、多くの場合、自分で努力しようとしないので、お金だけ払って、何にもならないことが多い。それよりも、自分で本でも買って実践した方がいいのに、それをやる代わりにお金を出そうとする人たちなのだ。そういう人たちを相手に商売しているスピの師匠たちもたくさんいるけれど、お金のためにやっているのではない人たちは、こういう大金持ちはあまり相手にしたがらない。お金は入るけれど、時間と労力の無駄だったりするからだ。しかも、思ったようにならないと文句を言ってくるのは、だいたいこの類の人たちだったりする。
しかし、この大金持ちの男は、「そうした戒律は、子供の頃から守っています」と真面目に言った。それでイエスは、ただの大金持ちというわけではないな、と思ったのかもしれない。マルコ書には、そのときイエスが彼に目を留めて、彼を愛しいと思った、とある。これは、マタイとルカには書いていない。それでイエスは彼に言うのだ。「帰って、持っているものをすべて売り払い、貧しい人に施しなさい。そうすれば、天に宝を持つようになるだろう。そして、私について来なさい」
それを聞いて、この大金持ちの男は、哀しみながら立ち去った、とある。たくさんの資産があったので、その資産をすべて手放すわけにはいかなかったのだ。それを見てイエスは、「富裕な人が神の国に入るのは、なんと難しいことだろう。それよりも、ラクダが針の穴を通る方がやさしいくらいだ」という、あの有名な言葉を言ったとある。
この大金持ちの男が、永遠の命を受けられるようにして欲しい、とお金で買えるみたいな調子で言ったので、まさにこのお金を持っているということが、この人にとって本当の自分の魂と繋がることを妨げるブロックになっているのを、イエスは見抜いたのだと思う。財産をすべて手放してしまえば、彼は解放されるだろう。それで、自分についてこいと言ったのだから、あとあとまで面倒を見るつもりで引き受けたわけだ。そこまでオファーしたのに、この大金持ちの男は去っていってしまった。それでイエスはがっかりしたのだと思う。それで、「ラクダが針の穴を通るよりも」というあのセリフになったのじゃないかと思う。
ところで、永遠の生命とか神の国とか言っているものは、何なのだろう? 神の国とは、カラシの種のようなもので、ごく小さいけれども、成長するとものすごく大きくなる、と言ったということが、マルコ書には書いてある。ここで言っている神の国とは、ハイヤーセルフとか宇宙意識とかと繋がる高次元領域のことなのだろう。神さまとかハイヤーセルフと出会う体験をした人は、まさにひと粒のカラシの種が大きな植物に育つような勢いで、高次元領域が意識の中で大きくなっていくのを経験して知っていると思う。
高次元意識というのは、ないと思っているうちは気がつかないけれど、一度あるということに気づいてしまうと、実は今までもずっと存在していたということに気づく、というようなものなのだ。現実の世界は、物質的な次元だけではなくて、意識の次元が存在していて、実はそれによって現実ができていたことに気づく。それは、今生きているこの世界が、とつぜん魔法の国になったかのような感覚だ。だから、最初はほんのわずかな「もしかして、本当なんだろうか?」というほどの信心でも、そこに意識を向けたとたんに、ものすごい勢いで広がっていく。世界の何もかもすべてが、実は意識の次元でできていたことに気づいてしまう。それがまさに、ひと粒のカラシの種が大きな木のようになる、というようなことなのだ。
ところで、その次元の意識を知ってしまったら、資産などは何でもないことがわかってしまう。実際、何かの理由で財産を手放すようなことになった人は、必要なものや欲しいものが、不思議なシンクロでどこからか手に入るという経験を一度や二度はしたことがあるんじゃないかと思う。財産を持っているとか持っていないではないのだ。必要なものならちゃんとどこからかやってくることになっている。しかも、いくらお金があっても、ちょっと手に入らないような、ぴったりのものが不思議とやってきたりもする。
イエスは、大工をやめて放浪生活を始めてから、いつも行きあたりばったりで、必要なものは何でも出していたのだから、そのことをよく知っていたはずだ。だから、資産をすべて売り払えば、「天に宝を持つようになる」と言ったのは、死んだ後に天国に行けるとか何とかそんな話ではないと思う。天の神が必要なもの欲しいものは、何でもその都度出してくれるということを知ることこそは、「天に宝を持つ」ことだ。これを知ってしまった人は、もう地上の所有権なんかは、それに比べたら大したものではないということを、知ってしまう。
資産なんか初めからなかったり、あるいは何かの事情で失ったのならば、自分から手放す必要もない。だけど、資産を持っていて、それを自分で売り払うというのは、容易なことではない。「神の国」なるものを知る前に、本当にそういうものが来るということを、信じなければならないわけだから。それは大金持ちの人間にとっては、騙されて財産を取られるんじゃないかみたいな疑いを乗り越えていかなければならないことだ。それがまるで、「ラクダが針の穴を通る」ようなことだというわけだ。
もう一つ、キリスト教の人たちがよくお金のブロックを抱える原因になっているのは、イエスが弟子たちに、「杖の他は何も持たずに」旅に出したということだそうだ。イエスは、12人の弟子に悪霊祓いを伝授して、その近辺の村へ行って、そこで人を癒やしたり、福音を伝えたりするようにと言った。そのときに、お金も食糧も着替えも何も持たず、ただ杖一本だけ持って行けと言ったというのだ。
それを聞くと、何だか貧しさに耐える苦行の旅にでも出かけていくようなイメージを持つ。空腹で凍えたりするような思いをすることで、魂を清める旅に出るというような。ところで、村に入ったら、一つの家にずっと滞在しているようにと、イエスは弟子たちに言っている。そして弟子たちは、飢えも凍えもせず、無事に帰ってきた。多くの病人を癒やしてきたとあるから、行った村々でもてなされてきたのだと思う。
何かの使命を感じて旅に出たことがある人なら、同様のことを経験して知っているかもしれない。そういうとき、何のあてもなくても、不思議とちゃんと泊めてくれる人が現れたり、ちょうど食べたかったような料理が出てきたりする。お金がいくらでもあったら、ホテルを予約して行くから、そういう経験はできない。しかし、お金もろくにないような状態で、それでも行かなければと思って出かけた旅では、まるで奇跡の連続のようなことが起こったりする。行く先々で、車で送ってくれる人が現れたり、宿が出てきたり、思わぬご馳走が出てきたり、本当に必要なものは何でもその都度出てきたりする。天気まで、外に出た瞬間に雨が止んだりすることもある。そういうときは、上の次元ですでに準備がされていて、まるで次々案内されていくみたいに移動しているように思える。
それを考えると、イエスが弟子たちをわざわざ杖だけで旅に出したのは、その経験をさせるためだったのに違いないと思う。実際あの頃、イエスが病人を癒やすというので、近隣から人々が大勢集まってきていたのだ。その弟子たちが、人々を癒やしに出かけたのだから、多くの村では、彼らは歓迎されたのだと思う。それで、食事も衣類も十分にもらってきたんじゃないかと思う。そのことを体験して知った人たちは、財産だとか地位だとか職業だとかに縛られることはなくなる。ただ真実のために生きてさえいれば、必要なものはすべて与えられるということが、身体でわかってしまうからだ。
2023年10月31日

***
【隣人を愛すること】
ナザレのイエスは愛することを教えたと言われているけれど、マルコ書を通して読んでみると、愛することについては、実はほとんど書いていない。4つの福音書の中で、作り話や歪曲が最も少ないと思われるのがマルコの福音書だ。文学や歴史学の研究法を学んだ人ならば知っていると思うけれど、ある文書が信頼に足るものなのか、あるいは偽書の可能性があるものなのかを判断するには、中の記述に整合性があり、人間心理から見て筋が通っているかどうかを見る。犯罪捜査で、証人の証言を証拠として扱うことができるかどうかも、同じやり方だ。あっちとこっちで言っていることに矛盾がある場合には、真実の証明にはならない。論理的に筋が通っていなかったり、人間心理として無理がありすぎる場合は、虚偽であるか、歪曲が入っている可能性がある。
そうした観点から4つの福音書を読み比べてみた場合、マルコの福音書には、一貫した論理があり、筋が通っていて、起こっているできごとを人間心理からして理解することができる。ところが、他の3つの福音書では、書いてある内容に矛盾がありすぎ、言葉と行動も一致していないし、人間心理としても、当人やまわりの人間の反応に不自然なことがとても多い。そのことからして、3つの福音書は、のちに改ざんされたり書き換えられたりしており、他の人物の記述やまったくの作り話などが混ぜ込まれている可能性が高い。
マルコ書で、愛することについて書かれているのは、第12章で律法学者に、戒めの中でどの戒めが一番大事なのかと聞かれて答えているところだけだ。イエスは、第一の戒めは、主なる神を愛せというものであり、第2は、自分を愛するように隣の人を愛せというものだと言っている。
これは、イエスが群衆を連れてエルサレムに来たときのことだ。パリサイ派の律法学者やヘロデ党の人たちは、イエスを逮捕して有罪にしようとしていたので、その証拠になるものをつかもうとして、引っかけ質問をしに来ていた。それで、ローマ帝国に税金を払うべきなのかとか、イエスに聞いていたのだ。当時のエルサレムはローマ帝国に支配されていた状態で、ローマの取税人は嫌われていた。けれど、税金を払うべきではないと言ったら、ローマ帝国に対する反逆だとみなされる。それでイエスは、お金はシーザーの肖像が刻み込んであるシーザーのものなのだから、シーザーに返したらいいだろう、と言ったのだ。
エルサレムでのやり取りでは、彼は敵に尻尾をつかまれないように巧みに答える必要があった。その意味で、彼はまったく絶妙なやり取りをしている。尻尾をつかまれないようにしながら、一言で相手にピシリと返すようなことを言っている。そうしたやり取りの中で、彼は神を愛することと隣人を愛することが、戒めの中で一番大事だと言っているのだ。そして、こう答えると、質問した律法学者は、まったくその通りだとイエスに同意するしかなかった。するとそのあと、彼に質問しようとする者はなかった、とある。
大金持ちの男に、永遠の生命を受けるにはどうしたらいいかと聞かれたときには、イエスは「殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、親を敬え」という戒めを守れと言っていて、この二つの戒めは言っていない。そのことからして、神を愛せ、隣人を愛せ、という二つの戒めが最も重要だと言ったのは、質問した律法学者に対して言ったことなのだと思う。人殺しと不倫とどっちが悪いのか、みたいな話を避けて、突っ込みどころのまったくない、文句の出ない答えを出すために、イエスは神を愛することと隣人を愛することだ、と言ったんじゃないかと思う。これなら、律法学者もイエスを論争に巻き込むことができない。それで、まったくその通りだと答えて、それ以上は質問をしないで行ってしまったのだ。
この隣人を愛せというのは、レビ記の第19章に書いてあることで、神がモーゼに、人は何を守るべきかを伝えたというものだ。それで、祭礼のしきたりだとか、安息日に何をするべきかとか、人の裁き方だとか、婚姻の決まりだとか、そういう法律みたいなものがいろいろと書いてある。その中に、「自分を愛するように隣の人を愛せ」とある。これは、他の刑法とか民法みたいなものとは違って、人の基本的な生きる姿勢ようなものだと言える。何がいけないとかどうすべきだとかいうようなものではなくて、たがいに平和で友好的であれということを言っている。
律法学者たちが、イエスに質問しに来たとき、まさにこのことを彼らは守っていなかった。彼らはイエスを敵対視して、何とか引っかけて訴えようとして、やってきたのだ。だから、イエスにそのように返されて、律法学者はまったくその通りだと引き下がるよりなかった。
ところで、この「自分を愛するように」というのは、原文だと「あなたのように」という意味なのだそうで、だから、自分が自分を愛するように隣の人を愛しなさい、ではなくて、隣の人もあなたと同じだと思って愛しなさい、というような意味になるのだそうだ。つまり、あなたは私、私はあなた、ということだ。まわりにいる人たちを、自分と同じ仲間だと思え、同じ人間だと思え、ということ。そう思ったら、自ずと愛着が湧くし、信頼関係ができていく。まさにこれこそは、平和と調和へ向かう、シンプルにして効果的な言葉だと言える。
それ以外では、子供たちを闇に引き込むようなことをするくらいなら、罪を犯させる片手を切り取っても、命の道を行けというようなことを言ったあとで、「あなたがたの内に塩を持ちなさい。そしてたがいに和らぎなさい」と言っていることくらいが、イエスが愛について語っている部分だ。ここでは彼は、愛せではなくて、和らげと言っている。つまり、たがいに平和的であれということだ。これも、あなたと同じ仲間だと思え、というのと同じことだ。
これがどうして、「自分を愛するように隣の人を愛せ」と変わったのだろう? 確かに言えることは、「自分を愛するように」と言ったとき、相手を愛することが、とたんに難しいことになってしまうということだ。そもそも、愛というものは、自分のまわりの存在に対して、私たちが抱く感情なので、自分に対して向けるものではない。私たちは、まわりの存在を目にしたときに、これは好きだ、これは嫌いだ、という感情を自然に持つのだけれど、それは自分にとっていいものなのか、よくないものなのかを示している。
私たちは、育っていくうちに、何がいい、何が悪いというのを外から植えつけられていくので、自然の感覚のままに好き嫌いを感じる感性が鈍ってしまっていることが多い。だけど、小さい子供などは、まだこの感性が純粋で、相手が信頼できる人なのか、それとも裏切る人なのかを、かなり確実に感じ取る。野生動物は、好きか嫌いかという感性で、どれが自分に合ったおいしい食べ物なのか、どれが有害な食べ物なのかを、正確に感じ取るのだ。だから、好き嫌いというのは、本来は、私たちを守ってくれ、望むような方向に導いてくれる重要な感性だと言える。それはそもそも、愛せよ、という風に強制するべきことではない。
だから、相手もあなたと同じ仲間だと思いなさい、そして愛しなさい、というならば自然になる。同じ仲間だと思えば、自然と好きだという感情は湧いてくるものだ。私たちは、どういう人間は警戒しろ、どういう人間とはつきあうな、と言われて育つ。だから、人に出会ったとき、相手はつきあうべき人間なのか何なのかと思うわけだけれど、そういう警戒心や差別意識が植えつけられていなければ、相手が本当の悪党でないかぎり、愛の感情は自然に湧くのだ。まわりの人間を敵と思うのではなくて、仲間と思え、ということを、皆が守っている社会なら、自然と平和で友好的な生きやすい世の中ができる。イエスが戒めの中でこれが最も大事だと言ったのは、そういう意味でなのだと思う。
しかし、「自分を愛するように」と言ったら、自分というものを外から見る意識になる。外から見て、自分は愛されるような人間なのか、愛される価値のある人間なのか、といった思いが浮かんでくる。他の人たちと比べてどうなのか、というような比較の意識も出てくる。自分は悪い人間ではないかというような思い、悪いことをしてしまったのではないか、何かが足りないのではないか、というような思いも湧いてくる。これで自分を愛せと言われても、愛の感情は自然には湧いてこない。そして、そのように隣の人を愛せということになったら、一体どうしたら愛したことになるのかもわからなくなってしまうだろう。
その結果、本当は自分が欲しいものを相手にプレゼントするとか、自分が変えたいと思っている欠点を、相手に変えるように説教するとか、何かしら不自然な行動に出たりすることにもなる。だけど、そういう行為は何だか押しつけがましさがあって、相手にウザがられることになりがちだ。それで、ますます自分が嫌いになり、ますますどう愛したらいいのかわからなくなる、というような悪循環に陥ったりすることにもなる。
マルコ書には一切そうした記述はないのだけれど、マタイの福音書には、人はどうするべきだとか、どういう人間が優れているとか、神に愛されるとか、そういう言葉がたくさん出てくる。これは、人を仲間だと思え、自分と同じだと思って友好的にしろ、ということとは正反対だ。貧しい人や苦しんでいる人は幸いだ、とか、善行は隠れて行えとか、人を裁くなとか言っている。そうしないと、神に愛されないとか、神の国に入れないとか、自分(イエス)にはふさわしくないとか言っている。
こういう風に人を差別化して、こうしろああしろというのは、人を思い通りに動かしたい人たちがよく使う手だ。4年前に奇妙なパンデミックが始まってから、政府とメディアが一緒になって、どうするのがいい人で、どういうのが悪い人なのか、というキャンペーンをしきりとやっていた。その結果、大半の人たちを、そうでもなかったら絶対にやらないような行動に、自分から向かっていくようにしてしまったのだ。それで私たちは、大衆操作の手法というものが存在していて、それが昔から使われてきたということを、知ることになった。
それを考えると、このマタイ書の記述は、大衆操作のために紛れ込ませた作り話のようになにおいが濃厚にする。貧しくて苦しんでいる人、迫害されている人がよくて、善行は隠れてするべきで、人を裁いてはならず、敵を愛せ、というのだから、つまり、搾取されても文句を言わず、目立つこともせず、搾取している人たちに自分から従って、気に入られるように仕えろということになる。人々が自分からそのようになろうとしていたら、支配者にとっては、実に都合がいい世の中ができることになる。
マルコ書には、どうするのがいい人間だとか、こうしないと神に愛されない、みたいなことはどこにも書いていない。書いてあるのは、彼が「神の国」と言っている高次元領域がどういうものなのかとか、何がすべて可能なのかというようなことだ。そして何よりも、彼は何がすべて可能なのかを、実際に人々の目の前で示して見せたのだ。そして、どうして信じないのかとか、どうしてそんなに信仰が薄いのかと事あるごとに嘆いているのだけれど、それは弟子たちが、イエスが示して見せる奇跡のようなことが、自分にもできると思って、やってみようとしないということを言っている。
それを思えば、イエスがその高次元領域の存在を人々に示してみせたそのこと自体が、かぎりない愛であり、贈り物だということがわかる。それを目にし、この世界で何がまだすべて可能なのかということを知ったとき、それがひと粒のカラシの種のように、その人の意識の中で、大きく育っていくのだ。それは何より、この世界がどれだけ多くのすばらしい体験を私たち人間に与えてくれているのかということに気づかせてくれる。そしてそれを知ったとき、神を愛し、神を讃えよ、というあのことは、言われなくても自ずと湧いてくるのがわかる。
2023年11月1日

***
【パンを増やす方法】
ナザレのイエスは、パンと魚を増やす奇跡を行ったと言われている。あれは、物理的に増やしたわけではなくて、何かの比喩だというような解釈がされていることが多いのだけれど、あれはまったく書いてあるそのままに起こったのだろうと、私は思っている。
それというのも、あの話は、4つの福音書で、ほとんどまったく同じ言葉で、同じことが書いてあるからだ。もし何かの比喩ならば、書き手によって解釈にバラつきがあるから、まったく同じ言葉で同じことが書いてあるという風にはならないはずだ。ところがこの不思議な物語については、そのバラつきがまったくない。そして、その記述は奇妙なくらいシンプルだ。
イエスと弟子たちは、群衆が追いかけてきて休めないので、舟に乗って、人気のないところへ行こうとしていた。しかし人々は、歩いてイエスの舟が行く先へ行って待ちかまえていたので、イエスは舟を降りて人々を癒やすことになった。何もないような場所だったし、食糧がないので、群衆を解散させて、食べ物を買いに行かせなければと言っていたとき、イエスは、群衆を解散させないで、食べ物をやるようにと言った。しかし、手持ちの食糧は、パンが5つと魚が2匹あるだけだった。群衆は、男だけでも5千人いた。食糧が足りるはずがないと弟子たちは言った。するとイエスはパンと魚を切り裂いて分けて、弟子たちに配らせた。すると全員満腹するまで食べて、残りを集めたら、12のカゴいっぱいになった、ということだ。
この話については、パンが5つに魚が2匹とか、男だけで5000人とか、12のカゴだとか、そういう数まで、すべての福音書で完全に一致している。状況も、イエスが言った言葉もほとんど同じだ。そして、何より奇妙なのは、どうしてイエスがパンを裂いたら、それが増えたのかが、どの福音書にもまったく書いていない、ということだ。
もし比喩で書いたのなら、それぞれの書き手が、何かしら書いたはずだ。どうして増えたのかとか、どういう風に増えたのかとか。ところが、そうしたことがまったく書いてなくて、ただ、イエスが分けたら、皆がお腹いっぱいになるだけ配れた、と書いてあるだけなのだ。
これは、その場で見ていた人が、それ以外にまったく言いようがなかったからなのだと思う。いったいどうしてそんなことが起こったのかわからないけれど、しかし確かに起こったのだ。だから、そのように語る以外になかったのだと思う。奇跡が起こるときというのは、得てしてそうしたものだ。どうしてなのかわからないけれど、ただ起こる。しかも、まるで普通のことのように起こる。だから、ただ起こった、という以外の言葉がない。
ドイツのドキュメンタリー作家のクレメンス・レヴィが、チベットのラダックに行ったとき、子供のラマが石の玉座に座って、手を玉座の端について座を降りたとき、石の上に手の跡のくぼみができたことがあったということを書いている。その後、人々はその石の玉座にできたくぼみに触らせてもらうために、長い行列を作ったというのだけれど、お付きのラマ僧たちに、どうやってやったのかといくら聞いても、「彼はやったのです」という答えしか得られなかったそうだ。誰にも説明できなかったのだ。ただ、起こった、という以外には、何も言うことができなかった。
だから、不思議なことが現実に起こったときほど、それを語る言葉は少ない。科学で説明できないような不思議なことは、実はけっこう頻繁に起こっているけれど、そうしたことを実際に見たり経験したりした人なら、その感覚がわかるかもしれない。その感覚を知っていたら、パンと魚を増やした奇跡を読んだとき、これはやはり、まったく書いてあるそのままに、現実に起こったのだということが、感じ取れるかもしれない。
物理的な次元だけが現実だと考えたら、不可能なことはたくさんある。しかし、この頃では、これまで不可能だと思われてきたことの多くが、実は昔から可能だったことが表に出てきたりもしている。念を送っただけで、病が治ったというようなことも、前は不可能だと思われていたけれど、この頃は誰でも遠隔ヒーリングの講習とかに行って、できるようになるということが知られるようになった。人間は食べないでは生きられないと思われていたけれど、実は中国で不食と言って、そうしたことをする人たちが昔からいたことがわかった。インドのサイババという人は、その人に意味があるような宝飾品を、その場で手から出すのだそうで、それを現実に体験した人は、世界中にたくさんいる。だから、物質を出したり消したりすることも、現実に可能ではあるらしい。
2007年に、初めてナザレのイエスとコンタクトしたとき、パンと魚を増やした奇蹟のことを聞いてみたことがある。あの頃から私は、彼が本当にやったのだということを確信していた。それで、ごく率直に聞いてみたのだ。「あれ、本当にやったんでしょ? どうやってやったの?」と。すると彼は、何だか照れたみたいにヘラヘラして言った。「ああ、あれ? 簡単なことだよ。こうやって。。。」
それから彼は、どうやってやったのかを、手マネで示してみせた。丸くて赤っぽく光っている炎のようなものを持っていて、それを両手で分けると、右手と左手に同じくらいの大きさの炎ができる。それをさらに二つに分けると、それぞれまた同じ大きさになる。それを皆に行き渡るまで続けていった、というのだ。
どうして分けたものが、同じ大きさになるのかはわからないけれど、炎のようなものならば、分けたら確かにどんどん大きくなっていくのだろう。食べ物とは、生命エネルギーだ。エネルギーは炎と同じで、分ければ分けるほど増えていく。だから、炎を分けて増やしていくのと同じように、パンと魚を分けて増やしていったということらしい。
それは、ホメオパシーのレメディが、希釈していくほどにパワフルな波動になっていくというのと、同じようなことなのだろう。あれもまた、分ければ分けるほど無限に増えていくエネルギーだ。そしてそれは、食糧ではないけれど、人々に生命エネルギーを与え、満たしもする。
そういう風に、エネルギーを分ければ無限に増えていくというのはわかるのだけれど、それがどうしてパンとか魚とかいう物質的なものになったのかは、やはり謎だ。しかし、そんなことも可能なのだと、ナザレのイエスは言っていた。「まあ、そんなこともあるのさ。エネルギーのことを知っていれば、誰でもできるようなことなんだよ」
パンと魚を増やすのは、そのあとまた、群衆とともに荒野にいたときに、人々がもう3日もいて、食べるものがないというので、7つあったパンを分けて、4000人が食べたということが、福音書に書いてある。そして、残りを集めたら、7つのカゴにいっぱいになったそうだ。しかし、弟子たちはそのあとで、パンが足りないと話していて、それを聞いたイエスは、パンが増えたときのことを弟子たちに思い出させてから「まだ悟らないのか」と言ったとされている。
あまり不思議なことが起こると、人はそれをリアルに経験していても、なかなか認められないものなのだ。それは、西洋医学で不治の病とされているものが、別なメソッドで治ったときに、多くの医師たちは、その病気が治ったということを認められないのと同じようなことなのだろう。ある精神科医は、統合失調症の患者がホメオパシーで治ったときに、治ったということを認める代わりに、「統合失調症は治らないのだから、統合失調症だというのは誤診だったのだろう」と言った。そんなものなのだ。教わったことが間違っていたことを認めるくらいなら、自分の診立てが間違っていたと思うことの方を選ぶ。もっと大きな可能性が世界には存在しているということを、認めようとはなかなかしないのだ。
イエスは、神の国とは、ひと粒のカラシの種が木のように大きく育っていくようなものだと言っているけれど、それはまさに、「これが現実だ」と私たちが思っている世界の外に、もっと大きな可能性が広がっているということを知るようなものなのだと思う。だから、最初はほんのわずかにでも「こんなこともあるのか」と思ってみることで、私たちは「これが現実だ」と思っているマトリックスの外を覗くことになる。そして覗いてみたときに、とてつもなく大きな世界が目の前に現れてくる。「神の国とはひと粒のカラシの種のようなものだ」ということは、まさにそうしたことを言っているのだと思う。
2023年11月2日

***
【無条件の愛という罠】
私が初めてナザレのイエスの魂とコンタクトした2007年の頃、私はまだ、彼は無条件の愛を生きることを教えていたと思い込んでいた。あの頃、私は元夫と別れて別居し始めたばかりで、無条件の愛なんかを生きようとしたら、死ぬと思っていたところだった。おそらくは、だからあのとき、私はナザレのイエスの魂と繋がったのだと思う。そんなことではないのだと、伝えに来たのだ。
相手を無条件に愛さなければと思って、ボロボロに傷つく女性は多い。こんなに愛を与えても、何も返ってこなかったと、裏切られただけだったと言い、だけど相手を責める代わりに、自分が愛し切れなかったことに罪の意識さえ感じている。自分を守ること、自分の感情を表に出すことができずに、ただ自分を責めてしまうのだ。
そういう人とコンタクトすると、ナザレのイエスのエネルギーは、ピンク色の光のようなエネルギーになって、背中の真ん中の、心臓があるあたりから、すっと中に入ってしまい、その人の心臓が壊れないように守っている。
何故といって、人を無条件に愛そうとして傷つく人が、唯一無条件に愛していないものは、自分自身だからだ。それで多くの人は、自分自身を守ることができないで、ボロボロになるまで傷つけさせてしまう。その無防備の心臓を、ナザレのイエスは、ピンク色の光のような愛のエネルギーで、守ってくれるかのようだ。
無条件の愛というものについて、あまりによく言われているので、当然、聖書に書いてあるのだろうと思って調べてみたら、マルコ書にはそんなことは一言も書いてなかった。愛を勧めるようなことさえ書いていない。他のどこかに書いてあるのかと思って、ネット検索してみたら、教会関係のサイトがいくつか出てきて、ヨハネの第一の手紙の第4章にそういうことが書いてあると書いてあった。けれど、その箇所を読んでみると、そこには、神は愛であるということが書いてあるだけだった。そして、罪を犯すと神の愛はないとか、イエスを認めないと神の仲間ではないとか、愛さない者は神に愛されないとか、そういうことがいろいろと書いてあって、無条件どころか条件だらけのようだ。
ナザレのイエスの教えはエッセネ派から来ていて、ハワイのシャーマニズム、フナ(ホオポノポノ)も、エッセネ派から伝わったものではないかと言われている。フナでは、「アロハ」と呼ばれるものが、無条件の愛の力に当たるものなのだけれど、アロハとは、「一緒にいるのが幸せだ」というような意味で、人に何かを与えるとか何かをしてやるとかいうようなことではない。人と一緒にいて、うれしい、楽しい、と思うその感情がアロハなので、その力こそは世界で最大の力を持つとされている。
シンプルに言って、人と一緒にいて、うれしい、楽しい、と感じているとき、身体が緩んで、暖かくなる。ハートが開いて、意識が外に開いている。こういうとき、実際に身体の調子もよくなるし、人間関係もよくなる。だから、望んでいるような方向に、現実が動いていく。それは、努力して何かを与えようとするようなこととは、むしろ逆のことでさえある。
福音書の中で神の無条件の愛について書いていると思われるものには、放蕩息子の帰還の譬え話がある。これは、ルカ書にだけ書いてある。私が唯一信頼しているのは、マルコの福音書だけなのだけれど、しかしルカ書にあるこの譬えは、高次元領域をかなりリアルに表現していることからして、真実を伝えている話だと思う。
私が2006年に初めてハイヤーセルフとコンタクトしたときも、まるで放蕩息子の帰還の話そのものだと思った。神さまは大喜びして、何でもかんでも出してくれるかのようだった。キリスト教でよく言っているような、人の行動をすべて監視していて、罰しているような存在ではなかった。まるで親バカもいい加減にしろというくらいの甘やかし放題の親みたいだった。
放蕩息子の帰還の話というのは、親の遺産分けをしてもらって、財産を手にした息子が、そのすべてを放蕩に使ってしまって、奴隷みたいな暮らしまで落ち込んでいたときに、こんなことをしているくらいなら、怒られてもいいから親のところに帰ろうと思って、実家に帰ったという話だ。怒られると思ったら、父親は泣いて喜んで、歓迎した。立派な服を着せ、宝飾品も着けてやり、ご馳走を作らせて盛大な宴会を開いてくれた、という話だ。
行方不明になっていた息子が帰ってきたら、どんなことになっていたって、親は泣いて喜ぶ、という譬えなのだ。神と出会うとは、そういうことなのだと。財産を下らないことに使い尽くしてしまおうが、乞食のようなありさまになろうが、どんな放蕩をしようが、そんなことはぜんぜん関係がない。神の愛とはそういうものだ、という話だ。
ところが、キリスト教会は、放蕩息子は悔悛したから赦されたのだ、という風に解釈しようとするのだ。悔悛したから赦されたけれど、悔悛しなかったら赦されなかった、と。無条件ではなく、やはり条件付きなのだ。キリスト教会の神さまというのは、人間の親よりも了見が狭いらしい。ヨハネの第一の手紙に神の無償の愛について書いてあると言いつつ、条件だらけの話しか書いていないというのと、これも似たような話だ。
マルコの福音書には、「人の子らには、すべての罪も神を穢す言葉もゆるされる。しかし、聖霊を穢すものは永遠の罪に定められる」とイエスが言ったということが書いてある。イエスが悪霊祓いをして人々を癒やしていたら、それは悪魔の力だと、エルサレムからやってきた律法学者たちが言ったときのことだ。それに腹を立てたイエスは、聖霊を悪魔呼ばわりするようなことだけは赦されない、と言ったのだ。
マルコ書では、イエスが罪だと言っているのは、そのようなことだけだ。イエスの力は悪魔から来たとか言ってケチをつけるのは、それによって、癒やされる可能性があることを人々が信じなくなってしまうということを意味している。つまり、「神の国」を封じ込めてしまうということだ。イエスは、この世界にどんな可能性があるのかを、人々に示そうとしていた。それによって人々の意識が三次元的な物理的な次元だけに制限されるのではなく、意識の領域へと開かれていくようにだ。ところが、あれは悪魔の技だとか何とか言って、封じ込めようとする人々がいる。こういう人たちは、自分たちの宗教権威を保つために、人々が目覚めないようにするのだ。イエスが永遠の罪だと言っているのは、そうしたことだけだ。
ハイヤーセルフとコンタクトしてみたことがある人なら、わかると思うけれど、実際、高次元意識である神さまは、私たち人間が罪だとか悪いとかダメだとか思っているようなことは、すべてかわいいようなことでしかない。小津安二郎の「東京物語」の最後のところで、笠智衆演じる父親が、戦死した息子の嫁と二人きりで話す場面がある。原節子演じる嫁が、「私ずるいんです」と自分を責めて、ずっと独身でいるのがときどきとても恐くなると言っているのを、義父は彼女がかわいくてしようがない、という感じでニコニコ笑って見ている。まだ若い彼女は、自分が罪深いと思って真剣に悩んでいるのだけれど、そんなことは、年老いた義父にとっては、かわいいとしか思えないのだ。それで、義父は優しく微笑みながら、「いい人があったら、嫁に行っておくれ。そうして欲しいんだ。そうしてくれなければ困るんだ」と言う。それで、嫁は緊張が緩んで泣き崩れてしまう。
高次元意識とアクセスするのは、まさにああいう感じだ。私たち人間が罪だと思っているようなことは、本当に人間の狭い考えで思い込んでいるようなことにすぎなかったりする。だけど、神の次元になると、世界はもっとずっと多くの可能性に満ちていて、どんなことでも許されているのだ。この世界では、ありとある体験をすることが可能で、神さまはそれだけ大きな遊び場を用意してくれているようなものだ。それを、あれはダメ、これは危険、と封じ込めているのは、人間であって、神ではない。
実のところ、神の次元のその大きさを知ることこそが、神は無限の愛であるということを知ることに他ならない。無限の愛を生きるとは、それ以外のことではないのだ。これは、経験してみればわかるけれど、神が無限の愛であるということを知ったとき、私たちは本当の意味で、他の人々に対して寛容になれ、たがいに赦し合うこともできるようになる。
自分自身に対して許せないものは、他人にもやはり許せないのだ。だから、神があれやこれやを禁じていると思って、それを守ろうとビクビクしたり、守れないからと自分を責めたりしている人は、よかれと思って、他の人に厳しくしたりする。そうしていると、ますます世界の可能性が狭められて、たがいにギスギスとして、窮屈な生きにくい世の中ができていってしまう。そして、一極支配の構造は、まさにこのたがいに制限し合おうとする意識を植えつけることから、できあがっていったのだ。
ナザレのイエスの魂とコンタクトしたときに、彼のエネルギーがピンク色の光のようになって、背中から入っていって、私の心臓を包んだことに、私はびっくりしたのだけれど、彼はそれによって、制限だらけでガチガチになっていた私のハートを、温めて緩めていたのだ。そのことが、今になってよくわかる。あれこそは、私たちのハートに仕込まれていた封印を解く力だったのだということが。
2023年11月3日
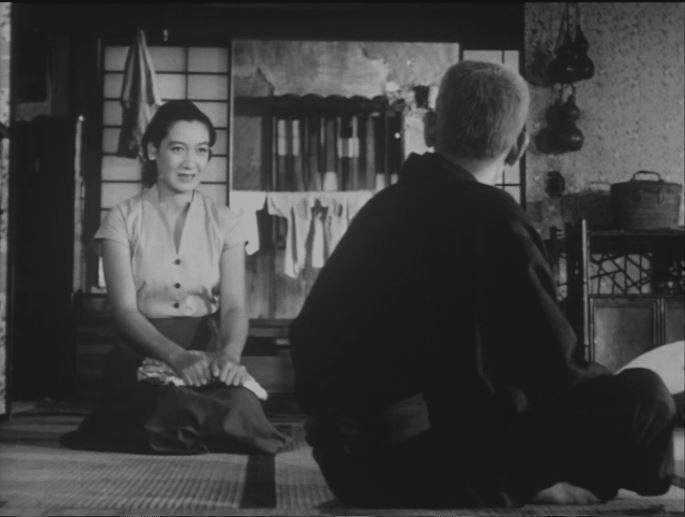

***
【愛の封印装置】
キリスト教が無償の愛を第一に語りつつ、まさに愛を封印するようなことになっているのは、実に逆説的なのだけれど、事実だと思う。そのメカニズムを見ていくと、見事にしかけられた封印装置のようだ。愛を求めれば求めるほど、愛が搾取されていくようなことになっている。
無償の愛、無限の愛、といったとき、多くの人は、自分が与えなければいけないと思うのだ。それは、地上で生身の身体を持って生きている存在には不可能だし、そもそも地上というところは、そんなことをする場所ではない。キリスト教で神と言っている存在は、生身の身体を持たないからこそ、永遠の次元に生きていて、だからこそ無限で無償だ。だから何でもできるし、すべてを知り得、すべてを持っている。
しかし、生身の身体を持って生きている私たち地上の生き物は、身を守ったり、望むことをしたり、いろいろな冒険をしたりするために生きているので、怒りもするし、攻撃したりもするし、人をからかったり、軽蔑したり、憎んだりさえする。それによってありとある経験が可能になり、ありとあるドラマ、ありとある愚行、ありとある偉業が可能になる。そして、そのすべての経験は許されている。それを可能にしているこの世界こそは、無限の愛だ。
神はすべてを許している、というと、多くの人は、自分が許されていると思う代わりに、自分が許さなければいけないと思うのだ。だから、自分を攻撃してくる悪党たちも、あの人にも事情があるんだし、とか一生懸命にかばおうとする。悪党たちの悪行が許されているのなら、悪党たちをやっつけることもまた、許されているはずなのだ。両方許されているからこそ、世界のバランスが取れる。悪党たちの悪行は無限に許して、それに腹を立てることは禁じているのなら、それこそ悪党天国ができあがってしまう。
キリスト教では無償の愛を語りつつ、多くの場合、それが見事に引っくり返されている。無限の愛ではなくて、無限の支配、無限の服従のようになっている。それが深層心理まで入り込んでいて、抜け出せない状態になっている人も、少なくない。
ナザレのイエスの死後、十字架につけられた受難の像が、無償の愛のシンボルとして、崇拝されることになった。その時点で、無償の愛というものが、神が人間に与えるものではなくて、人間が身を犠牲にして与えるものであるかのように、すり替えられたのだ。生身の人間には、無償の愛は不可能だし、そんなことをするために、神は人間を作ったのではない。その不可能なことを要求し続けるシンボルがつねに突きつけられて、すべての人はそれができないことに罪の意識と欠如の意識を負い続けることになる。そして、そのために、自分の本当の思いから離れて、善いと言われたことを何でもやろうとするようになってしまう。
4年前に奇妙なパンデミックが始まってから、支配者が政府とメディアを使って、大衆心理操作を行っていることが表に出てきた。一体どうして、こんなに多くの人々が、筋の通らないことを信じ込んで、自分の身を危険にさらすようなことをしてしまうのか、その謎解きが始まった。そこで、トラウマ療法を専門にする心理学者たちが、これはストックホルム症候群と同じ現象だと言っていた。
ストックホルム症候群というのは、ストックホルムの銀行で起きた強盗事件のときに見られた、奇妙な心理現象から来ている。強盗団が人々を人質にして立てこもったときに、人々は殺される恐怖に長時間さらされた結果、しまいに犯人を好きになってしまい、協力さえするようになってしまったというのだ。人質救助に来た警察官を攻撃したり、のちの証言でも、犯人をかばったりしたそうだ。中には犯人と恋愛関係になってしまった人もいたらしい。
生命の危険にさらされ続けると、生き延びていくために、もともとの自我を殺して、加害者の価値観に合わせた自我を作り出す心理メカニズムが働くというのだ。それによって、とにかく危機を生き延びていくことができる。しかし、その状態になってしまうと、本当の自分は消え去ってしまい、自分を支配する人間の気に入るように、何でもするようになってしまう。シェイクスピアの戯曲「じゃじゃ馬ならし」は、まさにそうしたやり方で、強情女を従わせてしまうという話なのだけれど、その結果、彼女はまるでロボットのように、何でも夫が命じた通りに無思考、無批判で従うようになってしまう。これを成し遂げた男は、鷹狩の鷹を仕込むときのやり方だと言っている。つまり、食べさせず眠らせず、生命の危機を長時間感じさせておいて、言う通りにしたら優しくする、というようなやり方だ。
パンデミックのときには、ひどい病気で死ぬみたいな恐怖を繰り返し与え続けておいて、政府がこうしろああしろと命令し始めた。それで、それに従わない人々は、大悪党みたいに扱われたのだ。それで、多くの人は、無思考、無批判に、言われたままに従うモードになってしまった。そういう状態を、政府とメディアが一緒になって、意図的に作り出していたというのだ。こうしたメソッドを使うと、人に自分の身を犠牲にするようなこともさせてしまえるし、愛する人を犠牲にすることさえさせてしまえるのだという。
これについては、イギリスの諜報機関が深層心理研究所を使って、メソッドを研究させていたというような話もあったけれど、シェイクスピアも書いているくらいだから、昔から知られた手法だったのだろう。それを思うならば、キリスト教会というものは、まさにそうした手法でできているように思える。地獄だとか受難だとかの恐ろしいイメージを絶えず与えて、無償の愛を与えろとかすべてを許せとか、不可能なことを命じて、それができないことに絶えず罪の意識を感じさせたり、すべてを犠牲にして従う人だけが、神に愛されて救われるみたいな印象を与えている。それは、ナザレのイエスが教えたこととまさに正反対なのだけれど、教会ではそれが見事に引っくり返されている。
この状態になった人が、自分を取り戻していくには、極度の苦しみを経験して、もうどうなってもいいから、自分を守ろうとする気になるようなプロセスが必要だったりする。禅宗を作った臨済は、師匠にあまりわけもなく殴られるので、しまいに師匠を殴り返して悟った、と言われている。それによって、世間がどうだろうが、まったく揺るぎない自分の意識というものが取り戻されたのだ。
私は、元夫と別居することになる数ヶ月前、心理的に責め続けられているような状態になっていて、このままこんなことをやっていたら、死ぬなと思っていた。その頃すでに、私はハイヤーセルフとコンタクトしていたのだけれど、元夫に責めつけられて死にそうな気分になっていたとき、ふいに神さまがそこに現れたことがあった。言い争いの合間に二人で黙り込んでいたときのことで、部屋には一触即発の緊張感がビンビンに漂っていた。そこに神さまは、そんな空気をものともしないように、朗らかなエネルギーを放射しながら、現れたのだ。まるで、うれしくてたまらないといったような様子が、部屋に漂っている陰惨な空気と、激しいコントラストを成していた。
そこで驚いたことに、神さまはギラギラ光るサーベルを私に差し出したのだ。これで彼をやっつけておやり、と。サーベルは実に恐ろしげにギラギラと光っているような代物だったのだけれど、神さまはそんなことは意にも介さない風だった。まるで、チャンバラごっこで負けて泣いている子供を慰めるみたいな調子で、まあまあ、いいじゃないか、これで仕返しをしておやり、と。私はさすがに怖気づいて、こんなものは受け取れません、と断った。すると神さまは、困ったなぁという表情になった。それから、これならいいだろうと、別なものを差し出した。それは、漬物石みたいな大きな丸い石だった。「それじゃ、これならどうだい? これを彼に投げつけておやり」と神さまは、子供におもちゃでも贈るみたいな調子で、そう言った。
私が受け取りかねていると、神さまはしきりに、石を投げるしぐさをしてみせる。ほら、いいから、こういう風に、やってごらん、としきりに勧めるようにだ。それで私も、神さまがそんなに勧めるんならと思って、その石を受け取った。そして、ラップトップの前に座っていた夫の頭上に意識で移動して、頭めがけて、その石を落とした。彼が椅子から転がり落ち、ラップトップが粉々に砕け散るイメージが、稲妻のような鮮烈さでパッと現れた。その瞬間、バリバリに固くなっていた私の心臓の殻が裂けたのがわかった。心臓から彼に対して激しい憎悪が湧いてきて、それが自分を守る大きな愛になったのがわかった。
すると次の瞬間、受け取らなかったはずのサーベルが、私の手の中にあることに気づいた。「このサーベル、やっぱり使わせていただきます!」と私は言うと、彼の心臓めがけて、思い切り突き刺した。これほどの怒りを自分が持っていたことに、私はそのとき初めて気がついた。そして、まさにそれだけのことを、彼にされていたことにもだ。
怒りもまた、神が私たち人間に与えたものだということを、私はそのとき初めて理解したのだ。怒りとは、私たちが自分を大事にして、その身と自由とを守るために、与えられた力なのだということを。
神さまは、私が自分の心臓を守れないでいたときに、意識上のサーベルだの丸石だのを持って来てくれた。あれこそは、神の無限の愛というものだった。
自分で自分を守れなければ、人を守ることだってできない。キリスト教会で条件づけられた人たちは、自分を守る力を奪われたような状態になっている。その状態で他の人に何かをしようとすると、愛と言いつつ、押しつけになってしまって、結局のところ、ストックホルム症候群を再生産するようなことになっていたりする。それを見ていると、これはまったく見事に作られた封印装置だと思わないではいられないのだけれど、この封印も、どうやらついに解けるときが来たようだ。
2023年11月4日


***
【罪をゆるす権威】
ナザレのイエスが、担架で担がれている中風の人に向かって、「あなたの罪はゆるされた」と言ったとき、それを見ていた律法学者たちが、罪をゆるすなどということは、神にしかできない、と批判したという話がある。それは神を穢すことだ、と。
イエスはそれに腹を立てて、「人の子は地上で罪をゆるす権威がある」と言っている。それから、中風の男に、「起きよ、床を取り上げて、家に帰れ」というと、本当にその男は起き上がって、床を持って帰っていったそうだ。
罪がゆるされたら、中風が治ったというのだから、ここで言っている罪とは、つまり病の原因になっている意識のことだと言える。中風というのは、年を取ってきたときに、中枢神経系の障害で半身不随とかになったりする、麻痺症状のことをいうそうだ。だから、何かの深い罪の意識によって、そのような状態が作り出されているということもあり得る。おそらく、イエスはそれを見て取ったので、「罪はゆるされた」と言ったのだと思う。それによって、罪の意識を取り去って、病を癒やすためにだ。そのとき律法学者が文句を言ったので、罪がゆるされたと言うのと、起き上がれというのと、どっちが簡単なのか、と言っている。つまり、イエスにとっては、どちらも同じようなことだったらしい。
ホメオパシーとかバッチフラワーとか、波動を使ったヒーリングの勉強をした人ならば知っていると思うけれど、病の原因というのは、つまるところ、意識から来ている。それは、過去の恐怖の記憶だったり、表現されないままになっている怒りの感情だったり、罪の意識だったりする。だから、その元が解消されれば、身体的な病も自ずと癒えていく。
「人の子には地上で罪をゆるす権威がある」とイエスはそのとき言っているけれど、ここで言っている「権威」とは、ドイツ語訳ではVollmacht フォルマハトとなっていて、これは委任状のことだ。本人の代わりに、誰か代理の人が書類に署名して、事務手続きをする権限のことを言っている。イエスは、すべての罪はゆるされている、と言っていたのだから、つまりそもそも神は罪などというものを設定していないということになる。だから、すべての罪をゆるしている神に代わって、あなたが思っているその罪を、神は最初からゆるしていますよ、と人に言ってあげることができる、ということになる。
英語のauthority オーソリティーに当たるAutorität アウトリテートも権威という意味だけれど、これだと、その人に決定する権限があるという意味になる。だけど、アウトリテートではなくて、フォルマハトと言っているのだ。つまり、別にイエスがこれは罪だとか罪ではないとか決めているわけではなく、神がすべての罪をゆるしているから、それを代理人として伝えているだけだ、ということになる。
弟子たちに悪霊祓いを伝授したときも、弟子たちにその権威を授けた、と書いていて、この権威もフォルマハト、委任を意味する言葉だ。つまり、神の代理で「罪はゆるされている」と言うことは、イエスだけではなくて、誰でもできる、ということになる。
イエスは、取税人や罪人と一緒に食事をしていたといって批判されたときに、健康な人には医者は要らない、病気の人に医者がいるのだ、と言っている。つまり、イエスにとっては、罪とは、病のようなものなのだ。病を治したら健康になるのと同じように、罪もまた、癒やして消し去ることができるようなものだと、彼は考えているということになる。
身体的な問題であれ、精神的な問題であれ、それは過去のトラウマが、その人のエネルギーの流れを妨げているために起こっている。それが身体的な病気になったり、あるいは犯罪を犯してしまうような心理を作り出していたりする。それが、依存症や攻撃性、盗癖や虚言癖などになって現れるのだ。それを考えれば、まったく現実的な話として、罪というものも、病と同じようなものだと言える。
ヒーリングをやったことがある人ならば、知っているかもしれないけれど、問題が始まった頃に何か変わったことがなかったかどうか調べると、だいたい何かしらトラウマになるようなできごとが起こっている。だから、その過去の精神的な傷を癒やすと、身体の症状も自ずと消えていったりする。イエスが「罪をゆるす」とか「悪霊を祓う」とか「癒やす」とか言っていることは、そうしたことに他ならないと思う。
だから、イエスが言っている罪というのは、善行を積んで贖わなければならないとか何とかいうようなものではない。当人のせいでさえなくて、病のようなものなのだ。それをもともとの状態に戻すことを、「罪をゆるす」と言っているようだ。
私がナザレのイエスと初めてコンタクトした2007年の頃、私はホメオパシーの勉強を始めて7年くらいになっていた。ヒーリングの勉強をして、実際に人をヒーリングする仕事を始めると、ほとんどの人がヘルパー・シンドロームを経験する。人を助けたいと思うあまり、相手が望んでいるのかどうかを考えないで勧めようとしてしまい、拒絶されて、傷ついたり自信をなくしたりする時期があるのを、ヘルパー・シンドロームと言っている。理解されていないように感じたり、愛を裏切られたみたいに感じたり、相手に対して支配的になったり、人によっていろいろなのだけれど、根底にあるのは、ヒーラーとしての自分がまだしっかりした軸を持てないで、相手の承認を必要としてしまっている、ということだ。
ちょうどあの頃、私はまさにそのステージにあって、愛を与えるとはどういうことなのかもわからなくなっていた。こんなに傷つくのなら、ヒーラーには向いていないのだとも思っていた。それであのとき、私はイエスの魂に、自分を犠牲にしないで愛を贈るにはどうしたらいいのかと聞いたのだ。そういうテーマについては、彼はエキスパートなはずだと思ったから。
すると彼は、卵くらいの大きさの小さな丸いものを、人に次々と手渡しているようなしぐさをしてみせた。こうやって贈ればいいのだ、と言いたいらしい。これくらい小さいものでいいのだと。そうすれば、自分が燃え尽きることなく、与え続けることができるからと。「これくらいの愛でいいんだ。人が飲み込みやすいように、丸いきれいな形にしてからね。ただ、そっと差し出すだけでいい。受け取らなかったら、放っておけばいい」
その小さな丸いものは、あの頃私が作っていた陶芸オブジェのような卵型をしていた。あのオブジェは、何となくイメージが浮かんで作っていたのだけれど、あれはイエスの目だ、とふと気づいたとき、イエスの魂とコンタクトが開けた。意識の中のイメージは、霊的な世界の深い真理を表していて、何年も経ってから、その真意が見えてくることもある。あのイメージの中で、イエスが人々に手渡していた、小さな卵型のものは、イエスが譬えで言っていた「カラシの種」のようなものだなと、ついこの頃、思い当たった。
神の国とはどんなものなのかについて、それはひと粒のカラシの種のようなものだ、とイエスは言っている。カラシの種はほんの小さなものだけれど、育つときには、まるで木のように大きくなる。しかし、種がどこに落ちるかによって、鳥が食べてしまうこともあるし、根が深く張れなくて、直に枯れてしまうこともある。藪の中で光が入らずに、大きくならないこともある。それはそれで、しかたがないのだ。それでも、条件がそろった場所に落ちたら、何百倍にも大きくなって、たくさんの実をつける。
結局私は、職業的にヒーリングをやるのは断念したのだけれど、ヒーラーとして重要なのは、種が大きくなることもあれば、大きくならないこともある、ということを、受け入れることなのだと思う。それは、宇宙の大きな力が決めているようなことなのだ。人はそれぞれの物語を生きているので、そのとき何が合うのかは、それぞれの文脈によって違う。だから、差し出したものを受け取らなかったら、それはその時季ではなかったということなのだろうし、あるいは、それはその人が経験するべき物語ではないのかもしれない。
かつてヘルパー・シンドローム状態になっていた頃、私はまだ相手のエネルギーの状態が、何を求めているのかまでは、見えていなかった。人は、ある特別な経験をするために、病を必要としていることもあるのだ。それは、健康であることよりも重要な何かを学ぶためであることもあるし、治ることが、その人の人生のシナリオに入っていない、ということもある。何かの理由で、病とともにでなければ、生きていけないような状況にあることもあるし、その病がその人が選んだ人生の去り方であることもある。
だから、それぞれのあり方を尊重するということを、ヒーラーは自分の身を守るためにも、知らなければならない。小さなカラシの種のようなものを差し出したら、それをその人がどうしようが、それはそれぞれの運命だ。人の人生を変えてしまうほどに大きな力を動かす人ほど、人それぞれのあり方を尊重することを知らないと、身を滅ぼすことになる。
実際、人間の目には、災難のようにしか見えなくても、それによって、ずっと大きなことが可能になっていることもある。そうしたことは、何年も経ってからやっとわかるようなことも多いのだけれど、世界のそういう部分が見えてくると、私たち人間がよかれと思って人に押しつけようとしていることなんか、実は人間のごく狭い了見にすぎないということが、わかってしまう。
2023年11月5日

***
【犠牲を望む神と、すべてを可能にする神】
リチャード・バックの「イリュージョン」という小説は、ナザレのイエスのような力を持った救世主が、救世主をやめて飛行機ジプシーになるという話なのだけれど、この男が救世主をやめさせて欲しいと神に祈って許されたあと、群衆のところに戻ってきて、神さまが命じたことを話すシーンがある。神さまの命令には、どんなことでも従いますか、と救世主が尋ねると、人々は、どんな苦しみであっても、神が命じたことなら従う、と叫ぶ。それを何度も尋ねて確かめたあとで、救世主は言う。「神さまは、あなたたちに幸せになるようにとお命じになりました。だからあなたたちは、もう私に頼らないで、自分で幸せになりなさい」それで、救世主は、群衆を置いて立ち去り、元いた自動車整備工場に戻っていった、という話になっている。
キリスト教会は、ナザレのイエスが処刑された十字架をシンボルにしていて、自ら命を犠牲にするような行為を称賛しているようなところがある。だけど、犠牲を喜ぶような神など、そもそも存在するのだろうか? もし、神というものが、この世界を作り出し、人間を作り出した存在なのであるとすれば、どうして人間が自分の命を犠牲にするようなことを喜ぶのだろう? 少なくとも、マルコ書で書かれているイエスが説いていた神というものは、そんな犠牲を称賛したりはしていないようだ。それに、そもそも、どんなことでも可能にすることができる神が、人間の犠牲など必要とする理由など、どこにもないように思える。
イエスは、いろいろな場面で人々や弟子たちの信仰のなさにいら立っているけれど、それは、神に何がすべて可能なのかを、人々が信じないことに腹を立てているのだ。弟子たちと一緒に舟に乗っていたとき、天候が荒れて、舟が沈みそうになったことがある。弟子たちがあわてて恐れているのを見て、どうしてそんなに信仰が薄いのか、とイエスが言っている。それで、嵐に命じると、海が穏やかになった、とある。
だから、イエスが信仰と言っているのは、神には何がすべて可能なのかを信じる、ということだ。不可能に思えるようなことも、実は可能なのだということを知ること。ところが、キリスト教会では、神がそう言ったというのであれば、どんなことでも無条件に正しいと信じて従う、というようなことを、信仰と言っているようだ。その神が何を言ったのかは、教会が決めているのだから、つまりは教会権威に絶対服従するということになる。そのことを信仰と呼んでいるわけだ。
自分の命を犠牲にして人々を救った、というような話が、キリスト者の鑑とされているというのだけど、どうもそれは違うのではないかと私は思う。神にすべてが可能だと信じるのなら、命を犠牲にしたりしなくても、奇跡が起こることの方を信じるべきなんじゃないかと思う。イエスが嵐を鎮めてしまったようにだ。彼は、弟子の誰かに犠牲になって嵐を鎮めろなどとは言わなかった。どうして信じないのか、と言ったのだ。神にはすべてが可能なのだということを信じろ、と。
ピラミッド型の支配社会は、上の言うことに服従して、認められれば、成功する、という社会だと言える。キリスト教会は、まさにそうした絶対服従の意識を人々に植えつけてきたようだ。神を信じるということが、上の言うことが正しいとして服従するようなことにつけ替えられてしまい、自分の命を犠牲にするようなことも称賛される。これは神の信仰ではなく、ファシズムとでも呼ぶべきものだ。実際、ローマ・カトリック教会は、そのようにして、歴史を通じて多くの侵略戦争を行い、そのために命を犠牲にすることを、あたかも神聖なことであるかのように持ち上げてきた。
ナザレのイエスは、不可能と思われている多くのことが、実は可能であることを示した。手をおいただけで病気が治ることも教えたし、水の上も歩いて渡れたり、パンが増えたりするということもだ。必要なときには、何でもどこからか出てくることも、示してみせた。そしてそれは、神というものが、どんなことでも可能にすることができ、私たち人間が望むことなら、何でも叶えようとするような力なのだということだ。イエスが人々に神を信じろと言ったのは、そのこと以外のことではない。
精神科医のエリザベス・キューブラー・ロスは、死についての研究をしていたために怨まれて、毒殺されそうになったことがある。顔が腫れ上がり、猛毒にやられたことに気づいたとき、たまたま壁にかかっていたイエスの肖像に向かって、「イエスさま、私は治ります」と言ったのだそうだ。すると、翌朝には腫れが引いていて、彼女は危機を脱していた。
40年くらい前に、イエスの方舟という教団が、信者の女性たちとともに、雲隠れしてしまった事件があった。メディアでは、教祖が千石イエスと名乗って、女性たちを騙し、水商売をさせていた、と報道されていたけれど、事実はまったく違っていた。家族に虐待されていた女性が、家に帰りたくないと言って、教会にかくまわれていたのだけれど、家族が引き渡せと言って教会を訴えたりしたので、皆で一緒に逃げることになった、というのだ。
多くは、家族の中に居場所がない女性たちだった。神父は、虐待されている女性たちにも、家でしっかりやっていきなさいと言って帰していたのだけれど、そうしたら自殺してしまったということがあった。それで、また教会にかくまって欲しいと言ってきた人がいたときに、もう家に帰すのはやめて、皆で一緒に雲隠れしようということになったというのだ。その神父がイエスと名乗っていたとか、水商売をさせていたというのも、メディアが作った嘘だった。女性たちは彼のことを「おっちゃん」と呼んでいた。彼女たちがナイトクラブのホステスになったのも、皆で暮らしていきたいから、何とかお金を稼がなければというので、神父が反対するのを押し切って、女性たちが働きに行ったという話だった。
犠牲になるのではなく、皆で幸せになることを目指すのならば、ありとある可能性が存在する。それを信じて、集団で放浪生活に出るという選択肢もある。すべてが可能だと信じたときに、その可能性が開けるのだ。何かの事情があって、冒険に飛び込んでいくようなことをしたことがある人なら、経験しているんじゃないかと思うけれど、そういうときには、本当にまるで神が導いているかのように、不思議なシンクロが続発して、助けられていったりもする。
「イリュージョン」の救世主は、救世主をやめたあとで、旧式の小型飛行機に乗って、アメリカ中を放浪する生活を始める。そこで、筆者に出会って、ともに放浪の旅を続けるという物語なのだけれど、それが、ナザレのイエスと弟子たちとの放浪生活と重なっている。筆者は、いろいろな奇跡を経験しながら、すべては可能なのだということを知っていく。その筆者が、コミカルな説教をしてみせるシーンがあるのだけれど、そこで彼は言っている。「あなたはあなたがしたいことをすればいいのです。マゾヒストに出会ったら、あなたは彼のお尻に焼きゴテを当ててやる必要はありません。あなたが彼にしたいことをしなさい」
それは、隣人愛を実践するべきだというので、自分の欲求を殺して、相手に合わせようとするクリスチャンがたくさんいる現実があるからなのだろう。だけど、自分の欲求を抑圧していたら、結局のところ、幸せな人間関係などはできない。自分に対してしていることは、結局のところ、他人に無意識でしていることでもあるからだ。自分の自然な欲求や感情を許していなかったら、他人にも許さないようなことになっている。その結果できるのは、利害だけで成り立つ、不自然で窮屈な関係だ。
まずは自分自身が、ありのままの自分を認め、自由であることを許してこそ、人と豊かな関係を持つことができる。たがいに監視し合い、抑圧し合うような関係ではなくて、ともに解放し合い、無限の可能性を体験する関係をだ。
リチャード・バックは、世間的なアメリカの生活をするのが窮屈で、だから旧式の複葉機で村から村へと、放浪する生活をしていた。空を飛んでさえいれば、自由でいられるからと。それは、職人としての世間的な生活をやめて、弟子たちとともにいきあたりばったりの放浪生活を始めてしまったイエスのあり方とも重なる。人を世間的な価値観に縛りつけようとする力から、絶えず逃れていくことこそは、イエスの精神だとも言える。だからこそキリスト教は、ときにアッシジの聖フランチェスコみたいな生き方を産み出すことがあるのだ。イエスの方舟事件もまたしかりだ。そこにあるのは、すべてを許し、すべてを可能にする神の力への本当の信仰だ。イエスが信じよと言ったのは、実のところ、それ以外のものではない。
2023年11月6日

イエスの方舟事件のあとで、女性たちが作ったナイトクラブ「シオンの娘」についての記事です。
***
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
