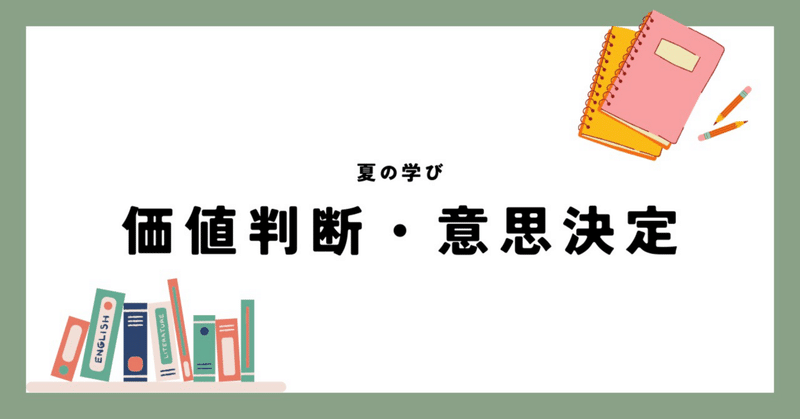
価値判断・意思決定#3 夏の学び【40】
今回も、価値判断・意思決定の学習について考えていく。
前回は、価値判断・意思決定の授業理論についてまとめた。
論争問題を取り入れ、トゥールミンモデルを使って歩み寄りながら合意点を探っていく方法を紹介した。
その他にも、政策を批判する能力を育成する学習や、提案する力を育成する授業もある。
提案する力を育成するものとして、小西(1992)「提案する社会科ー未来志向の教材開発ー」が挙げられる。
小西によれば、社会科の授業において、「〜はどこか」や「〜は何か」といった問いは、現在の事実、未知の事実を暴いていくもので、答えがあらかじめ決まっている。
社会科の教科書に載っている学習問題や本時の問いの多くは、このようなパターンのものが多いだろう。
教科書は、使う人がそのまま使うことができるように、問題と答えを対応させて、それを読めば全てがわかるようにできているからだ。
「提案する社会科」においては、事実がどうであるかではなく、あらゆる可能性を秘めた世界に放り出されて、提案を考えることとなる。
つまり、「どうすれば良いか」ということを学習者自身に考えさせるのである。
ある程度の回答の広さは許容され、子供たちが発言しやすくなることが容易にわかる。
そこでは、できる子・できない子という区別はなく、それぞれの提案が、子供たち自身の論争によって根拠を厳しく追及される。
この、論題に対して論争をするということが、価値判断・意思決定力を育てる社会科の中で欠くことのできない学習活動であると言える。
その過程の中で、多様な解釈や価値が存在することや、他の意見を吟味したり自分の意見を合理的に説明したりすることの大切さを学んでいくのである。
独りよがりの考えではダメだし、相手の意見を受け入れないのもダメだ。
合理的に説明するためには、根拠が必要で、根拠を調べるということも社会科においては大切な力だ。
未来を語ることで、社会を作ることを疑似体験し、価値判断・意思決定の大切さと難しさを実感する、とある。
自分がこれまで書いてきた「社会をつくる!社会科授業」が、まさにこれである。
こうした体験を経た子供たちが、実際の社会を担っていくように期待したい。
今回は、提案する社会科について書きました。
お読みいただきありがとうございました。
ご参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
