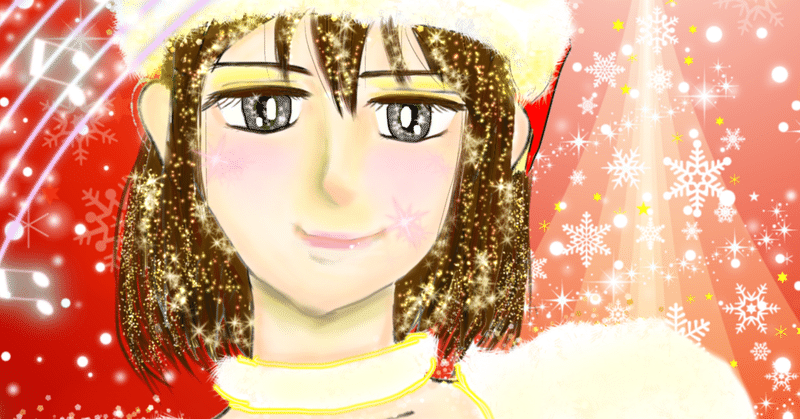
僕は君になりたい。 第22話「聖夜の夢 胸がドキドキしませんか?」
#22
その夜、僕はなかなか眠れなかった。
雨を降らした雲は既に遠く、家の外は美しい星空の安らぎに包まれているはずなのに、僕の心臓はドクドクと肋骨を激しく打ち鳴らし、体中に血液を大量に流している。
布団の中で、胎児のように背を丸めてジッとしているのにも関わらずだ。
それに、暗がりの中、目はバッチバチに冴え切っていた。
…明日、大丈夫だろうか?
今日は突然で動揺もあり、何も考えられなかったかもしれないが、明日は少し冷静になって、よく考えてみたら腹が立ち…高柳のやつ、態度を180度変えたりしないかな。
冷たくされないかな…。
そんなことばかり考えていた。
彼が一方的に僕を大事だと思ってるように見えるかもしれないが、むしろ、そんな彼が居てくれることで安心している自分がいて…
…結局、両思いなのだ。
「…やっぱり、言わないほうが良かったかな」
暗闇に独りつぶやいていると、不意に携帯電話がぶるぶると震動して何か通知がきたことを知らせた。
僕は気になって、画面を開く。
「…あ」
高柳からのメールだった。
ーーごめんな、夜中に。疲れて寝てるよな。
最初の一文を読む。
ーオレさ、まだ信じらんなくて。もう一回だけ確認させてほしいんだ。
僕は、彼も眠れずにいたことを知った。
ー流伊は、「琉唯」なのか?
ーごめんな。しつこくて…。
ーでもよ、だとしたら、オレ、お前にメロメロって、ことだよな? 好きすぎて、やばいよな?(笑)
ー朝でいいから、返事くれ。じゃあな。
時間は、もう夜中の2時を回っていた。
僕は返信を打った。
ーオレは「琉唯」だ…お前をメロメロにしてる。
ー突然すぎたか? でも、オレはちっとも突然なつもりはなくて…いつ言おうか、ずっと悩んでたんだ…。
ーま、お前には突然だったよな。
ーごめん。
ーだけど、やっぱり知って欲しかった。
ーこれでもオレはお前を信用してるんだからな!
そして、最後に、彼同様「じゃあな」と付けて送った。
ドキドキが止まらない。
また、携帯電話が震える。
そこには、ニ言だけつづられていた。
ーありがとう。お前も起きてたんだな(笑)
僕は返信しなかった。
ただここにはいない親友に電波では届かない微笑みを捧げ、布団をまた被る。
…が、やはり眠れやしないのであった。
☆
「お前、足は平気なのか?」
おはようを言った後、何となく目を逸らした僕に高柳が言った。
「…湿布は貼ってるけど、大丈夫だよ。あの後、医者に行ってレントゲン撮って、骨に異常はないって確認してる。でもまだ腫れてて痛いんだ」
「そっか…」
席に座っている僕に、まだ何か言いたげな雰囲気だったが、我慢しているようだった。
「…あのあと、眠れたか?」
僕は訊ねてみた。
「あ、うん。2、3時間は寝たと思う。流伊は?」
「…全然。オレ、今日は足痛いし、体育は見学するから」
「そうか、そのほうがいいよ」
どこかぎこちない。
腫れものに触るようなよそよそしさだ。
やっぱり、重かったかな…。
秘密を抱えた事実なんて、教えられても迷惑だろう。知らないほうが幸せなことって、いっぱいある。
彼は『琉唯にゃん』が…あんなに大好きだったアイドルが、実は『僕』という、どうしようもない現実を知ってしまった。
戸惑わないほうがおかしい。
「な、流伊。オレ、思ったんだけどさ」
「ん? なにを?」
「…オレ、憧れの女の子と、ずっと友だちだったんだな」
「ああ。そうだな、それは謝るよ」
「いや、そうじゃなくて…」
1時間目のチャイムが鳴った。
高柳は諦めて、自分の席に戻っていった。
何が言いたかったのだろう。
その後、2時間目の体育の時間、体育館の隅で体育座りをしてじっとしていると、バスケットボールが1つ転がってきた。
僕がそれを止めると、高柳が走ってきて「サンキュ」と受け取った。
「…駿、あのさ」
すぐ戻ろうとした彼を、僕は呼び止めた。
彼はくるりと振り返る。
「今日、ヒマだったら、放課後…ウチに来れないか?」
「…ん。分かった」
友人はにっこりと笑い、クラスメートたちに呼ばれて、試合に戻っていった。
☆
僕らは肩を並べて下校した。
これで僕が女装していたなら、カップルに見えるだろうか?
…我ながら、“バカな想像”だ。
それより、もし本当に僕が女子だったら、彼のことを好きになるだろうか?
…これこそ、“バカな想像”だな。
「お前、女子だったら良かったのにな。もしかしたら、璃音お姉ちゃんより美人だったんじゃねーの?」
……やはり、“バカな想像”だった。
絶対好きになるはずがない、こんなやつ。
「…ったり前だろ。それにお前の友だちにもならなかっただろうな。眼中にねーし」
「流伊が、男で良かった」
高柳は晴れ晴れとした表情で言う。
白い息が一瞬ハート型っぽくなってすぐ消えた。
僕の家に到着する。
「お帰りなさい。あら、高柳くんも一緒?」
夕飯支度中の母が、エプロン姿で台所から顔を出す。
「そうだよ。悪いけど、お茶出してよ」
「こんにちは。お邪魔しまーす」
高柳が挨拶すると、母は急に烈火がごとく早口で彼に言った。
「いつも仲良くしてくれて、有難うね。あんまり本心言わないうえ、プライドだけは高くて面倒くさい性格だけど、懲りずに、これからも友だちでいてやってね!」
「…あ、いえ。むしろオレのほうが、流伊くんにお世話になってるんで」
「そんなことないわよ〜。ね、流伊?」
僕は母を無視して、さっさと2階へ上がっていった。高柳もそれに続く。
部屋に入って、僕は鞄を机の上に置くと、詰め襟のホックを外した。折り畳み式の小さいテーブルを出して座布団を置き、座るように友人に勧めた。
僕は床に座ると足首が痛むからと彼に断り、向かい合う形で、ベッドに腰掛けた。
母がお茶と焼き煎餅をテーブルに置いて、部屋を出ていくのを待ってから、僕は口を開いた。
「…オレもな、こんなことする予定じゃなかったんだ…アイドルなんてさ…。
自分でも、何だか分かんないんだよ。
まあ…きっかけは、カオルンなんだけど。
倒れたカオルンの情報が欲しくて、中の人に聞きたい、できれば本人に確かめたいって思って、勢いで女装でオーディション受けてみたら、まさかの飛び合格しちゃって。
冗談だと思った。
けど、社長に気に入られちゃったうえ、
カオルンの後押しもあって、
…それで、まぁ、やることにしたんだ」
「…なんか、分かんないけど、すごいな」
「自分でもびっくりなんだよ」
「で、完璧主義のお前は、負けず嫌いも相まって猛練習の末、今、爆走状態なんだな?」
「…まあな」
僕は、煎餅を食べてお茶を飲む高柳のバリバリボリボリ、ズズズーという音を聞きながら、自分の湿布臭い足首を見つめた。
痛みは落ち着いてきたが、もうあのブーツは履けない…と誠さんや雪乃さんに言おうと思った。
「これから、どうするんだ? 続けていくのか? お前これからまだ背も高くなるだろ? 実際、徐々に高くなってるよな?」
「…あと、8か月で辞めるつもりだよ。高い声も出なくなると思うし」
「夏休みまでか」
「それまで、持てばな…女子で」
僕は息を吐き出した。
「大変だな」
「大変だよ…もう」
高柳は噛み砕いた煎餅を飲み下し、煎餅臭い口のまま、僕の横に座った。
「…な。足挫いたとき、焦っただろ? オレ、席後ろのほうでさ、よく見えなかったんだけど、琉唯にゃんが一生懸命謝ってたのは聞こえててさ、やっぱりいい子だなって思ってたんだけど、あれがお前だって知ってたら、もっとハラハラしてただろうなって思う。頑張れ〜って思ったと思う。お前の自分傷んでるのに『ちゃんとしなきゃ』って性格、オレよく知ってるからな」
そう言って、煎餅臭い息を吐きながら、高柳は僕の背をちょっと撫でた。
「…なあ、オレって面倒くさい性格か?」
僕が訊くと、
「はは、相当面倒くさい性格だぞ。でも、オレは好きだ」
彼は笑いながら僕に告げる。
湿布と煎餅と面倒と…。
色んな臭いが充満し、混沌とした夕暮れの締め切った窓を。
僕はどろっとぼやけた視界のまま、ぼんやりと見つめた。
☆
次の日、事務所の玄関を入るとすぐ何故か綾香が立っていた。
何か手に持っていて、僕の顔を見ると、ちょっと緊張した面持ちで近づいてきた。
「…流伊くん、足大丈夫?」
「ああ、大丈夫だよ…」
どうしたのだろうか。
いつもの能天気な感じではない。先日のイベント前の様子と似ていて、僕も少し緊張した。
「日曜日にさ、言えなかったことなんだけど…これに書いてきたからさ、家に帰ってから読んでほしいの。ここだと…みんなの目があって、恥ずかしいから。ね?」
「あ、うん…分かった」
綾香が手渡してきたのは、淡いレモン色の封筒で糊づけもしてあった。『流伊くんへ』と書いてあったが、彼女の名前は書いてなかった。その代わりなのか、封のところに大きめの桃のシールが貼ってあった。
僕は受け取った手紙を、鞄の中にしまった。
今日は未発表のアルバム曲の練習と聞いていた。
僕は仕事モードになるため、いつもの黄色いトレーナーに着替えたが、実際、4人でその曲を通しで歌うレッスンだけだった。
「琉唯。今週金曜の夕方だけどさ、顔出せるよね?」
美咲に声をかけられる。
そういえば、『クリスマスパーティー』をメンバーでやるから来いと言われていた。あまり行きたくなかったが、断れない雰囲気だった。
「ああ、行くよ」
「絶対だよ」
ドスを利かせた美咲に逆らえるわけもない。
僕は震えながら、帰途に着く。
夕食後、風呂に入って髪を洗い、ようやく寝支度したのは夜11時過ぎだった。
僕は、一昨晩に続き、またドキドキしていた。
1つ深呼吸をしてから、綾香から受け取った手紙の封を切る。
流伊くんへ
気づいてるかもしれないけど、言わせて下さい。
“好き”です。
ごめんね、我慢できなくなっちゃって…。
迷惑なのは分かってるんだ。
だから、明日からも昨日までと何も変えなくていいからね。
神永ヘレン綾香
マ、マジか…。
僕のドキドキは、加速した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
