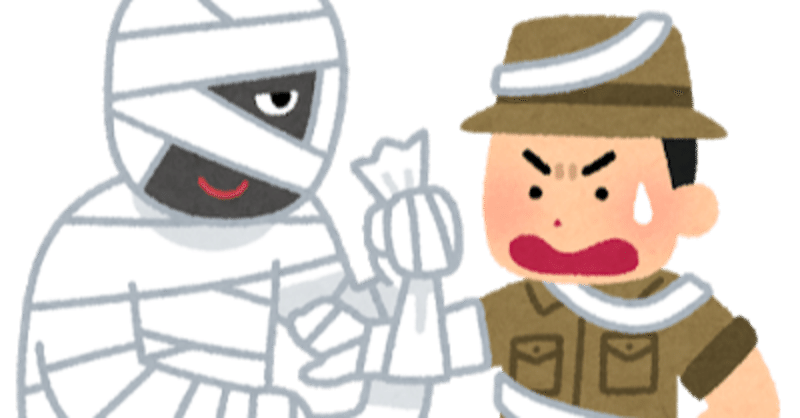
ミイラ取りは初めからミイラである
医者の不養生という言葉がある。ふつう,goo辞書のように,「人に養生を勧める医者が,自分は健康に注意しないこと」。それを聞くと,ああなるほど,まあ確かにそうだ。腑に落ちるところがある。
人に言っていても,自分に実践できないことなんてざらにある。自分を大切にするのって,意外に難しいものなのである。他者に毛布をかけることはできるが,自分が冷えているときに自分に毛布を掛けることはあまりない。「寒いなあ~」なんて言って,動くの面倒だから動きません。
厚着したら動きにくくなる。洋服だって寒がりの癖に家では薄着をする。肩が凝るから。そんな考えは浮かぶんですけど。別に,いちいちそれを考えてやっていないという訳ではない。ただ単に,患者に対して言うことを,自分に実践することは中々できないのである。
果たして,自分を大切にとは,いったいどのようなことなのだろうか。
医者の不養生,Googleで始めに検索して出てきたのは「口では立派なことを説いているが,実行が伴わないことのたとえ」と出てきた。随分の言われようだ。図星のようで,とはいえだからと言ってなんなんだと反骨精神もむくむくと湧き上がる。ムキになる気持ちは,「”人には””自分が”立派なことを説いているが,”いざ自分には”それを”実行することが伴わないこと」だと,主語が抜けていること。そして私はその主語で自分を慰めることができるのである。
タイトルに書いた,「ミイラ取りは初めからミイラである」とは,まあ,医者の不養生とやや似た言葉かもしれない。
ミイラは長時間原型をとどめている死体である(出典・Wikipedia)。また,本来の”ミイラ取りがミイラになる”とは,「人を連れ戻しに行った者が、その目的を果たさずにとどまって帰ってこなくなること。また、人を説得しようとした者が、逆に相手に説得されてしまうことのたとえ。(出典:故事ことわざ辞典)」とあった。
上記は今初めて調べたのだが,これって複数解釈できますよね?人を連れ戻しに行ったって,ミイラを連れ戻しに行ったのではないですか?丁寧に長期保存された死体をなぜ取りに行ったの?
他にも,「ミイラ取り」は,家族や大切な人を迎えに行く,墓参りのようなものなのかもしれません。実はミイラはアインシュタインのように有名な人で,その人の髪の毛一本でも取りに行ったのかもしれません。
勿論,もっとちゃんと調べれば,いろんなことが分かると思うんです。でも,別に真相が知りたいのではなくて,「ミイラを取りに行っている時点で,その人は”あの世”に行こうとしたか,お彼岸のようにお家へと招き入れたかったのかもしれません。それに故事ことわざ辞典の「人を説得しようとした者が、逆に相手に説得されてしまう」って,その通りだと思うんです。
患者に救われることもたくさんあります。自分がどんなに辛くても,環境変動しても,患者はやってきます。でもそんなとき,ミイラは一体どっちなの?
患者に説得されて,腑に落ちることも多々あります。うん,筋が通ってて,その通りだと思う。納得してしまうんです。でもそれを否定するのがミイラ取りなのか?我々は最初からミイラなんです。否定が治療とも限らないし。ただただ,理解をしに行っている。それがミイラ取りと言われるのかもしれない。
でも,ミイラはどっちなのか。傷のなめ合いをしている訳じゃないけど,そんなときだってあるんです。ミイラ取りはミイラです。ミイラ取りがミイラになっているとき,そのミイラ取りはミイラなんだと,僕は思います。
とりとめのない言葉も,今日はここまで。
kinoの雑記より
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
