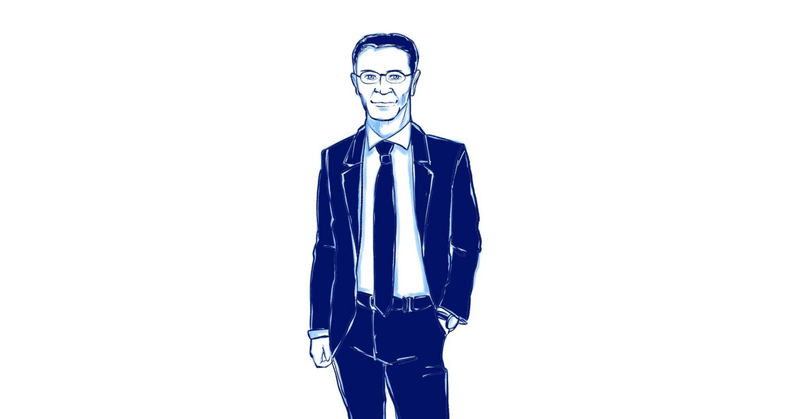
警察に囲まれた私
会社帰り。私はついにやられた。いや何のことってアレである。職質ってやつ。警官による職務質問である。久しぶりに床屋でスッキリしたあと歩いていたら、グイーンと男の顔が私の前に出現した。私は小さく叫び、慌ててワイヤレスイヤホンを外した。
「お忙しいところすみません」
生々しい見事な警察である。三十代と二十代の警察官二人が私を取り囲んでいた。
「え? あ、はい、どうしたんですか?」
私はうわづいた声で聞き返した。
「今、防犯のために警戒中でして、職務質問よろしいですか?」
やたらと冷静にこんな風に言われると、こっちも意地になる。
「えー、私にですか? はい、いいですよー」
私は即座に余裕ある態度を作り上げた。その途端ポケットの中のスマホや携帯用消毒液、定期などを差し出すことになり、黒い網状の巾着の中に保管された。その次はカバンの中である。ここまで来るともう流れに逆らえない雰囲気。さすがプロの警官である。私は力強くゆっくりと迫り来る雪崩に足をとられたように身動きがとれなくなり、あれよあれよと着ぐるみを剥がされる無力な木偶の坊と化した。
警官たちは何かを必死に探すように、私の財布やポシェットなんかを開けては詳細に確認していく。警察二十四時的なドキュメンタリーに入り込んだみたいだ。
しかし人間とは不思議な生き物である。こうした場面において頭によぎるのは、なぜか幼少の頃にやってしまった数々の記憶なのである。三歳の頃に網に入ったオハジキを出来心で盗んでしまったこと。六歳の頃に石投げで近所の家の窓を割ってしまったが、ついに謝りに行かなかったこと。中一の頃に兄のT字カミソリをこっそり使い、自らのすね毛を全て剃ったこと。エッチな本が大量に捨ててある山の奥がとても好きだったことなど、あらゆる罪悪感が次から次へと、まるで壊れたトコロテン製造機のようにひねり出てきたのである。
私の隠しておきたいデリケートな部分が、この警官たちの敏感な臭覚によって暴かれるかもしれない。
そんなえもしれない恐怖心が全身を包み微細な震えを感じた。この動揺を隠すため、私は健全な市民ぶりをさらに発揮する。
「どうぞ何でも見てってください。協力しますよー。いやー初めての経験です、これが職務質問なんですねー。頑張ります」
何を頑張るのだろうか。話せば話すほどに不審さが漏れ出てくるようで自分が嫌になった。
警官たちはひと通り調べ尽くし、その結果、特段怪しいものも無かったようだ。
「お忙しいところありがとうございました」
「はい、良かったです。ありがとうございました」
マッサージでもしてもらったかのように私は頭を下げて、初めての職質は終わった。
しばらく続く胸の高鳴りを感じながら私は考えていた。
どうして私が職質に値する人物として選ばれたのだろうか。
怪しい雰囲気だったのか? いやどちらかというと人に危害を与えない風貌であることは、自他ともに認める事実だと信じている。ならば何だ。まさか警官たちの職質数ノルマみたいな制度の餌食にでもなったのだろうか。それならできるだけ素直に従いそうな人物を選ぶだろう。合点がいく。つまり私のことをチョロク感じたのか?
そう考えると無性に腹が立ってきた。いっそのこと床屋でスキンヘッドにでもしてもらったほうが良かったのか? それなら舐められずに済んだかもしれない。いやいや、それこそ完全に職質に値する怪しい人物だ。グルグルと私の思考は空回る。
ま、どうでもいいか。とにもかくにも逮捕されることもなく、こうして私はシャバに戻れたのだ。これでいいではないか。
職質という『善良診断』は突然やって来る。そのため普段からの心がけが肝要である。間違ってもハーブティの葉っぱとか、余った片栗粉、刺身包丁なんかを忍ばせて歩くなんてことはやめたほうが良い。警官と共に小旅行へ出発する羽目になるだろう。想像しただけで冷や汗ものである。
悔やまれるのは、少々ぎこちない私の対応だ。多くの通行人の目もある大切な場面である。もっとウィットな冗談なんかを織り交ぜて、最後は握手で終わるくらいの紳士な対応で乗り切りたかった。
ようし次はもっと上手くやるぞー。危険性の無い人物であることをもっと上手くアピールしてやる。できる、私ならきっとできる!
次の職質をギラついた目で待ち望む、充分に危ない私であった。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
