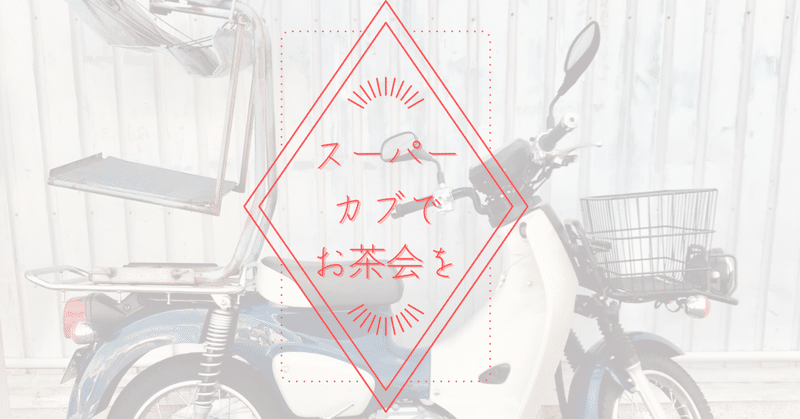
スーパーカブでお茶会を 第四話
第四話 【ムテキ・ピンク】
シロナは物持ちが良い。アカネに言わせると「余計なものまで持っている」のだが、その余計なものの中に宝物が発掘されたりするのだから、面白い。
今日もまたシロナが持ち物を入れている引き出しからポロリと落ちてきたカード形状の物体を拾ったアカネが思わず声を上げる。
「えっ……このチェキいつの?!」
「アカネの誕生日イベントの時に一緒に撮ったやつだけど正確には七年前ぐらいかな?」
「まだ新人の頃じゃーーん!」
恐らくシロナに言われて渋々片手でハートマークの半分を作らされて左右で合わせてハート型を作らされているアカネの表情は苦虫を噛みつぶしたようだったが、シロナは大層機嫌良くニコニコしていてロング丈のメイド用ワンピースの裾を軽く引き上げている始末だ。
「……なんであんたとチェキ撮ってたんだっけ……」
「ボトル入れたから」
「……あ!! そうだ!!」
新人ちゃん初イベントお疲れって意味を込めてカフェ・ド・パリ入れてツーショチェキ撮らせてもらいましたと変わらず頬を緩めているシロナは、実ははなかなかの酒豪である。
アカネが現在の店の前身でである実店舗の『Cafe Cherish』でバイトを始めたばかりの頃はシロナが一年前に入った先輩メイドとして勤務していた。その頃はシロナもキッチンだけでなく店頭にでることもあり、二人が仲を深めたのもそのような理由がある。
「てかわっかい……七年も前ならそりゃそうか」
「七年分一緒に年取ってきたってことよ」
「……いや一応設定上永遠の十七歳だからさ……」
「わたしは十七以上の数を数えられなくしているわ」
すごいでしょ、というシロナの企み顔に、はいはいと返すアカネは珍しそうに写真の中を眺めながら、ん? と気付いたような表情でカウンターの椅子に座る。
「これ誰が撮ってくれたんだろ」
「クロサキ氏じゃない?」
「いやそうじゃなかった気がする……クロサキ氏は誕生日イベントにそんなに前に出てこなかったと思うけど?」
誰だったかな……と記憶を探る様に額を擦っているアカネを無視して、店内の電話が鳴る。はいはい、と小さく呟きながらシロナが電話に出ていつものように応対する。
「はい、『Cafe Cherish』でございます。……はい、出前承っておりますが、お菓子のご希望等はございますでしょうか? ……はい、エルダーフラワーとレモンのケーキ……? あ、もちろんございます」
額から手を外したアカネは、はっと気付いたようにキッチンの方へ近づく。そのケーキをオーダーする人と言えば、心当たりがあった。
「……? まだわからない、とは……?」
「シロナ! モモちゃん先輩!」
「……モモセさん?! あ、本当だお声がモモセさんのお声……! すみません気付かずに!」
モモセは、シロナやアカネが入る頃にはすでにレギュラーメンバーの中でもベテランクラスで働いていたキッチンメイドである。そんなモモセが一番好きと言っていたのが、エルダーフラワーとレモンのケーキで、仕上がりに感嘆したモモセが認めたことでキッチンメイドとしてシロナが本格的に働き始めるきっかけになったお菓子でもある。アカネは夏場が近づいてケーキが用意される度にモモセのことを思い出していた。
「はい、お店なんとか続けてまして……ええ、はい。是非」
あ、と立て続けに記憶のドアが開いたアカネがもう一度チェキを確認する。このチェキを撮影していたのは、モモセだった。カフェ・ド・パリを片手にキッチンから出て来て『うちが撮ってあげる』と気軽にチェキ本体を受け取ってくれたことを思い出す。
店の火事騒ぎが起こるよりも数年前にモモセは卒業してしまっていたが、どこかで店を続けていることを知ったのかこうやって注文をしてきたのだろうと理解したアカネは水出しのアイスティを用意しながら同じく冷蔵庫で冷やしておいたコーディアルシロップを取り出す。
モモセはアカネの作るドリンクの中でもアイス系を特に愛好していた。最近買ったエルダーフラワーのコーディアルシロップが役立つときが来たと張り切って支度をしていると電話が終わったようでシロナがばたばたと支度を始める。
「やだもうモモセさん注文とかじゃなくって普通に連絡くれたら良かったのに……」
「モモちゃん先輩らしいじゃん、サプライズ好きでしょあの人」
「お茶はアカネに任せるって……もう支度してる」
「ま、好みは把握してますからね」
モモセは紅茶にも造詣の深い人だった。簡単な紅茶だけじゃ足りないから一ひねりと思いながら支度をするアカネに、シロナは少しすんとした顔をして小さく頷いて話を続ける。
「……そうね。アカネはモモセさんと仲良かったもんね」
その言い方にふとした違和感を感じながらアカネは支度を続ける。シロナもケーキのセッティングをしてあっという間に準備は終わる。
「それじゃあ私の分までモモセさんによろしくお伝えください」
「ああ、うんもちろん。てかシロナも来ない?」
「どうやって?」
「全力ダッシュで着いてくる」
「嫌よ! ……どうせだったらモモセさん今度プライベートで会えるようにお願いしておいて」
「もちろん」
じゃあ行ってきますとおかもちにお茶会セットを入れたアカネが出かけていくタイミングで二階の事務所からクロサキが階下へ降りてくる。
「……おや、注文かい」
「はい、前にうちにいたモモセさんが注文してくださったんですよ」
「……モモセくんか」
あの子かぁ、と顎のあたりを触ったクロサキは少し苦い顔をして深く息を吐く。
「何かありましたか?」
「いや、カノジョね、今同業他社なんだよ」
「……ってことはメイド喫茶にまだ勤めてるんですか? お店は?」
「ああ、完全に裏方に引っ込んでるからなかなか出てこないけどね、経営側にいるから」
「……え」
「なんか変なことなかったらいいんだけどねえ」
「……モモセさんに限ってそんなことはないでしょ」
私たちの先輩ですよ? というシロナの言い分に、クロサキはいやいやと首を振る。
「カノジョは食えない人ですよ」
なんせあのメイド喫茶で長年キッチンメイドを仕切っていたのですからね、女を制せられる女はなかなかいませんよと言葉を続けたクロサキは目をこらすようにアカネが出て行った扉の先を見る。
「……アカネくんが無事帰ってくることを望みますけどね」
「そんな物騒な」
「わかりませんよ? そのまま引き抜きとかあり得ますからねえ」
「……そんなこと、ありえないです」
「どうして?」
「……アカネは、アカネだからです。あの子がうちの店を裏切るなんてこと、絶対あり得ないです」
私は信じています、とクロサキと同じく真っ直ぐに扉の先を眺めているシロナを横目でチラリと見たクロサキは、若いって言うのはいいねえと呟く。
「仲間っていうのはいいもんですよ」
「そんなん、わかってますよ」
「……飼い犬に手を噛まれることもありますけどね」
それで言えば、モモセくんは手痛かった、と苦笑いをしたクロサキが二階に戻ろうと背を返す。
「……クロサキさん、モモセさんとは何があったんですか」
「なあに、『Cherish』のかつて辞めたキャストを一定の間隔を置いてダミーを仕掛けてから総取りされたぐらいですよ? カリスマ性のあるメイドの元には人が集いますからね」
新人だけに店を任せた日に火事を出すような店長には着いて来られない子たちにとってはモモセくんのような人がいいのでしょう、と一言おいてクロサキは階段を上っていく。
「……クロサキさん!」
その背中に呼びかけたシロナが、決意をするように拳を握る。
「私はみんなのことを信じてます! クロサキさんも、モモセさんも、アカネも!」
「……シロナくんはそういう優しいところが美徳だ」
どんな表情をしているか分からなかったが、クロサキは柔らかい声で話すと二階へゆっくりと上っていき、シロナはその背中を眺めていた。
*
「アカネちゃん久しぶりやんかぁ」
通された場所はオフィス内の個室、扉には『CEO’s Office』と書かれていた。しーいーおー、なんか聞いたことあるな、ぐらいの感覚のアカネにとってはニコニコと笑いながら「お久しぶりです!」と元気よく白いレースのテーブルクロスを用意して張り切る様子を見せている。
「相変わらず元気やなあ、シロナも元気?」
「はい! モモちゃん先輩に会いたいって言ってましたよ」
今度みんなで遊び行きましょ、と言われたモモセはニコニコとせやんなあと笑う。モモセは一四〇センチ台と背が低く自然と見上げるような目線になることがあって、庇護欲を誘われる。
「っていうかモモちゃん先輩今スーツなんですね、メイド服しか見てなかったから新鮮」
「せやろ~? うちもあんまり慣れへんのよ」
メイド服で社長やってもええねんけどな、と続けたモモセの言葉にアカネは準備をする手を止めてまじまじとモモセを見下げる。
「……しゃちょー?」
「うん、名刺いる?」
「ええー! 今モモちゃん先輩社長なの? すっごい、あ、しーいーおーってそういう意味か!!」
なんかニュースで言っとりましたわ! と思い出して点と点が繋がったらしいアカネが納得してテーブルの上に広げた白いクロスの上にカトラリーを並べてケーキを用意している様子を眺めながらモモセは少し唇をとがらせてから笑ってみせる。
「上達したねえ」
「まあ練習もたくさんしましたからね」
「ええメイドさんになったやないの」
相変わらずスカートもショート丈で足出してかわいいかわいい、と褒められたところでふっと振り返るとじっと見つめているモモセとアカネの目が合う。
「……なんかありました?」
「アカネちゃん何も見とらんかったの?」
「何も……って、」
呼び出された場所は秋葉原、かつてのアカネたちの勤め先でもある。雑居ビルの最上階に到達するとそこはオフィスエリアであったが、階下にいくつもコンセプトカフェがあることがあるのも当たり前だと思っていた。
「うち、このビルのお店全部経営しとるんよ」
「うっわ、すご」
クロサキ氏余裕で越えてるじゃんと呟いたアカネに、そりゃそうやでとからかうようなコロコロとした笑い声で返す。
「あのオジサマよりかは手広くやらせてもらっとるわ」
「まあクロサキ氏も頑張ってますけどね! 出前でメイド喫茶やろうって言い出したのもクロサキ氏なんですよ。ほら、Uberとか流行ってるからってメイドも配達しちゃえばいいだろって」
「単純な考えやんなあ」
「……モモちゃん先輩なんか」
おかしくないっすか、とアカネはケーキを盛り付けたあとの手を止めてじっと見つめ返す。
「モモちゃん先輩、前ならもっと面白いなあとか言ってくれたりしてたじゃないですか。なんか、こういうの違うなって思って」
「ふふ、そう?」
でも、もしかしたらみんなが変わってへんだけかもしれないなあと含み笑いをしたところでアカネはいよいよカトラリーから手を離して不審げにモモセを見直す。
小さい背に合わせてあつらえた、柔らかいピンクベージュのツイードスーツ。かわいらしい様子は昔から変わっていなかったがその中身はなにかを抱えているようだった。
「……モモちゃん先輩、言いたいことあるんだったらちゃんと言って下さい。アタシバカだし、わかんないことはわかんないんっすよ」
「……そっか、ほんなら直球はあんまり好きやないけど言うわな」
――アカネ、うちの店で働く気あらへん? という一言にアカネは唾を飲み込む。
「店も燃えて無くなって、出前でやってるなんて面白いこと試してみたって店の回転率は悪いやろ? さっさとあのオッサン見切ったらよかったのに。アカネならどこでも大歓迎やろ」
「……でもうちは金稼いで家に送らないと」
「ほんならより一層あの店で働いている意味あらへんやないの。もっと稼げるところもあるで? うちとか」
「……あとこの仕事はシロナと一緒にやっていくって決めたんで」
「あの子ももうそろそろイギリス留学するんやなかったっけ? それで考えたらそろそろ潮時なんと違うかなあ?」
「それは……自分で決めますよそれぐらい」
「いつまであの店にべったりなん。いや、二人に?」
「それは、」
アカネがかすかに声を震わせる。あの夜天が橙色で燃えさかっていた夜にシロナと二人で決意したことは、決して誰にも踏みにじらせまいとしていた。それが喩え、尊敬している先輩からの一言であったとしても。
「……モモちゃん先輩、まずはうちの仕事をおわらせましょう。ご注文のエルダーフラワーとレモンのケーキと、それに合わせてエルダーフラワーのコーディアルシロップを注いだ水出しアイスティご用意いたしました」
「あら、美味しそう。二人とも実力あるんやしせっかくならシロナも留学なんて辞めて一緒にうちの店にきてくれたらいいのになあ、」
「……まずはお召し上がりください」
「はいはい」
「返事は一回って、先輩が言うとりましたよね」
「……はい」
おおこわ、と小さく呟いたモモセがテーブルに向かい直してアカネが引いた椅子に座るとそのままケーキを一口食べる。
「ん、おいしい。やっぱシロナはお菓子の作りが丁寧やな」
「……ありがとうございます」
「アカネのお茶も……ん、良い香り。エルダーフラワーで併せてるのも香りが立ってええねえ」
「ありがとうございます……」
やっぱりより一層人材としては欲しくなったわ、とモモセは片方の頬を上げて笑う。
「うちに来てくれたらいくらでも好待遇するで?」
「いや、あの」
「本気よ、うちは」
真剣な、『経営者』としての顔でアカネを見たモモセはもう一口アイスティを飲み込む。
「破天荒に見せといて、紅茶の知識は誰よりもたたき込んである。見た目以上に正統派メイドのアカネはほんまに即戦力やし、ついでにシロナも引っ張ってきてくれるんだったら最高」
「……アタシはあの店を続けたいんです」
「じゃあ店ごと買い取ろうか? 『Cafe Cherish』として」
「それは」
「……ほら、それなら悪くはない話やろ?」
アカネは、モモセの腹の中を読めるほど現状に理解が追いついていない。ただ――度胸だけは人一倍にあった。振り上げた手をそのままテーブルの上に叩き付けて振動を起こす。
「いくら先輩だって言っても、言って良いことと悪いことぐらいわからないんすか」
「言うてあげた方がええ事実もあるで、世間には」
激しい音と振動にも応えずに、モモセはアイスティを口にしてケーキを頬張る。
「せっかくアカネにセッティングして貰えた美味しいお茶会の途中やから邪魔せんといて」
「アタシらの邪魔してんのはあんただろうが……っ!!」
ぎっ、と視線を強くしたアカネの鋭い眼光にモモセは笑顔で返す。
「脅しぐらいでどうとでもならへんで」
「違います、これはアタシの決意です」
絶対にアンタになんて店を譲ったりしない。シロナも渡さないし、クロサキ氏のことを馬鹿にすることも許さないと続けるアカネの言葉にそうか、と頷いたモモセはフォークを置く。
「ほんならもう今日はここまででおしまい。これ、もうほかしといて、」
「……残ってますよ、先輩」
「邪魔も入ったしもう十分やわ」
「出されたもん残すなんて、あんたそれでもキッチンメイドの端くれか」
「いややわ今はしがない社長やで」
もうキッチンメイドのモモセはおらんのよ、と鼻の先で笑ったあとではよかたして出て行って、と言った一言は今日いち冷たい声をしていた。
「この後すぐ打ち合わせやねん」
「……言われなくても失礼しますよ」
「まだ猶予があるから言うといてあげるけど、どっちに着いた方が後悔せんことになるかちゃんと考えてからにしたほうがええで」
「……アタシの後悔はアタシが決めます。勝手に決めないでください。それと」
絶対にシロナのことはここに連れてこない、二度と会わせないと言い残して用意したカトラリーを片付けたアカネは必要な会計を終えて素早く個室を後にする。気分は最悪で、雑居ビルの外に出るともう少しで雨が降り出しそうな曇天が広がっていた。
*
「アカネちゃんって今度紅茶の試験うけるんだって?」
「あ、はい。まだ勉強中なんで試験はまだなんですけど」
狭い休憩室のテーブルで向かい合ったアカネとシロナは、お互いにモモセの作った賄いのホットサンドを食べながら話をしていた。
「シロナさんもキッチンメイドになれるようにって今色々頑張ってるところじゃないですか」
「いやー、まあなかなかだけどね……」
アカネは茶色い表紙の紅茶の本を、シロナはクリーム色のお菓子の本を机の上に載せている。休憩中も勉強しようと黙りこくっていた中でモモセがタイミング良くホットサンドを持ってきてくれたこともあり、ふたりはようやく落ち着いて食事に向かい合えるようになった。
「おいし、」
「うん、おいしい……コンビーフとジャガイモっていかにもイギリス流でいいなあ。さすがモモセさん」
「そうなんすか?」
「うん、コンビーフって元はイギリス海軍が開発した保存食でね」
「へえ……」
シロナさん物知りっすねえ、と呟いたアカネがもう一口ホットサンドに口を運ぶ。
「……アカネちゃんはここでバイト続けてもうすぐ一年だっけ」
「はい、ちょうど誕生日過ぎてから勤め始めたんでー、次のバースデーイベントが初めてのイベントっすね」
まあでも誰がどれだけ来てくれるかわからないっすけど、と呟いたアカネをじっと見つめたシロナは、そうだ、と目を輝かせる。
「その日、私ボトル入れちゃおうかな」
「……えええ?! いやいいですってそういうの」
「いいの。お祝いは大事」
そんなことされてもお返しできないっすよ、と怪訝そうな顔つきで話したアカネにシロナは首を横に振る。
「別にそういうのはいらないの。ただね」
「はい」
「アカネちゃんとは出来るだけ一緒に長く働きたいなって思って」
「……はあ」
「ほら、新陳代謝早いじゃないコンカフェ界隈って! 私だって一緒の時期に入った人どんどん辞めちゃったし。そういうのなんか寂しいから私は出来るだけ気に入った人と長く一緒に勤めたいなあって思ってるし、アカネちゃんは努力家だからきっと長いことここにいてくれるんじゃないかなってそういうこと思ってたの!」
なんか変なこと言っちゃったかしら、と口に運んだホットサンドの耳を囓ったシロナを見てアカネはしばらくぼうっと眺めてにやりと笑う。
「シロナさん面白いっすね」
「……こっちは至って真剣よ?」
「いや、アタシもなるべく長く勤めたいっすよ。実家に送金しないといけないし」
「ああ、ご家族の教育費がとか言ってたっけ」
「それもあるし、割と色んな人と沢山話したりするの性に合ってるなあって思ってきたんで」
ここで長く勤められるんだったらちょうどいいかなとは考えていましたけれど、と話を続けたアカネはホットサンドを平らげてごちそうさまでしたと手を合わせる。
「まあでも確かに、アタシが紅茶をがっつり用意して、シロナさんがお菓子やご飯用意してくれるんだったら店としても万全じゃないっすか?」
「そ、そうよそうよ、そういうこと!」
二人で組めたらそういう相性がいいってことが言いたかった! と続けるシロナにアカネはなるほどと頷いてじゃあなおのこと勉強しなきゃだなあとウエットティッシュで手を拭いて紅茶の本を手に取る。
「……やだ。真面目」
「結構難しい試験なんすよ。受験料たっかいし」
「まあそりゃ必死になるか……」
私もがんばろ、とホットサンドの続きを食べ進めるシロナに、シロナさんだったらすぐにキッチンメイド合格出ますよと何故かアカネの方が自信満々で答える。
「……ボトル入れるけどさあ、カフェ・ド・パリ、何味が良い?」
「あれ色々ありますよね」
「やっぱアカネだけに赤色のストロベリーとかにしちゃおっかな」
「わ、そういうことしてくれるんですか」
ラッキー、と笑い合っているところで休憩室の扉が開く。モモセが顔を覗かせてニコニコとして二人を見ていた。
「二人ともホットサンドどうやった?」
「あ、おいしかったです!」
「コンビーフ久々に食べましたけどいいっすねこれ」
「せやろ~? お皿片付いてたらもう洗っちゃうから出して」
「あ、すみませんありがとうございます!」
「二人とも休み時間でも本読んで偉いねえ」
「あ、いやまあ」
「まだ勉強中の身なんで」
ねえ、と顔を合わせる二人を見て笑ったモモセは、はよ二人がベテランになってくれて店を引っ張ってくれるのがが楽しみやわと嬉しげに話す。
「二人が頑張って盛り上げてくれる頃には頃にはどんな店になっとるんやろうねえ」
「いやあ……どうなることやら」
「モモちゃん先輩もいてくださいよ?」
「まあなるだけな」
三人で笑い合っていた頃にはすでに、モモセの魂胆は決まっていたのだろうか。そう思うとアカネはやけに腹立たしくなり帰り道崩れてきた天気に思わず悔し紛れにヘルメットの下で舌打ちをしてしまうのだった。空からは間もなく、雨が降り出しそうな揺らぎが見えていた。
*
「……おかえり」
「……ありがと」
まず真っ先にバスタオルを差し出してきたシロナに会釈をして濡れた髪を乾かそうとして拭いているとシロナは着替えの服も出してくる。
「……あんたの替えのメイド服じゃん。やだよロング丈の裾踏んじゃうんだよ」
「たまにはおしとやかに過ごしてなさい」
「……はいはい」
「はいは一回」
「……はい」
何処にぶつけたら良いか分からない戸惑いや怒りを、うろうろとさせてアカネはとりあえず着替えを済ませてカウンターに戻る。おかもちからさっさと皿を取って片付けをしていたシロナは、泡の立ったスポンジで皿を洗っている。
恐らく、大半が残されていたケーキは捨てられたのだろう。と、アカネは推察してその悔しさにまた胸を焼き付けそうにさせながらカウンターの椅子に座る。
「アカネ」
「何?」
月日は様々なものを変えていく。モモセの計略も、アカネとシロナの距離も七年も経てば変わる。褪せたチェキの中で笑い合っている様子だって、遠い話だ。
「……モモちゃん先輩、結構変わってたよ」
「そう」
「しゃちょー、だって。てか、しーいーおーだって」
「……アカネ、あのさ」
「大丈夫。心配しないで。アタシまだここでやるよ」
「……」
「引き抜きも受けない。てか引き抜かせない。もちろんシロナのことだってね」
「……やっぱ被害合ってたの」
あんたがが出かけた後でクロサキ氏から嫌な話聞いてたから嫌だったのよとため息をついたシロナが皿洗いを終わらせて水栓を上げる。
「別にいいのよ、私も留学行くかもしれないしそれだったらモモセさんのお世話になった方が」
「……だってシロナが言ったんじゃん。出来るだけ一緒に長く働きたいって」
だったら最後の最後まで一緒に働くつもりだよとアカネは続ける。
「なんならシロナが留学中でも店を残すためにアタシ一人でもどうにかやるよ」
「……お菓子はどうするのよ」
「それはー……クロサキ氏に頑張って貰うとして」
「オッサンの焼くケーキかあ……」
それはそれで需要のあるところはあるかもしれない、というシロナの発言にふっとアカネは鼻で笑う。
「そうなったらいよいよ執事服着て貰おう」
「セバスチャンだセバスチャン」
二人で盛り上がっているところで、ドアが開く。外から入ってきたのは渦中のクロサキだった。
「あら、クロサキ氏雨の中何処行ってたんです?」
「ん? たまには仕事終わりにみんなでここで飲むのも良いかと思ってね」
「やだー不良店長、もうお酒買ってきたんですか?」
「そう、いいでしょう時々こんなことがあってもさあ」
クロサキがエコバッグから取り出したのはカフェ・ド・パリのストロベリー味と、マスカット味の二本。
「アカネくんとシロナくん、バースデーイベントの時はいつもこれがボトルだったでしょう」
「……なっつかし」
「あ、それだったらクロサキ氏、ボトル入れてくれましたし私たちとチェキ撮ります?」
「いらないよなんならキミたち二人で撮りなさいよ」
顔を見合わせたアカネとシロナは一気に破顔して、七年ぶりに撮るかと大笑いをする。多分、ハートマークは今なら躊躇無くできそうだった。
「チェキあったかなチェキ」
「フィルムもないと」
「ポスカほしい~」
「あ、こっちあるある」
「君たちなんでそんなにチェキ撮るの嬉しいの」
女の子ってよくわかんないねえと呟いたクロサキは、それでも今までと変わらずに二人揃っていてくれることに安堵したのか、頬を緩めて顎のあたりを満足そうに撫でていた。
「君たちは変わらないねえ」
「そうっすか?」
「うん、素直で元気の良いあの時と変わらないメイドたちだよ」
「一応七年は経ってるんですけどねえ」
さすがにそろそろ大人にならんとダメだな、とうなずき合いながらあれやこれやと捜し物をする二人は、確かにあの小さな休憩所で本を広げながら将来を夢想していた頃とかわらないような明るい表情をしていた。
<つづく>
第五話【結構毛だらけ猫灰だらけ】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
