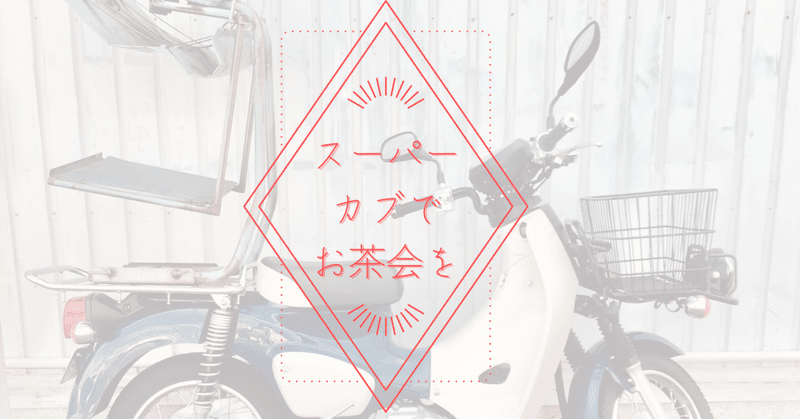
スーパーカブでお茶会を 第一話
あらすじ
本格英国菓子が売りのコンセプトカフェ『Cafe Cherish』は突然の火事により店舗を焼失してしまう。
故郷の弟妹のために仕送りを続ける必要があるアカネ、菓子作りの勉強のため英国留学を目指すキッチンメイドのシロナは窮地に陥るが、『Cafe Cherish』のオーナーであるクロサキが『出前メイド喫茶』というコンセプトを思いつき閉店寸前の中華料理屋から店舗もスーパーカブも出前機も借り受けて急遽店を続けることになる。
アカネとシロナは小さなお茶会を通じて様々な人とつながり、同時に彼女たちも様々な局面で成長や新たな将来のきっかけを手にする。
急ごしらえの出前メイド喫茶は今日も街中を走り抜けていく。(296文字)
第一話 【マリッジブルーブルーブルー】
「ねえどういうこと?!」
息せき切って走ってきた女性の白い金髪の髪の毛がオレンジ色の炎が照らされている。元より、炎のように燃えさかっている赤い髪をした女性は蹲り、地面の上を指先で握りしめている。
「……アタシらの店がっ……!」
「クロサキ氏は?!」
「しょっ引かれてる」
「みんな助かったの?」
「ご主人様もお嬢様も無事。メイド達も」
じゃあよかった、と白金髪の女性はため息をつきながら消防車に囲まれた燃えさかる建物を見る。
「今日って……」
「新人営業デー」
で、出火したって。誰も怒れなくてやりきれないよと小さく首を振った赤い髪をした女性が呟く。
「これ、もう店、やっていけないね」
「そーだね」
「……どうしようね」
「めずらし、アカネが弱音吐くんだ」
「いやだって……アタシの勤め先ってこんな簡単に消えちゃうんだって思うとあっちゅうますぎて」
「……そうだね」
「シロナどうすんの……もっとお菓子の勉強がしたいってイギリス留学の準備進めてたんでしょ? 日本での経歴だって必要だからあと一年はかかるって言ってたけど……」
「アカネだって残りの弟妹の学費出すって……」
いきなり稼ぎ口が無くなりましたとなるとさすがにそれぞれにしんどい事情も存在する。ため息にならない息が漏れて熱波の中に吸い込まれていく。
「……店やろう」
「え、」
「どのみちアタシもシロナも店が無いとダメだ。とにかくなんでもやってこの店続けよう」
「い、いやあの、アカネ? やる気があるのはいいんだけどど、でもまだ店燃えてるしさ」
「これは景気づけ! やる気の炎ってやつよ!」
さあてどうやって続けてやろうか! と腕を組んで高らかに宣言したアカネに、シロナはため息をつきつつあなたはそういう人だからねと返す。
『Cafe Cherish』の二枚看板ことアカネとシロナはいつもこうやってお互いのことを支え合っていた。
*
「はい、お電話ありがとうございます『Cafe Cherish』でございます」
午後の光が差し込む中、ゆったりと受話器を片手に電話に出るロング丈のメイド服姿の女性は白に近い金色の髪の毛を少しだけ揺らして穏やかに微笑んでいたかと思うと一瞬で表情を変える。
「大変申し訳ございません。こちらの以前のお店は閉店されまして……あの、ラーメン二つとチャーハンと仰ってもうちではそのようなメニューは……あ、はいそうなんです、そうなんですよ中華屋さん閉店されまして……はい、私たちはそこを居抜きで貰って電話番号もそのままという……ええはいあの、誤解を招いてしまいで大変申し訳ございません」
電話越しに頭を下げているシロナをカウンターの小さく背の高い椅子に座りながらアカネが肘を突いて眺めている。同じくメイド服姿だったが、高く結った髪の毛は西日を浴びて燃えるように赤く輝いている。膝丈のワンピースから出た足の膝のあたりを掻いて頓珍漢なやりとりを見ている。
「はい、ですのでラーメンは別のところにご注文を……うちではご提供出来かねますので……ええと何があるかと言いますとまずスコーンと、クッキー、キャロット……あ、はいそうですうちカフェなんです……メイド喫茶なんです……」
徐々に受け答えがしなしなと萎えていく様を眺めてにやにやとしたアカネは何かしらをメモに書き付けてシロナに見せる。
一瞬、視線をメモにやったシロナは「ばか!!」と大きく口だけを動かしてすぐに電話の受け答えに戻る。
「ええはい、つまりその、ここまででおわかりの通り、ラーメンはご用意できないので別のお店に……あ、え、なんで出前専門のラーメン屋がメイド喫茶になったか? ってそれはあの、大変お話が長くなりますが……ええっと……以前からお店をやっていたんですけれどもそこが火事になりまして閉店を余儀なくれまして、」
「貸して、」
ついに席を立ったアカネはいとも簡単にシロナから受話器を奪う。
「あ、もしもし? 『Cafe Cherish』のアカネと申しますが――うん、だからラーメンやってないんだわ、うん。あ、それはわかってんのね、おっけーおっけー。じゃああとは興味あればうちの菓子とお茶頼んでくれたらどこでも出前行くけどどう?」
シロナは安心したのと同時にぎろりとにらみ付けてアカネに詰め寄る。
「ああ、そうなの。んじゃ改めてUberでどっか好きなラーメン屋注文したってね~はいじゃあまいどあり~」
ガチャン、と乱雑に切られた電話に対してシロナは声を上げる。
「アカネ! いい加減にして」
「それを言うならアタシの方に決まってんだろシロナぁ! あんたいつまでもねちねちねちねち話して向こうの良いようにされてんだよほんっとめんどくさい!」
「お客様のお電話を無碍に切ることなんて出来ないに決まってるでしょうが!」
シロナは大きくため息をついてキッチン内の椅子に座り込む。
「……それにしてもやっぱ電話番号だけは変えておくべきだったわね、一日一回は確実にラーメンの出前頼まれてるわよ」
「その時間で本当のお客さん来てるかもしれないじゃん! あーー機会損失!」
「うるっさいわねわかってるわよ」
クロサキ氏にあとで相談しよう、と口にしたシロナはふとアカネの方を見ると少しの間を置いて、ありがと、とだけ呟く。
「……私一度電話に出るとなかなか切れないから……正直助かった」
「だから電話番アタシでいいって言ったじゃん」
「それは不安なのよ」
「なんでさ」
「言葉が乱暴」
心当たりのあるアカネはニーハイソックスとスカートの隙間をどこか心許なく掻いてみせる。ただしシロナの気の弱さも問題だと思いながら打開策を考えてみる。
「……クロサキ氏電話番にしたら?」
「いやよただでさえ狭い店が狭くなる」
『Cafe Cherish』の本来の店長であるクロサキは勝手に店員達にいじられていることも知らずに、二階にある事務所で帳簿を見比べていた。
「じゃあ自動音声で一分ぐらいずっとここはラーメン屋じゃありませんとか流すとか」
「本来の客も逃げるわよ」
「んじゃあ電話用のメイドちゃんもう一人雇っちゃう」
「人件費が大爆発しておじゃんよ」
「じゃあどうすんのよ」
「まあ……付き合ってくしかないんじゃないの? ラーメン半チャーハンと」
「ってことになるわよねえ……」
はあ、と同時にアカネとシロナのため息がキッチンに消えた頃、電子音が鳴ってシロナがいそいそとオーブンに向かう。
「何作ったの~?」
「カレンズ入りのスコーン」
「わ、」
「アカネ好きでしょこれ」
「……え、何作ってくれたの?」
「まあたまにはね」
優しい~と笑ってみせたアカネが焼きたてのスコーンに合うであろうアッサムティを準備しようとしたところでまた電話が鳴る。
「またラーメン半チャーハン?」
「しっ、静かに」
アカネのおふざけを停止させたシロナがそのままゆっくりと電話に出る。
「はい、お電話ありがとうございます『Cafe Cherish』でございます……ご注文ありがとうございます。はい、今ご用意できるお菓子ですとプレーンのスコーン、クッキー、キャロットケーキなどございますが……ああ、今ちょうど焼きたてのスコーンがございます。カレンズ、といってレーズンの仲間が入っているスコーンですがいかがでしょう? ……承知いたしました。ではプレーンスコーンとカレンズ入りのスコーンとそれに合うお茶、ですね」
お、と表情を変えたアカネが湯を沸かす準備をする。
「はい、これより参りますのでお名前とご住所、お電話番号をお願い致します」
ってことはアタシのスコーンは仕事終わりまでお預けかあとなったアカネは若干嬉しそうにしていた。やはりなんだかんだいって仕事があるのはいいことだ。
「承知しました。ではアオキ様、これより準備の上配達に参りますのでしばらくお待ちくださいませ。失礼致します」
カチャン、と受話器が置かれたところでアカネはやかんに火を掛ける。
「どんなお客様?」
「女性の方、割と落ち着いてた」
二十代後半ぐらいかな、というシロナの読みになるほどと頷いたアカネはそのまま茶葉を用意する。
アッサムティーは濃厚なコクと甘み、芳醇な香りを持つのが特徴。そのままストレートでも楽しめるがミルクを入れることで、よりその特徴を感じられると言われる。
またアッサムティーに三つのクオリティーシーズンと呼ばれている旬が存在する。セカンドフラッシュと呼ばれる夏摘みの五~六月に収穫されるアッサムティーには「モルティーフレーバー」と言う甘く奥深い芳醇で少しスモーキーさも感じる香りと濃厚で力強いコクが特徴だ。
アカネのとっておき、お気に入りのセカンドフラッシュ茶葉を出したところでシロナはかごの中に二つのスコーンを並べる。
「大丈夫よアカネ、帰ってきたあと用にあんたの分は取っておくから」
「クロサキ氏に気をつけてよ~あの人すぐ食べちゃうんだからさ」
「わかってるって」
ぐらぐらと沸き立ち始める湯に、準備を万端にしたアカネは白い丸く大きなティーポットを取り出してそこにお湯を注いで事前にポットを温める。
再び火に掛けたやかんのお湯がぼこぼこと五百円サイズの気泡が湧いてきたところで温めて多めの茶葉を入れておいたティーポットにお湯を注ぐ。ふわっと茶葉の香りが立ったところで蓋をして三分間しっかりと蒸らしながら抽出し、同時にお茶を詰め込むための大きめの赤いタータンチェック柄をした水筒にミルクを先に入れて支度をしておく。
「アッサムのミルクティかー」
「うん、王道っしょ」
抽出の終わったお茶を水筒に注ぐと熱々のミルクティが出来上がる。きゅ、と蓋を閉めたところでシロナからレースのハンカチを掛けられたかごを渡される。
「住所は携帯に送っておいたから確認して行ってね」
「わかった、ありがとう」
いってきます、と声を掛けて出かけたシロナは店の前に置かれていたスーパーカブの後ろに乗せられた出前機を開けてを渡された一式を仕込んでから運転席に乗り込む。
携帯を確認してシロナから送られてきた道順を確認し、即座によしと頷いてエンジンを掛けてスーパーカブを走らせた。
メイド喫茶『Cafe Cherish』は店舗を持たず出前営業をする店に生まれ変わった。シロナは小さなキッチンとカウンターだけがある店内で電話番とお菓子作りを担当し、アカネは紅茶と配達を担当するメイドとしてこの界隈を原付きで爆走しているのが最近名物になりつつあった。
*
ドアを開けたアオキは、ぽかんとしていた。インターフォンのビデオから相当頓珍漢な様子が伝わってきたが実際にドアを開けると本当に開いた口がふさがらない状態になってしまった。
目の前にいる女性は膝丈よりも短いメイド服を着ていて、ガーターベルトが覗く先に黒と白の太めのボーダー柄をしたニーハイソックスを穿いて足下は三ホールのドクターマーチンを履いている。
高く結ばれたポニーテールの髪は火花が散るように赤く、胸元に名札が着けられていた。いかにも相貌に合った太字のマーカーで「アカネ」と書かれたその文字に、あかねさん、と口にする。
「はい、アオキさん――もといお嬢様、ご用命いただいたお茶菓子を用意いたしました」
テーブルのセッティングをいたしましょうか、それとも天気がよろしいのでよかったらお外にでも行きませんかとアカネの提案に突如お嬢様扱いされて動乱するアオキはちらりと背後の部屋を見て誰かを入れられるような状態ではないと慌てて首を横に振る。
「外にしましょう。近くに公園が……」
一応外に出られる格好をしていて良かったと納得して靴を履いたところではっと気がつく。アカネが持っている物体は白色で塗装し直されていたが明らかに形状からして。
「おかもち」
「あ、はいおかもちです。前の持ち主のやつを使わせて貰ってまして」
「前の……?」
「ああ、玄関先で喋っていても周囲にご迷惑おかけしちゃいますから早く外出ちゃいましょう」
「あ、はい。そうですね」
アオキが貴重品と鍵と携帯電話を入れた小さなトートバッグを片手に外に出て行くと思った以上に天気が良く、カーテンを閉め切って過ごしていたことを少し後悔する。
「お嬢様、公園はどちらの方にありますか?」
「うち出て右手側に……」
アオキは公園で過ごすのが好きだった。友人が来るといつも家で過ごすよりも公園で過ごすことの方が多く、公園向かいのコンビニで買ったお菓子やホットスナックをピクニックだと言って食べていてケタケタと笑っていることが何よりも楽しかった。
マンションの敷地を出てから前をずんずんと歩くアカネがピタリと止まって振り返る。次どっち行けば良いですか、と交差点を指さされて左へ、と伝えるとそのままアカネが話を続ける。
「お嬢様」
「あ、はい」
「心ここにあらずという感じっすね」
「……そう、かもしれないですね」
「うちの焼きたてのお菓子がありますから元気出してください。カレンズのスコーンめっちゃ美味しいですから」
あとはアタシが淹れたたっぷりのミルクティー。と得意げに赤いタータンチェック柄をした水筒を持ち上げられる。
「うちのことは何で知ったんですか?」
「あ、えっと……会社の人がなんかすごい出前見たって言って。メイドがカブで配達するって……」
「あっはは、アタシの仕事中ばっちり見られてましたね」
「それでなんか気になってSNSで調べたら話題になってて……そこで電話番号も分かったんで注文してみよっかなって思って」
「度胸ありますねえ、いきなりこんなの来てびっくりしたでしょ」
「あ、いやー、」
アタシそんなにメイドらしくはないもんでと大きく笑ったアカネはすたすたと歩いていく。
「あら、あれですかね。公園」
「そうです」
「通り渡ったところなんですね」
へえ、と軽く頷いたアカネは歩調を緩めずに歩いて行く。まるで全ての道を把握しているかのようなペースにアオキは少し驚きを感じていた。通りを渡ろうとしたところで横断歩道の信号に引っかかって、少しだけ待ちの状態になる。ワンマイルウエアにトートバッグを下げたアオキと、メイド服におかもちと水筒をぶら下げたアカネが並んでいる様は周りが見たら何と思うだろうかと感じながらアオキはじりじりと赤信号を待っていた。
「アタシねえ、初めて来たところでもすぐに地理把握するのが得意なんですよ。地図見てもあっという間に目的地までの道がわかるんです。空間把握能力っつうのかなあ。出前始めてみてやっと気付いた特殊能力なんすよねえ」
お嬢様は何かへんな能力あります? と話しかけられて固まったアオキは、そうだなあ、と誤魔化しながら青信号を待つ。
「……誰かと一緒にご飯、食べるとき。美味しそうに食べてるねってよく言われるぐらいかなあ」
「それは大事なことですよ」
アタシたちにとっては最高の能力ですねと嬉しそうににやりと笑ったアカネ越しに信号が変わる。
「行きましょうか」
「そうですね」
公園にたどり着くとアカネがすぐに見つけた東屋のあたりを指さして、あそこだったらちょうどいいかもしれませんねと提案を受けて二人で歩いて行く。
少しだけ先を歩いたアカネは先に東屋にたどり着くと机の上におかもちと水筒を置き直して、おかもちから大きな白い布を取り出す。
ふわ、と広がった姿をよく確認するとレースで縁取りをされた丸いテーブルクロスで、東屋のベンチにも丁寧に一枚、クロスを引かれる。
「さあどうぞお嬢様」
白く塗られたおかもちからは茶器のセットや皿が出されてあっという間にセッティングが終わる。白い陶器に水筒からミルクティが注がれるとふわりとあたたかな湯気があふれ出して、用意されたスコーンは高く焼き上がってがばっと口を開けていて。
「……おいしそー」
「是非お召し上がりください。スコーンにはクロテッドクリームとジャムを沢山つけてから紅茶をどうぞ」
プレーンのスコーンに手を伸ばして裂け目から力を入れるとかぱっと開かれて粉の香りがふわりと沸き立つ。
「良い香り」
「うちは粉もこだわってるんで」
まあうちのキッチン担当の腕がいいですからねと得意げに笑って見せたアカネはアオキのそばについてまっすぐ立っている。一瞬破天荒に見えるがテーブルセッティングや立ち振る舞いはしっかりと訓練をされたメイドと遜色ない様子だった。
クロテッドクリームを凸凹とした表面に塗りつけてそこから更に苺のジャムを載せる。こってりとした煌めきに思わず口を近づけて歯を立てるとほろ、とこぼれて口の中にあふれる。
「ん……!」
「ふふふ、確かにお嬢様は顔に出やすいお方ですね。じゃあここで紅茶もどうぞ。アタシが茶葉から選んだダージリンセカンドフラッシュのミルクティです」
「……んんっ!」
「そうでしょうそうでしょう、うちのスコーンと紅茶は最高なんです」
満面の笑みで紅茶とスコーンを交互に食べているアオキを見て嬉しそうにしているアカネはサーブに足りていないものはなにかと目を配らせながら、笑顔でそばに立っている。
「さいっっこうです。いや、私もそこそこアフタヌーンティとか行ってますしスコーン大好きですけどけどこんな美味しいスコーン出たの初めて、え、なんっっで他のお菓子も頼まなかったんだろ!」
「まあまあ、まずは導入編ってことでね。無論他のお菓子も最高ですから是非お召し上がり頂きたいのでその時はまたお電話ください」
すぐに原チャ飛ばしてきますからと言ったアカネを見たアオキは、即検討しますと頷いて今度はカレンズ入りのスコーンに手を伸ばす。まだ暖かさを残していたことに驚いてそういえば焼きたてだと電話口で言われたことを思い出す。ゆっくりと裂け目から開いていって、湯気があふれ出してくることに驚きながら慌ててクリームとジャムを塗らずに一口食べる。焼きたて独特の香りと甘み、カレンズの甘酸っぱさ、粉のしっかりとした感覚に思わず顔が更にほころぶ。
「おいっしい……」
「カレンズはクリームなしでもいけますよね。あ、でもつけるとまたおいしさが変わるのでつけてみてください」
「そうさせていただきます」
「もっと沢山の種類をということでしたらアフタヌンティまでいかなくてもデザートプレートみたいな形でご提供するのも可能ですよ。お一人だけじゃなくてお知り合いを誘って頂いてちょっとしたパーティなんてしてもらってもいいですし。……ちょっとしたパーティに着ていける服って一体何なんでしょうねあれ」
アカネの言葉を聞いて、アオキの手がふと止まる。スコーンを更に置き直してミルクティを飲むと躊躇いがちに口を開いてもう一回ミルクティを飲む。
「いかがなさいましたか」
「……アカネさん、あの、私の話を聞いて貰っても良いですか」
一瞬虚を突かれた状態の表情になったあとで、アカネはにっと笑う。それも、仕事のうちですと胸を叩きながら。
*
アオキにはよく遊ぶ友人がいた。女友達だった。大学時代からの知り合いで、カラオケで一夜を明かしたことも何度もあったし、気がついたらアオキの家に友人が何泊もしていて友人用の下着や寝具類が置かれているのが当たり前になっていた。
天気の良い日に「ピクニックに行こう」と言ってコンビニで買った商品をこの東屋で一緒に食べていたのも女友達とだった。ほぼレタスで構成されているサンドウィッチを食べているアオキの横顔を見ながら、
「アオキちゃんは美味しいもの食べるとすーぐ顔に出るねえ」
と満足げに唐揚げ串を食べていた横顔を今でも鮮明に思い出せる。同い年なのに、甘やかすのが得意な人だった。甘えるのも得意な人だった。
一緒に居ると心地が良くて、だらだらと過ごす日々も二人でなら特別な一日になった。アオキ自身はきっと、彼女にとっての最高の友人なんだろうって思っていたけれど、アオキにとっての彼女は違っていた。
「もしかしたら恋をしていたのかもしれないです」
アオキは、二杯目を注いで貰ったミルクティを飲みながら小さく呟く。
「このまま二人で過ごせたならどれだけ良かっただろうとずっと思ってました。おばあちゃんたちになるまでずっと一緒に。でも、彼女みたいな人誰もほうっておくことなんてなかったんです」
彼氏が出来たあとも、友人はアオキとよく遊んでいた。ほーにんしゅぎだからさ、と笑っていたけどアオキはどこか疑心暗鬼だった。あえて、三人で遊んでみようと提案してみると彼氏も喜んで着いてきて、それもまた優しい人でアオキは頭を抱えるばかりだった。
「わたしばっかりドロドロした感情にまみれてて友人達はめちゃくちゃ優しかったんです。その優しいところが大好きだったんだけど――」
アオキちゃん、アオキちゃん、とカップル揃って仲良くしてくれる度にアオキの心にはすこしずつヒビがはいっていくようだった。それが悲しくて、悔しくて、距離を置こうとした時期に友人が遊びに誘ってくれて着いていくと、うやうやしく封筒を渡された。
「結婚式の招待状を、もらいました。式から出て欲しいって、いやー、驚きですよそんな……ねえ……」
私みたいなのが一番出ちゃ行けないだろって思っていたのに、アオキちゃんがいないと絶対に式なんてやらないまで言われちゃってそんな、式は二人のためのものであって私を巻き込まないでよって逆恨みしはじめちゃって……と、言い切るとアオキはまだ食べかけのカレンズのスコーンを食べて紅茶を飲む。
「それが明日なんです。雨降れって思ったのにめっちゃ晴れてるし」
「明日もお天気だし気温も高いってニュースで言ってましたね」
「そうなんですよ。絶好の結婚式日和」
一人で部屋にこもってたらどうにかなりそうで、その時出前してくれるメイド喫茶っての思い出して思わず電話しちゃいました、すみません、という言葉にそういう時こそ頼っていいんですよとアカネは返す。
「お嬢様の言うとおり好きな人の幸せな姿を見るのは必ずしも自分の幸せに繋がるとは限りませんよね」
「……」
まるで自分が幸せな彼女の姿を祈っていないようにも思えてアオキは一瞬気落ちしたが、アカネは言葉を続ける。
「お嬢様はご自分でお友達のことを幸せにしたかっただけなんですよね」
「……はい」
それはエゴだと分かっていた。決して、正しい感情ではないことも。
「だけど、お嬢様の幸せもお友達の幸せも別々に存在してるんですよね、何故ならアタシたちは他人なので。幸せが通じ合うってことは滅多にないことなんですよ。多分、奇跡みたいなもので。だから――」
そばにいられる幸せだけでも、大事にしてみませんかね。と、アカネはアオキに目を合わせて離す。
「お互いの幸せの形は違っていても、きっとそれだけなら出来るはずです」
「……はい」
そばにいるだけでも楽しかった時のことを思い出す。話をしていなくても隣でペットボトルのお茶を飲んでいるだけでもケラケラ笑えた日のことを。
「んもうどうしよっかなあ」
明日のドレス結構サイズきつめだからダイエットしてたのにこんなに美味しいお菓子食べちゃったよ、と苦笑いするアオキにアカネは心の栄養になったから平気っすよと返した。
それからは他愛のない話をアオキとアカネは繰り返していた。
「え、中華料理屋を居抜きでまるっと貰ったんですか?」
「そうなんすよ、出前専門でやっているお店があって、もう閉めちゃうからって原チャも出前機もおかもちも全部くれちゃいました。あとはキッチンを改装して」
「すっごーい、よく出前メイド喫茶って思いつきましたね」
「ボヤ通り超してガチ火事になって前の勤め先がなくなっちゃったんで、もう店持つのが嫌になったんすよ。だったら宅配系って最近はやってるしありじゃね? って。おうちや外でお茶会出来たら最高じゃんってなって」
「確かにー、すごい気持ちよくて最高でした」
「ねー、真夏と真冬と雨の日以外は外でお茶会個人的にもオススメなんですよ」
「いいですね、次も外でお願いしようかな」
「お嬢様のおうちは近くにいい公園もあるからちょうど良いですしね」
「……あの、場所指定するとかもありですか?」
「もちろん! 何処でも行けるんで」
「じゃあ別の公園にしたいな、ここから少し歩くんですけどもっと花が綺麗なところがあるんですよ」
「確かにここ、目の前がコンビニっすからね」
「そう。あと彼女との思い出が沢山あるからちょっともうここで終わりにしよっかなって思って」
「……なるほど。じゃあ次は別のお菓子と一緒にお花を眺めながら、ですね」
一通り片付けられたテーブルの上の中身をおかもちに全部しまったアカネはではそろそろと声を掛ける。アオキは言われたとおりの金額を支払ったが額面よりもずっと満足度が高い時間だった。
「……アカネさん、私最初なんか変な人来ちゃったなあって思ってたんですけど」
「あ、よく言われるんで慣れてます」
「でも来て貰えてすごくよかったです、ありがとうございます」
今度もまた楽しみにしていますねと笑ったアオキに、アカネももちろんと笑顔で返す。駐車場に停めているスーパーカブの背面にはかわいらしい文字でこう書かれていた。
【うれしいとき、かなしいとき どんな場所でもメイドがお茶会を開いてあなたのお話伺います。
Cafe Cherish TEL 〇三ー○○○ー○○○○】
「すごい広告ですね」
「そうなんすよ、おかげでいたずら電話も沢山」
「じゃあ私はみんなにちゃんと宣伝します」
「ありがとうございます!」
じゃ、お嬢様様とアオキに向き直ったアカネが深々と礼をする。
「毎度あり!」
「……メイドがそれでいいんですか」
「前の店からの売り文句なんですよアタシの」
一応破天荒キャラでやらせてもらってましてね、と話したアカネはそのまま駐車場の会計を済ませてスーパーカブへ乗り込む。
「またのご用命をお待ちしております!」
「是非!」
「あと! ……明日、いいお式になるといいっすね!」
「……はい!」
満面の笑みで返したアオキに安堵したアカネはそのまま駐車場を出てスーパーカブに乗りこみエンジンを掛ける。いつまでも、アオキは見送ってくれているのをサイドミラーで確認しながら最初の曲がり角を右折したタイミングでふっと心が柔らかくなったことを感じていた。
アカネがこの仕事をしているのは弟妹のために金を稼ぐ云々を別にしても、人の話を聞けることを愛しているからだった。本格的な英国菓子を提供するコンセプトカフェとして運営されていた以前の店に勤めている頃からゆったりとした時間の中でご主人様やお嬢様たちが話をしてくれることに耳を傾けることが好きで、自分なりの答えを返すことで人がまた立ち直ってくれることに、ちょっとした達成感を抱いていた。
もしかしたら、この職業向いているかもしれないなと気付いてからバイト気分から正社員になるほどまで長いこと勤めるようになって、事業主となった『十七歳を八留した程度の年齢』の今でも、ニーハイソックスは忘れずにチャームポイントとして残している。メイドととしての心得は忘れてはいないが、さすがに猫耳などをつけたりするのはきつくなってきたところだ。まさか、それが簡単に火事で失われることになるとは思いもしなかったが。
ところでカレンズ入りのスコーンはまだ残っているだろうかと不安に思ったアカネはもう一段ギアを入れて早めに帰路につく。シロナはきちんとそのことを分かって、クロサキ氏の分とアカネの分をそれぞれに取っておいてあることを連絡していたが、そのことはまだ携帯を確認していないアカネには伝わっていなかった。
<つづく>
第二話 【ミセスイエローの審美】
第三話【ラブオブザグリーン】
第四話【ムテキ・ピンク】
第五話【結構毛だらけ猫灰だらけ】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
