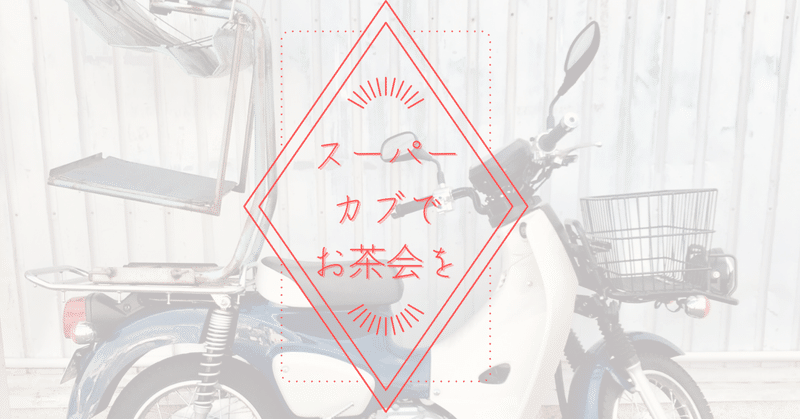
スーパーカブでお茶会を 第三話
第三話 【ラブオブザグリーン】
「……今日は出前来るかねえ」
「雨の日は逆に増えるとかいうけどね、ピザ屋さんとか」
「人間、残酷すぎない?」
中途半端な時間に取った休憩時間を持て余していたアカネは、シロナが作った賄いのオムレツを挟んだサンドウィッチを食べながらぼうっと外を眺める。ざあざあと降り注ぐ雨ではなく周囲の景色をぼやかせる小糠雨、原付を走らせていると気付けばじっとりと濡れているタイプの雨だ。
もう一つ食べようかとしたところでアカネの携帯が鳴る。慌てて手を拭いて着信主を確認するとすぐに指をスライドさせて電話口に出た。
「もしもし? なじら? ……ああうん、うん、そう、確認出来た? わざわざ連絡してありーがとうね。こっち? 今雨だすけ、そっちは? 今日晴れてる? あらーそいだらいがったけど。はい、はい、わかった。こっち雨でさーみからさ、うん。外出るとき気をつけるわ。うん、じゃあまた。はい、はーい」
電話の様子を見ていたシロナがじっとアカネのことを見ていてアカネは思わずなんだよ、と素で返す。
「いっつもアカネと実家の電話ってすごいなあって思って見てるのよ……ほら私東京生まれだからそういう方言ってないし」
途中でDas Gemeineみたいなところあったけれどあれなに? と聞かれて脳内で再生させたアカネは
「だすけ……は、~だから、みたいな感じかな」
と答えるとシロナはすごーい太宰の小説のタイトルみたいときゃっきゃとしてみせる。
「別にアタシの実家は方言キツい方じゃないよ。青森とかさ、訳せないレベルじゃないわけだし。新潟はそんなに訛らない……はず」
「まあ確かに聞いてたらちょっとはわかるけどいやでもやっぱり家族と話しているときのアカネってなんかいいわ。なんかの用事でもあったの?」
「いや、仕送り届いたって連絡。それぐらいLINEでいいんだけどね」
「わざわざ電話してありがとうって伝えてくれるご弟妹でよかったじゃない」
「うちはもう弟妹で寄り合うしかないしさ」
シロナは、アカネの家庭事情を知っている。元より母だけで育てられたアカネは自分が高校を卒業したら家計を助けるためにすぐに就職する予定だったのが、就職先が経営の都合で急に採用を取りやめた結果手っ取り早く稼ぐために東京に出て来たという経緯がある。
「知ってる? 新潟県民の上京率って日本一らしいよ」
といつぞやかアカネは語っていた。自分が故郷を離れたことを悔いているのかどうなのか、東京で生まれ育ったシロナにはよくわからない。
ただ、東京以外に帰る場所があるのはうらやましいな、と思う。実際にアカネが実家に帰ってきたあとはたくさんのお土産と弟妹の話で盛り上がっていてそれは『故郷がある人』特有の幸せそうな表情だったからだ。
故郷があるというだけで、帰る場所があるというだけで。東京以外の場所が受け入れてくれるというのがシロナにとっては未知の領域で、その安心度は想像もつかない。
「いいなあ、帰る場所があるってのは」
「シロナも実家あるでしょうが」
「数駅離れてるだけだよ」
シロナはアカネと比べて一人っ子で過ごしていたので周囲に兄や姉、弟や妹がいるという環境も慣れていない。家に帰れば母と父が待っているだけの数駅先の実家。長旅でもなければ情緒もない。
きっとアカネにいったら『それは望郷ではなくて旅情だ』と鼻で笑われてしまうだろうなあと思ったのでシロナは黙っていたが、確かにその気持ちは旅情にも近いものがあった。
「今度私も新潟連れて行ってもらおうかな」
「なにもないよ。あ、うそ、水族館がある。むしろ水族館ぐらいしかない」
でもご飯は美味しいからいつの時期に来てもオススメ、と念を押すように言ったアカネはふっと視線をそらした。
「どうしたの」
「……そと、ひといる」
「人? ……あら、こどもじゃない」
ニスを塗り直した深い色をしたドアの向こう、雨宿りをしているのかそれとも甘い香りに吊られたのか幼い兄妹がガラス越しにこちらを見ている。ぱっと見たところ周りに保護者はいないようだった。
「……」
「どうする?」
「……開けてみようか」
ゆっくり、近づいてアカネがドアを開けるとベルが鳴る。からん、ころん、と言う音に驚いたのか少しドアから離れた兄妹はアカネのことをじっと見る。
「こんにちは」
「……こんにちは」
「雨宿りしてたの?」
「うん、あといいにおいした」
「ここでケーキやクッキーを焼いてるんだ」
「けーき!」
「お母さん一緒にいる? よかったらおいで」
「……」
「……おかあさんいない」
「――え?」
「おかあさん、夜遅くにならないと帰ってこないから」
「そ……っかあ」
シロナが追って店の前に出ると、兄妹はまた目をあちらこちらへと動かす。
「ふたりともおやつあるからおいで」
「シロナ、」
「いいよ。今日は雨でお客さんもいないから」
小さなお客様ならうちのカウンターでも大丈夫でしょう。と二人を案内して椅子に座らせる。
「アカネ、お飲み物用意して」
「ああじゃあえーっと……二人ともココア飲む?」
「のむ!」
元気な返事に安堵しながらアカネはどこかたどたどしく支度をする。アカネも同じように、母が遅くまで帰ってこない中で生活していてあんな風に店の軒先で雨宿りをしていた日があったことを思い出していた。その時はこんな風にやさしく迎え入れて貰えなくてすぐに追い出されてしまったなあとココアの粉に砂糖を加えて練りながら準備をしていると興味深そうに兄妹はのぞき込んでくる。
「ココア作るの、見たの初めて?」
「うん」
「こうやってねえ、しっかり練って火を通すと美味しいココアになるんだよ」
「へえ……」
「二人ともクッキーすき?」
「すきー!」
「じゃあ今日はクッキー出してあげるね」
予想外だったのはシロナの動きだった。一人っ子で育っていたことをアカネは知っていたからむしろこどもの扱いなんかには困るだろうと勝手に思っていたのだったのだが、アカネよりもよっぽど自然に兄妹のことを受け入れていた。
もしかしたら下手に先入観抱いてしまったのは自分の方だったかもしれないな、と思いながらアカネはココアを火に掛ける。ゆっくりと牛乳を入れて、徐々にココアの粉を溶かしていった。
帰らない家族を待つ間はいつも心のどこかが空虚になっている。もしかしたら一生戻ってこないのじゃないか、そうしたらアタシが他の弟妹をどうにかして面倒を見て大人にしてあげなきゃいけないのじゃないか。アカネは、小さい頃から強迫的に感じていたところがある。家族がいないと生きていけないのは、実を言えばアカネの方なのかもしれなかった。
クッキーを先に食べている兄妹はおいしいねと言い合いながらその小さい口を動かしている。いつかあったかもしれない光景に思わず泣きそうになるのを堪えながらアカネは少しぬるめに仕上げたココアを注いであげて二人に、あついから気をつけてとコップを手渡した。
「……アタシこんなおやつ食ったことなかったなー」
「今食べてるじゃない。嫌ってほど」
「小さい頃の思い出ってやつ」
「逆に言えば私は母親が頻繁にお菓子作ってくれたからなあ……これが普通って言うか」
自分が与えられる優しさは、与えられただけの優しさで出来ている。シロナは満たされて育っていたから自然とそう振る舞えるのだと思うとアカネは自分の中で育ちきっていない足りないところに気がついてしまう。
アカネにとっては、傷と向き合うような一時だった。ただ待つことしか出来なかったこどもの頃の自分と、二人の様子がダブっているような気がして、幸せそうにおやつを食べているところを見ると嬉しさと悲しさが渦巻いてしまう。
「……もしもおなかすいたときとかあったら、」
今度はすぐにドアを開けて入ってきて良いよ、とアカネが小さく話しかけると、シロナも頷いていつでもご馳走するよと微笑みかける。
「クッキーの他に何がすき?」
「ケーキすき、いちごの」
「……英国菓子はお子様にはまだ早いかねえシロナさん」
「……かもしんないわね」
でもキャロットケーキとかなら健康にはいいわよ、多分。という一言に二人は顔を見合わせてふと苦笑いをする。雨はそろそろ止みそうになっている。もうすぐ虹が見えることかもしれない。兄妹はそんなことに気付かずにぱくぱくと忙しそうにクッキーを食べてはココアを飲むのに夢中になっていた。
*
『この度は大変お世話になりまして……』
念のため、と持たせた店の名刺に書き添えた【雨が降っていた時に店先にいたので雨宿りをして貰いました。おやつも大変元気よく召し上がっていました】という一言にきちんとお礼を伝えてきたのは、あの兄妹の母親で、ミドリカワと名乗っていた。
「とんでもないですこちらこそ……お帰りになってから気付いたんですがアレルギーなどは大丈夫ですか?」
『二人とも主なアレルギー食材はないので……』
「そうだったんですね、それはよかった」
『帰ってきてから二人とも、お姫様達がクッキーくれたって大騒ぎしていてなんのことか全く分からなくって絵も描いてくれたんですけど……お名刺頂けて大変助かりました。こちらの都合でご連絡遅れてしまい申し訳ございません』
「いえ、全くお気になさらず!」
『そちらは喫茶店……? なんでしょうか』
「いえ、店は小さくて店舗営業をしていなくって……代わりに出前を中心にやってます」
『でま……あ、本当だ出前メイド喫茶って書いてあり……ますね』
そっかだからお姫様みたいなって言って……という納得感にホッとしたように息を吐いたのが伝わってきた。
「いつでもお茶会の準備は出来ますのでよろしければご用命くださいね」
『出前? え、出前でお茶やお菓子を運んできてくれるんですか?』
「はい、お電話を頂けたらどこにでも駆けつけます」
『お茶会……なんかすごい縁遠い言葉すぎるなあ』
うちは母子家庭で、最近全然余裕もなくって、と苦笑い気味に話す受話器の向こうにシロナはそっと話しかける。
「お疲れの時こそ、お茶とお菓子でゆっくりするのが一番良いですよ」
『……いいなあ、そういう一日過ごしてみたいなあ』
「……これは勝手なご提案なのですが」
と前置きをした上でシロナは話し始める。
「ご兄妹はこちらの店に遊びに来て貰ってお母様はお一人、ご自宅でゆっくりとお茶とお菓子を召し上がるのはいかがでしょう?」
『それは……』
こども達にも申し訳ないだとか、自分がそんな贅沢をしてはいけないだとかそんなことが頭を過ったのだろう。母親は思わず声を止める。
「きっと、お母さんが少しでも楽しくなれたらお子さんも喜びますよ」
『そう……でしょうか』
「勿論です」
『あ、でもそんな、人が来れるような家でもないし……』「うちのメイドは些末なことは気にしませんので」
『……』
「あ、もちろん! 強制ではないのでミドリカワ様が気になったらで良いのでいつかまたお電話くださいませ」
『……はい。この度は重ね重ねありがとうございました』
深々と礼をしたであろう間が空いて、それでは失礼しますと電話が切られる。様子をうかがっていたアカネはどうやら話は穏便に済んだらしいことを理解して胸をなで下ろしつつカウンターに座り直した。
「怒られなくてよかったね」
「まあそうね」
「しっかし、まさかシロナが積極的に営業するとは思わなかったな」
「……え、どういうこと?」
「いや、もし良かったらご兄姉はこちらの店に~って」
「ああ……なんか切羽詰まってる感じがしたのよ」
私が聞いていて、ね? と前置きをしたシロナに納得するようにアカネも頷く。
「余裕がないというか、その日その日生活するので精一杯というか」
「まあ母親はどうしてもそうなりがちだよね。うちの親もそうだった」
「なんか……助けてあげられないかなあって思っちゃったのよ」
シロナはどちらかと言えば理性的な人間だったがたまに人に対して懇意にしてしまうことがある。持って生まれた優しさのせいだとアカネは思っているが、アカネは逆にこういう時になると一歩引く癖がある。自分では助けられる範囲が限られていることを理解しているからだろう。
どちらが言い悪いでもなく、ただ考え方の違いだとアカネは理解している。だからこそシロナが急にあの家族に踏み込んだことが唐突でかつシロナだからこそ出来る提案だと思って耳をそばだてていたのだった。
「出来ること、って限られてるわよね」
「そりゃそうだよ。アタシたちの腕なんて広げて二人抱えられるかどうかぐらい」
「大きくなったら世界を救えるかもなあなんて思っていたはずなのにね……」
「うわ、めっちゃ良い子」
「いや、こう、魔法少女的なね?」
「そういうやつね」
大人になれば、自然と身につくと思っていたはずの強さはなかなか一朝一夕には手に入れられないもので、気付けばまだまだ戸惑うことばかりの自分たちにふと嫌気が差す瞬間もある。
「……まあいつかみんな揃って来て貰えたら良いね」
「そうね」
アカネもシロナも、その日は穏やかにやってくるだろうと信じていた。だがそれは突然に、落雷のようにやってくる。
数日後、もう看板を仕舞おうかという時間に、ドアをどんどんと鳴らす音が聞こえる。慌てて外に出たアカネは真っ赤な顔のまましゃくり上げて、妹を守るようにして抱きしめている兄がいた。
「……どうしたの」
「おかあさ、おこって、もうでてって、って」
「……」
「どしたの……あら」
「……二人とも、おうちの住所わかる?」
「アカネ、」
「行ってくる。多分今一番やばいのはお母さんだよ。シロナ、二人のこと頼んだ」
泣きじゃくりながらも兄は自分の手持ちの荷物をみせてくれて、緊急連絡先の書かれたメモを確認したアカネは慌ててパッケージされたお菓子を手に取って、シロナが個人的なおやつとしていくつか用意していたチョコレートを手持ちのトートバッグに入れる。原付で行かなくても走って行けばすぐの距離だったが、子供にとっては途方もない距離だっただろう。
「大丈夫、お姉ちゃんがお母さんと話してくる」
「二人はお母さん戻ってくるまでこっちでおやつ食べよう? あったかいミルク飲む?」
シロナが案内してくれたことを背後に感じてそのままアカネは駆け出す。革製の厚底のメリージェーン形の靴を履いているとは思えないスピードで、夕暮れの街をアカネが走って行くのを見て、街の人は珍しそうに眺めていた。
頭の片隅に残っていた住所から、近所の地図をつなげてたどり着いたのは古ぼけたアパートの前だった。必死で息を整えてから階段を上る。かつん、かつん、と鉄骨むき出しの階段と靴底が当たる音は懐かしく時に耳障りだった。
部屋番号のドアの前でしばらくアカネは佇む。自分がしようとしていることは間違っているのかそれとも、ぐっとこぶしを堅く握りそのまま正面を見た瞬間に、がたんとドアが開く。
ドアから現れたのは、何もかもを投げ捨てて慌てて外に出ようとする女性で、あまりの勢いの良さでアカネはその女性を思いっきり抱きとめた。
「なにっ、なにすんの、こどもが!」
「ミドリカワ様、ですよね? 『Cafe Cherish』の者です! 今お子様達は揃ってうちの店で休んでます!」
「え、……あ……あの、この前の……」
「はい、出前メイド喫茶の者です」
こんな説得力の無い格好ですみません……とアカネが話すと女性は呆然とした様子でいいえ、と首を振ってずるりと力を抜いてアカネにしなだれかかる。
「あ、あのこたち、無事ですか」
「はいもちろん、今この前電話で話していたメイドがお世話をしています」
「それなら……それならよかった……」
ごめんなさい、私が怒って二人を追い出したのにこんなワガママ言って……と徐々に涙声になっていく女性を改めて抱きしめ直したアカネは、今度は真正面からその泣き顔を見る。
泣きじゃくる顔は、母も子もそっくりだった。
「……あの、お母様。よろしければこれからすぐに店に行くのではなくて、おうちで少しおやつを食べてからにしませんか?」
「え……」
「いつもみたいなちゃんとしたお菓子は用意出来なかったんですけど、とにかく甘いものを食べましょう。そんで冷静になりましょう」
「でもあの子達迎えに行かないと……」
「大丈夫です。きっと二人にもゆっくりする時間が必要です。何よりお母様、あなたが一番ゆっくりしないとだめですよ」
紅茶、淹れて来られなかったので今日はホットチョコレートでもいいですか? と尋ねると女性は、一番好きな飲み物ですと泣きながら答えた。
*
小さな台所の、小さな鍋を借りてアカネはホットチョコレートを作った。とは言っても特別なものではない。温かくした牛乳にチョコレートを溶かしただけの単純な甘みのある飲み物だ。キャラクターの描かれたマグカップに注いだホットチョコレートを手渡すと、女性はすぐに一口飲んだ。
「……おいしい」
学生時代、よく行っていたケーキ屋さんの喫茶室でホットチョコレートが出てたんです、美味しかったなあ、あの時の味がするなあ……と懐かしむように何度も繰り返してもう一口飲んだ。
「うちのクッキーです。二人も大好きで沢山食べてくれたんですよ」
同じくキャラクターの描かれたお皿に広げたクッキーはアイスボックスクッキーで、シロナが細工を凝らした模様が綺麗に浮かび上がっていた。
「おいしい、ですね」
「はい、うちのキッチンメイドが毎日張り切って作ってますから」
「ああ、そういえば昔こういうの作ろうと思って失敗しちゃったなあ……母親と一緒に作って上手くいかなくってあまりにもひどかったからゲラゲラ笑っちゃって……」
母親は、母親である前に一人の女性で、一人の子供だ。彼女はそれを気付かぬうちに忘れてしまっていたのだろう。思い出を取り戻すように何度もクッキーとホットチョコレートを行き来する。あっという間に食べ終えると、女性はふう、とため息をついた。
「お仕事、大変だったんですか?」
「あ、はい、最近シフト増やして夜勤に入れさせて貰うこともあって……」
「そうだったんですね、それは疲れちゃいますよね」
それぐらい必死だったんですよね、とアカネが横に座って見つめ返すと女性はまたはらはらと涙を流してしまう。
「でもあの子達、あんなに責めちゃったら一生懸命働く意味なんて……」
首を振る女性に、そんなことはないですよとアカネは手を取る。
「みんな生きているだけで一生懸命なんです。子供も、大人も。一生懸命だからぶつかっちゃうんです」
自分の母親が朝も晩もなく働いていることはアカネは知っていた。だから自分の求めるときに母親がいないことも仕方ないと諦めていたし、泣いている弟妹をたしなめるのがいつものことだった。
夜中に目が覚めたタイミングで、聞いたことのない母の泣き声を聞いたことだってある。アカネは、大人はそうやって我慢をして生きているのだと理解していた。
「……アタシの母も、アタシと弟妹のことを女手一つで育ててくれました。朝晩ずっと働いてひどい無茶をしてたのもわかってます。多分、子供は大人が思っているよりもずっと頑張ってるってこと知ってくれていると思います」
だから、たまには子供に甘えても良いと思います。と、アカネは話を続ける。アカネは、自分に甘えてくれない母のことがあまり好きじゃ無かった。弱さを見せないようにする姿は、大人としてのプライドだったのだろうけれどそれは子供にとってはもどかしいものでもあった。
「人間ってきっと誰かを助けたいように作られてると思うんですアタシ、それって母親だろうと子供だろうと関係ないって思ってて」
アタシ、出来ることだったら中学から働きたかったし高校も行く必要ないって思ったけど母親が反対したから仕方なく行って。今こうやって働いているお金はほとんど家族の仕送りにしてて、それで十分だと思ってて。
「早く大人になりたかったんですアタシ、じゃないとみんなのこと助けらんないから……っ」
おい、こっちが泣いてどうすると冷静な自分が突っ込むよりも先に、アカネの頬を涙が伝っていた。
「多分……ご兄妹もきっと、そう、思ってます……思っている、はずです」
結局、アカネと女性は二人で向き合ったまましばらくしくしくと泣き合って窓の外がとっぷりと暗くなる頃まですごした。
その時間を切り裂いたのはアカネの携帯の着信音だった。
「あっ、すみません携帯……ああ、シロナだ……あ、うちの店の者です。すみません失礼します」
『もしもし? アカネ大丈夫?』
「大丈夫。お母様とも話せた」
『……やだ泣いてる?』
「ないてねーし!!」
メイド服のエプロンで雑に涙を拭いたアカネは震える声を止めようと努めていた。
『もうこっちは二人とも疲れて寝ちゃったよ。二階クロサキ氏の事務所にあるソファで寝かせてる』
「そっか、じゃあお迎え……いきましょうか、ね」
『うん、二人とも待ってるよ』
だから早くおいでとシロナは優しく話しかけてくれる。ああこの人がビジネスパートナーでよかったなあと心から思いながら着信を切って女性に手を伸ばす。
「行きましょう、『お母様』。お子様たちがお待ちです」
「……はい」
互いにうなずき合った二人は食べ終わった皿とコップを片付けてそのまま家を出る。鍵を閉めるところでちりりとなる鈴の音がして、そういえば母親もつけていたなあと思い出して懐かしさでまた泣きそうになる。
「今度はお一人じゃなくて三人でお茶会にしてもいいかもしれませんね」
「そうですね、多分私一人だと落ち着かないと思います」
「お子様達は何が好きですか? うちのキッチンメイドが喜んで腕を振るいますよ。まあでも苺のショートケーキはちょっと専門外ですけど」
「あ……そうですねバナナとか大好きなので……」
「バナナケーキですか、いいですねえ」
階段を降りて店までの道のりを歩く。外はとっぷりと暗くなっていて、家々の明かりが漏れて街路を照らす。
「……今日の晩ご飯、何も決めてなかったなあ……」
「なんでもいいですよ、みんなで食べられるんならきっとなんでも満足できますよ」
「私料理もあんまり自信が無くって。お菓子もあんなに綺麗に作れないし」
「そしたら他の人に頼めばいいんですよ」
お惣菜最高! アタシは近所のスーパーのお惣菜だけでここまで大きくなりましたよと胸を張るアカネに女性はくつくつと笑う。
「そうですね、頑張らなくってもいいんですもんね」
「そうですよ、もうとっくに頑張ってるんですから」
しばらく他愛のない話をして一緒に帰ると、目の前に見えてきた珍しく深い時間まで照明がつけられた店先はいつもよりずっと明るく見えるようだった。
「……アカネさん、」
「はい?」
「子供の時、叶えたかった夢ってありましたか?」
「あー……大人になることでしたね。早く稼いで母親と弟妹に楽させることが夢だったんで。あーでも、きっとそれは目標みたいなもんでしたかね」
「他の夢はありましたか?」
「……なんだろ。でも少なくともメイドではなかった気がします」
その言葉に思わず笑った女性は、私はね、と呟く。
「お母さんになりたかったんです。子供を育てるのが小さい頃の夢でした。でも夢は夢で終わらせちゃだめですね」
ちゃんと、私が育てなきゃと小さく頷く。
「……だめですよ、私だけで~しなくちゃってなったら。また視野狭窄になってますよ」
「あ、本当だ! 大変」
「こまったらうちの店に電話、はい約束、ね?」
「……はい、そうします」
店のドアをくぐるときに笑い合った声が聞こえたのか、シロナがカウンターの中から顔を出す。
「あ、二人ともよかった! ……やだ目が真っ赤!」
蒸しタオル作ってあげるからちょっと待っててね! と慌てて用意をし始める。
「大丈夫です、先に子供達迎えに行くんで」
「アタシもへーき、もうメイクも取れるぐらい泣いたし」
「なんでお母様はともかく二人とも泣いてるのよ……」
「それはまあ詳しくはあとで話すよ」
アカネの案内で二階に連れて行くと、クロサキは居住まいが悪そうにデスクに向かって帳簿を覗きながら
「やっとお迎えに来てくれたのかい」
と安堵したように呟く。ソファでは兄妹が寄り添ってぐっすりと眠っていた。
「……よかったですね」
「ええ」
そっと肩を揺らして子供達を起こした女性は、ごめんなさいと真っ直ぐに謝って手を広げて二人を抱きしめる。私たちの腕は広げても二人ぐらいしか抱きしめられない。でもそれで、十分なのかもしれない。
「ごめんね、お母さん怒ってひどいこと言っちゃったね。本当にごめんなさい。みんなでおうち、帰ろう? スーパー寄るけど何食べたい?」
まだ眠たそうにしている二人はううん、と言いながら目を擦る。
「すぱべっちい」
幼い妹がたどたどしく話すと、女性は顔を明るくさせて笑って頷く。
「スパゲッティ、食べよう。うん。お兄ちゃん何食べたい?」
「からあげ!」
そうだね、と頷きあっているところを見てアカネは先に階下に降りる。きっともう大丈夫だと信じて。階段をのぞき込んでいたシロナが心配そうな顔をしていて、大丈夫だってと笑い飛ばしたけれどきっと腫れた目では説得力が幾分か欠けていただろう。
<つづく>
第四話【ムテキ・ピンク】
第五話【結構毛だらけ猫灰だらけ】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
