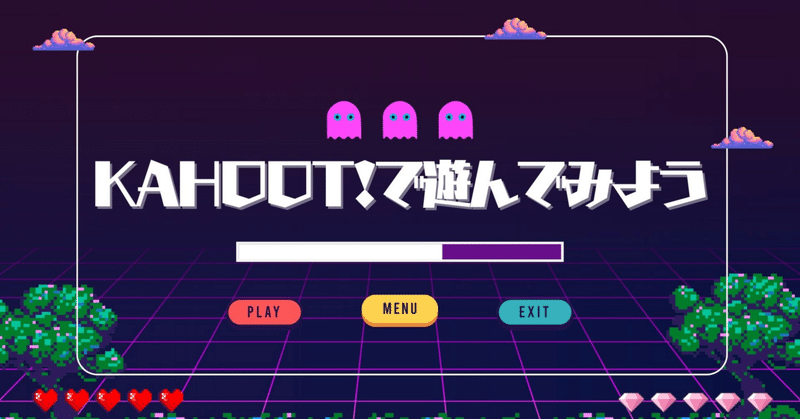
#25 kahoot!の研修会を開いたっていう話〜強めの負荷をかけたアウトプットの場を用意せよ!〜
どうも。こみっくです。
先日職場の同僚とタッグを組んで有志参加の研修会を開きました。
同僚は教育版「桃鉄」、僕はkahoot!を担当しました。
教育版「桃鉄」はコチラ↓
クイズアプリkahoot!とは↓
X(旧Twitter)をみていると、研修をする立場の方がたくさんおられて、いつかは自分も研修を開けたらええなあ…と思っていました。
いま勤務している学校では若手主体の勉強会があるのですが、その会で主催という立場で今回の機会を得ることができました。ありがたや。
今日は研修を開くという立場を経験して得た所感を書いていきます。


1.めっちゃいい経験になる
このことを声を大にして言いたい。
めっちゃいい経験になる。
当たり前ですが、人様の前で研修をすることになるので、自分が研修内容をしっかり把握していないといけません。
kahoot!とは?
どんなことができるのか?
なにがメリットなのか?
ということを説明する必要があるのです。
だから研修までに簡単なスライドを作りました。
よりよく皆さんにkahoot!の魅力を知ってもらうのが大切だと思ったからです。
こういう準備が大切だと思います。
資料作成や、人前で話すことが何よりもいい経験になりました。
そして、僕が最も感じたことが
「自分に負荷をかけた場面でのアウトプットの機会は財産になる」ということです。
どういうことか。
なんとなく本や動画などで自分が学んだこと(インプット)をより自分のものにするには外部への発信(アウトプット)が必要だと僕は思っています。
つまり、インプットとアウトプットは自転車のタイヤのようにニコイチ。
ふたつあって初めて自転車は走り出すのです。
では負荷をかけるというのはなにか。
自分を追い込むということです。
今回の場合は、研修会で自分が主催者となることで自分に強制的にアウトプットの機会を持たせました。
Twitterで指を滑らせての発信ではなく、自らの口で語る発信はそれなりに負荷がかかります。
会の中ではトラブルもあるでしょうし、分からないところを聞かれることもあるでしょう。
また、場の雰囲気もあるでしょう。
そこを打破して自分で空気を作っていく。
これが自分に負荷をかけるということ。
こんな機会を得ることはそうそうないです。
今回は職場の皆さんがよりよい教育活動を過ごせるようにという願いを込めて研修を開きましたが、実は裏テーマで自分の発信力向上というのもありました。笑
自分が主催者になることで得られる財産はとても大きい、と今回学びました。
と、同時にですよ。こうも感じました。
今回の僕の場合は10名程度の会で、知った職場の人たちへのアウトプットでした。
しかし、Twitterで発信されているスゴい方たちは知らない人何百人を対象にアウトプットの機会を作っています。
そのスゴさたるや。
自分もそのステージまで行けたらええなあ。
そんなことも感じた次第です。
2.自分よがりでなく相手意識を持つ
研修会は僕がやりましょーと声をかけて始めました。
正直、やりましょうとは言ったもののホンマに人来るんかいな…と不安でした。
しかし、前述したように10名ほどの先生方に来てもらえました。
ありがたや。
もちろん、研修の準備はしていましたし、こんな感じの流れで〜と事前に考えていました。
しかし、気をつけないといけないと思ったことは「自分よがりになってはいけない」ということ。
今回で言うと「kahoot!ってめっちゃいいよ!子どもも大人も楽しめて授業で絶対使ってや〜!」という押し付けではなく、
「kahoot!というのはこういうものなんですけど、よければ使ってみておくんなまし。」
というちょっとしたお裾分けのイメージを持ちました。
そこに自分よがりであってはいけません。
あくまで低姿勢で、謙虚に。
「こんなんありまっせ。よければどうぞ。」
くらいの感覚がちょうどいいかもしれません。
あとは、参加者のニーズを知ることも大事。
今回だと、kahoot!ってなに?というところが1番大きなところだったので、まずはみんなで遊んでみようよ!という内容でした。
例えば今回いきなり、子どもにkahoot!の問題を作らせるやり方を研修しても参加者は???だったと思います。
参加者はなにを求めているのかということを見極めてそれを謙虚に提案してみる。
そんなマインドが研修会では大事だと思いました。
3.学び続けることこそが教師の本質
主催する側としてkahoot!とは何かということを知識として定着させておく必要があります。
つまり、自分でkahoot!をある程度触れる状態にしておく必要があるのです。
そこに必ず学びがあります。
ここをこう作業したらこうなる、とか
このゲームモードではこんな力がつく、とか
よく学び続ける教師といいますが、これは本当に大事なことだと思います。教員に必要な資質だと思います。
学びをやめない。
学び続けることで知識は定着していきます。
この時代ですから、子どもたちに教えることはたくさんあります。
だからこそ教師が学び続けることが必要なんだと今回思いました。
また、ありがたいことに、今回の会に50代の先生方も参加されていました。
ベテランの領域に入られた先生でも僕みたいなペーペーが主催している会に参加してくださる…
しかも内容は桃鉄とkahoot!。
これこそ学び続ける姿勢。
そんなベテランの先生を自分も真似していきたいと強く思いました。
4.まとめ
今回は、自分が研修会を開いた所感を書いてみました。
大きな研修会でもないですし、内容も大したことはないかもしれませんが、自分にとっては非常に大きな機会だったと思います。
実際に、会の終わりには「参加してよかった!」と言って頂き嬉しかったです。
もし、また機会があれば次回はCanvaを触ってみよう!みたいな勉強会ができればいいなと思います。

こういうのもアウトプット
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
