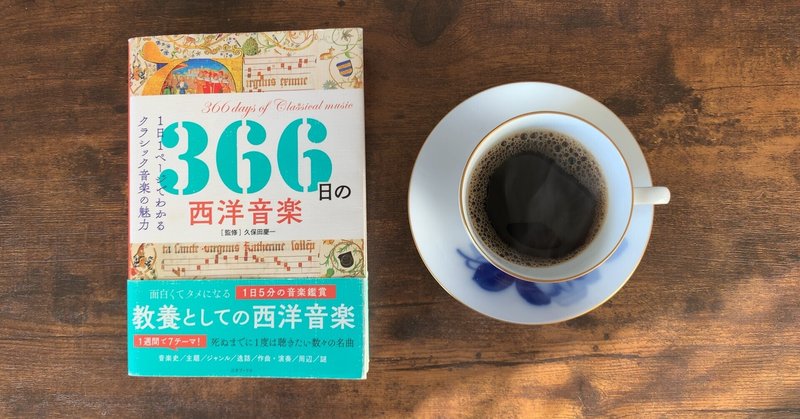
【音楽×珈琲 鑑賞録】4月10日~ジョン・フィールド 夜想曲
音楽観を鍛える鑑賞録。
4月10日のテーマは、【ジャンル】
とりあげる作品は、
ジョン・フィールド /
夜想曲
です。
ジョン・フィールド
John Field
1782年7月26日 - 1837年1月23日
19世紀の初めに活動したアイルランドの作曲家、ピアノ奏者。
夜想曲(ノクターン)の開祖ということで有名な音楽家ですね。
この記事を書いている時分、早朝に聴く夜想曲もまた乙なものといえましょう。
アイルランドに生まれ、ロシアで活躍するという珍しい経歴の持ち主です。
ミハイル・グリンカを師事するなど、ロシアのピアノ名曲の源流はこの人から始まったと言えるかもしれません。
2021年を生きる人類からしてみたら、独奏ピアノが奏でるたゆたうようなメロディは馴染み深いものですが、18世紀から19世紀前半の人類にとってみれば、斬新だったといいます。
ピアノ、特にレガート・ペダルが進化し、長いサスティンがえられるようになったことが、このジャンルを生み出した要因になっています。
ある意味、ライトハンド奏法を産み出したエディ・ヴァン・ヘイレンのような人だと思うと、偉人な印象がより色濃くなりますね。
ジョン・フィールドはこの課題図書で「夜想曲」のみ取り上げられています。
わたし個人としても、あまり馴染みのない音楽家だったので、今回綴るにしても言葉が出てこないわけですが、「夜想曲の開祖」、「ロシア音楽の父の師匠」という音楽史において超重要人物であるのに、あまり話題になってこなかったところに注目したいと思います。
往々にして、「ファースト・ペンギン」を受けて「セカンド・ペンギン」が潮流をもたらします。ゼロイチを起こすフロンティアが開拓した場があるからこそ、その新しいマーケットでスターが生み出されて活躍できるというものです。
わたしたちは輝かしいスターにばかり目がいきますが、それよりも苦境からリスクを冒して挑戦した人や、始祖に着目する方が大切です。
二匹目のドジョウを狙うでも、そのつもりはなくても、わたしたちはなにかしらの先人達の下地のもとに生きながらえています。
やりたいことや活躍したいと思っていることがあるのなら、まずはその源流をしっかりと捉え、敬意をもつ。
その意向がないと、ふわふわとした中途半端な立ち位置で、うごめくだけになってしまいます。
夜想曲といえばのショパンは、自身の楽曲に対してフィールドを引き合いに出された際、
「フィールドと並び称されるなんて、僕は嬉しくて走り回りたい気分です」
と語ったといいます。
ショパンも先達を私淑していたことを思わせるエピソードです。
自分は何者かと問われたとき、「わたしは○○です。」と明言できるには、ルーツを明確にし、敬意をもった学びを血肉化しておく必要がある。
その営みの先、まだ見ぬ開拓場があれば、次世代に遺すに値する行動をすればいい。
そんなことを思いながら、ジョン・フィールドの調べを聴き、穏やかな気持ちになる有り難みを噛み締めています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
