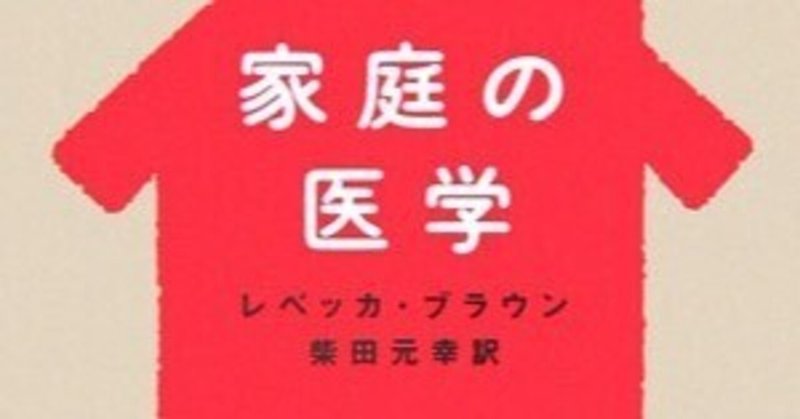
『家庭の医学』 レベッカ・ブラウン
米国の小説の名手レベッカ・ブラウンが、ガンに侵された母親の発症から亡くなるまでの生活をつづった手記です。病の進行に従って母に現れる症状は次第に深刻さを増していき、その一つ一つに向き合う作者一家の経験は、読んでいて胸が塞がるような気持ちにさせられます。
ただ、この本には、各章の扉に医学事典から抜粋した症状や療法の解説を掲げるという構成上の仕掛けがあります(原題はExcerpts from a Family Medical Dictionary-家庭医学事典からの抜粋-)。たとえば、「metastasis(転移) 病原体や細胞が、血管やリンパ管を通って運ばれることによって、疾患が最初の場所から、直接関係していない体内の別の部位にまで拡がること。癌はこの方法によって拡がる。」といった具合です。
身内の「死んでいくプロセス」の生々しいシーンを描く各章の冒頭に、あくまで医学的・客観的に記された症例の解説があることで、読む者はそれがどこにでも起こり得る一般的な出来事であることを、常に意識させられます。残酷な運命はこの世界の至るところに遍在しているのだ、とそれは告げているのです。世界を眺めるこのような静かな視線は、この作品の文章にある種の厳(おごそ)かさをもたらしているように思います。
文体というのは重要な要素なのだと、この作品を読んでいて思います。たとえば作者はしばしば言葉を反復して使います。母の口に綿棒で水分を与えるときの場面では「まるごと飲み込んでしまわないよう、しっかり持っていてやらないといけない。私はそれを持っていた感触を覚えている。私は覚えている。引っ張られる感じを、あの渇きを。」手の感触として伝わってくるものを痛切な生命の営みとして、繰り返される言葉が描いています。それを、何か大切なものが人生に訪れる瞬間を描くための文体、と言ってもいいでしょう。
風景の描写にも、作者の文体の力を感じさせるものがあります。母の病院に行くために飛行機に乗る場面など、何気ない風景が普段では想像もしないような見え方で見えてくる。あるいは母の遺灰を手に渓谷の淵に立つときの、遥かな眺め。何を言葉にして何を言葉にしないか。その厳しくも透徹した選別によって風景は、世界とはかくあるべしといったイデーを指し示すかのように見えてくる。世界は人間に苦しみや悲しみを与えることを止めませんが、それと対峙しそれを超えて進むことを可能にしているのは、人が言葉を持ちそれを用いることによってなのではないか。そんな思いすら抱かせる書の一つです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
