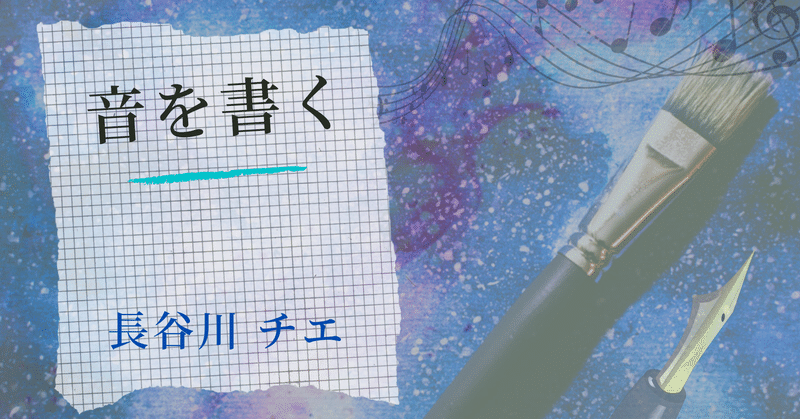
連載小説『音を書く』の伏線を回収して歩く
Culture Cruiseにて、小説プロジェクトを立ち上げ、数カ月に渡って連載を行いました。
ある音楽を聴いた時の、主人公の心情を文章で表した『音を書く』という作品です。
▼第二章まで試し読みできます。
読み返すと伏線があるのですが、Web上での連載だったためページが分割されて理解しづらかったかもしれないので、解説文を書きました。
これ以降は盛大に種明かししまくっておりますので、ネタバレなしで読みたいという方がもしもいらっしゃれば、先に物語をご一読ください。
-------------------------
まず、冒頭から最後の一文が登場するという不思議な構成。
▼序章だけ読むと、病室にいるのは“私” と受け取れると思います。
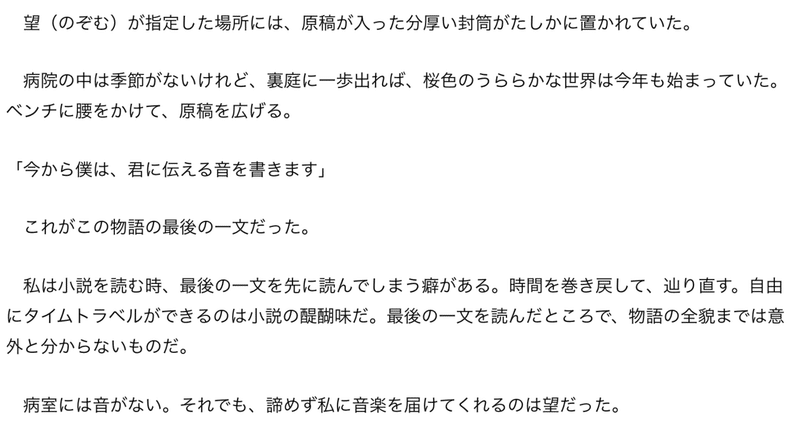
そして原稿を読み始めます。書き手は“望” で、“きみ”に宛てて書いていることが分かります。
星川奏(ほしかわそう)というシンガーソングライターのライブで感じたことが書かれていて、第三章で初めて“祐希”という名前が出てきます。
僕がきみに宛ててこの物語を書いたのは、きみの声が僕は大好きなのに、きみがずっと黙っているからだったんだ。もっと輝いてほしくて。それに、こんなことを考える僕はおかしいのか、誰かに聞いてほしくなった。
第六章のこのあたりで、「あれ? ずっと語りかけてた“きみ” という相手と、祐希は別人なのかな?」という仮説が成り立ちます。
-------------------------
その後も過去を振り返ったりしながら、音の聴こえ方が丁寧に書き綴られ、第十三章の「静かなる旋律」で、望は静寂の中で音楽を感じる方法を思いつきます。
祐希は音のない世界を生きている人です。雨を通して望と祐希がつながることができるのもそのためです(第八章「雨と虹」)。
雨粒が傘に落ちる音。祐希と歩きながら聞くあの音が好きだ。祐希は、雨粒が傘に当たった瞬間に伝わる感覚が好きだって言う。だから雨の中を一緒に歩く時は、祐希が傘を持ちたがる。手を伸ばして、わざと雨に当たってはしゃいだりしている。
この日は一人だったから、歌ってほしくなかったのに。この曲で、祐希と僕はつながれるのに。こんな時にかぎって、胸を締めつけるほどの美しい涙雨が降り注いだ。
望は祐希に伝えたくて、一生懸命音楽を文章で表現していたのでした。
第十四章では、ライブも終わって無事に帰宅すると思いきや起きてしまう事故。
そして第十五章で、なぜこの物語を書こうと思ったのか、望の想いが綴られています。病室にいたのは祐希ではなく望でした。
さらに終章まで来ると、語りかけていた相手(きみ)は病院の待合室にあるピアノで、読んでいたのは祐希(君)だったことが分かるという内容です。
望が指定した場所には、原稿が入った分厚い封筒がたしかに置かれていた
と冒頭に書かれている場所が、待合室のピアノだったということです。ここに封筒があっても、誰も気付かない。それくらい背景と化していたピアノのことが、望は気になったわけですね。
このピアノは、母が入院してお見舞いに行った時に、実際に1階のロビーに置かれていたピアノがモデルになっています。写真に撮って、眺めながら書いたりしました。
-------------------------
ちなみに、祐希については序章と終章で“私” と自分のことを呼んでいますが、小説の中では性別は出てきません。
また、この物語は星川奏さんの音楽を中心に進んでいきますが、奏さんという人物は一度もセリフを発していません。望の描写によって読み手が想像しているだけのはずです。
セリフがあるのは望と祐希だけで、本編は望のモノローグ、序章と終章は祐希のモノローグだけで成り立っています。
シンプルな構成の中で、ストーリーが大きく展開する様子を表現できたらと思いました。
文字だから成立する言い回しも含まれています。『音を書く』というタイトルも、文章で読むから意味が伝わるものにしたいと思って名付けました。
映画やドラマの映像作品も素晴らしいですが、口語では「書く」と「描く」のニュアンスの違いは表現しづらいと思うので。
小説ならではの表現を考える時間が楽しかったです。
「僕は描く人に憧れていて、自分は書くことしかできない。でもいつかは、自分も文章で描ける人になりたい」と願う望。
そんな望が書いた、
「今から僕は、君に伝える音を書きます」
という最後の一文を、”描きます” と鉛筆で書き直してしまう祐希。
この瞬間、望は描く人になれたという意味と、「次は私が描くよ」という二つの意味があります(二つ目は解説しないと伝わらなかったですよね)。
最後の一文から読む祐希の癖を知っていた望は、これを祐希へのメッセージ、最後にして最初の前置きとして伝えたわけです。
-------------------------
こんなに著者が伏線を語り尽くすのも野暮ではありますが、理解していただくにはまだまだ力不足の私なので、補足が必要かなと思いました。
これらを踏まえて、序章から読んでいただくと理解していただけるのではないかと思います。
細かいつながりは他にもたくさんあるので、暇で溶けそうな時にでもどうぞ読んでやってくださいませ。Amazonにて出版開始しました。
▼執筆にあたってインスパイアされた音楽のプレイリスト
拙著の連載にお付き合いくださった皆さま、ありがとうございました。
▼SNSのフォローもよろしくお願いいたします!
【最近の音楽記事】
— 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐂𝐫𝐮𝐢𝐬𝐞 (@CultureCruise) May 28, 2021
▼Shinn Yamadaさん(インタビュー)https://t.co/pTnIdqLA0w
▼YOASOBIhttps://t.co/Q9KY6rt5Xn
▼FIVE NEW OLDhttps://t.co/pPrJWR50Bc
▼眠りたくない夜のプレイリストhttps://t.co/sJKx6lzkkY
▼DISH//https://t.co/lhXWTTP4kv
▼藤井風さんhttps://t.co/VyNTWglGms
ここから先は
¥ 100
Culture Cruiseへのサポートとして投げ銭していただけると喜びます。 大切に使わせていただきます。
