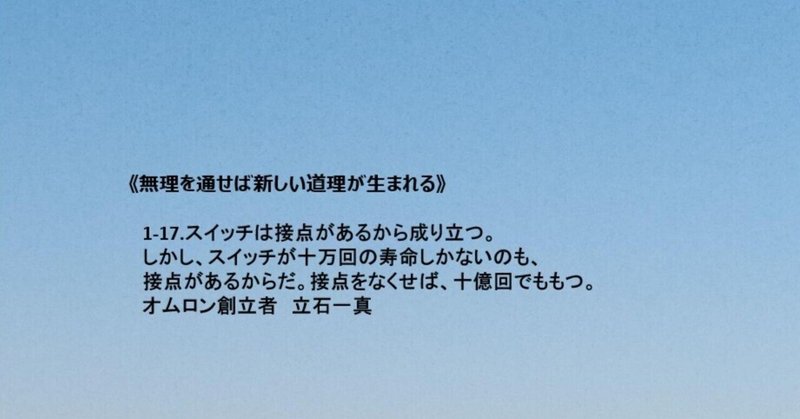
1-17.スイッチは接点があるから成り立つ。しかし、スイッチが十万回の寿命しかないのも、接点があるからだ。接点をなくせば、スイッチは十億回でももつ。
1-17.スイッチは接点があるから成り立つ。
しかし、スイッチが十万回の寿命しかないのも、接点があるからだ。
接点をなくせば、スイッチは十億回でももつ。
オムロン創立者 立石一真
オムロン(旧立石電機)は昭和16年にマイクロ・スイッチの生産から創業した会社である。戦後、各種のオートメ機器を開発して成長してきたが、その成長のきっかけとなったのが、無接点近接スイッチの開発である。
普通、スイッチは接点があって成り立っている。
しかし、スイッチの最大のネックもまた接点にある。接触・切断を繰り返すたびに接点は摩耗する。この部分の寿命がスイッチの寿命になるのである。
昭和33年、客先から、それまで1万回くらいしかなかったスイッチの使用寿命を1億回にしてほしいとの要求を突きつけられた。
受けた立石は、当然スイッチの接点の強度向上を目指して研究を開始するが、いかんせん物理的な接触である。強度は増しても回数が増えれば接触面は摩耗する。1万回の寿命を10万回まで伸ばしたが、そこから先が進まないのである。技術開発はそこで頭を打った。
「そんな時に、接点があるから無理だということに気がつき、接点のないスイッチの発想が出てきた。接点があるからこそスイッチだが、接点をなくせば1億回はいけるのではなかろうかと、気がついた」。
タイミングもよかった。この頃ちょうどトランジスタが出回り始めていた。立石に時代も味方した。結局、立石はこのトランジスタを使ってスイッチと同じ機能を持つ回路(無接点スイッチ)を開発する。
接点を切り替えるのがスイッチという当たり前の常識・技術を否定したことで、新しい技術が生まれたわけである。
接触10億回という数字は一見、「無理」に見えた。しかし、立石はその無理を無理とせず、実現に向けて懸命に努めた。その取り組み姿勢が、立石に非接触スイッチという新しい「道理」を生み出させたのである。そして、時代に合ったニーズに真剣に取り組んだからこそ、運もまた立石に味方したのであろう。
TDKの専務増島勝は、技術開発に当たっては「肯定技術と否定技術の2つに分けて進めるべきだ」と主張している。つまり立石のケースでは、現在採用されている物理的なスイッチの構造は否定技術であったわけで、これを否定したがゆえに、その技術に代わる新しい技術が生まれた。
とはいえ、何事も肯定するのはやさしいが、否定するのは難しい。モニュメントが偉大であればあるほど難しさは増すというのは東芝常任顧問・元副社長の川西 剛である。
かつて東芝は、マツダ真空管で東洋一を誇っていた。半導体は真空管に代わるとしても、せいぜい10パーセントくらいがやっとだろう、と言われていた当時、先見性のある先輩がいたと川西は次のように語っている。
「その先輩は、『半導体はそのうち真空管を追い抜く。なぜなら構造がデジタルでシンプルだから』と言うんですね。確かにそのとおりになった」。
この先輩の意見は大勢にならず、東芝はマツダ真空管という偉大なモニュメントを否定することができず、半導体への切り替えに遅れをとってしまったという。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
