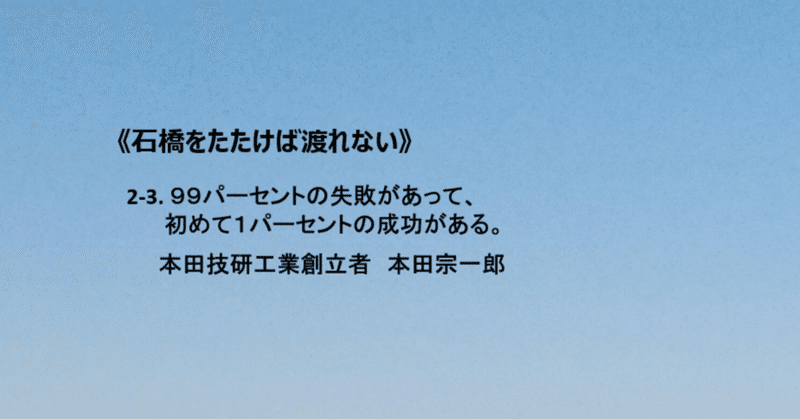
2-3.99パーセントの失敗があって、 初めて1パーセントの成功がある。
本田技研工業創立者 本田宗一郎
思い切って始めなければ何事も始まらない。しかし、始めれば失敗はあり得る。
本田は独創の人と言われている。浜松の小さな町工場から始めて、自動車用のエンジン開発に打ち込み、二輪車、四輪車と開発を続けてきた本田を、多くの人は成功を続けてきた人と見る。
本田は最後まで技術者であった。肩書きは社長ではあっても、作業服姿で油にまみれ、第一線で技術者と一緒になって開発することが好きだった。それだけに、現場の担当者が開発するものでも、社長という立場を超えて、技術者としての評価を下すことが多く、たいていの場合、その独創的な判断がホンダを成長させるもとになってきた。
しかし、そんな本田でさえ、いくつものつまずきを経験している。その一つが、低公害のエンジンCVCCの開発である。オイルショック後の日本の自動車業界は低燃費、低排ガスの省エネエンジンの開発が大きな課題となっていた。自動車会社はどこも低公害型エンジンの開発に社運を賭けて取り組んでいた。
ホンダも同様で、当時、空冷を主張する本田に対して、技術陣のリーダーであった久米是志たちは水冷車を主張していた。社内では2つの意見が真っ向から対立して、大きな論争が起こっていた。話し合いが何度も行われたが、お互いがそれぞれの信念を主張し、どうしても譲らない。
「私たちは水冷でなくてはダメだと主張しましたが、社長は空冷だと言う。仕方がありません、私たちはうまくいかないと思いながら、一生懸命、空冷エンジンの研究をやりました。しかし、どうやってもうまくいかない。そこで、こっそりと水冷エンジンの図面を作ろうということになって、絶対に宗一郎さんが行かない2階の部屋を確保して、そこで水冷エンジンの図面を引いていた」(久米是志)。
ところがこれがまもなく見つかってしまい「お前たち、オレの目を盗んで2階で何をやっているんだ!」と大目玉を食らってしまう。しかし、それ以上は何も言わない。技術論だから本人の考えと違ってもある程度許してくれたのだろう……とは久米の分析である。
しかし、それで空冷/水冷論争はまたゼロに戻ってしまった。この間、意見の対立から久米は3ヶ月ものあいだ会社に出社しない日を送る。お互いにそれでも譲らない。技術者としての人生をかけた壮絶な論争である。結局、折れたのは本田宗一郎であった。
「藤沢さんから、あなたは技術者としてこの会社に貢献するのか、社長として貢献するのかと迫られて、本田さんは『やはり社長としてやるべきだろうな』とおっしゃった。藤沢さんはそれを聞いて、じゃ、水冷でいいのですねと念を押して、『いい』という答えを引き出した」(久米是志)
この結果、ホンダはシビックに搭載されて世界をあっといわせた独創的な低燃費、低公害のCVCCエンジンを開発することになるのだが、技術者・本田宗一郎にとって、空冷エンジンの開発は失敗に終わったのである。
後年、藤沢武夫は「本田さんに空冷エンジンをやらせてやりたかった。あれだけの人だから、きっとやったに違いない」と語っていたという。
本田のすごいところは、異論がある人に任せてやらせた点である。自分の主張に対して猛反対した久米が3代目の社長になるということでも、そのことがわかる。他の会社ではまずあり得ない人事であろう。
心の中でいまいましいと思っていても、結果を出せば「そうかな」と納得する。本田の口癖は、
「新しいことに挑戦せよ」
「理屈をこねまわさんで、まず、やってみよ」
「手で知り、手で考えるのが創造の原点」
である。
これは、多くの失敗を前提にしている。そして表題の本田の言葉をかみしめると、任せた人への信頼が基盤になっているということがわかるのである。
エジソンも有名な、「天才とは1パーセントのヒラメキ(インスピレーション)と、99パーセントの努力(パースピレーション)である」という言葉を残しているが、これも同じことを言っているのであろう。
失敗があるから成功がある。失敗をした分だけ成功がある……というのが本田の主義である。
とはいえ、失敗にも、将来に道を開く失敗と、まったくどうにもならない失敗がある。
ホンダではこれを区別し、将来につながる失敗をも奨励する意味で、
「成功だけでなく失敗さえも表彰する失敗表彰制度」が作られている。
研究開発・商品開発の場では、ある失敗が土台になって新しい開発が成功するなどは日常茶飯事である。しかし通常、そうした失敗は、土台になったからといって、あくまで失敗として、しばしば減点の対象にさえなる。
逆に、その失敗を土台に成功した人間は高い評価を与えられる。これは技術者の評価としては必ずしも正当ではない。
そこで生まれてくるのが、失敗も正当な評価が必要ではないかという主張である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
