
『サスペリア』(2018) 「クローゼット」が同性愛であることを隠しているメタファーであると気が付くかどうか
in the closetがLGBTであること隠している暗喩であるのを知らない映画評論家の解説を聞いても無意味。主人公が同性愛だと気が付かないと理解が難しい、魔女社会をLGBTコミュニティーのパラレルとして描いた作品。
一般の映画ファンでも、雰囲気からなんとなく同性愛映画と感じている方も多いようだが、はっきりと指摘している日本の映画評論家はいないようだ。これでは解説にも考察にもならないだろう。in the closetについてもスカーレット・レター(緋文字)についても、本作品の英語版Wikipediaでは触れていないので、英語版Wikipediaパクリ専門の映画評論家達は気が付いていないようだ。
あえてダリオ・アルジェント監督の『サスペリア』が公開された1977年という設定、舞台は地理的にイタリアにも近いフライブルクだったのが、本作品では西ベルリンになっている(できれば、40周年にあたる2017年に公開したかったのかもしれない)。
ベルリンの壁に象徴される「分断」とか、魔女やユダヤ人に対する「迫害」とか盛り込まれていて、「わかった、これはトランプ大統領や反グローバリスムのアレゴリーだ」と言い出す人も出てきそうだが、監督も、いちおう狙ってるのかもしれない(トランプ大統領は明確にイスラエル支持だし、娘婿もユダヤ人なんだけどと、一応ツッコんでおく)。広く浅く、あれこれ盛り込んであって様々な考察ができるのだが、実の所ポリティカルには、そこまで深くもなく、ヘクセン(魔女)、ナチ、フリーメイスンリー(フリーメイスンはドイツに限らないが、ナチは徹底して反フリーメイスンだった。また1977版では至る所にフリーメイスンのシンボルが散りばめられており、魔女のバレエ学校=フリーメイスンである。)、ドイツ赤軍、アーリア人概念、ベルリンの壁といった、ドイツのダークな面を、サウザン・ゴシックのように誇張したかっただけではないかと思う。本作品を理解するうえで「ドイツの秋」についての知識など不要。60年代のアメリカを舞台にした作品に、時代背景として公民権運動や反戦運動、TVやラジオから流れるヴェトナム戦争のニュースといった描写があっても、それがテーマとは限らないだろう。なにしろ、ドイツといえばグリム童話に代表される残酷なメルヒェン(昔話)の本場である。私はこれを「ジャーマン・ゴシック・ホラー」と名付けたい。
さて、クロエ・グレース・モレッツは本作品を評して「現代のキューブリック」と言ったとか。たぶん『アイズ ワイド シャット』のことなんだろうけど、あれは最もキューブリックらしくない作品とか、キューブリック本人が後悔してたとか言われているのだけれど…。もし『博士の異常な愛情』のことを言っているとしたら、モレッツは若いのに、なかなか鋭いと評価したい。『博士の異常な愛情』といえばピーター・セラーズの一人三役が有名だが、本作品でティルダ・スウィントンは一人三役(マダム・ブラン、クレンペラー博士、ヘレナ・マルコス)を演じている。『エンジェルス・イン・アメリカ』でメリル・ストリープも三役を演じたが、ラビは声でストリープだと分かった。クレンペラーも声で女性が演じているとバレバレ(ドイツ訛りの英語は評価できる)。ちなみに、スージーの母親役のマウゴザタ・ベラも「死」と二役だが、これはちょっと気が付かない。
《以下、物語の核心や結末に関する記述》
アルジェントの『サスペリア』は、『白雪姫』と『不思議の国のアリス』の影響が強いと言われている。私は『オズの魔法使』の影響もあると考えている(バレエ学校で何故か一旦門前払いを食らうシーン等)。2018年版も、帰ってこないヴァリエイションの『オズの魔法使』ともいえるし、スージーがドイツ系で、ドイツへ帰ってきたのだともいえる。なにしろ『オズの魔法使』は、少女が悪い魔女を二人も殺す話である。
ヘレナ・マルコスを王妃と考えれば、『白雪姫』だ(本作品も、鏡が重要なモチーフになっている)。ちなみにグリムの初版では、王妃は真っ赤に焼けた鉄の靴を履かされ、火傷を負いながら死ぬまで踊らされたという結末になっており、昔から魔女と踊りというのは関係が深かったことが伺える。
主人公の体を乗っ取るつもりだったマルコスが最後は逆に殺されてしまうのは、『赤ずきん』の狼と同じ。ユングの「赤ずきんの狼は呑み込む母親」という解釈は有名だ。つまり、大人への成長を遂げるには、人間は誰しも、自我を呑みこんで離すまいとする「呑みこむ太母」と対決し、それを克服せねばならないというものだ。ユング派の心理学者たちによれば、世界中の神話やおとぎ話など怪物を退治する話は、この困難と必要性を表現したものだという。マルコス・タンツグルッペは、ユングの言う母性の本質「慈しみ育てること、狂宴的な情動性、暗黒の深さ」の象徴である。ヘレナ・マルコスは「呑み込む・支配する・主体性を奪って一体化する・死」といった、ユング心理学の童話/神話におけるグレートマザーそのものだ。また、マルコスは主人公の「元型の影」でもあり、それを自分の一面として認識し受容することで、大いなる自己への成長を果たした物語と言えよう。1977年版サスペリアも、「死のイメージ=拒絶・誘惑・束縛・呑み込む」であるバレエ学校を脱出した主人公は微笑んだように見える。ミッド・クレジット・シーンは、最後に鑑賞者の記憶を消している、ベルリンの壁が崩壊する呪いをかけている等様々な解釈ができようが、1977年版の有名な、青いアイリスを回すシーンのオマージュのようでもある。私は『太陽がいっぱい』でアラン・ドロンがサインの練習するシーンを連想した。マルコスの王座とタンツグルッペの乗っ取りである。しかし、故淀川長治氏によると、あれはモーリス・ロネの唇を手で擦っている意味だという…。
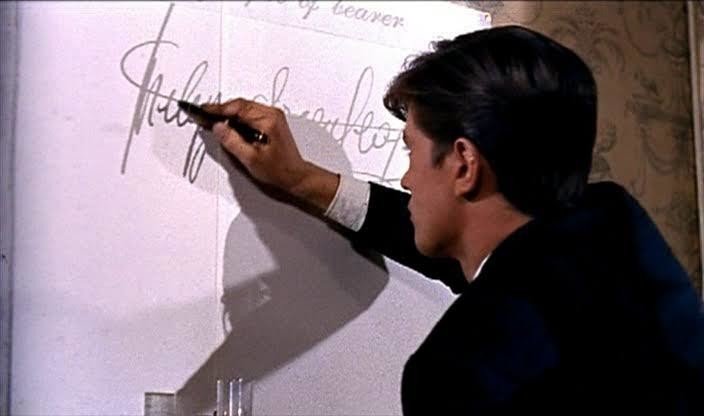

クライマックスの儀式が行われる部屋は、暗く長いトンネルを抜けた奥にある。もちろん『不思議の国のアリス』の影響であるのだが、フロイト流に分析すれば子宮の象徴という事になるだろう。悍ましい儀式と粛清、主人公の覚醒も全て子宮の中で起きたということになる。生き残った少女たちもクレンペラーも、その記憶は無いのだが、胎内記憶が無いのと同じだろう。魔女の鉤も、映画の文法でいうと性的暴行の意味と考えていいだろう。
本作品はアルジェントの『サスペリア』のリメイクではなく、まったく別の作品という批判も多いようだ。しかし、少女の成長を描いた、母性がテーマのファンタジーという点では、1977版と変わりは無いのだ。
【『地獄の黙示録』や『スターウォーズ』『マッドマックス 怒りのデス・ロード』との類似性「王殺し」と「王位継承」】
『地獄の黙示録』のカーツの部屋には、王殺しの由来が書かれた『金枝篇』と、病んだ王のために聖杯を探しに旅に出る騎士の物語「聖杯伝説」を分析した『祭祀からロマンスへ』の2冊が置かれていた。『祭祀からロマンスへ』によると主人公の任務は、病気または老齢による病弱に苦しむ王に健康と活力とを回復させることであるという。ちなみに『地獄の黙示録』の主人公ウィラードも、スージーと同じオハイオ出身だ。スージーが職員室の引き出しから何かを盗むシーンは、特別完全版でウィラードがキルゴア中佐のサーフボードを盗むイタズラを連想させる。また、簡素な暮らしをしている家庭の出身であるスージーが、友達の服を借り、他のダンサーから主役の座を奪い、最後はマルコスの座も奪う様は、やはり『太陽がいっぱい』を思い起こさせる。
本作品では、マルコスは少女たちに聖杯(次の器)を期待していたのだが、主人公スージーによって殺される。病んだ世界の中心にいる王を殺すことによって王位は継承され、世界は豊かな空間として回復されるという、「森の王」の王権を巡る神話と同じである。
【実はLGBTこそがテーマ】
ドイツの秋(1977年西ドイツで発生した一連のテロ事件のこと)だの、アウシュビッツの反省と恥だの、イタリア人であるルカ・グァダニーノ監督がなんでそんなにドイツのことばかり考えてるんだ?と思う人もいるかもしれないが、脚本はグァダニーノではなく、アメリカ人のデイヴィット・カジャーニッチ。グァダニーノが同性愛であることは知られているが、デイヴィット・カジャーニッチも同性愛であるとのこと。
マルコスは独裁的な権力と、その腐敗の象徴かというと、実はそうでもない。魔女たちは多数決をとったり、曲がりなりにも民主的である。また、魔女たちは酒を飲み歌を歌い、男性刑事にイタズラをして、わりと楽しそうに暮らしている。この楽しそうな女性達はフェリーニの『女の都』のオマージュだろうと思って観ていた。『女の都』はフェリーニ版『不思議の国のアリス』だと私は確信している。クレンペラーがダンスアカデミーに連れ込まれる辺りも『女の都』を連想させる(奇声をあげて飛び出してくる魔女はオリジナルの『サスペリア』のオマージュだろう)。『女の都』の影響は概ね間違いないとは思うが、それだけでは腑に落ちない点も多い。マルコスの老いて醜い姿は『ベニスに死す』の老作曲家ではないか…?スージーは最初からマルコスの視線を意識しているのも同じだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
