
【9/21】救われるために逃亡するわけじゃない
アメリカ人の作家であるポール・ボウルズという人が書いた、『極地の空 The Sheltering Sky』って小説がある。私はこの小説が好きすぎるので、ことあるごとに、自分の書くものの中に登場させている。

『極地の空 The Sheltering Sky』は、アメリカ人の夫婦が、北アフリカのモロッコを期間を定めずに旅するという物語だ。ところがこの2人、新婚じゃないし、どうやらただ仲がいいだけの夫婦ってわけじゃないらしい。夫は現地で褐色の肌の女を買うし、妻は同行してきた友人とベッドで体を重ねてしまう。
お互いの気持ちが、もう完全には重ならないことはわかっている。しかしそれでもなお、2人はお互いを求め続けることをやめられない。破滅に向かうことをわかっていながらも、途中で止まることはできない。アフリカ大陸の熱気が、そんな2人の頭の奥をぼんやりと溶かしていく。溶かされついでに夫は腸チフスに感染して死の淵を彷徨うことになるんだけど、この先は、ネタバレになるので一応やめておこう。

ところで、旅先でもし深刻な病気になったら普通は、なるべく清潔なところへ、なるべく都市部へ、足を向けそうなものである。呪術と占いもやってそうな掘立小屋のヤブ医者よりも、大きくて白くて清潔な病院にいる、由緒正しき医者に病気を診てもらいたいというのが文明社会に生きる人の心ではないか。
だけど、『極地の空 The Sheltering Sky』の妻キットは、腸チフスに感染した夫ポールとともに、なぜかモロッコの奥地へ、奥地へと逃げていく。奥へ行けば行くほど、当然ながら大きくて白くて清潔な病院らしきものからは遠ざかる。文明の香りは薄くなっていく。かわりに濃くなるのは、乾燥した砂漠の空気、砂、幻惑的なモロッコの音楽。言葉は通じにくくなる一方だ。妻キットは行く先々で病院を探しているので、夫の死を覚悟してヤケクソになっているというわけでもないらしい。「なんでそっちに逃げるんだ?」と、私の中でこれは長年の疑問だった。
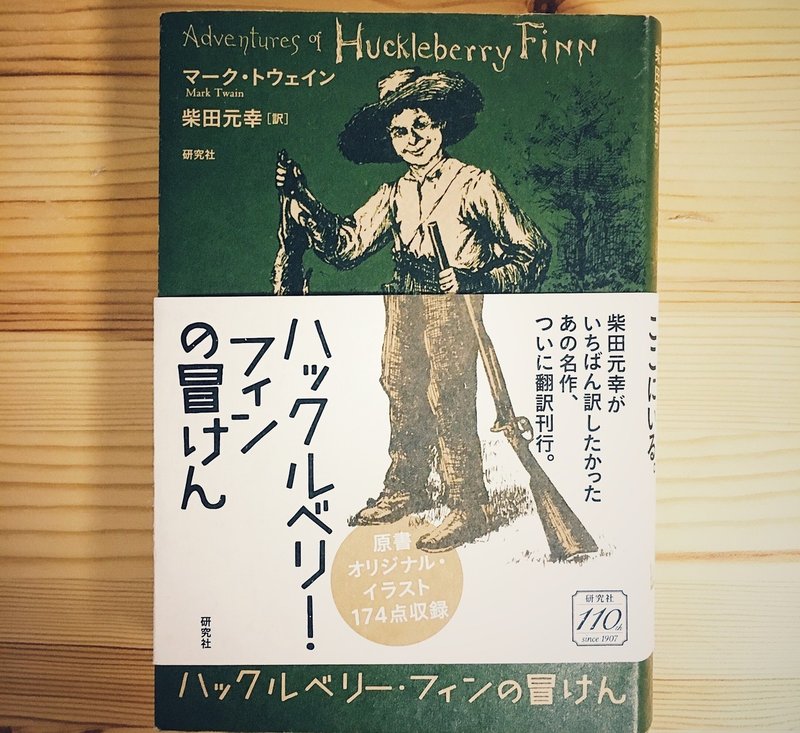
そういう意味では、今年に入って読んだマーク・トウェインの『ハックルベリー・フィンの冒けん』もまた、不可解な小説なのだ。
トム・ソーヤーの友人である、ハックルベリー・フィン。アルコール依存症の父親に嫌気がさして、ハックは逃亡を試みる。自分が殺されたような工作をして父親を煙に巻いたあと、筏に乗り込み、川をどんどん下っていく。途中で、同じく逃亡してきた黒人奴隷のジムと合流する。
『ハックルベリー・フィンの冒けん』で不可解だというのは、ハックとジムが川の流れに沿って、南へ、南へ逃げているという点だ。
通常、逃亡した黒人奴隷が向かう先は北である。北部では奴隷所有が認められていなかったから、上手く逃げればまだ助かる見込みがあるのだ。でも2人は、筏の上の生活を「楽ちんだもんな」と楽しみながら、川の流れに沿って、いずれ逃げ場がなくなるはずの南へ、南へと進んでいく。途中で周囲に勘付かれそうになると、「まっさかあ。逃亡ニガーが南へ逃げますか?(p.228)」なんて言い訳をしたりもする。どうしてわざわざ助かる見込みのない南部へ逃亡するんだ? というのが、この小説の抱える大きな矛盾なのだ。
あるとき、ウラの森に行って、じっくりかんがえてみたことがある。おいのりしたものがなんでも手にはいるんだったら、なぜきょう会しつじのウィンさんは、ブタですったカネをとりもどせないのか? なぜ未ぼう人は、ぬすまれたぎんのかぎタバコ入れをとりもどせないのか? なぜミス・ワトソンはふとれないのか? やっぱりこんなのイミないんだ、とおれはおもった。ないとかんがえたほうが、スジがとおる。(p.28)
ハックが逃げているのは、アルコール依存症の父親だけではない。日曜日に教会にお祈りにいくような、"正しき”市民社会からも逃亡している。未亡人に「お祈りして手に入るものは、魂の贈りものなんだよ」なんてそれらしき言葉で説得されても、「ようするに神様ってのは二種類いるんだな」と独自解釈をし、自分の好きな人間を否定せずとも、折れない。社会で「こうあるべき」とされているルールや規則をまず疑って、屁理屈をこねて、周囲の人間を錯乱させる。ハックの精神のあり方は、私の好きなトリックスター的であるともいえると思う。
そのことを踏まえると、ハックとジムがなぜ南へ逃れたのか、また『極地の空 The Sheltering Sky』のキットとポールがなぜ病に犯された体を抱えつつも奥地へ逃げたのか、少しだけ見えてくるような気がする。

つまり彼らは、今いる地以外のよりよい場所へ、救いを求めて逃亡しているわけではないのだ。「ここではないどこか」に行けさえすれば安寧の地があって、そこにたどり着けば助かるはずだなんて、ハナから考えちゃいない。
世界は狭くないが、そこまで広くもない
逃亡するのはどこかへたどり着くためではなく、今ここにあるルールから新天地のルールに乗り換えるためでもなく、ただ、逃亡こそに意味がある。「筏の上って楽ちんだもんな」とハックは言うけれど、その言葉通り、筏はどこかへたどり着くための道具じゃない。筏の上にいることにこそ、意味があるのだ。
おれなんかがただしいことをやれるようになろうとがんばったってムダなんだ。ちいさいころにただしくはじめなかったやつは見こみナシなんだ。いざっていうときに、やるべきことをやらせるささえがないから、あっさりめげちまう。それからおれはすこしかんがえた。ちょっと待て、とおれはじぶんに言った。もしただしいことをやって、ジムをひきわたしてたら、おまえ、いまよりもっといい気ぶんになってるとおもうか? いいや、やっぱりひどい気ぶんだとおもう、とおれはじぶんでこたえた。いまとまるっきりおんなじ気もちだとおもう。それだったら、ただしいことをやれるようになってなんの足しになる? ただしいことをやるのはタイヘンで、まちがったことをやるのはぜんぜんタイヘンじゃなくて、のこるものはおんなじなんだろ? おれは行きづまった。これにはこたえようがない。それでもう、これ以上かんがえるのはよそう、これからはとにかくとっさにおもいついたほうをやろうときめた。(p.168-169)
道中で、逃亡奴隷を匿っているんじゃないか? という疑いを向けられたハックは、ジムがいることを上手く誤魔化して、「逃亡ニガー見たら、ぜったい逃しません(p.168)」と威勢よく嘘をつく。ハックの時代、逃亡した奴隷を見逃すことは大罪だ。自分はその大罪を犯すのかと、ハックは葛藤する。葛藤の末、当時としては「正しくない」選択を、つまり逃亡奴隷のジムを助ける選択をするわけだけど、決心したあともハックは悩む。「ジムをひきわたしてたら、おまえ、いまよりもっといい気ぶんになってるとおもうか?」と自問自答する。そして最終的に、正しいか正しくないか、タイヘンかタイヘンじゃないかじゃない、「とにかくとっさにおもいついたほうをやろう」と決めるのだ。
救いを求めて逃亡するわけじゃない。筏はどこかへたどり着くための道具じゃない。正しいからやるのでも、正しくないからやるのでもない。逃亡はその状態にこそ意味があり、筏はただその上に乗って「楽ちん」と思うことに価値があり、そして、何をやるべきでやらざるべきかは、「とっさにおもいついたほう」でいい。"逃亡する"アメリカ文学が示唆を与えてくれるのは、こんなふうなことだ。
人はそれを刹那的だと馬鹿にするかもしれないけど、私をはじめある種の人間は、そういうふうにしか生きられないような気もする。そしてそのイノセントな危険性はおそらく、J・D・サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』など別のアメリカ文学に、課題として持ち越されることになるのだろう。
※柴田元幸訳『ハックルベリー・フィンの冒けん』の巻末にあることと同じことを書きますが、私はこの文章内でいくつかの侮蔑的、差別的な表現を用いています。しかしこれは、小説の忠実な引用を心がけた結果であることをご理解ください。
شكرا لك!
