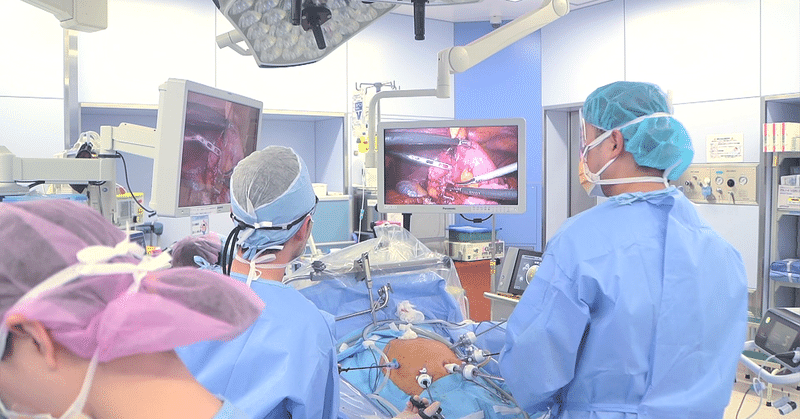
【映像+リポート】新型コロナ(COVID-19)と日本の医療政策
メイン動画「コロナと医療崩壊 -人災としてのパンデミック-」(2021)
1.感染症対策と新型コロナ(COVID-19)
新型コロナのパンデミックを語る上で重要なのは、そもそも日本の感染症対策がどれだけ充実していたかという点である。実は、結核患者の減少により、日本では保健所が全国的に減らされてきた経緯がある。保健所の数は、1960年代から一貫して800カ所を上回っていたが、1992年の852カ所をピークに、現在は469カ所(2000年)にまで減少していた。
また、病院にとって感染症は小児科、救急、産科と並び手間がかかるわりに一人あたりの収入が少ない「不採算部門」であり感染症指定病院の数よりも感染症専門医の数のほうが少なかった。その意味で、日本は特に感染症に対して、歴史的には構えが緩んでいた状態だったといえる。
そんななか「コロナと医療崩壊」の舞台となっている済生会栗橋病院(現在は移転)は第2類指定感染症対応の病院で、もともとある程度の備えがあったため、ダイヤモンドプリンセス号の患者を受け入れることができた(2020年2月)。当初は、一つの階をすべてレッドゾーンとイエローゾーンに分け、陰圧をかけて管理されていた。翌年、駐車場を潰して、プレハブの専用病棟を建設、感染病棟を移設した(2021年3月)。
感染管理においては、ICT(感染制御)の資格を持つ、2名の看護師が病院全体を維持管理し、ほぼ完璧な隔離病棟の運営に成功した。レッドゾーンの入り口には、ストレッチャー用のスロープが設けられ、救急車の着く場所も異なるので、一般病棟とは完全に独立した動線を確保した。その後に取材した複数の病院の対応と比べても、栗橋病院の感染管理は最も厳密だった。病床は70床を設けたが、酸素供給の機材不足と、何よりも医師不足によって、実際に運用されたのは34床にとどまった。
取材に入ったのは2021年9月から、断続的に、密着取材を行った。ただし、この鉄壁の専用病棟さえ、時々の政策変更に「振り回された」というのが率直な印象だ。
2.後手後手の対コロナ政策

本来、感染症対策とは「早期発見」「早期隔離」「早期治療」が鉄則といわれる。しかし、政府の対策はこれらがすべて後手に回った。第一に「PCR検査」である。感染者を見つけなければならない段階で、「発症者」に限って検査するというのは、大きな誤りだ。新型コロナの場合は、無症状感染者という存在が厄介なのであり、これを放置することは、市中感染を放置することと同義である。
また、特に注意しておきたいことは、テレビ報道で繰り返された「感染者数」というデータは、統計的にはほとんど意味がないという点だ。都道府県により人口も異なるし、調査数にも違いがあるはずで、母数を示さない時点でそれは統計でない。厚労省は「無作為抽出で、統計をとるべき」だし、マスメディアは「感染率を報道する」べきである。でなければ全体の趨勢がわからない。わからない中で対策はできない。日本の感染者が果たして多かったのか少なかったのか、未だ以って不明であるというのは大問題だ。本当はこの時点で、無作為抽出な感染傾向の検査とシミュレーションおよび大規模な隔離政策を行うべきだったのである。
さらに減少してしまった保健所では、すぐに業務がパンクしてしまい、保健所経由での入院は2020年のすなわち第2波・第3波あたりで減少を始めた。事務作業が追いつかないためであり、電話はほとんどつながらない状態だったという。これは、東京、大阪でも同じだった。「早期発見」どころか、重症者が直接入院するようになったのもこの頃だ。隔離が十分でない病院では院内感染が多発した。
その間政府はGoToキャンペーンなどを断続的に行い「早期隔離」は困難だった。重症すなわち血中酸素飽和度(サチュレーション)を肺から維持できない患者に対しては、「エクモ」という人口肺が導入された。しかし、その操作には8人ほどのスタッフが必要で、現場を圧迫した。
そして、「ワクチン一本足打法」と揶揄されたのちの、第5波では政府と東京都は「自宅療養」へと方針転換。家庭内感染と家庭内重症化が急増した。もはや、保健所とは無関係に、重症者が救急搬送されるのが日常となり、現場では治療の順序に迷う、いわばトリアージを強いられる状況になった。この時点で抗体カクテル療法は認可されていたが、その方法や、あるいは軽症者の隔離については無策だった。
この期に及んで、国と東京都はさらなる病床提供を呼びかけ、「協力しない病院の名を発表する」とまで脅しをかけた(2021年8月)。しかし、単に病床を増やすだけでは問題は解決しない。感染管理には、資金と労力が必要であり、何よりも絶対的医師不足の日本では、スタッフが足りないのだ。ベッドが勝手に治療してくれるわけではない。為政者たちにはそういう現場への想像力が全く欠如していたとしかいいようがない。
そして、第5波の重症者・死亡者数はそれまでで最高数を記録した。この失われた命に為政者はなんら責任を負わなかった。
また、新型コロナのために病床数を増やせば、他の疾病・怪我の患者はどこに入院すればよいのか。新患の受付や健診を中止した診療科も少なくない。新型コロナのパンデミックの間は全国すべての病院が面会禁止となった。家族と患者のコミュニケーションを求める悲痛な声も上がった。
第5波での「自宅療養」方針は、政治的にも医療の上でもまったくなんの方針でもなかった。これは単なる棄民政策であり、新型コロナのパンデミックにおいて、まさに、国民の医療へのアクセスが完全に断たれた瞬間だった。国民の権利を考えるとき最も批判されるべき所業だったといえる。

3.医療の質を変える独法化
だが、話は終わりではない。第5波と第6波の間に、東京都は都立病院の独立行政法人化および公社病院との再編統合の定款を議決し、翌年計画を開始した。コロナ患者の受け入れ病床数は全国で11位までが、都立病院・公社病院だった。それをなぜこのタイミングで縮小するのか。組合や市民たちが大きな反対の声を上げた。
感染症対策の手薄なところにコロナが猛威を振るった、その事実への反省などさらさらないようである。独法化は単に公立病院が民営化に向うだけではない。産科・救急・小児科・感染症等の不採算部門が、切り捨てられる恐れがあるのだ。
この看過できない事態に、医療問題の取材で師と仰ぐ本田宏医師と共に、独法化と再編統合の問題を取材し、短編映画に仕立てようと企図した。これが「公的医療はどこへ行く」(製作中)である。私たちは各地の現状を仔細に取材することになった。
まずは新型コロナ患者死者数・全国一の大阪の現状を見た。大阪府では府立病院が独法化され、24あった保健所が8箇所まで縮小されていたため、医療崩壊が急速に進展したようである。だが、コロナ問題よりも驚いたのは、あまりにも不均衡な医療医療の質の変容である。
独法化の進展はすでに不採算部門の切捨てに至っており、コロナ死全国一の理由の一つだったという。パンデミック発生後、加算は臨時に上げられたものの、急に感染症部門を再開させられるものではない。
すでに、独法化は不採算部門の患者にとっては医療へのアクセス権を奪う結果になっていた。逆に大阪では、診療報酬が2倍以上になる外国人医療、すなわち医療ツーリズムが跋扈。大阪城を見下ろす国際がんセンター、医誠会国際総合病院などである。周囲にはいくつもの急性期病院があり、過当競争が懸念されている。

4.患者を見捨てる再編統合
次に病院の再編統合問題だが、もっとも厳しいのは山間部である。広島県府中市上下町は、もともと独立した中山間部の中心地だったが、平成の大合併(1999-2010)により、平野部の府中市と合併。これに伴い、病院ももともと医療圏の異なる、府中市民病院と合併することになった。最新の医療機器も、医師たちも府中市民病院へ移管され、2018年には一般病床が廃止となってしまった。
これをきっかけに、上下町そのものも衰退し、人口も減少。今や、高校が廃止される見込みとなってしまった。平野部の府中市民病院とは30km離れており、積雪や路面凍結のため、冬場は救急車でも1時間を要するという。府中北市民病院を中心とした医療圏そのものが、医療へのアクセス権を奪われたといえる。
また、宮城県では仙台市内の4つの病院、すなわち宮城県立精神医療センターと東北ろうさいセンターを合併して富谷市へ、宮城県立がんセンターと仙台赤十字病院を合併して名取市へ移管するという計画を独自に発表。仙台市および市民の猛反発を食らっている。これらの病院は、期待される病院機能が異なるため、市民の医療へのアクセス権は大幅に損なわれる。

こうした、行政区分や医療圏を越えた病院の再編統合は珍しくない。兵庫県の三田市民病院は、神戸市・済生会神戸病院との合併計画があるが、どちらとも遠い立地で合築されるため、両者の患者たちから反発の声が上がっている。 再編統合の目的はいうまでもなく、行政から病院への繰入金を減らすことだが、その「目的達成」にも疑問がある。青森県・西北五地域では、統廃合の結果、医師も患者も集まらず、5億の借金を抱えてままならぬ状況に追い込まれている。病院の再編統合は今、アクセス圏を奪うだけでなく、採算性についても一部で疑問視される。

5.医療費抑制政策の限界

実のところ新型コロナ情勢で叫ばれた「医療崩壊」は、長年の医療費抑制政策が招いてきた危機であり、たまたま新型コロナのパンデミックによって、実態が露呈したにすぎない。
戦後の日本には、一時医療大国としてOECD諸国に追いつく勢いがあったが、二度の石油ショック以来、これは封じられ、どんどん縮小されてきた。いわゆる土光臨調が、その始まりであり、1983年にはほかならぬ厚生省の役人が「医療費亡国論」なる言葉を使って、医療費抑制政策を称えた。国・厚労省・財界一体となった臨調は国鉄分割民営化や米の減反政策などに舵をとり、小泉政権下での郵政民営化等、新自由主義政策につながっていった。
医療費抑制政策では、医学部定員の削減、研修医制度、病院・保健所の再編統合、公的/公立病院の独法化が具体例として挙げられるが、中でも医学部定員の削減は、医師の絶対数不足につながり、さまざまな医療問題の元凶となってきた。厚労省データから換算した本田宏医師による計算では、現在日本の絶対的医師数は、OECD平均よりも13万人不足している。世界に冠たる高齢社会の日本で、これ以上医師が減れば。「保険あって医療なし」の時代に逆戻りし、医療へのアクセス権は崩壊する。

6.医師の働き方改革という欺瞞
このように「経済優先」で進められてきた医療費抑制政策だが、新型コロナによる経済的ダメージを考えれば、そのもくろみは大きく失敗したといえる。
また、医師不足は、単なる病院の問題ではない。2000年頃からは医療過誤事件の報道が目立つようになり、また、医師の過労死、過労自殺もしばしば起きてきた。私自身が医療問題の取材に深く関わったのは、2008年の日テレ「医療を、救う」という年間企画だった。医師の過重労働について各診療科の事情を取材・オンエアした。同様の報道ですでに問題は公に知られている。
厚労省は、去年「医師の働き方改革」を発表し、表向きは問題解決を図っているようにみえるが、その推計でも未だ8万人の医師が過労死ライン越えで働かなければ医療を維持できないとされている。いわば労働問題を司る厚労省自身が、労働基準法違反の計画を立てているのである。この狂気じみた転倒には驚かざるを得ない。そもそもなぜ厚労省が、医学部の定員をコントロールする権限があるのか。その法的根拠も私は寡聞にして知らない。
第一に医師不足、そして独法化、再編統合と続く医療界の動きは、すべて国民にツケが回る。つまりアクセス権は奪われる。

7.地域主権という希望
この閉塞した事態を打開するために、何が必要なのだろうか。問題の根底にある医師不足という元凶に対して、本田宏医師は「医師補助職」の活用が現実的であると述べている。

また、医療経済学の立場からは、病院が雇用を生み、地域経済を活性化させるという考え方が注目を集めている。兪炳匡(ゆうへいきょう)氏の提唱する「プランB」である。視点はやや異なるが、兵庫県明石市は「子育て」を軸にして、土木建設の予算をすべて再配分。その結果、人口と税収が大幅に増えていることで知られている。医療や福祉に予算を回せば、地域が活性化するという好例だ(地域主権)。

コロナ禍の中でかすかな救いだったのは、世論が医療関係者へ様々な形でエールを送ったことだ。ただし、医療を軸にした地域主権を構想する場合、広範な情報の共有が必要だ。注目すべきは仙台4病院問題である。宮城県に対して仙台市が抗弁していること、そして、運動の中で中心となっているのは、町内会連合なのである。仙台の人々は医療問題を自らの問題として捉えている。アクセス権を軸とした各地からの法律家、市民からの声が大きな世論を作り出すことが重要である。
さらに考慮しなければならないのは、前述の通り、医療従事者の世界では厳しい労働環境が蔓延しているが、実のところ大きな組合組織は全国的に少ないのである。社会問題の解決には本来であれば、当事者が先頭に立つことが有効なのだが、そんなヒマもないほど、医療従事者は忙しい。このことは、彼らに代わり、取材者として、声を大にして言っておきたい。いや、むしろ実際に患者となる市民こそ当事者であると発想を切り替えることが必要だ。
だからこそ日弁連が医療問題に関心を寄せていただいている点を、私は心より喜ばしく思う。医療問題を解決するには、法律家や一般市民の力がどうしても必要なのだ。そこにおいて「檻」でもがく医療従事者と共闘することが、ひいてはアクセス権を取り戻すことになる。統合については賛同する病院があることも、運動的には、やや留意の必要な点だ。アクセス権の問題が、大きな歴史的政策に遡り、根底に医師不足があることをご理解いただき、今後も一般市民への呼びかけをお願いしたい。
私自身もビデオジャーナリストとして、医療問題はライフワークの一つである。短編映画「公的医療はどこへ行く」の完成のあかつきには、世論づくりのため、ぜひとも多くの地域で上映会を開くなど、広くご協力を賜りたいと考えている。

(この論考は2023年9月7日に行われた東京弁護士会プレシンポジウムにおける、講演抄録に加筆修正したものです)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
