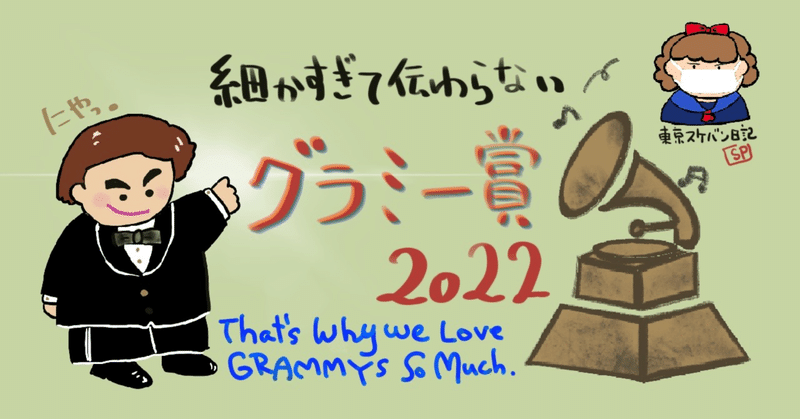
細かすぎて伝わらないグラミー賞2022よもやま(その3の3)
【第64回グラミー賞ノミネーション クラシカル部門(3)〜最優秀オペラ・レコーディング賞の巻】
まずはだいじなお知らせ。速報です。
日本時間の1月6日、2月1日に開催される予定だったグラミーの授賞式は延期されることになったとレコーディング・アカデミーから正式発表がありました。オミクロン株の感染拡大に伴い、関係者の安全を最優先するうえでの判断で、新たな開催日は近日中に発表されるとのことです。
After careful consideration and analysis with city and state officials, health and safety experts, the artist community and our many partners, we have postponed the 64th #GRAMMYs. https://t.co/oMzV1U9Tsc
— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2022
東京でも、ここ数日は倍々ゲームの勢いで新規感染者数が増えていますしね。ようやく今年は明るい気持ちで新年を迎えられたと思いきや…。でも、まぁ、まぁ、これは仕方ないですね。大晦日あたりのアメリカは「コロナ終わった!いぇーい!」ムードで超もりあがっていたので、いちど全開にしたものを再び閉じるのは難しいだろうなとも思っていましたが。さすがグラミーの判断は迅速ですね。
年末、「このままだと2月頃には日本にも再び1日数千人級の感染が来る」という専門家のコメントをニュースで見て不安になりつつも、さすがにもうそこまでの大事には至らないだろうという楽観もちょっとありました。アメリカやイギリスのほうを見れば、感染再拡大が加速し始めた時にも、コンサートはノー・マスクの観客が圧倒的に多かったようだし。「もう二度とロックダウンはしない」という強い意志のもと、目前にせまった“勝利宣言”へと、やや食い気味の勢いでまっしぐらに突き進んでいる感がありました。
やや食い気味に、というところがアメリカっぽいポイントですけどねw。
来日公演関係の話題もちらほら始まってきて、日本以上に慎重な蟄居暮らしをしていたアメリカ在住の知人たちも冬眠から目覚めたように動き出しているという話を聞き、「だったら、日本もきちんと自衛していれば大丈夫かなー。うん、大丈夫だよね」なんて会話をしていたばかりでした。
が。結局、グラミー賞も延期。とはいえ、開催するからには、リモートでも無観客でもなく本来のセレモニーでなければ意味がない…という、前向きな意味での思いもあるのでしょう。もしかしたら、続くトニー賞やアカデミー賞も同じことになるかもしれません。とにかく、どちらさんも無理は禁物です。
そんなわけで、ですね。
実は、こんなふうに1部門賞につき1万字もみっちり書いていたら、クラシカル部門だけでも授賞式の2月1日までに終わらねーな、と、薄々あきらめていたわたくしだったのですが。開会式が延期ということは、つまり「タイムリミットも延長」ということ。
今、わたしは、8月29日くらいになって、まだ宿題の半分も終わっていないことに気づいて愕然としていた小学生のもとに、先生から突如「あ、今年の始業式は10月1日になったから」と連絡が来たようなミラクル感を味わっております(笑)。
これでまた、さらにのびのびと長々と書けるぞという喜びと共に、しかし、そうなるとさらに長々と書いてしまいそうな自分に警戒しつつ、あせらず、ちびちびと、しかしさっさと先を急ぎたいと思います。
さて。本日はクラシカル部門の2つめ。《最優秀オペラ・レコーディング賞/Best Opera Recording》を見てゆきたいと思います。オペラといえば、今回ノミネートされているネゼ=セガン&メトロポリタン歌劇場オーケストラの来日公演も発表されたばかりです。まぁ、ある意味で、本日のタイムリーな話題でもあるかもしれません。
《最優秀オペラ・レコーディング賞/Best Opera Recording》
オペラ録音(ライヴまたはスタジオ録音)の指揮者、プロデューサー、主要ソリストに贈られる賞。ここでは簡略にして指揮者とオーケストラのみを表記しておきます。
【1】バルトーク:青ひげ公の城
スザンナ・マルッキ指揮 ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団
『Bartók: Bluebeard's Castle』
Susanna Mälkki,Helsinki Philharmonic Orchestra
今回のオペラ・レコーディング賞で印象的なのは、ノミネート5作品のうち2作品が女性指揮者ということ。半数とまではいかないけれど、全体的な男女比から考えると快挙ではないでしょうか。ただでさえ女性指揮者が世界的なオーケストラを指揮する機会は本当に(理不尽に)少なく、ましてやオペラともなるとさらに(理不尽に)狭き門。シモーネ・ヤングがウィーン国立歌劇場にデビューした時には、同歌劇場初の女性指揮者ということがニュースになったそうですが、それがたかだか90年代前半のこと。つい最近です。そう思うと、今では有名な歌劇場の年間スケジュールに女性の指揮者、演出家、そして作曲家の名を見つける機会はものすごく多くなったように思います。そのうち、もっと多くなるのでしょう。
フィンランド生まれのスザンナ・マルッキ(1969年生まれ)は、もともとはチェロ奏者として活躍していたひとです。本格的な指揮キャリアはまだ20年そこそことはいえ“破竹の勢い”の活躍ぶりで、16年にはヘルシンキ・フィルハーモニー管の主席指揮者に就任。アメリカでも活躍していて、フィンランドの先輩エサ・ペッカ・サロネン直系の指揮者として、現代音楽とオペラを得意とする持ち味が高く評価されています。サロネンが音楽監督の時代から北欧作品に力を入れてきたLAフィルでは、現在、主席客演指揮者です。メトロポリタン・オペラ史上初の女性作曲家によるオペラ作品として、やはりフィンランド出身の作曲家カイヤ・サーリアホの「遙かなる愛」が2016-2017シーズンに上演された時の指揮者もマルッキです。ちなみに、メトのオペラでは史上4人目の女性指揮者だそう(少ない!)。
今回ノミネートされた作品は、盟友ヘルシンキ・フィルハーモニー管との録音によるバルトーク「青ひげ公の城」。彼女はヘルシンキ・フィル管を近く退任することが発表されているので、卒業作品のひとつとなるのでしょうか。
「青ひげ公の城」は、いわばバンパイア・ホラー系の元祖というか、かなりゴシック・ホラー色の濃い作品。重くて暗くて憂鬱になるし、ヒロインが気の毒だし、いくらバルトークとはいえ個人的にあまり好きでない演目だったのですが。もしかしたら、この作品は女性指揮者のほうが向いているのかもしれない。アン・ライスの昔から、バンパイア物語でも女性のことを弱いだけの“獲物“としては表現せず、ゴシック・ホラーの暗鬱さも耽美に妖しく艶やかにドラマティックに描くのが得意なのは、そりゃもう、圧倒的に女性作家たちだったわけですから。
▼同じくマルッキが指揮した、ベルリン・フィルのコンサート形式「青ひげ公の城」のダイジェスト映像。
ヘヴィメタの怖ジャケとか、スプラッタ・ムーヴィーみたいなおどろおどろしいホラー美学ではなく、今どきのゴシック・ホラー・ロマンス物語にも通じる儚さや妖艶さをはらんだ『青ひげ公の城』。それを女性指揮者が、北欧の名門ヘルシンキ・フィル管の深く重厚な響きによって描きあげる…というのは、ありだと思います。
【2】グラス:アクナーテン
カレン・カメンセック指揮 メトロポリタン歌劇場オーケストラ
『Glass: Akhnaten』
Karen Kamensek, The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus
メト(MET)、メトロポリタン歌劇場は、今回は2作品がノミネート。
まずはフィリップ・グラスによるオペラ『アクナーテン』(1983年)のメト初演、2019ー2020シーズンに上演された舞台の録音です。こちらの指揮者も、メトとしては珍しい女性指揮者のカレン・カメンセック(1970年、シカゴ生まれ)。現代もの全般を得意とする指揮者で、特にグラスとのコラボレーションが多いことで知られています。
『アクナーテン』(1983)は、古代エジプト王アクナーテンの生涯をグラスが描いたサブカル大河ドラマ(←ものすごくおおざっぱに言いました)。グラスにとって3作目のオペラ作品で、共作として台本にもグラス自身が名を連ねています。メトとLAオペラと英国ナショナル・オペラによる共同制作で、LAでは16年に、英国では19年に初演、で、大トリがメト…という感じです。カメンセックは、この作品で英国ナショナル・オペラとメトの両方でデビューを飾ることになりました。
▼メト版のトレイラーはこちらです。
なんかもう、圧倒されすぎて言葉が出ない。巨大な美術品みたい。実写版大英博物館みたいな、超ド級スペクタクル。
トレイラーだけでも言葉を失います。このセットに負けないコスタンツォ、尊すぎて目がくらみます。
演出はローレンス・オリヴィエ賞ウィナーの英国人演出家、フェリム・マクダーモット。
キャストやダンサーなどの人間以外のほとんどすべてのことを劇場の自前組織でまかなっているのだから、ほんとに歌劇場ってものすごい効率の悪い芸術だなぁと思います。いい意味で、効率が悪い。効率が悪くなければ手に入れることができない、味わうことができない豊かさがあること。そのことを可視化して教えてくれるために、これだけ贅沢な非日常空間を作り上げてしまう。すごいと思いませんか。
LAオペラ、英国ナショナル・オペラ、そしてメトのすべてでタイトルロールを歌ったのは、今をときめくカウンター・テナーのアンソニー・ロス・コスタンツォ。日本では、2018年に来日して歌舞伎座の『源氏物語』に出演したことでも有名ですが。もはや、現代アメリカン・オペラ界のアイコン的存在といってもよいスター歌手です。キラキラのスタァ。歌ってよし、ルックスもよし、俳優やモデルとしても活躍しているだけあって、舞台での存在感もすごい。ときたもんだ。
無言ですっと立っているだけで、見る者の心に音楽が聞こえてくるようなフシギなオーラが漂っています。
▼そして、その歌声もまた、心の中に直接歌いかけてくるような…。
このひとの歌声を聞いていると、今も空を待っているリアルな天使っていうのがいるとしたら、こういう姿かたちと声をしているのではないかと思ってしまう。
映像ニュースサイトのVoxによる、メト版のメイキング・ドキュメンタリー映像があります。10分ほどの長さなのですが、リハーサルの様子やコスタンツォのインタビュー、スペクタクルな舞台や圧巻のダンス・シーンの裏側などもあって面白かった。ご興味ある人がいるかもと思い、ご紹介しておきます。
▼ライヴ・ビューイング中継の幕間インタビュー。仲良しのジョイス・ディドナートおねえさまとも、キャッキャッいちゃいちゃしてかわいい。いちゃいちゃしながらも、お互いに、それぞれが現在のアメリカン・オペラ界を担う存在だということを認めてリスペクトしていることが伝わってくるのもすてきです。
王妃ネフェルティティ役のジャナイ・ブリッジスも、素晴らしいです。同じ黒人歌手としてジェシー・ノーマンやキャスリン・バトルと並べて語られる、メゾソプラノの逸材。ド迫力、かつ、ぎゅっと抱きしめてくれるような慈愛に満ちた歌声。
▼『アクナーテン』でのクリップが見つからなかったので、サンフランシスコ・オペラの公式YouTubeで公開されている、ブリッジスをゲストに迎えたスペシャル・セッション番組を載せておきます。どぞ。
いちお「最優秀オペラ・レコーディング」という賞は、音源のみが対象となっているわけですが。やっぱりこれは映像で見たいですよね。この映像や美術、ダンサーの要素なども全部ひっくるめて、グラスが思い描いた『アクナーテン』の世界が完結したのではないかと思います。そのあたり、グラス先生のお言葉を聞きたいところですが。
【3】ヤナーチェク:利口な女狐の物語
サイモン・ラトル指揮 ロンドン交響楽団
『Janáček: Cunning Little Vixen』
Simon Rattle, London Symphony Orchestra; London Symphony Chorus & LSO Discovery Voices
サイモン・ラトルは2018年、長らくつとめたベルリン・フィル芸術監督を63歳で退任しました。惜しまれながら辞任する理由を問われ、リバプール出身のラトルが「そろそろ、自分が64歳になった時のことを考えるようになった」とポール・マッカートニーの書いた曲のタイトルを引き合いに出し、激務のベルリンを辞して母国でやり残した仕事をやりたいんだ…と語りました。この発言は、ごくごく一部のビートルズ・ファンの心をつかみました。ごくごく一部、の。ですけど。
ポールといえば、ベルリン・フィル時代にポールと同じ時期に来日していたことがあって、しかも団員(の一部かもしれないですが)はポールが公演中の東京ドーム横にある東京ドームホテルに宿泊していたらしく、彼らが「今、このホテルの隣ではもうひとりのリバプールのSirが公演を…!すげー!」と感動していたという深イイ話を聞いたことがあります。ジョンとポールが生まれたひとつの小さな地方都市で、彼らの10年くらい後にはサイモン・ラトルという別ジャンルの天才が生まれているという奇跡。そのことを考える時、「この売り場から1等3本出ました」という張り紙のある小さな宝くじ売り場のことを思い出します。あんなの嘘だと思っている人が多いかもしれませんが、たぶん、時にはそんなこともあるんです。
ヤナーチェクの『利口な女狐の物語』はラトルのお気に入り演目のひとつで、91年には英国ロイヤル・オペラを指揮した録音がリリースされています。今回は、現在音楽監督を務めているロンドン響との録音。同響が運営するインディーズ、LSOレーベルからのリリースです。
ちなみに、ベルリン・フィル退任の前年(といっても、実質ほぼラスト・イヤー)にしてロンドン響に就任した年でもある2017年にも、ラトルはベルリン・フィルの定期公演でコンサート形式の『利口な女狐の物語』を指揮しています。
▼ベルリン・フィルでの予告映像(有料会員になると公演全編も見られます)。
ベルリン・フィル就任前、ベルリン・フィル時代、そしてベルリン・フィル後…と、それぞれの節目に同じ演目を残したことで、このアルバムはリスナーが“定点観測”的な比較のできる作品にもなりました。比較してもらっても全然オッケー、むしろその変化を見てほしい。そんなおおらかな自信に満ちた作品がノミネートされた今回の結果は、サー・ラトルにとっても意義深いのではないでしょうか。
【4】リトル:ソルジャー・ソングス
コラード・ロヴァリス指揮 オペラ・フィラデルフィア・オーケストラ
『Little: Soldier Songs』
Corrado Rovaris,The Opera Philadelphia Orchestra
2012年に初の長編オペラ『Dog Days』が大絶賛された若き作曲家、1978年ニュージャージー生まれのデイヴィッド・T・リトル。「ソルジャー・ソングス」は初期に書かれた作品のひとつで、バリトンとアンプリファイドな7重奏のための1幕オペラ(上演時間60分)です。初演は06年、もともとピッツバーグのニュー・ミュージック・アンサンブルによる委嘱作品でした。今回ノミネートされたのは、現代オペラで名高いオペラ・フィラデルフィアによって上演された新演出版です。
指揮者のコラード・ロヴァリスはベルガモ出身のイタリア人で、オペラ・フィラデルフィア創設30周年となる2005年に同オペラ初の音楽監督に就任。現在も音楽監督、主席指揮者の座にあります。
モーツァルト、ヴェルディからゴリホフ、ミューリーまで。フィラデルフィアは、全米でも屈指の幅広いレパートリーを誇るオペラ・ハウスで、最近では社会性、メッセージ性の強い現代オペラを積極的にとりあげたり“全米でもっとも攻めてる歌劇場”としても知られています。また、フィラデルフィア管やフィラデルフィア・チェンバー・オーケストラなどでも活躍する地元の精鋭ミュージシャンたちが揃うオーケストラも高く評価されています。
この『ソルジャー・ソングス』も、いかにもオペラ・フィラデルフィアらしい演目です。音楽的にも、こめられたメッセージ的にも、それを今、上演するというタイミング的にも。
主人公は、ひとりの帰還兵。彼の孤独と怒り、苦悩、喪失…を描き、よき市民である兵士たちにとっての戦争とは何かを問いかける硬質な社会派オペラ。こういった現代社会を描くにあたり、当然のことながら時代背景となるジャズやロックの要素もたっぷりと入ってきます。自身がドラマーでもあるというリトルの作品は、リズムによる感情表現の豊かさも特徴的で、いわゆる正統派のクラシカル・オペラになじみがない音楽ファンにも親しみやすく、ひとつの音楽劇として興味深く聴くことができる作品ではないでしょうか(映像で全編を見たことはないですが、ホントは舞台のほうがCDよりさらにぐっとわかりやすいはず)。
▼オペラ・フィラデルフィアによる公式トレイラー。ほぼほぼ映画、としか。
▼こちらは、上演ステージからのピックアップ映像。映像を駆使した演出で見せるマルチメディア・オペラ、という説明どおりです。
こういったオペラは、今、いわゆる“フォーク・オペラ”などと総称され、モノによっては「アメリカーナ・オペラ」と称されることもあったり…という、音楽理論的というよりも概念的な意味でポスト・ロック、インディー・フォークの進化系とも解釈できる新しいオペラ音楽として、じわじわと広がりつつあります。その先頭をゆく作曲家のひとりは間違いなくリトルであり…となると、今回、その作品が現代オペラの庇護者ともいえるオペラ・フィラデルフィアの演目としてグラミー賞にノミネートされた…というのは、やがてエポックメイキングな出来事だったと語られるようになるかもしれません。
デイヴィッド・T・リトルのお名前、ぜひ記憶の片隅にでも留めておいてください。
アメリカの小さなクラブやライヴハウスのスケジュールを眺めていると、バンドやら何やらの中にまじって、フッと謎のオペラ作品の上演がまぎれていたりすることがあります。音楽学校の学生や、作曲家や歌手の卵たちだったりするのでしょうか。トランプ一族をシェイクスピア喜劇風に描いたオペラとか、現代の政治や社会情勢を題材にとりあげているものもあるし。学生の卒業制作のような、意識高すぎてよくわからないようなやつとかもあるし。もしアメリカに住んでいたら、ちょっとのぞいてみたい作品がたくさんあります。
「フォークとオペラは今、急接近しつつあるのよ」と最初に教えてくれたのは、2016年、シンガー・ソングライター(そして、かつてはオバーリン音楽院でオペラ歌手を志していた)のリアノン・ギデンズが初来日した時のことでした。わたしにとっては、彼女の語ってくれたことはものすごく重要な予言というか、希望の言葉というか、その時の話がずーっと心の片隅に刺さったまま今に至っています。そして、このオペラ部門のノミネートを見ながら、彼女が言ったことの現実味が再びじわじわと身に染みてきているところです。
ちなみに、リトルの初の長編オペラ『Dog Days』のほうもかなり社会的メッセージ色が濃い作品です。
近未来を舞台に、戦時下で飢餓生活を送るアメリカ人家族の一家のところに、ある日、犬スーツ(?)に身を包んだ人間がやってくる…という、なんかもう、難しすぎるので、音を聞いて苦手な英語の解説を読んでいるだけではよくわからないお話なんですが。
▼こんなトレイラー見ただけで、めっちゃ見てみたくなります。
なんだかニール・ヤングの『グリーンデイル』を思い出します。
これは現代社会への厳しい一撃を見舞う「Cats」的な意味での犬なのかもしれない…とかシノプシスを読みながら想像しているだけでも、アメリカのオペラ界の未来が楽しみでニマニマしてしまいます。
ああ、どうにかして『Dog Days』と『Soldier Songs』は観てみたいなと願っております。二期会に、深作健太氏の演出で上演してほしいとも想像したり。
ところで。
前回の管弦楽部門の記事でも触れましたが、現在、メトロポリタン歌劇場(MET)の芸術監督として次々と画期的な改革を成し遂げているヤニック・ネゼ=セガンは、フィラデルフィア・オペラとはきょうだい関係にあるフィラデルフィア管弦楽団の音楽監督でもあります。
ネゼ=セガンはMETの音楽監督に指名された時点ですでに、今後のオペラ界を活性化してゆくためにも、将来的にはMETとオペラ・フィラデルフィアはもっと活発に行き来をするべきだと考えており、自分がそれを繋ぐ役割ができればという思いを語っていました。
オペラ・フィラデルフィアがネゼ=セガンに与えた影響は、有形無形をあわせてたくさんありそうです。昨年秋には、MET史上初の黒人作曲家作品となるテレンス・ブランチャードのジャズ・オペラ『Fire Shut Up in My Bones』をシーズン・オープニングで上演したり。2023年のオープニングにはアンソニー・デイヴィスによる1986年のマルコムXオペラ『X, The Life and Times of Malcolm X』を予定していたり。そんなこんなも、NYCオペラのインディペンデント精神というよりは、オペラ・フィラデルフィアのやってきたスモール・メジャー的な発想に近いように思います。今後、メトとオペラ・フィラデルフィアはますます絆を深めて、いずれ本格的な連携プレイを始めるだろうというのが、長年のネゼ・ウォッチャーとしてのわたくしの見解であります。
【おわび】このCDが、なぜかアマゾンjpでは2013年版しか見つからないんですがご参考までに載せておきます!! この盤はサブスクでも聴けるのでぜひ。
※あとでまたリリースを調べて追記します。
【5】プーランク:カルメル会修道女の対話
ヤニック・ネゼ=セガン指揮 メトロポリタン歌劇場オーケストラ
『Poulenc: Dialogues Des Carmélites』
Yannick Nézet-Séguin, The Metropolitan Opera Orchestra, The Metropolitan Opera Chorus
ノミネート作品、最後はいよいよネゼ=セガンです。メトの2018〜2019年シーズン・フィナーレを飾った、プーランクの『カルメル会修道女の対話』。この作品と『アクナーテン』、今回メトはオペラ録音賞で2作品ノミネートの快挙です。
『カルメル会〜』は、フランス革命時代のカルメル会修道女たちの愛と信仰、そして彼女たちが信念と引き換えに処刑台での殉教を受け入れるまでの悲劇を描いたフランス・オペラの最高峰とされる作品です。陰鬱な題材、究極のバッドエンド…という、プッチーニのメロドラマなどとは正反対に位置する重く苦しく理不尽なストーリーでありながら、人間の声と管弦楽を極限まで研ぎ澄ました美しい音楽に救われ、心洗われる。そんな裏腹さに満ちたところにもまた、この作品に貫かれるオペラの真髄を感じます。
▼シアター・ビューイングの日本版トレイラー映像。「本当はこわいグリム童話」みたいなタイトルですが…劇的な終幕でのネゼ=セガンは、残酷なまでにパワフルに、「死」の破壊的なイメージを容赦なく思いっきり振りきります。
映画館のライヴ・ビューイングで見たのですが、その日はちょっと眠れなくなってしまったくらいすごかった。深く深く、えぐられました。でも、そんなつらい作品なのに、俗世まみれの魂が洗い流されてゆくような解放感もあるのですよね。
それは、ブランシュ役を歌ったイザベル・レナードさまの清らかさに救われるせいなのかもしれません。凛とした美しさ。
▼レナード、風の時代のディーヴァ。そんな雰囲気です。
この作品は、プロデューサー・オブ・ザ・イヤーにノミネートされているデイヴィッド・フロストが手がけた作品。なので、この賞でもフロストは受賞対象として名前を連ねています。
ネゼ=セガンが手がけるフランスの作曲家作品。最高です。
彼にとってのフランスって、こういう色彩なのかな…と、いうのが伝わってきます。えもいわれぬ色気と粘っこさ、そして大人っぽい素気やユーモア…などなどを散りばめ、その作品が持つ魅力の間口をぐっと広げてくれるような。
そういえば、ネゼ=セガンがメト・デビューしたのもフランス人作曲家ビゼーの『カルメン』で、その時にもフランス語圏モントリオールに育った自分にはフランス作品との相性のよさがあるんだと語っていました。
今回、ネゼ=セガンがオーケストラ指揮者、オペラ指揮者、ピアニストという3つの才能によって3部門にノミネートされたことは、前回のオーケストラル・パフォーマンス賞のところでがっつりと書きましたのでご記憶の方もおられるかもしれませぬ。
でも。何度書いてもうっとりしてしまうので、もういちど書きます。
・最優秀オーケストラル・パフォーマンス賞(フィラデルフィア管の指揮者として)
・最優秀オペラ録音賞(メトロポリタン・オペラの指揮者として)
・最優秀クラシカル・ソロ・ヴォーカル・アルバム賞(米国のメゾ・ソプラノ、ジョイス・ディドナートと共演したアルバム『冬の旅』で、ピアニストとして)
アメリカ合衆国建国の舞台となったフィラデルフィアのオーケストラとは、黒人女性作曲家の先駆者による作品を称え、再評価したことでのノミネート。オペラ指揮者としての本領を完璧に発揮したフランス・オペラでのノミネート。そして、いちばん最初に音楽への扉を開いてくれたピアノという楽器と共にノミネート。
もう、最強ネゼ=セガン大全集のような3つのノミネートではないですか。
できれば、すべての部門で受賞してほしい。
グラミー賞の授賞式がいつになるかはわかりませんが、その日がネゼ=セガン劇場になりますように。といっても、3つとも、テレビで放映される授賞式の前にチャチャっと発表されちゃう賞ですけどね。

…というわけで、今回もオペラ部門ひとつで1万字を超えてしまいました。
授賞式までには、10万字くらいになるかもしれません。頭おかしいな、俺。
ところで。このメトロポリタン歌劇場が、今年6月に〈METオーケストラ〉名義で11年ぶりの来日を果たします。オーケストラといっても、そうそうたる歌手陣を迎えてのワーグナーやベルリオーズもあります。世の中がこんな状況なので、正直なところ、無事に幕が開くまではドキドキの日々ですが。これから半年間は6月のことを考えただけで生きていけると思うくらい、本当に楽しみです。まー、チケットは、お高いんですよ。来日オーケストラの高騰チケット価格を見慣れたわたしでも思わず3度見してしまったくらいのお値段なので、そのことを考えると別の意味で動悸が激しくなってきますが。いつ海外に行けるかわからないし、彼らが日本に来てくれることも当分ないかもしれないですからね。
メトは11年前、東日本大震災直後の混乱した状況の中でまっさきに来日してくれて、素晴らしい舞台を見せてくれました。あの時は、どれだけ励まされたか。うれしかった。原発事故の問題が世界中で報じられ、来日公演のキャンセルが相次ぐなかで、事前にニューヨークで専門家からレクチャーを受けて来日公演に支障はないと判断し、生まれたばかりの赤ちゃんを連れて来日してくれた歌手もいました。感謝で泣けてきたことを思い出します。
なので、そんなご恩もあり、大好きなネゼ=セガンとMETオーケストラの来日公演を見られる最高に幸せを思えば、大げさではなく本気で失神しそうなチケット代もがんばれます(あら、日本語がよくわからなくなってきました)。
この来日公演を生きがいに、6月まで元気にがんばります!

あ、その前に。次回の「細かすぎて伝わらないグラミー賞」は、最優秀合唱パフォーマンス賞(ベスト・コーラル・パフォーマンス賞)を見てゆきたいと思います。ひき続き、よろしくおつきあいいただければ光栄です。
ではでは、本日はこのへんで。
ここまでお読みくださったみなさま、本当にありがとうございます。こんな駄文におつきあいいただいたわたしは、雪の日に笠をかぶせてもらったお地蔵さんの心境でございます。よかったら最後に「スキ」のハァトを押していただけるとうれしいです。よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
