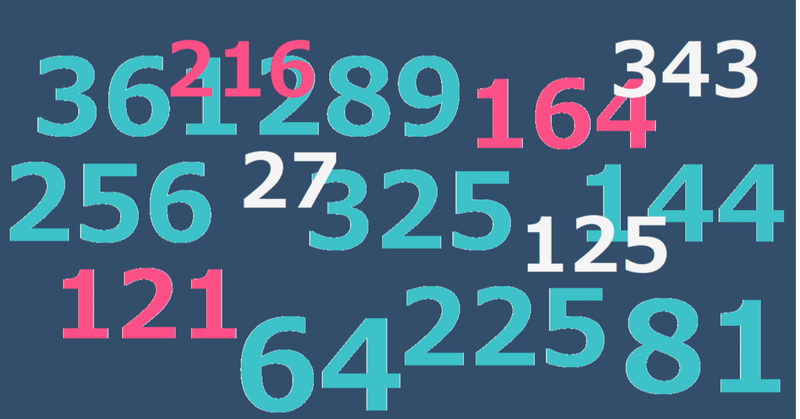
机上の計算を全て鵜呑みにして大丈夫?
住宅業界では、近い将来、更に高い性能が基準となります。
地球温暖化(沸騰化)、エネルギー問題、ゴミ問題、自然災害、などを考慮すれば、しかたのないことかもしれません。
また、性能を決める上では計算が必要となり、
建築士や職人の知識や経験ではなく、PCなどによる計算が全てになりつつあります。
計算上、高い性能があると判断された住宅は確かにその計算された性能については高いのでしょうが、施工性、耐久性など、他の項目に弊害は出てきませんでしょうか?
計算ばかりが進みすぎて、人間の理解が追い付かない状況が生まれないよう、造り手は慎重に判断していかねばならないと感じています。
ぶ厚すぎる壁
断熱性能を上げようと考えた場合、
手っ取り早い方法としては、壁をぶ厚くすることです。
木造住宅よりも壁が厚い鉄筋コンクリート造の住宅が暖かいと感じるはこのためです。
最近では、木造住宅においても、柱の外側にまで断熱材を張り付けて、その上に外壁を張る「外張り断熱工法」が広まっていますが、柱の外側に設置された断熱材が外壁と柱の間に挟まれた様子は、構造的に何となく頼りなさを感じてしまい、今のところ、私どもは採用しておりません。
充填断熱工法にて、高い性能の断熱材を採用しています。
屋根を軽くして重くする
最近は新築にとどまらず、リフォーム現場でも屋根の軽量化はどんどん広まっています。
しかし、一方で、屋根に重量物を載せることを推奨、または、義務化する流れもあります。
構造的に考えると、何をしたいのか理解が難しいですが、エネルギーの観点のみで進められているのは間違いないと思います。
防水上、構造上、重要である屋根の上、
メンテナンスがしづらい屋根の上、
に重量物、かつ、電気設備、を載せるのにはどうしても躊躇してしまい、今のところ、私どもでは採用しておりません。
もっと軽量化、かつ、屋根以外への設置が可能になるのを期待してます。
床下を密閉する
24時間機械による計画的な換気を実施し、家の隙間も極力無くそう、地面からの熱の流入出を抑えよう、と計算していった先に、床下の通気を留め、床下を密閉空間にする工法が生まれました。
床下が自然に通気されているということは、床下空間が外気と言う扱いになりますので、自然通気を留めて、より断熱性を高めようと考えるのは分かりますが、断熱性以外の面で考えた場合、
例えば、劣化などにより水漏れが発生して床下に水が漏れた場合には、水の乾燥がしづらくなると考えられますし、そもそも、床下の空気が澱むのではないかと考え、私どもでは、現在は床下の気流を留める工法は採用していません。
床下、外壁内、屋根内、には自然の風が通り抜けるような工法を採用しています。
造り手により色々な考えがある
どこかの会社が開発した工法、
自社独自の工法、
いま流行している工法、
など、木造住宅と言っても様々な造り方があります。
弊社もこれまでも様々な工法の住宅を建築して参りましたが、
新築からリフォーム、メンテナンスまで全てを自社で行っていますので、微々たるものですが、新築時には見えなかった部分のノウハウが蓄積していく中で、家の造り方を自分たちなりに進化させてきました。
弊社で建ててくださったお客様が長く安心して暮らしていただくには、どのように家を建てればよいか、どのような家を建てればよいか、探し続けています。
今日より明日は良い家が建てられるよう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
