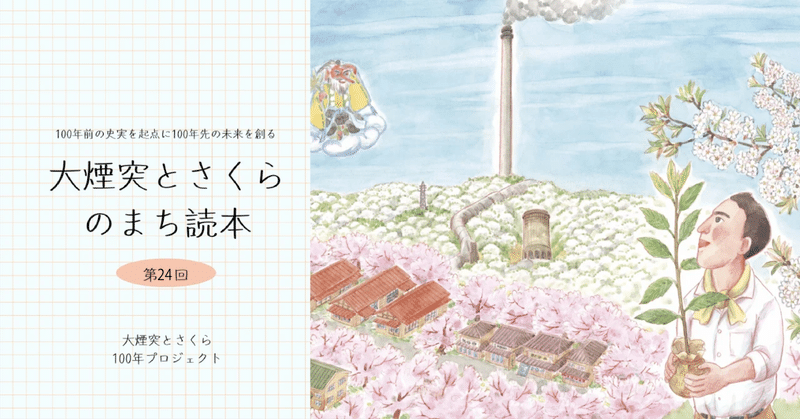
閉山と大煙突の倒壊
日立鉱山の閉山
工業都市日立の誕生(原点)、その後の発展において大きな原動力となった日立鉱山は、鉱量の枯渇により、昭和56年(1981)9月30日に閉山し、76年の歴史に終止符を打ちました。
鉱量の枯渇とは、採算可能な銅鉱石がなくなったことを言います。これ以上操業しても赤字が増大してしまうため、やむなく閉山(※1)しました。
最盛期には、8000人もの労働者が働いていましたが、最後に残った195人の労働者は今後の生活に不安を抱きながら最後を見とどけました。
閉山後の本山
日立鉱山の最盛期には一万人もの人々が供給所、病院、劇場、小中学校、通りに面した小売店や理髪店などがある本山地区に暮らしていました。昭和35年(1960)以降は、合理化等により人口は減少していきました。
閉山後は、数年間、元従業員とその家族約80世帯が暮らしており、通りに面した小売店や理髪店なども数軒営業を続けていました。
残念ながら現在は、社宅は全て取り壊されてしまい、数世帯しか住んでいません。
日立鉱山の跡地には、昭和60年(1985)に日鉱記念館が建設され、日立鉱山をはじめとするJX金属の歴史や煙害問題に地域住民と共に取り組んだ大煙突の歴史が展示されています。
また、社宅があった大角矢・熊ノ沢地区には日立市が運営するキャンプ場を中心としたレジャー施設である「もとやま自然村」が開設されました(現在は閉鎖)。
大煙突の倒壊
大煙突は、工業都市である日立のシンボルとして立ち続けており、周辺の学校(仲町小・宮田小・平沢中など)では、「校歌」にもなっていました。
78年間、日立市を見守っていた大煙突は、平成5年(1993)の2月19日午前9時3分頃、3分の1を残して倒壊(※2)してしまいました。
倒壊の瞬間を見た人の話では、音もなく、わずかな時間に、その姿を保ったまま、ゆっくりと倒れ、スローモーションの映像を見ているようだったそうです。「一瞬とても厳かな感じがしました。ほんとにそんな感じがしたんです。あの日はきれいな青空だったんです。そしたら・・・・まさに大往生という感じでした。貴重なものを見せてもらったな、という感じです」
またある人は、「前日は大煙突の下に、小さいながらクリーンリサイクル炉の煙突ができて、その足場をとりはらったところなので、『俺の役目終った』と思って倒れたのかなと、しみじみ思いました。小学校の頃は遠足というと大煙突、鞍掛山でしたし、冬雪が降ると煙突の見えるカラミ山で雪合戦したり、あの辺り一帯を遊び場にしていたものですから、なんかこう、一つの時代が終わったのかなと、寂しい思いがします」と話していました。
文=篠原 順一
(※1)やむなく閉山
大雄院製錬所では、昭和53年から産業廃棄物から有価金属を回収するリサイクル事業を開始し、日立鉱山は「銅山」から「都市鉱山」へと転換しました。今でも大煙突からは、リサイクル事業によって出た水蒸気が排出されている。
大煙突のライトアップ
平成2年(1990)には、日立青年会議所が大煙突のライトアップを実施した。

(※2)倒壊
「市役所の天気相談所では北西の風16.3メートル(最大瞬間風速)を記録していた。当時、相談所の日誌には、発生時刻とともに「0903大煙突倒壊」と異例の記述が残る」(「茨城新聞」1993年2月18日付)
【主な参考文献】
『大煙突の記録―日立鉱山煙害対策史―』(株式会社ジャパンエナジー・日鉱金属株式会社/1994年)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
