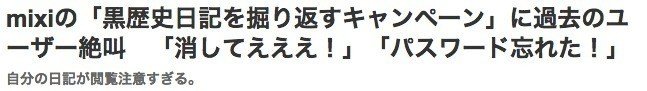6年前の"リアル"を辿る
最近、mixiに久しぶりにログインして、黒歴史を発掘するのが流行っているらしい。
そういえば僕も"mixi日記"とか、大学時代にちょこっとやってたなぁ、などと思いつつ、登録したメールアドレスやパスワードを頑張って思い出しながらログインしてみると、青春をこじらせていた過去の自分の残念すぎる日記が出るわ出るわ。こりゃヒドい。見事なまでの地獄絵図である。もう用も無いことだし、これを機に退会でもしようかしらと思いながらも怖いもの見たさで読み進めていると、ちょうど6年前の年末年始の日記が出てきた。
ほとんど忘れかけていたその内容。だけど、世の中の社会課題に対し、クリエイティブの力で解決を図る"ソーシャルデザイン"と呼ばれる領域への挑戦を決意し転職した今となっては、この当時の体験が、何か原風景的なものとして心の片隅に残り続けていたんじゃないかと感じてしまう。このとき抱いた思いだけは、消してしまうことなく、きちんと残しておかないといけないような気がして、こうやってnoteに再び書き写してみることにした。
・・・
当時、卒業に必要な単位も取り終え、就職も決まっていた大学4年生の後半6ヶ月、僕はインドの商業都市ムンバイで働きながら暮らしていた。海外インターンというやつだ。
就職活動中、周りの人間が平気な顔で言う「自己PR」や「学生時代頑張ったこと」の合唱に内心辟易としながらも、自分にそのように誇らしげに語れる「頑張ったこと」があるかと聞かれれば何一つ無いことに自暴自棄になりつつあった僕は、そんなそれまでの自分を振り払いたい一心で、縁もゆかりもないインド・ムンバイの地に身一つ飛び込み、日本市場に向けたオンライン英文ライティング添削サービスのマーケティングのお手伝いをさせていただいていた。(写真はその会社の"Bonenkai"でのヒトコマ)

そして、今からちょうど6年前、2010年から2011年にかけての年末年始に長期の休暇をいただいた僕は、会社の同僚と二人で、タージマハルやガンジス川で有名なインド北部へ放浪に出かけていた。
これは、その旅のちょうど折り返し地点となる2010年12月末、インドの真ん中から少し北西にあたるジャイプールという町での出来事だ。

〜〜〜 当時の日記、ここから 〜〜〜
日が落ちて辺りが薄暗くなった頃、僕らは朝早くからのジャイプール名所巡りを終え、少し早い時間ながら安宿で休んでいた。
しかし、町の名所には立ち寄ったものの、住民が暮らす町そのものを自分たちの足でほとんど見て回れていないことに満足いかなかった僕らは、疲れた体を起こし、しばらく宿周辺の町をぶらぶらと歩いてみることにした。

しばらく町を歩いていると、地元のインド人と思われる青年二人にカタコトの日本語で呼び止められた。僕らはどうせ何かの客引きだろうと思い、無視して歩き続けた。インドではこういった客引きは日常茶飯事であったし、足を止めてもロクなことがない。しかし、彼らが執拗に話しかけてくる内容をよく聞いてみると、どうやら客引きとは少し様子が違うようだった。客引きを追い払うのにも慣れっこだった僕らは、興味本位からダメもとでいいから少しだけ彼らの話を聞いてみることにした。
彼らが言うには、彼らは何度も日本を訪れたことがあるくらい日本が好きで、(そしてそのうち一人には当時日本人の綺麗な彼女までいて) 日本人らしき僕らを見かけて声をかけずにはいられなかったそうだ。その彼女とのツーショット写真や日本での思い出なんかを見聞きしながら僕らはだんだん仲良くなり、これから家で一緒に飯でも食べながら、日本の話を聞かせておくれよということになった。(※後述のとおり、彼らは本当に素晴らしい人たちでしたが、途上国ではこのように信頼を得ることを目論みつつ用意周到に練られた犯罪まがいのこともよくあるので、特に女性や一人旅の場合においては、見ず知らずの現地人にこのようにやすやすとついていくことは非常に危険です。お気をつけください。)
・・・
僕らは片方のインド人の青年の家で、日本のこととか、インドのこととか、将来のこととか、とにかくいろいろ話をした。インドと日本の架け橋になるというその青年たちの夢から、彼らが日本を訪れた際、日本のラブホテルの至れり尽くせり加減にひどく驚かされたという下世話な話まで、狭くてボロいアパートの一室で、とにかくたくさん話をした。
彼は言った。「俺が日本を初めて訪れたとき、金が底をつきかけててほとんど何も食べていない時期があった。」 「朝方、まだかなり早い時間に一人で喉の渇きと戦いながら路上に座っていると、町を掃除していたおじさんが俺に気づいて、自販機でジュースを買って俺のところまで持ってきてくれたんだ。ほらよ、って。俺は別に何も言っていないのに、だ。信じられなかった。」
「それが俺が日本を好きな理由だよ。」 彼は言った。「朝早くに町の清掃なんかしているおじさんの給料は、そんなによくはないだろう。少なくともいい職業とは言えない。」「そのおじさんが、どこの国の人間だかわからないような男にタダでジュースを買ってくれたんだ。インドじゃ考えられないよ。」 彼は声に力を込めてそう言った。
「ところでお前らは今日、ジャイプールのどの辺りに行ってきたんだ?」 彼らは尋ねた。僕らは『地球の歩き方』に載ってるような名所の名前をいくつか答えた。「おいおい、観光地ばかりじゃないか!」 彼らは声を荒げた。「それでこの町やインドの本質を何も理解せずに帰って行くってのか!? お前たちはここに何をしに来たんだ!?」 彼らは言った。「明日、俺たちに時間をくれないか? "本当のインド(Real India)"を見てもらいたいんだ。」
「明日、"スクール"がある。お前たちを明日、そのスクールに招待したい。」 僕は、彼らが大学に通っていると聞いていたので、きっとその大学を案内してくれるものだとばかり思っていた。インドの大学生がどんな毎日を送っているのかを見せてもらえるものだと。興味が湧いた僕らは少し迷いつつも、翌日の予定をキャンセルすることを決め、その場で「わかった」と答えた。
「よし、とにかく今日は仲良くなれたお祝いをしよう! この家の2階は手作りディスコになってるんだぜ。そこで酒でも飲んで、思いっきり踊ろうぜ!」 照明からDJブースまで、本当に手作り感満載のディスコの中で、僕らは彼らと飲んでは踊った。「今日は良い日だ。親友ができた。ありがとう。」 彼らは言った。「俺たちはこの瞬間のために生きているんじゃないかって時々思うんだ。こうやって、思い出を集めてるんだ。そして死ぬときに、一つひとつの思い出をもう一度思い浮かべながら、最高な死を迎えるんだ。だから俺は、この瞬間を絶対に忘れない。」
楽しい夜も22時を過ぎると、前日が凍えるような車中泊だったこともあり、さすがに疲れがどっと出てきたので、僕らは明日会う場所と時間を決めて、宿へと戻った。
・・・
次の日の朝、僕らは宿の近くで待ち合わせをし、彼らの友達も加えた5人で"スクール"へと向かった。
「この中だ。」 彼らに案内されたその場所は、観光客や外国人なんて一人もいない、寂れた町の一角に、まるで壊れた踏切のようにひっそりと佇んでいた。においが違った。すぐにわかる違いだ。彼らは言った。「俺たちのスラムへようこそ。」

僕らはその中にあるという"スクール"に向かった。僕らの姿を見つけた子どもたちが駆け寄ってきては、物珍しそうに僕らを眺めた。外国人の来客なんて、そうそうやってこないのだろう。「この子たちには親がいない。俺たちが親代わりだ。」 彼らは言った。正直、そのとき僕は、アフガニスタンの難民キャンプを訪れた藤原紀香にでもなったような気分だった。目に映る全てが、ガラス細工のように脆く瞬いていた。



「ここが俺たちの"スクール"だよ。さぁ、中に入ってくれ。」 通された場所は、とても教室とは言いがたい、冷たい空気が肌に染みる狭くて何も無い、ガランとした灰色の部屋だった。「俺たちはここで、英語や音楽を子どもたちに教えてるんだ。ボランティアとしてね。さ、もうすぐ授業だ。まぁ、その辺に腰掛けて見てってくれ。子どもたちもきっと喜ぶ。」
しばらくすると、子どもたちがどこからともなく集まってきた。ここに来る途中で見かけた子どもたちの姿もあった。みんな、授業が楽しみなのか、笑顔ではしゃいだり、じゃれあったりしていた。子どもたちの笑顔は、ひどく眩しい。

子どもたちは"先生"と一緒に、ABCの歌を歌って、習ったアルファベットを復習していた。「どうだい、みんな賢いだろ?」 "先生"は自慢げにそう言った。「さーて、次は音楽の授業だ。"あれ"を取ってきてくれ。」 しばらく待っていると、一人の男の子がタブラ(インドの打楽器・パーカッション)を持って現れた。
「こいつはタブラがすごくうまいんだ。みんな、歌の準備はいいか?」 子どもたちは童謡『チューリップ』のヒンディー語バージョンを合唱した。さいたさいたのメロディーに合わせて僕らは手拍子をした。

「このコはな、ダンスが得意なんだ。ほら、お客さんに見せてやりな。」 そう言われると子どもたちは待ってましたと言わんばかりに立ち上がり、タブラの演奏に合わせて踊りを披露してくれた。
僕は、子どもたちが歌ったり踊ったりする姿を眺めながら、一人ぼんやりと思いに耽っていた。12月。もうすぐ年が明ける。この6ヶ月の海外インターン生活の中間地点。もう半分が過ぎて、春にはまた現実に戻らなければいけない。子どもたちは歌う。僕はまた歩き出す。"始まりの終わり"と"終わりの始まり"のあいだで、君は歌って、僕は笑った。

・・・
"スクール"が終わると、彼らは「見せたい場所があるからついて来てくれ」と言った。僕らは子どもたちとお別れをし、彼らの後を言われるがままについて行った。
ちょうどスラムの真ん中辺りにその場所はあった。低いコンクリートの塀で囲まれた、ただっぴろい空き地。ビニール袋やら家庭のゴミやらが、まるでそこがゴミ捨て場かのように、あたり一面に散らばっていた。汚い場所だ。僕は思った。その場所の汚さは、スラムの中でも際立っていた。
「ここはな、"希望の場所(Place of Hope)"なんだ。」 彼らは目を細めながらそう言った。希望? ここが? このゴミと悲しみの吹き溜まりのような場所が?
「俺たちは寄付金を集める活動もしているんだ。少しずつだけど、お金も集まってきている。本当に少しずつだけどね。十分なお金が集まったら、新しい学校を建てるんだ。今の"スクール"とは比べ物にならないような立派な学校をね。俺たちはその日を信じて活動してるんだ。学校が建つんだよ。この場所に、いつか、ね。」
僕は自分が2ミリくらい地面から浮かんでいるかのようなふわりとした気持ちで、漠然とした空白を感じながらその場所に立ち尽くしていた。何も言えなかったし、何も考えられなかった。彼らの言うとおり、そこには確かな希望があった。夢や希望について歌ったどんな歌よりも確かな希望がその場所にはあった。こんなにゴミだらけで薄汚れた美しい希望は初めてだ。僕はそう思った。それだけを、思った。

・・・
スラムを出て市街に帰る途中、僕は子どもたちの無垢な笑顔を思い出していた。スラムの子どもたちは確かに貧しい。親もいなければ、十分な教育だって受けられない。でも、あのコたちは僕が持っていないものを持っていた。僕が失ってしまったものを持っていた。僕が欲しくてたまらないものを持っていた。
それは、純粋性だ。ガラス玉のよう滑らかに透き通った、混じりけのない純粋性だ。その乱暴な純粋性は僕の心を小刻みに摩擦し、熱を帯びた僕の心はジャイプールの渇いた風に吹かれてヒリヒリと痛んだ。
彼らは自分の足で立って歩いている。子どもたちも、それを支援する青年たちも。僕らは固く握手をした。「忘れないよ。ありがとう。いつかまた会おう。元気でな。」

・・・
僕は次の目的地に向かって歩き出す。はたして僕は、しっかりと自分の足で歩けているのだろうか。その答えは、誰も教えてはくれない。
年末年始に僕が見た、もう一つのインド。『地球の歩き方』には載っていないこの国の影。人生の歩き方を問われる、もう一つのリアル。
〜〜〜 当時の日記、ここまで 〜〜〜
先述したとおり僕は、世の中の社会課題に対し、クリエイティブの力で解決を図る"ソーシャルデザイン"と呼ばれる領域への挑戦を決め、2016年末に転職をした。その背景にある思いについては、いつかもう少し詳細に書き綴ろうとは思っているが、この6年前のジャイプールでの出会いが、"スクール"のにおいが、"希望の場所"の風景が、ずっと心の片隅に残り続け、僕をこうして導いてくれたんじゃないかと、そんな思いを噛みしめている、2017年の初頭である。
<このnoteを書いた人>
Daiki Kanayama(Twitter @Daiki_Kanayama)
1988年生。大阪大学経済学部を卒業。在学中にインド・ムンバイ現地企業でのマーケティングを経験。ソフトバンクに新卒入社後、孫社長直下の新事業部門に配属。電力事業や海外事業戦略など、様々な新規事業の企画、事業推進に従事。創業メンバーとしてロボット事業の立ち上げを経験後、専任となりマーケティング全般を担当。2017年、プランナー兼コピーライターとして、活躍の舞台をブランディングを軸としたクリエイティブエージェンシー AMD ltd. に移し、CSVやSDGsに絡んだ新規事業、新商品サービスの企画、自社事業となるSOCIAL OUT TOKYOなどを担当。2020年、ビジネスインベンションファーム I&CO にエンゲージメントマネージャーとして参画。
受賞・入賞歴に、Clio Advertising Awards、Young Cannes Lions / Spikes、Metro Ad Creative Award、朝日広告賞など。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?