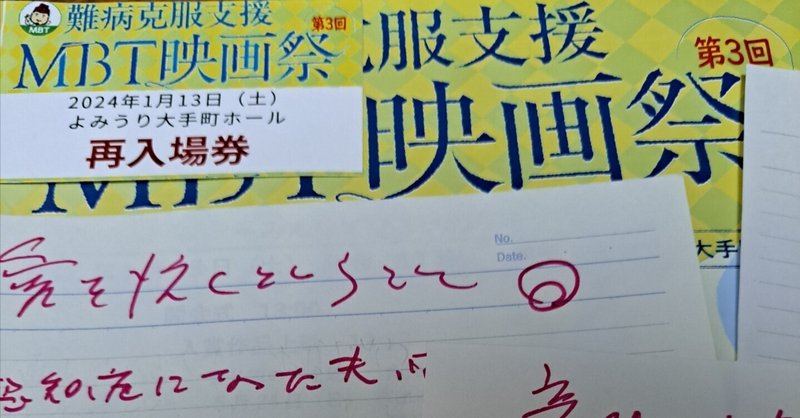
難病克服支援 第三回 MBT映画祭
去る一月十三日、私は「難病克服支援 第三回MBT映画祭」に参加するため、よみうり大手町ホールまで出かけた。

この映画祭は、難病により社会から孤立しがちな患者の苦境を多くの人に理解してもらい、難病研究者やその治療に携わる人を支援する「難病克服キャンペーン」の一環とした映画祭で、テーマ"はみんなで守る命"だが、難病に限らずあらゆる命にまつわる題材の映像作品を募集した映画祭である。
「公立大学法人奈良県立医科大学」と「一般社団法人MBTコンソーシアム」 主催で、当時、コロナ禍真っ只中にあった二〇二一年からスタートした。
今回が初参加という形だったので、一体どんな作品が上映されるのか私には想像もつかなかったが、今回、この映画祭に参加できて、とても有意義な時間を過ごすことができた。
この日は出掛けの電車の中から、映画祭は始まっていたような気がする。たまたま私の隣に座った女性がヘルプマークをぶら下げていた。
女性がスマートフォンを落としてしまったことで、私が声をかけていれば話す機会はあったのだが、さすがに初対面の方に、
「日常生活でどれくらいこのヘルプマークを認識している人、もしくは気づいてくれる人がいるのか?」
などと質問するのはどうかと思い、私は知りたい気持ちをグッと堪えて女性が電車を降りるのを見送った。
すぐ隣に体に不具合を抱えている人が世の中にいるのだと、私はこの時、改めて思ったのだった。
会場であるよみうり大手町ホールに到着し、座席に着いた私は隣に座った女性と話をする機会を得た。
女性は現在七十五歳でリウマチを発症し、それから五年前に指定難病である原発性胆汁性胆管炎(PBC)を発症したという。
私はこの病名を初めて聞いたものだから全く何のことか分からず、女性に了解を得てあれこれと質問させて頂いたが、どちらかというと症状がはっきりと出るリウマチの方が辛いと言い、指定難病である原発性胆汁性胆管炎の方は、症状が悪化しないと、良くも悪くも病気が表立って出ないため、日常生活に於いては余り気にならないという。
自分も指定難病を患っていることもあり、偶然、この映画祭の存在を知り、今回、思い切って出かけて来たのだという。当事者のリアルな話を聞けて、私は女性に礼を言った。
今回は丸一日と言ってもいい日程、十三時〜十九時半過ぎまでという長丁場だったが、中々観る機会のないテーマの商業映画ではない短編、長編作品を観ることが出来た。
入賞作品は以下の七作品【タイトル・監督(敬称略)】である。
「寄り鯨の声を聴く」角洋介
「5月24日(日)」恵田侑典
「サンクスレター」相馬優太
「産むということ」マキタカズオミ
「愛を抱くということ」宮田悠史
「イスラム|君と歩む」磯部和弥
「彼女はヴィーガン」安田瑛己
どの作品も、最終選考まで残っただけあり素晴らしかったが、その中でも私の心に最も残った四作品を挙げたいと思う。
「5月24日(日)」
三人家族の主人公の女性がだんだんと耳が聴こえなくなっていく状況を描いた作品だったが、息子や夫が帰って来ると台詞が一枚膜を被ったような音に変わり、観客はその音声がどうして膜を被ったようになるのか最初は理解に苦しむが、それは段々と耳が聴こえなくなっていく女性の「耳の状態」を表しているということに、観ていくうちに気がつく。
最後にはその一枚膜を被ったような声さえも聴こえなくなってしまう状態になるのだが、演出とはいえ台詞という点を考えると、観客に聞き取れないのは致命的だった。ここは敢えてサイレント映画時代に伊藤大輔監督が用いたような、字幕そのものが生きた人間の台詞のように使われていたら分かりやすかったのではないかと感じた。
リピートの映像には少しくどい印象を受けたが、耳が聴こえなくなって行く当事者と、見守る側の人間のどちらの立場も見せた演出は、良かったのではないだろうか。
「サンクスレター」
幼い頃、臓器提供を受けた中学三年生の大智が、臓器提供者に向けて出すサンクスレターをテーマにした作品。
大智はクラスメイトにサッカーを誘われても断り、顰蹙(ひんしゅく)を買っている。 全てのことにおいて「抑えた」日々を送っていたが、それはもしかしたら臓器を提供してくれたドナーに対する、彼なりの礼儀とでもいうのか、最低限しなければならないことだったのではないかと思った。
自身の健康に自信が持てないまま成長したことで、もしかしたら内気になっているのかと思ったりもしたが、実は受け継いだ臓器を大切に思う余り、大智は自分の中でしてはいけないことを知らず知らずに作って生きて来てしまったのかもしれないとも思えた。
この脚本を担当した女性が、私のすぐ目の前の関係者席にいらっしゃったので、その真意を聞きたいと思ったのだが、結局訊けず仕舞いで終わってしまった。
この大智の「本音」がどれに当てはまるのか。そこがどうあるかでまた作品の印象も変わったかもしれないと思った。
「産むということ」
出生前検査の話をテーマに物語が進んでいく。
三十八歳で妊娠した女性が病院で検査を勧められた。医師は可能性という言葉で検査を受けてみてはどうかと話した。しかし、これらの検査を医師が患者に勧めた時点で、もう大体が陽性というのが世の常である。
そこから夫婦の葛藤が始まる。そんな中、女性の夫の仕事仲間が虐待の容疑で逮捕されるという、衝撃的な事件が起こる。
その子供は特に何の疾患もない元気な女の子だったというが、発見保護された時にはガリガリに痩せ細った状態だったという。
それから女性は中絶手術を決め、医師から淡々と説明を受けた。私は女ではないから分からないが、この中絶手術の説明を受けているうちに「産まない」という選択が覆ることはないのだろうかと、密かに思ったりしたが、やはり、中絶を選んだ女性は自分の選択が間違いだったのではないかという罪悪感に、退院してから苛まれ始める。
私はここで子供をあっさり産むという選択をしなかった母親の姿が、逆にリアリティがあって良かったと思った。
夫婦はもし、次に子供に恵まれる機会が訪れた時は出生前検査をせず、産んで育てようという思いを確かめ合った。そして、二度目に授かった子供は、一人目の時に検査を受けて判明したダウン症を持った女の子だった。
私はこのシーンを見た時、この女の子は一人目の子供の犠牲があって生まれて来た女の子なのだと思わずにはいられなかった。
この女の子は、夫婦に一人目の子を産むという選択をされていた場合、もしかしたらこの世に存在していなかったのかもしれない。そう思うと、出生前検査というものはあっていいものなのか、それとも悪いものなのか、私は分からなくなってしまった。
人の命が誰かの犠牲の上に成り立つということは、良いことなのか悪いことなのか、子を持ったことのない私には分からない。しかし、親になるということは、それだけ責任の重いことであることも確かで、一人目の子供の命を犠牲にしてまで考えなければ決断ができない程、覚悟を必要とすることなのだと、この作品は示して見せたのではなかろうか。
「愛を抱くということ」
認知症になった夫が自宅の庭の花を摘んで、バス停で誰かを待っているところから物語は始まる。
夫婦は中学生の時の同級生なのだが、もう夫は自分のことを覚えていないと妻は思っていた。それがどうしようもなく悲しく切なかったのだが、ある日、夫の真意を知った妻は、夫の病を受け入れることが出来た。夫は妻と初めて出会った中学生だった頃を生きていたのである。
妻に思いを寄せていたその気持ちは、認知症になった今も変わることがなかったことを妻は知り、再び夫と、そして認知症と向き合うことを決意する。
ストーリーとしては心温まる作品だったが、もう少し認知症患者と介護者の過酷な実態を交えても、説得力があって良かったのではないかと思われた。
最優秀賞を受賞したのは、マキタカズオミ監督作品「産むということ」だった。文句のない受賞であった。優秀賞は、磯部和哉監督作品「イスラム|君と歩む」特別賞は、相馬雄太監督作品「サンクスレター」
入賞は、角洋介監督作品「寄り鯨の声を聴く」恵田侑典監督作品「5月24日(日)」宮田悠史監督作品「愛を抱くということ」安田瑛己監督作品「彼女はヴィーガン」という結果であった。
全作品の上映が終わり、休憩を挟んで審査員の監督たちと、映画祭に出品した監督たちによるトークセッションが行われた。
映画製作に関する裏話的な話を聞けたことで、作品に対する印象もだいぶ変わる話も多かった。映画作りの難しさ、そして楽しさというものを監督たちから聞くことができたことも、貴重な時間であった。
この映画祭に参加した観客たちは、医療従事者の方々が多かったようだったが、それ以外の医療とは全く関係のない人間がこういった映画祭に関心を持ち、難病を抱えて生きている人間が自分のすぐ隣にいるということを認識する、そんなきっかけになれば何よりと感じた映画祭だった。
そしてこの日、最後に特別上映されるスペシャルプログラム「最高の人生の見つけ方」が上映された。
映画祭の主旨に賛同なさったこの映画の主演女優である吉永小百合さんがステージに登壇し、舞台挨拶をなさって映画祭のフィナーレに花を添えた。
曲がりなりにも物を書く人間である自分が、こうして分野の違う映画からも構成であったり、シナリオだったり勉強させられることが多く、得るものも多かった有意義な一日となった。
2024年1月14日 書き下ろし
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
