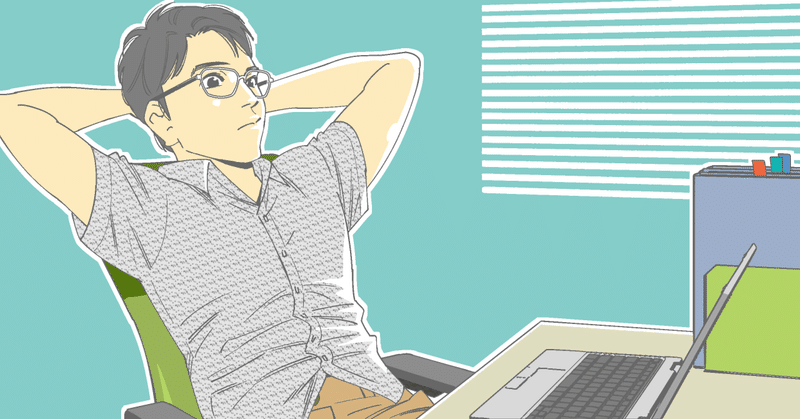
仕事は面白いものなのか?
以前コーチングをしているときに、クライアントから、「仕事は面白いものなのですか?私にはその感覚はありません」と言われたことがあった。「仕事は、生活するためにしていること、だから面白いものではない」というのがクラインの考え方です。何が、仕事の面白い感覚なのでしょうか?
仕事の「やりがい」や「楽しい」とは
クライアントに、仕事への関心や期待を聞いていくと「やりがい」「楽しい」といったキーワードに良くいきつきます。
こういったキーワードでWEB検索をしたらアンケート調査結果を見つけましたのでリンクを貼ります。その結果によると6割の人が仕事を面白いと思っているようです。主な理由としては、「感謝されたとき」「仕事がうまくいったとき」「顧客や会社に貢献できたとき」などのようです。上位の回答は、仕事を終えたときや結果が出たときの感想が多いですね。
4割の方は、仕事が楽しくないようです。私のクライアントは、それらの体験をしてこなかったのでしょうか?それともの楽しいと思う以上に「きつい」「つらい」体験をしているのでしょうか?
参照
「面白くない」から仕事を辞める
クライアントの論理は、仕事に「面白さ」を求めると、「面白く」なくなったときに、退職する結果になる。生きるために仕事をしているので、「面白い」ことを追求するものでもないようです。望ましい結果が出なかったときは、面白くなくなるのでしょう。確かにこれはこれで言い分がありますので、理解はできます。
一般的にいえるのは、どんな仕事でも、面白い部分と辛い部分があるということでしょう。自分がどこまで許容できるか、ということで各自が判断すれば良いのだと思います。辛い部分と向き合うことも重要そうです。
面白いことの感覚とは?
大人になるにつれて「面白い」ものが減ってきている感覚があります。昔は、友達と一緒にいるだけで楽しかった。友達と一緒に遊ぶ時間がなくなったことが原因でしょうか?
これらは、「楽しさ」「面白い」は他者に依存していることと考えています。言い換えると「与えられたもの」です。会社も、仕事仲間も、普通は友達ではないし、家族でもない。つまり誰も「面白さ」を与えてくれないのです。他人から与えられた「面白さ」は持続しないのです。
「面白さ」は自分自身で、意識して追求しなければ、手に入れられないのではないでしょうか?
逆の見方をすると、他者に依存しているものからの脱却であれば、「一人でも面白いと思える感覚」を探すことが、新しい視点になるかもしれません。一人で何かするのは、なかなか勇気のあることです、それにより今まで経験したことのない取り組みを探せるかもしれません。
「やりがい」の感覚について
スポーツを仕事にしているアスリートは、秀でた才能を職業にしており「天職」に恵まれた人たちだと思います。アスリートの努力は他人に依存したものではありません。日々の努力を、「辛い」という感覚を凌駕して前向きに消化していきます。
この感覚が、「やりがい」に近いのかなと、個人的には思います。
まとめ
仕事における面白さに裏にある。「楽しさ」「やりがい」を聞く質問を2つ考えてみました。ご参考になれば幸いです。
「それは、一人でもやろうと思いますか?」
「それは、努力(辛さ)を忘れて取り組めますか?」
最後までお読みくださりありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
