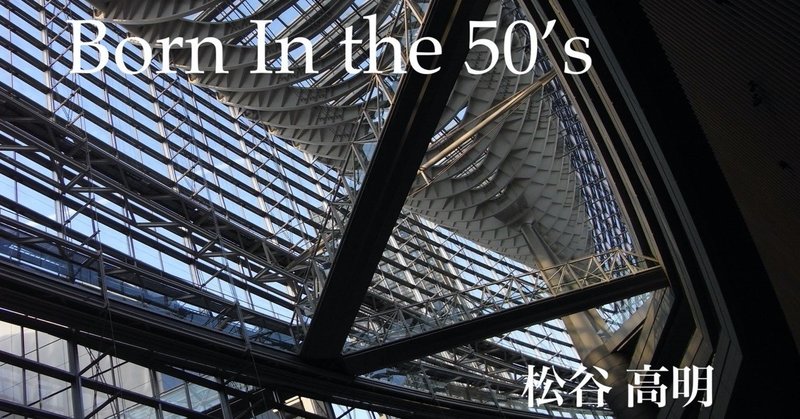
Born In the 50's 第八話 microSD
microSD
原稿をひとつ書き終えると石津は大きな伸びをしてiMacの画面で時間を確認した。
ちょうど昼時だった。
デスクの上においてあるカップの紅茶はすっかり冷め切っていた。
ひと口啜ると立ち上がり、カップを持ってダイニングへいった。流しの前に立つとカップの中身を捨てて、その場でカップを洗い、水切りカゴに置いた。
しばらくの間、逡巡したがどうしても昼を作る気にはなれず、出かけることにした。
ベッドルームでジャケットを羽織ると、リビングのデスクの上に置いたウォレットやiPhoneをポケットに入れた。
ドアに鍵をかけるとマンションを出て、バス通りをそのまま駅へ向かった。商店街を通り抜け、JR中央線のガードをくぐるとさらにバス通りを歩いていく。
やがて左手に本屋が見えてきた。
その脇の階段を登り、二階の店へと入っていった。
ドアを開けて中に入る。
「いらっしゃい」
カウンターの向こうで洗い物をしていたママの早紀が石津に声をかけた。そのとなりではマスターの昌夫が珈琲を淹れている。
「やあ」
石津はそう声をかけると店の奥へそのまま進み、窓側の一番端の席に腰を下ろした。窓の向こうにはさっき歩いてきたバス通りが見える。
店内を見回すとカウンターに近いテーブルにひと組客がいた。
「お昼?」
早紀はトレイに乗せて運んできたグラスをテーブルに置いた。
「うん、なにがある?」
「魚がいい? それともお肉かしら」
トレイを持ったまま早紀が尋ねた。年齢は石津よりもちょっと上といったところだろうか。ショートカットの髪を淡いブラウンに染めている。面倒見のよさそうな笑顔だ。
「そうだなカレーでいいか」
石津は早紀の顔を見ながら答えた。
「なにか乗せようか? カツとかハンバーグとか」
「じゃ、ハンバーグを」
石津が頷くと、早紀はそのままカウンターへと戻っていった。
昼間は食事と珈琲がメインで、日が暮れるとアルコールも飲める店だった。石津のいわば隠れ家のようなところだ。こうやって昼を食べに来ることもあれば、下の本屋で買った本を抱えてやって来て、そのついでにと珈琲を飲みながら読み耽けることもある。ときには帰りにふらっと寄ってバーボンを飲んで一日の疲れを癒すこともあった。
iPhoneでニュースを確認していると、やがて早紀がカレーを運んできた。
ご飯の上にはハンバーグと目玉焼きが乗せられ、その上からカレーがかけられていた。傍らにはサラダも添えられている。
「ねぇ、昨日の事件見た? すごいわよね、ハイジャックだって」
「ああ、昨日の昼過ぎから大騒ぎだったからね」
石津はスプーンを手に取ると頷いた。
「あっという間に姿を消したっていうじゃない。どういう連中かしら」
早紀は石津のテーブルの横に立ったまま続けた。
「プロだよ。武器もちゃんと用意していたみたいだし、戦闘を専門とするプロ中のプロだろう」
石津はカレーを食べながら答えた。
「いるんだ、戦闘のプロって」
早紀が訊いた。
「世界中にいるよ。傭兵をやっていたり、ガードマンやコンサルタントをやっているやつもいる。手際の良さから考えても、どこかできちんとした訓練を受けたやつだろうね。こういう犯罪って日本じゃ珍しい」
石津はサラダにも手を伸ばす。
「物騒な世の中になったってことなのかしらねぇ」
早紀はそういいながらカウンターへと戻ろうとした。
「でも、どうやって逃げたのかしら?」
途中で立ち止まるとそのまま振り返り石津の顔を見た。
「橋脚のところにロープが垂れ下がっていたって話だから、車両を爆発させている最中に、川へ下りたんだろう」
石津はちょっと考えてから口を開いた。
「泳いで逃げたのかしら?」
「まさかそれはないよ。きっとボートだ。いまだとアタッシュケースぐらいのサイズの折りたたみ式のカヌーもあるからね。それにしても大胆不敵だし、鮮やかな手口だ」
「お金も消えちゃったみたいだし」
早紀はそういってカウンターに戻った。
石津はiPhoneでそのニュースを確認しながらカレーを食べた。
「珈琲もらえるかな」
カレーを綺麗に平らげると、石津はカウンターに向かっていった。
「いつものでいいかい」
今度は昌夫が返事をした。
「ああ、頼むよ」
石津は頷くと、またiPhoneに視線を移した。
ドアベルが鳴ったあと、すぐに向かいの席にだれかがやってくる気配がして石津は顔を上げた。
男がひとり向かい側の椅子を引き、座ろうとしていた。がっちりとした体格。引き締まった顔をした男だった。スーツをきちんと着ているが、どこか後ろ暗さを匂わせる空気が漂っていた。
「相席するほど混んじゃいないと思うんだが」
石津が相手の顔を見て口を開いた。
「石津さんですね」
その漂わせている空気とは違って穏やかな口調だった。
「田尻といいます。申し訳ないが身分を証明するものは持ち合わせてはいません。職業柄ということでご理解いただきたい」
田尻はそういって右手をテーブル越しに差しだした。
「その田尻さんがなんの用件でしょうか?」
石津はその分厚い手を握り返すと訊いた。
「協力をお願いしたい」
田尻はそういうとまっすぐ石津を見た。
そこへ昌夫が珈琲を運んできた。
「ありがとう」
石津は昌夫にいった。
「わたしにも同じものをいただけますか?」
田尻も昌夫に声をかける。
「ブラックでいいですか?」
「ええ」
田尻が頷くと昌夫は訝しげな表情を残したままカウンターへと戻っていった。
「これを」
田尻はそういうと写真をテーブルに並べた。
そのとき、石津はスーツの下に下げられている銃を見た。
「それはグロック?」
石津は写真ではなく田尻の顔を見て訊いた。
「さすがですね。観察力が鋭い。わたしは早見さんと同じ職場で働いているものです」
「なるほど。だからそんな物騒なものを下げて街を歩けるわけだ」
「はい」
田尻は頷いた。
「で、この写真がなにか?」
それは早見の通夜と葬式のときの写真だった。石津に濱本それに近藤がそれぞれ写っている。
「早見さんの大学時代の友人ということでしたね」
「そうか、あのとき受付のテントにいたな」
「ええ」
田尻は頷いた。
「あなたたち三人がやられていることは、だいたい想像がついています。この前、北陸の方へいかれましたよね。三人揃って。それも制服を着て」
石津はどう答えていいのかわからず、ただ黙って田尻の顔を見た。
石津は表情をある程度コントロールすることができる。それはジャーナリストという職業柄、感情的な表情で迫っても相手からまともなコメントは引き出せた試しはないという経験からだった。
いまは冷静な振りができているはずだ。しかし、向かい合っている田尻も同様に表情に大きな変化がなかった。
どういうつもりでこの話を持ち出したのか? 石津にはそれを想像することができなかった。
「それで?」
努めて冷静に石津は訊いた。
「ですから協力いただきたい」
「どんな形で?」
「詳しい説明はあとでしますが、捜し物を手伝っていただきたいのです」
「捜し物?」
石津はそういうと腕組みをした。
「早見さんのお宅に伺って、あるものを探してもらいたい」
「北陸の話は?」
石津はテーブルに肘を突いて訊いた。
「わたしだけしか、まだ知りません」
「交換条件か?」
石津は珈琲カップに手を伸ばした。ひと口啜る。
「そう考えたいのであれば、それで結構です」
「その捜し物はなんのためだ? それでなにがわかる?」
石津はふたたびテーブルに肘をついた。
「もしかすると早見さんの事故についてもわかるかもしれません」
田尻はほとんど身動きせずに話を続けた。
昌夫が今度は田尻の珈琲を運んできた。
「ありがとう」
田尻は笑顔でいった。はじめて田尻が見せた表情だった。だが、石津に視線を戻すとその顔はまた元に戻っていた。
「その他にはなにがわかるんだ?」
「実は、なにがわかるのかわからないから探しているんです」
田尻はそういって頷いた。
「早見がデータに不正アクセスしたってことなのか?」
石津は早見宅へと向かう車の後部座席で田尻に訊いた。
「その可能性が」
となりに座っている田尻が頷いた。ハンドルを握っているのは、田尻を補佐する形で行動を共にしている局員の沢口だ。
石津たちは店を出ると沢口が運転する車、黒のマークXに乗り、早見宅へと向かうことになった。車はいったん環八に出ると南下して、中央高速を使い国分寺を目指していた。
「でも記録に残っているデータを調べても、とくに重要なものではなかったということじゃないのか?」
石津は頭を整理しながら田尻に質問をしていた。
「でもそれはあくまでも残っているデータは、ということになります。ファイルを入れ替えられていればその限りではありません」
「確かに、そうだ」
石津はちいさく頷いた。
「しかし、なぜ俺たちなんだ?」
「早見さんのことをよく知っているあなたたちなら、わたしたちとは違った視点で物事を捉えられるかと思ってのことです」
田尻は石津の顔を見ながら話をした。
「でももう徹底的に探したんだろう、お宅たちが」
石津は訝しげに訊いた。
「奥様もいますから、あくまでも可能な限りといったところです」
「だからといって俺たちなら見つけられるとは限らないぜ」
石津はそういうとシートに深く座り直して窓から外を眺めた。
車はやがて高速の出口、国立府中のインターチェンジに入った。高速を降りるとすこし逆戻りする形で国分寺駅を目指して北上する。そのまま駅の南側へ出ると早見宅へと向かった。
早見のマンションの前に車が着くと、そこには濱本が待っていた。石津が呼び出したのだ。
「早かったじゃないか」
石津は車から降りると、濱本にいった。
濱本は石津の後ろから下りてきた田尻の顔を確かめるように見つめてから口を開いた。
「連中か?」
「ああ」
石津はただ頷いた。
「どこまでバレてるんだ?」
濱本は小声で訊いた。
「なにブラフだよ。三人で出かけたことはバレてるみたいだけどね。なにをやったのかまでは解っていないはずだ」
石津は濱本の肩を軽く叩いて微笑んでみせるとそのままマンションのエントランスに向かった。濱本も続く。その後ろから田尻も着いてきた。どうやら沢口はそのまま車に残るようだ。
エントランスの中に入るとオートロックのパネルに向かって田尻が挨拶をした。
パネルの向こうから映子の返事が聞こえてロックは解除された。
今度は田尻を先頭に歩いていく。エレベーターを使い四階へ上がると、まっすぐ早見宅へと向かった。
チャイムを鳴らすと鍵を開ける音がして、ドアが開いた。
「お邪魔します」
田尻は律儀に一礼すると中へ入った。石津も続く。
玄関のところで映子が不安そうな顔をして立っていた。
「大丈夫か?」
石津は映子に声をかけた。
「なにがどうなってるの?」
映子は髪をかき上げると石津に訊いた。
「詳しいことは解らないが、早見が局からなにかを持ち出したらしい。それを一緒に探してくれというんだ」
「奥様、申し訳ないのですが、改めてご主人の部屋を確認させていただいていいでしょうか?」
田尻がいった。
「以前も家捜しされましたが、またなぜ?」
「失礼を顧みず申し訳ないのですが、納得のいくところまでやらせてください。それでなにも見つからなければ、わたしから局長へきちんと報告いたします」
田尻はそういうと頭を下げた。
映子は腕組みをして下げた田尻の頭を見ていたが、溜息をつくと、やがて頷いた。
「石津さんたちも一緒なのね」
映子の声に、田尻は頭を上げた。
「そのために同行願いました」
「一緒なら、いいわ。というか、しようがないでしょ。断ったとしても、今度はなにをされるのかわかったものじゃないし。気が済むまでやってください」
映子はあきらめたようにいった。
「ありがとうございます」
田尻はそういうと玄関から室内へ上がり、そのまま早見の部屋へ向かった。石津と濱本も続く。
映子はその石津の左腕をそっと掴んで口を開いた。
「頼むわね」
「ああ」
石津はその手に右手を重ねて頷いた。
「そうだ、あとで近藤も来るからよろしく」
「わかったわ」
ふたりのやり取りを見て濱本はただ肩をすくめた。
早見の部屋のドアの前で田尻はふたりを待っていた。
「徹底的に探してはみたんですが、なにも見つからなかったんです。あなたがたなら彼のことをよく知っているから、きっと見つけてもらえると期待しています」
「勝手に期待されも困るんだがな」
石津はそういって部屋へ入った。
マンションの廊下側の部屋だ。六畳ほどの広さで、ちょうど北側にあたる。
書架が壁の大半を占め、書籍類はもちろんだが、それとは別にスターウォーズ関連のグッズも並べられていた。窓側にはデスクがあり、大きな画面のパソコンのモニタと本体が乗っている。
「これ自作機か?」
石津はそのパソコンをひと目見て濱本に訊いた。
「ああ、そうだ。いろいろと相談されたよ。CPUとかマザボなんかについてね。水冷にしようかなんていってたけど、どうせあいつYouTubeぐらいしか見ないだろうから、勿体ないから普通のにしときなってアドバイスしておいたんだ。金使うならグラボとメモリにしろって」
「あいつは窓か」
石津はそういいながら本体の電源を入れた。
モニタのスイッチも入り、やがて画面にWindowsの起動画面が現れた。
「七だな。濱本、中を確認してくれ」
「わかった」
ふたりはほとんど田尻の存在を無視して会話をしていた。
「で、田尻さん、この部屋はどこを調べたのかな?」
石津は田尻に向き合うと尋ねた。
「パソコンの中はもちろんですが、机の引き出しの中に、書架ですね。あとは奥の押入の中です」
田尻は部屋の中を確認しながら答えた。
「徹底的に?」
石津は問い返した。
「ええ」
田尻は頷く。
「教えて欲しいことがあるんだが、もし持ち出したとしたらそれはデータだよな」
石津は考えながら口を開いた。
「そうです」
「だとしたら、そんなに大きなものじゃない」
石津は続けた。
「サイズでいえば一センチ四方ぐらいのものだろう。microSDならぺらぺらで厚みがないから、隠そうと思えばどこにだって隠せるさ」
パソコンに向かったまま濱本が答えた。
「確かにそうなんです」
田尻はまた頷いた。
「本は一冊ずつ調べたのか?」
石津は書架の本を取り出すと尋ねた。
「もちろん徹底的にですから」
そのときチャイムが鳴り、玄関から近藤の声が聞こえてきた。
やがて部屋のドアがそっと開き、その隙間から近藤が顔を覗かせた。
「石津、いるのか?」
「入れよ」
石津は手招きをした。
近藤は様子を伺いながらそろそろと部屋へ入った。田尻の顔を見て首を傾げた。
「なんだってまたこんなことに……」
近藤は田尻の顔を見つめたまま口を開いた。
「もしかしたら早見の事故の真相がわかるかもしれないからな。だから俺は協力してる」
石津は本を一冊ずつ手に取り、ページを繰って中を確かめながらいった。
「そういうことか」
近藤は納得したように頷いた。
「ぜひお願いします」
田尻が頭を下げた。
「なんだかガタイもいいし、暗い威圧感がある割には礼儀正しいんだな」
近藤がぼそっとつぶやいた。
「そういう職業もあるってことだ」
石津が田尻の代わりに答えた。
田尻はただ苦笑いをしている。
「それで、石津なにをしてるんだ?」
「だから、たぶんmicroSDカードだと思うんだが、データを記録したはずのメディアを探してるんだ」
「なんだよ、それ。ガラケーのおじさんにも解るように説明してくれ」
近藤は笑いながらいった。
「これだよ」
濱本が自分の持っているUSBメモリのケースを外して、中に入っているメモリカードを抜き出して近藤に見せた。
「ああ、それか」
それを見て近藤は頷いた。
「知ってるのか?」
石津が意外そうな口ぶりでいった。
「だって携帯で使うメモリカードと一緒じゃないか」
「そりゃそうだ」
濱本が頷いた。
「それをこの部屋から探そうというわけか」
近藤が部屋を見渡しながらいった。
「そうなんだ」
石津は溜息混じりに答えた。
「じゃ、あいつの習性から推理するしかないな」
近藤はぼそっとつぶやいた。
「え? あいつの習性?」
石津は思わず訊き返した。
「そう、あいつの習性。趣味とか、癖とかそういった類のこと。だからやたらめったら探すよりも、この部屋をじっくりと観察して、それで推理する」
そういうと近藤は絨毯の上に座り込んで腕組みをした。
「なんだからしくないな」
濱本が茶々を入れた。
「そういうなよ、これでもシャーロキアンだったんだから」
近藤が濱本に答えた。
「過去形か?」
「まぁな、いまはしがない中古車屋だし」
近藤はただ頷いた。
「でもホームズだったら一発で見つけるはずだよ、こういうシチュエーションだと」
「だってあれは小説じゃないか」
濱本がいい返す。
「なにをいうんだ。ホームズはホームズなんだ。ただの主人公じゃないんだよ」
近藤がめずらしく声を上げた。
「わかった、わかった」
濱本はなだめるようにいった。
「いや、近藤のいう通りだ。冷静になって部屋を観察した方がいいかもしれない」
石津はそういうと部屋の中を改めて見回した。
「あいつの趣味は──」
書架の一画に石津の眼が停まった。
「スターウォーズだよ、なにをいまさら」
濱本が苦笑混じりに答えた。
「だからさ──」
石津は書架のひとつに綺麗に並べられたスターウォーズのグッズを見つめた。
映画「スターウォーズ」シリーズの登場人物たちや乗りものなどのフィギュアとダースベーダーやトルーパー、ドロイドなどのマスクが並んでいた。
「ねぇ、レイア姫ってどこに隠したっけ? デススターの設計図」
近藤が立ち上がって書架に近づきながら話した。
「それだ」
石津は頷くとそこに並んでいたR2-D2を取り上げた。ちょうど片手で持てるぐらいのサイズのものだった。
「そうか、この中だな」
濱本も合点がいったのか頷く。
「どういうことですか?」
それまで黙ってやり取りを聞いていた田尻が不思議そうに尋ねた。
「あいつはスターウォーズが大好きだったんだ。熱狂的なファンの一人でね、グッズだけじゃなくて、映画もそれこそセリフのひとつひとつが全部頭の中に入っているほどの酔狂だ」
「それは、いま理解しました」
田尻は石津の説明に頷いた。
「エピソード四では、ヒロインのレイア姫がデススターの設計図を隠して、脱出用のポットに乗せてタトゥイーンに打ち出すんだ。このR2-D2をね」
「なるほど」
田尻は納得したのか頷いた。
「さてと、どこにどうやって隠してあるんだ?」
石津はそのR2-D2を手に取り、あちこちを探してみる。
「どこかにスリットがないかな」
濱本も立ち上がって近づく。
「スリット?」
石津が訊き返した。
「メモリカードが差し込めるようなところ。ルークがレイア姫のメッセージを観たのは、隙間のカーボンを取り除こうとして誤作動したからだろ」
濱本がR2-D2を石津から受け取った。
「みなさん、お詳しいですね」
田尻はちょっと呆れたようにいった。
「まぁ、この年代で映画好きならスターウォーズはそれこそビデオが擦り切れるぐらい観ているはずだからね。いまじゃデータで観られるから、擦り切れる心配はないかもしれないけど」
石津はそういいながら笑った。
濱本はそのままR2-D2を手にデスクに戻った。
「あいつ、そんなに手先は器用じゃなかったから、あまり細かなことはしていないかもしれないなぁ」
そういいながらR2-D2のあちこちを触っていった。
「まさかねぇ」
濱本はそういいながら頭の部分を捻ると、すぐ下にあるスリットからメモリカードが出てきた。
「おいおい、マジかよ」
濱本はそういいながら右手の親指と人差し指でつまむと引っ張り出した。
「あったよ」
そういってつまみ出したカードを石津たちに見せた。
近藤がそのカードを濱本から奪うようにして取るとしげしげと見つめた。
「この中にもしかしたら早見の命を奪うほどの秘密が隠されているわけか」
近藤はカードを見ながらポツリといった。
「そうかもしれません」
田尻はいいながら手を差しだした。
そのとき田尻の携帯が鳴った。
「どうした、沢口」
電話に出ている田尻の顔がみるみる険しくなっていく。
石津たちはいったいなにが起こっているのかわからず、田尻の険しくなったその横顔をただ見ていることしかできなかった。
「ここを出ます」
田尻は電話を切ると、近藤の手からmicroSDカードを取り上げ、石津たちにいった。
「どうしたんだ?」
石津は部屋を出ていこうとする田尻の腕を掴んで訊いた。
「理由がわからないと俺たちはどうしていいいか判断ができない」
石津はキッパリといった。
「保安課が来ています」
田尻は石津に向き直るといった。
「だから?」
「彼らはわたしを追ってきたようです」
田尻は石津の眼を見て答えた。
「同じNSAの局員だろ?」
「ええ、でも右手がやっていることを左手が知らないということもあります。できたばかりの局で、各省から寄せ集められた組織ですから」
そういいながら田尻は部屋のドアを開けた。
「局の内部事情はともかく、要するにここから逃げろということだな。でないと俺たちもどうなるかわからない」
「そういうことになります」
田尻は頷きながら部屋を出ていく。
「映子はどうなる?」
石津もあとを追いながら訊いた。
「奥様は関係ありませんから大丈夫です。わたしとそれからデータを追っているだけです」
「それほど大事なのか、そのデータは」
石津は玄関のところで立ち止まり、改めて田尻に確認した。
「どうやらそういうことになりますね」
「やぶ蛇だな。藪を突いたら、蛇が出たわけだ。で、俺たちはその巻き添えか」
濱本は皮肉っぽくいいながら、石津の脇を通っていった。
田尻を先頭に次々に玄関を出ていく。
その慌ただしい様子に玄関までやって来た映子は、ただ黙って突っ立っているしかなかった。
心配そうな顔つきの映子の姿を見て石津が口を開いた。
「なにも心配ない。どうやら面倒なやつらがあの田尻を追ってきたらしい。もし聞かれたら、なにか見つけて出ていったようだとだけいえばいい」
「わかったわ」
映子は石津の言葉に気丈に頷いた。
「気をつけて」
玄関を出て行く石津の背中に声をかけた。
石津は振り返ると、しっかりと頷いた。
四人は田尻を先頭に廊下を走り、そのままエレベーターホールへと向かう。エレベーターの階数表示でエレベーターが下降していることが判った。田尻はそのままエレベーターの前を素通りすると、階段へと向かった。
「階段で下へ」
振り返り、着いてきている石津たちにいった。
「判った」
石津が頷いた。
「運動不足なんだよな」
濱本はそういいながら後を追う。
「黙って走れよ、スーパーハッカー」
近藤が茶々を入れながら、さらにその後に続いた。
マンションを出たところへ沢口が車を回していた。
「さあ、いきましょう」
田尻が三人に車に乗るよう促した。
しかし、石津は首を横に振った。
「いや、申し訳ないが同行する理由がない。データの入ったメモリカードはそっちにあるわけだし、目的はもう果たしたんだろ。俺たちはこれからそれぞれ帰るよ」
「しかし、あなたたちも追われるかもしれません」
田尻は食い下がった。
「どうして? やつらが追っているのはお宅とそれからその手にあるメモリカードだろ? 俺たちはもうこの件とは一切関係がないはずだ」
石津はそういうとさっさとその場から立ち去ろうとした。
「どこへ?」
田尻がその背中に声をかけた。
「だから帰るのさ、俺たちの居場所へ」
そういうとまだなにかいいたげな田尻を気にも留めず駐車場へ向かうと、近藤が乗ってきたレガシー・ツーリングワゴンに乗り込んだ。
「いいのか?」
後部座席に座った濱本がナビゲーターシートに座った石津に訊いた。
「なにが?」
「いやだから、これで終わりでいいのか?」
「どういうことだ?」
石津が振り返ったとき、その横を沢口が運転する車が走り去った。
リアウインドから後ろを見ると、マンションから田尻たちと同じような格好をした男たちが転がるようにして出てきた。
「近藤、とりあえず車を出せ」
「どこへいく?」
近藤はエンジンをかけながら尋ねた。
「好きなところへやってくれ」
石津は後ろを見たまま答えた。
「そうだ、昔を思い出して河口湖ってのはどうだ?」
近藤はそういうと車をいささか乱暴にスタートさせた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
