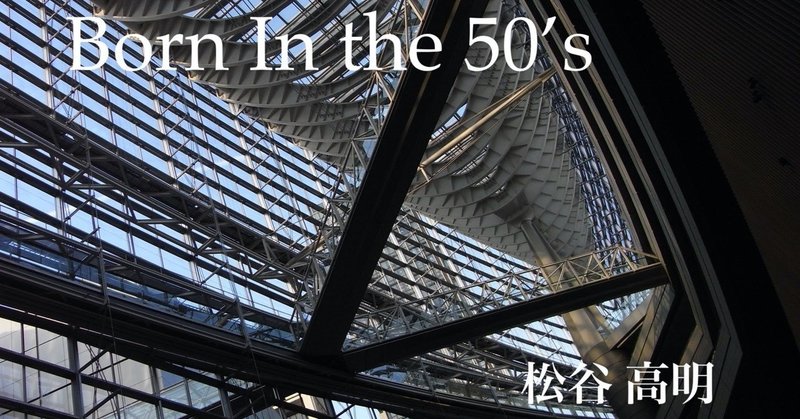
Born In the 50's 第一話 日本海
日本海
夜の海は怖い。
月の見えない空は漆黒の闇に包まれ、海の底は光が届かないほど深い。
第二永宝丸は日本海沖合を目指して、十七時三十分に小木港を出港した。前回は大漁だった。それこそ積みきれないほどのヤリイカを冷凍庫に保存して帰港した。もっと大きな冷凍庫があればと乗組員全員が思ったほどだった。
船長の三島はそろそろ引退の時期を考えるほどの年齢だった。船ももうかなり古くなっている。船主にいろいろと相談はしているが、しかし新しい設備を投入するのにはかなりの負担が強いられる。
イカ釣りの場合は電気の消費量が一番のネックだ。
中にはLEDを使い、発電に使う油の量をコントロールしている船もある。しかし、だからといってそれが漁の成果に直結するわけではない。
百二十トンというサイズも昔は誇らしいものだったが、いまはどちらかというと小さな部類に入るようになってしまった。
三島の頭を悩ませているもうひとつの問題は、人だ。
この船に乗っている仲間は、三島とはもう長い。そのほとんどがそろそろ船を下りようかと考えている。孫と遊んでいてもいい歳になってしまった。その代わり船に乗りたいという若者が減っている。
仲間の五人とはいつもその話になった。
自分たちは親の仕事をそのまま引き継いだ形になっているが、子どもたちは陸の仕事についていて、後を継いでくれる者は稀だ。
三島は手摺りにもたれながら風を浴び、ぼんやりと真っ暗な海を見ていた。
「船長、そろそろいいかな」
ブリッジから新三が顔を出した。
三島とは小学校からの友だちだ。同じ歳で、家も近い。同じ船に乗り、同じように年月を重ねてきた。三島の右腕といってもいい。
「ああ、そうだな」
三島は振り向くと頷いた。
「今日は穏やかだな」
新三も三島の横に並ぶ。
「珍しいほど静かだ」
三島は海を見ながら腕組みをした。
「節夫、用意してくれ」
新三は舳先に向かって大きな声を上げた。
節夫と呼ばれた男が返事をする代わりに右手を挙げた。
「じゃ、止めるよ」
新三は船長にひと声掛けるとブリッジに姿を消した。
「ああ」
三島は頷くと、そのまま舳先でアンカーの用意をする節夫の様子を見守った。
エンジン音が止み静寂が戻ると、船は惰性でそのままゆっくりと進む。
「節夫、いいぞ」
三島の声に、節夫は大きく頷き、シーアンカーを放った。アンカーが沈み、パラシュート部分が広がっていくのを見届ける。
「急冷室の準備も頼む」
三島は振り向いた節夫に声を掛けた。
「わかった」
節夫は頷くと、並んでいる集魚灯を避けながらブリッジへと戻ってきた。ブリッジの下に急冷室があった。吊り上げたイカは選別されるとすぐに冷凍にして魚倉に入れられる。
魚倉がいっぱいになるまで漁は続けるが、港に戻る日を決めるのは船長だ。積んできた食料や、漁の具合、あるいは天候などで判断することになる。
三島のモットーは、無理はしない、だった。
自然を相手の仕事だ。人にとってなんでもないと思ったすこしの無理が死を招き寄せてしまう。三島自身もそれこそ死を覚悟せざるを得ない経験も積んできた。それが、船長としての判断のベースとなっている。
一番大事な仕事は生きて港へ戻ることなのだ。
夜の海を眺めていると、まだ大人になる前、父親と船で釣りに出かけたとき、夜の海へ落ちたときのことをつい思い出してしまう。
人は水を飲み慌てると簡単に方向感覚を失ってしまう。息ができない苦しさに藻掻きながら、海上へと出るつもりで海の底へと泳いでしまうこともある。まるで死に神に招き寄せられるように海の底へと引き摺り込まれてしまうのだ。
海はそんな恐ろしさも持っている。
真っ暗な海へ落ちたとき三島はつい我を忘れて藻掻いてしまった。どっちを見てもただ真っ暗な闇があった。狂ったように泳ぎまわり、しかしいつまで経っても海から逃れることができない絶望感に満たされたとき、普段から父親に聞かされていた言葉を、ふっと思い出した。
──力を抜け。
そう、藻掻けば藻掻くほど事態は悪くなる。
海に身を委ねてしまうのだ。そうすれば自ずと身体は浮く。
息苦しさを必死に我慢しながら、三島は全身の力を抜いた。それでもまだ海の中だった。もう駄目だとあきらめかけたそのとき、身体がふっと浮いていくのを感じた。
海がまるで優しく三島を身体ごとそっと持ち上げてくれているようだった。
海上に顔を出して、肺が悲鳴を上げるほど息を吸い込み、思い切り吐き出したとき自らの命を思った。そして頬に当たる風を感じたとき、三島はこの海で生きていこうと決心していた。
あのときと同じように空は暗く、そして海は闇のような黒さを湛えている。
「船長」
イカ釣り機のチェックをしていた雄治が声を掛けた。
「どうした?」
「右舷の一番先頭のやつがそろそろ危ないって。もう寿命だな。今回の漁でいかれちまうかもしれない」
そういいながら船長に近づいてきた。
「なんとか機嫌取ってくれ。ひとつでも動かないと水揚げが減るしな」
船長はそういいながら雄三の肩を軽く叩いた。
「やるだけはやってるんだけどな」
肩をすくめると、そのまま舳先へと集魚灯を避けながら歩いていった。
三島は今度は船尾へとその視線をやった。そこで作業をしていた男に声を掛ける。
「春夫、そっちどうだ」
春夫はただ黙って手を挙げた。
もう一人ランプをチェックしている男がいた。船尾からブリッジまで。そしてブリッジから舳先まで、集魚灯が二列でずらりと並んでいる。ゆっくりとした船の揺れに合わせて、ランプも揺れる。
「船長、こっちは大丈夫だ」
ブリッジの近くまでやってくるとにっこりと笑いながら声をかけた。
「武志、前は?」
「ああ、港出てすぐに確認したから問題ない」
「そうか、ご苦労さん」
三島は大きく頷くとブリッジへ入った。
「発電機、頼むぞ」
新三に声を掛けると、そのまま甲板に出て舳先へと向かった。
新三は機関室にいくと、集魚灯を点灯するための発電機を慣れた手つきで作動させた。
最初は咳き込むように空回りをしていたが、すぐに唸るような音を立て、発電機が動きはじめた。この音が船全体に響くといよいよ漁のはじまりだ。
なんとなく身体全体がシャキっとする。
三島は舳先までいくと、発電機の音を心地よく聞きながら、両手を合わせて真っ暗な海へ祈りを捧げた。彼にとっての儀式だった。
祈りを終えると、神妙な面持ちでもう一度深く頭を下げた三島は、ゆっくりと振り返りブリッジへ戻ろうとした。
そのとき、レーダーがけたたましい警告音を発した。
「船長!」
新三の悲鳴にも似た声が三島の耳に届いた。
「どうした」
「右舷に船」
三島は身を乗り出すようにして右舷を見た。近づいているなら、その船の航海灯が見えるはずだった。しかし、真っ暗な闇がそこにあるだけだった。
「武志、ライトだ。節夫、アンカー上げろ、今すぐ」
武志は探照灯をスイッチを入れて右舷を照らした。真っ暗な海がそこにある。しかし、それ以外にライトが照らすものはない。
節夫は揚錨機に飛びつくとアンカーを巻き上げる。
右舷から船が接近しているなら、避けるのは第二永宝丸の方だった。
しかし、その対象となる船を視認することができない。
──なぜだ?
「どんどん近づいてくる」
新三の声がさらに大きくなった。
「エンジンかけろ。それからライフジャケットだ」
三島はそう叫ぶようにいいながらブリッジへ向かった。
ブリッジへ駆け込んだ三島は、新三といっしょにレーダーをのぞき込んだ。
「いかん、間に合わんぞ」
ふたりは顔を見合わせた。
「新三、通信だ」
新三は黙って頷くと、送信機のスイッチを入れた。
「メーデー、メーデー」
こんな言葉を使うのは、はじめてだった。新三はなにかとても不思議な面持ちで、通信機のマイクを握っていた。
自分の声じゃないみたいだった。
「メーデー、メーデー」
「武志、船は見えんのか!」
三島は怒鳴るようにして訊いた。
「まっくらだ。海しか見えない。あっ!」
そのとき第二永宝丸の横っ腹に相手の船の舳先がめり込むようにしてぶつかってきた。
激しいショックが襲う。
「ウワっ!」
武志が転んだようだ。
三島はしかし、舵にしがみつくようにして辛うじて体制を保つのに精一杯で、他のものたちがどうなっているのか確認することができなかった。
「新三!」
三島は思わず幼なじみの名前を呼んだ。
「船長、やばい」
新三の顔が引き攣っていた。
三島がはじめて見る表情だった。
ぶつかってきた相手の船は、いったん後進をかけたようだ。舳先が引いていく。
三島は相手の船を確認するために、ブリッジのガラス越しに右舷を見つめた。
武志が点けた探照灯の明かりの輪の中に船があった。真っ黒な船体。
──どこの船だ。
浮かんだ疑問を三島自身が把握する前に、また相手の船がこちらに向かってきた。
さっきと同じような場所に舳先を突っ込ませてきた。
バリン!
ブリッジのガラスが割れ落ちた。
船体全体がギシギシと嫌な音を立てている。
「船長、浸水」
春夫の声だ。
「どこだ?」
「第二と第三、魚倉がやられた。もの凄い勢いで水が入ってきてる」
普段、無口な春夫のしゃがれた声だった。
「逃げろ」
新三にいった。
「どこへ」
新三はすぐさま真顔で返した。
甲板の上に綺麗に並んで揺れていたはずの集魚灯が落ちて、派手な音を立てていた。ブリッジの壁もメリメリと音を立てて壊れていく。
「ジャケット着て、逃げろ」
「馬鹿いうな。こんな季節に海に入って助かるわけないだろ」
新三はそういうと握りしめていたマイクを通信機の前に戻した。
春がそこまで来ているとはいえ、日本海の海水の温度はまだまだ低い。海に浸かってものの五分も経たないうちに身体は動かなくなるだろう。ジャケットを着て浮いていたとしても、いつまで命を長らえることができるのか、確かに判らなかった。
「どうするつもりだ」
「船長は船と共にってつもりだろ。俺はお前の友だちだぞ。こんなに長くお前と友だちでいたやつは俺だけだ」
「新三……」
ふたたび衝突のショックが襲いかかってきた。
相手の船がどこの船かは判らない。しかし、これだけは確かだ。この船を狙っている。わざとぶつかり、この船を、第二永宝丸を沈めるつもりだ。
悲鳴のような軋む音が三島の耳を襲った。
船が折れたようだ。水がどっと襲いかかってきた。
三島は辛うじて身体を捻ると、最期に相手の船を見た。
真っ黒な船体。
それしかわからなかった。
あの日、海に落ちたときの海は、いまとは違って暖かかった。
身体全体の力を抜き、すべてを委ねようとしたが、真っ黒な水面がゆっくりと遠ざかっていく。
──もうあの風を感じられないのか……
第二永宝丸とその乗組員の全員が海の底へと沈んでいった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
