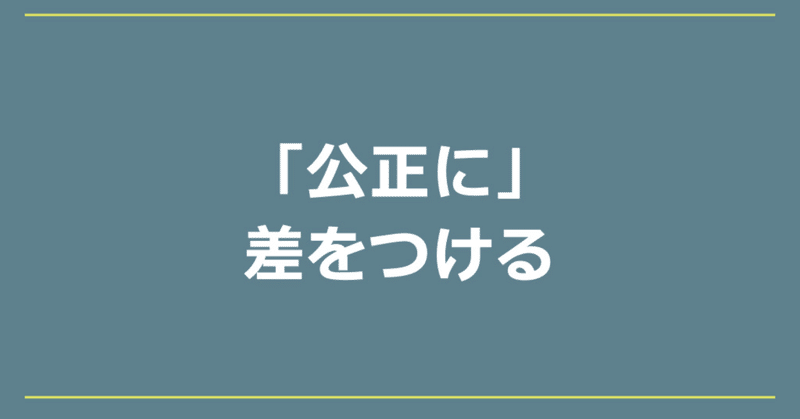
「公正に」差をつける (2022/6/28)
記事の長さはおよそ2,000文字。3〜4分程度で読めます。
【法税務】Business Law and Taxation
70歳まで就業、対応鈍く
法改正から1年、大企業が足踏み
記事のポイント
高年齢者雇用安定法の強化により、定年が70歳未満の企業で65歳以上70歳未満の社員への「就業確保措置」が努力義務となった。
だが経団連が2021年11月に実施した調査では「対応済み」企業は22%どまり。無検討の企業も10%あり、理由のトップは「努力義務だから」。
中堅・中小企業が多い日本商工会議所の同年4月の調査では「対応済み」は33%。大企業の対応の遅れが目立つ。
先行企業の取り組みは様々。
「65歳以上は人事部が(処遇を)一人ひとりジャッジしている」ジャックスの人事課長が話す。同社は65歳まで再雇用していたが、法改正を先取りし18年に上限を70歳にした。
65歳前と同様の仕事で賞与査定がある「エルダー社員」と、職務が軽く査定のない「シニアパートナー社員」に分ける。
振り分け基準は本人の意向に加え、65歳まで半期毎に実施した業務査定の結果と「長年の勤務で見えるもの」を加味する。
凸版印刷は4月に、65歳への定年引き上げと70歳までの再雇用を導入した。
70歳までの再雇用には選抜がある。専門性や成果を60歳から査定し、働きに応じて6割程度が再雇用対象となると想定している。
こうした先行企業は対象者基準について「全社的な人事方針や賃金政策との整合性が重要だ」と口をそろえる。
法令の努力義務を軽視する企業の多さも問題だ。
努力義務は多くの労働法で規定され、大きく2種類に分かれる。実効性のない訓示規定と、「時期尚早」ではあるが将来の義務化を見据えたものだ。
今回の65歳以上の就業確保措置の場合、厚労省は「(将来の義務化を)政府で決定したことはない。今は就業確保の必要性を理解してもらう段階」と話す。
日本の労働力人口は減り続け、高年齢者や女性の就業の拡大で不足を補う社会的な要請が高まっている。高年法対応は企業にとって将来への投資ともいえ、軽視は許されない。
**********************
70歳までの就業確保措置への対応が、特に大企業において進んでいないことが紹介されています。
記事では、「高年法対応は企業にとって将来への投資ともいえ、軽視は許されない」と対応の遅れへの対応を求める文章で締めくくられていますが、私は非対応の大企業の本音は、こんな感じではないかと考えています。
「成果を上げてくれる少数の人だけ雇いたいが、
客観的なデータがないので対応できない」
少子高齢化により人手不足が叫ばれて久しい日本ですが、顕著なのは中小企業であって大企業ではありません。
DX関連の技術者のように、大企業でも一部人手が足りない分野はありますが、全社的にみれば人が余っている大企業が多いのではないでしょうか。
多くの大企業が「早期退職」の募集をしているのがその証拠ですね。
厚労省の調査結果も、大企業と中小企業の不足感の差をよく表しています。
厚労省調査:
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/19/dl/19-2-2-1.pdf
人数を絞って再雇用したいと考えた場合にネックになるのが、客観的な根拠です。
Aさんは再雇用したけど、Bさんはしなかった場合に、なぜそうなったのかを客観的に示せないと問題になる可能性があります。
しかしこれまで日本では、
社員を「成果で客観的に評価」してきませんでした。
給料は年功序列で決まるので、評価が良くても悪くてもあまり変わりません。
そんな環境の中で、評価を悪くつけたりすれば、文句を言われたり嫌われたりするだけです。
そのため評価者は、差をつけることを避け、全員に無難な評価をつけがちです。
(しかも評価が上振れしがち)
誰を再雇用するかを判断するとき、全員に無難な評価がついているデータしかなかったら、選抜できないですよね。
もちろん、これまでの「社内の評判や人間関係」で選抜することも可能でしょうが、再雇用されなかった方から裁判を起こされたときに、そんな根拠で勝てるのか?
これが大企業で検討が進まない理由ではないでしょうか。
人間は一人ひとり違うので、同じことをやっても結果に差が出るのは当然です。
私は、その差が「公正に」評価されるのであれば、まったく問題ないと考えています。
評価者は、再雇用者に限らず全社的に年齢や性別・国籍などではなく、「成果」で「公正に評価に差をつける」こと。
そして被評価者は、「成果を出さなくても、いつまでも会社に雇ってもらえる」という考えは、もう通用しないことを肝に銘じること。
そこから始めませんか。
本投稿は日経新聞に記載された記事を読んで、
私が感じたこと、考えたことについて記載しています。
みなさんの考えるヒントになれば嬉しいです。
「マガジン」にも保存しています。
「学びをよろこびに、人生にリーダシップを」
ディアログ 小川
美味しいものを食べて、次回の投稿に向けて英気を養います(笑)。
