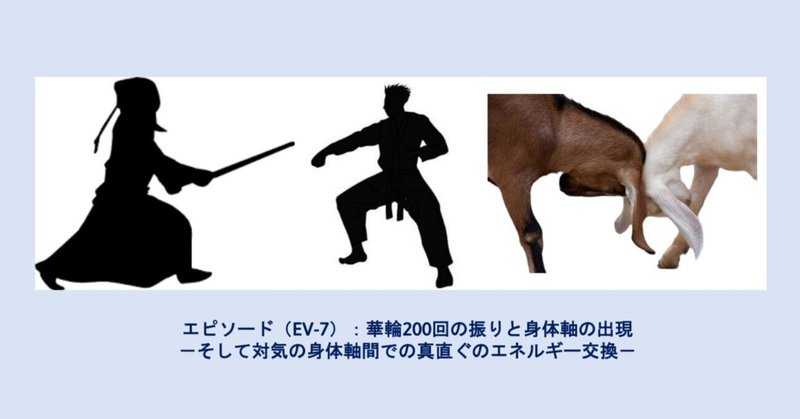
エピソード(EV-7):華輪200回の振りと身体軸の出現-そして対気の身体軸間での真直ぐのエネルギー交換-
身体軸が実際に身に付く、すなわち四肢筋群が体幹に連携して、自分の軸が実感できるようになると、実は次の稽古の「対気」で相互のイメージ交流が素直に行える。
そうした意味で華輪を稽古する時に、お互の身体軸回旋を観察することは、いい勉強である。
2回に分けた「華輪」稽古の一方は、休みながらも他の塾生の華輪を観察する時間である。
そして、この人の華輪(身体軸)は美しいと目星をつけた人と対気をしてみる。
相手から真っ直ぐに向かってくるエネルギーを感じられる。
不思議だ!身体のどの受容体がこの感覚を持つのか?
この生理学的背景は何だろう?
華輪で緩み、かつ即応性がでた身体軸と、対気における真っ直ぐなイメージ交流は、どうも関連している。
そして真っ直ぐにイメージを受けると、私の身体は気持ちが良い。
身体が喜ぶ。相手に感謝をしたくなる。
これが西野流呼吸法の魅力である。
では真っ直ぐとは何だろう?
身体軸は上下軸であるのに、相手から真直ぐ送られてくるものとは?
そもそも、locomotion運動惹起神経系が真直ぐ前進する機能と関連するのでないか?
(この機能は脊髄の神経細胞群自体のベクトル表示でも回転すると報告され、central pattern generatorsよりbalanced sequence generatorと呼ばれる、リンクhttps://www.nature.com/articles/s41586-022-05293-w)
Locomotionは脊椎動物に限らない。節足動物もそうである。
Locomotionで獲物に向かって真っ直ぐ進む。
たとえ身体は左右にくねりながらも、結果的には真っ直ぐ前に進む。
進化的に旧い硬骨魚類時代から、真っ直ぐ前にが原則である。
早い逃げ足にもなる。
一方、哺乳類では正面から、雄同士が頭をぶつけ合うシーンをよく見る。
偶蹄類、シカ、ウシ等の順位を巡る競い合いが思い浮かぶ。
こう考えると、不思議なことに日本の武道系は真っ直ぐ前への稽古が多い。
剣道の基本、面打ちでの真っ直ぐの稽古。
空手も正拳の突きは真っ直ぐ前である。
相撲のすり足歩き、突き押しの基本。
逆に日本以外では、あまり真っ直ぐのスポーツは思い出さない。
太極拳・推手は武道として、相手の真っ直ぐの勢いを上手に外しながらの稽古となる。
議論を華輪に戻そう。
華輪で身体軸が生まれると、対気において相手から真っ直ぐ届くエネルギーを感じる。ベクトル的な方向性を感じる。
身体軸は上下方向であるが、進化に戻れば四足動物など前後軸である。
その前後軸で獲物を捕まえる。一方、捕食者から逃げる。
動物自体が前進方向にエネルギーを出している?のかもしれない。
直立二足歩行のヒトは、身体軸は上下軸であるが、その軸の動きは真直ぐ前方に進む。
その進む方向に何らかのエネルギーが出ていると仮説せざるを得ない。
このエネルギーがnon-barbal communicationなのではないか?
「西野流呼吸法の対気で一見飛ばし合いをやって、それが何になるの?」
こうした疑問を持つ初心者は多い。
一つには相手からのSignalの衝撃が全身を突き抜ける爽快感。
衝撃感で気持ちが前向きになるから不思議だ。
この理由はDopamineが絡むと予想するが、noteでまた別に議論する。
もう一つは、社会生活において言葉以外のエネルギー交流。
仙台の稽古では、「対気」稽古は、社会生活での相手へのcommunication稽古だと説明している。
そんなエネルギーは、「華輪」により身体軸が身につくことで生まれる。
「そんな馬鹿な」というのが、現在の医学生理学的理解である。
しかし稽古をすれば、徐々にはっきり感じることができる。
未知の受容体が存在するのに違いないと私は信じている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
