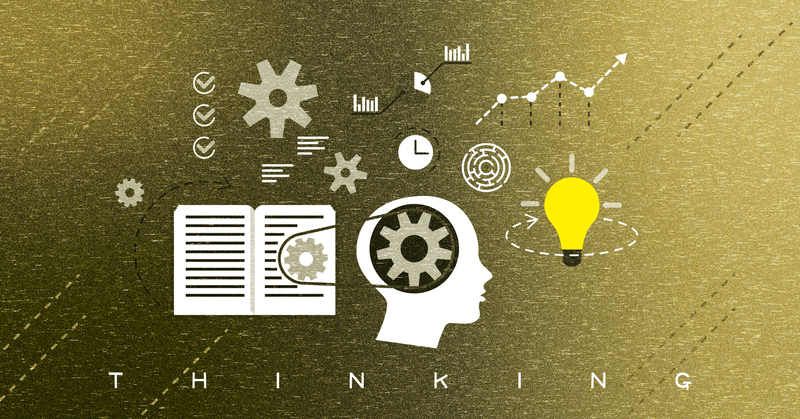
5月9日 The Center of the knowledge Society 知識社会の中心の問題
おはようございます。今日も #ドラッカー #365の金言 からスタートしましょう。本日 #5月9日
テーマは #The_Center_of_the_knowledge_Society
#知識社会の中心の問題
そして、本日の金言は、
#知識社会では 、
#教育が中心の問題となり
#学校が中心の組織となる 。
長い歴史を通じ、あらゆる職種において、18、9歳までの5年から7年の従弟時代に学んだ技能によって、一生職人としてやっていくことができた。今日では、学校教育によって、理論的分析的な知識を身につけなければならない。仕事に対する姿勢とアプローチも昔とは大きく異なる。何をおいても、継続学習の習慣を身につけることが必要となっている。
それでは、あらゆる人間がもつべき知識とは何か。学ぶことと教えることの質とは何か。知識社会では教育が中心の問題となり、学校が中心の組織となる。実に、学校教育における知識の獲得と配分にかかわる問題は、資本主義と呼ばれたこの2、3世紀における所得の獲得と配分にかかわる問題と同じ政治的位置を占めるようになる。
ACTION POINT
#学ぶことを今日から習慣にしてください 。
本日のテキストは、『未来への決断』(1995年刊行)から、とのことですが、該当記事を見つけることができませんでした。
21章 社会転換の世紀>知識社会の経済と政治>継続学習(288〜290ページ)は、タイトルが同様ですが、内容は違っていました。
ところで、昨年も #ドラッカー365 を記していましたので、昨年の記事から見ていきますと、、、
継続学習を続けた結果、遠くへ行ける、そんな話をご紹介していました。
ところで、ドラッカーは、実績でなく卒業証書で人を評価することの危険を記しています。
実績ではなく卒業証書で人を評価することは、極めて危険だからだ。おかしなことに思われるかもしれないが、知識経済の最大の陥穽は、中国の科挙に代表される資格制度にある。すでに資格偏重主義が、至る所で蔓延っている。しかし、実際には、これこれの人物は博士号は持っていないが、本当は優秀な研究者であると言わなければならない。学位は単に学位の有無しか教えない。そこに罠がある。人がどれだけ貢献できるかは、総合的に判断すべきことだ。
実際には、多くの日本の大企業は、事務処理重視だからか、実績よりも学歴・学位で採用を決めているように感じられます。そして、これから重要となる人材について、こう語っています。
これからは、分析よりも知覚が重要になる。組織を中心とする新しい社会では、期待するものよりも、存在しているものを理解するためのパターン認識の能力の方が重要となる。「今の製品を守ろうとするあまり、新しい製品を犠牲にしようとしているのではないか」と言える人が、これまで以上に必要となる。
実績を上げること。成果を上げること。やっていきましょう。
サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!
