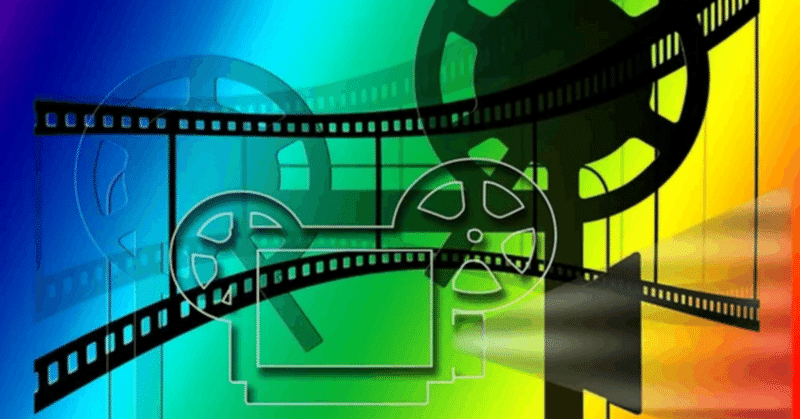
かつて『リュミエール』という雑誌があった・其ニ(「ハリウッド50年代」)
『リュミエール』は「人生」を擁護する
すでに述べたように映画雑誌『リュミエール』は、1985年に創刊された。その雑誌に私は惹きつけられるのだが、その理由は明白だった。80年代の文化が形成する言葉の表情と『リュミエール』のそれは、明らかに異質の肌ざわりを感じさせたのだ。『リュミエール』の言葉は、一言でいえば、「人生」に属するような言葉で出来上がっていたのである。80年代の文化は、「人生」を抑圧することを「イケてる」と思い込んだ不自由な環境だった。編集長を務めた蓮實重彦は、率先して時代との行き違いを演じようとしているかに見えた。
実は私は大学3年生の時、蓮實重彦の『表層批評宣言』の例の冒頭を飾る、文学言語が目覚める瞬間の現象学的記述のような(あれは一種のドキュメンタリーフィルムであろう)難解そうだが、実は極めて現実的である、うねるような文章に悲鳴を上げて退散した口で、蓮実のことは敬遠していた。そのころメディアで言われ始めていた「ポスト・モダン」の代表者のイメージもあって、積極的に読む気にはなれなかった。けれども、大学卒業間際に新聞の社会時評で、蓮實の「原理性と無責任さとのこうした微妙な触れあいからくる楽しみを、科学は<文学>から学んだのではない。人生から学んだのだ」(『中央公論』3月号に掲載)という文章が紹介されていて、「人生」という反時代的な記号を口にしてみせる姿勢に「おや?」と心地よい驚きを覚えた。
大学を卒業してホテルで働いていたころ、本屋に新刊の『物語批判序説』が横積みされていて、ちょっと読んでみようかと手にしたのが、蓮實を読む最初のきっかけである。この本は第1部と第2部に分かれていて、1850年代の文化の変容=秩序の崩壊(「王位はいまだ空位のままである」)を扱っている(ベンヤミンの影がちらちら見える)とても面白い本である。1982年に書かれた第1部は、人が眉を顰める蓮實特有の嫌味っぽさがちらちら垣間見えて鼻につくところもあるのだが(要するに80年代的)、1984年暮れに書かれた第2部は「ロラン・バルト あるいは受難と快楽」と題された章から反80年代的な表情を纏うことになる。
バルトの言説はみずから犠牲者たることを受け入れたもののそれに似ている。ほとんど犠牲者の言説そのものといってよいかもしれない。では、何のためにおのれの身を犠牲に供するというのか。いうまでもなく、物語が語りつがれるためにである。
みずからの排他性に無自覚な言説をも肯定し、それとともに読まれることの可能な文字通り開かれた「記号」となるべく、犠牲という名の快楽をみずから実践することこそが肝腎なのだ。それは厳密さの問題ではなく、繊細さの問題である。
「犠牲」。この言葉ほど、80年代から遠い言葉もあるまい。いかにして他人を出し抜き文化的社会的序列の中で優位に立つかという「新自由主義」的発想が80年代のモードだったのだから(今現在、中学高校で生徒を苦しめているという「スクール・カースト」の淵源はここにある)。ことによると、この「犠牲」という言葉は蓮實の根底にあるマゾヒズムと通じ合うのかもしれぬ。
テレビ局や広告代理店に代表されるいわゆる「ギョーカイ人」(この言葉は今や死語と化しているようだ)とはかなり違うのではないか、と思い始めたのが1985年の夏ごろで、同時期に出た『映画はいかに死ぬか』を読んで、「蓮實重彦=人生の人」という私の蓮実像は強固なのもとなった。
蓮實の世代に大きな影響を与えた、ドイツからの亡命者として、40~50年代のハリウッド映画を支えたダグラス・サークは、80年代には忘れ去られた人としてスイスで隠遁生活を送っていた。「73年の世代」の1人シュミットは、「ダグラス・サークからこうむった恩恵をアメリカ人が完全に忘れてしまっている。それならサークの偉大さを伝えるのはスイス人であるおれしかいない」と、テレビ番組でサークのドキュメンタリーを撮ったり、サークの映画の再上映を企画して、巨匠の晩年の心の支えとなった。1984年の夏、シュミットの紹介で蓮實は、サークに面会する機会を得た。そしてその出会いは、1年後に『リュミエール』を創刊するきっかけとなった。
彼が夏なのにつめたいアパートの中に一人で座っていて、こちらが汗を拭きながら入っていくと、、背中に大きな毛布のようなものをかぶり、まったく見えない目でこちらを見て、「あ、いらっしゃいましたね。東京から来てくれたとは嬉しい」と言って、迎えてくれました。しかし、近づいていって手を握ったときの彼の手の氷のようなつめたさから、まさに映画は死につつあると実感しました。あの『悲しみは空の彼方に』の巨匠が、こんなに冷たくなってしまって、目も見えなくなり、それでも生きていてくれる。そのような感謝の気持ちで僕は彼の手を握りしめたわけですけれども、それはまったく感傷的な振舞にすぎないでしょう。死にかけてはいながらも、なおかつ映画はいたるところで新たな可能性を拓こうとしている。不可能性と接し合った可能性として映画の現在を生き合っていくつもりのぼくは、これからも映画供養を続けてやっていくつもりです。
このような場面を、80年代の文化はけっして描くことができなかった。むしろそれよりも、このような場面を嘲笑することを良しとしたのが80年代の文化だった。80年代の文化が提供してくれない貴重なものが『リュミエール』にはあると確信し、それを読み続けたわけだが、じっさい、当時の文化からは得られない貴重な刺激をそこから得ることになった。
翳りと戯れる映画の歴史
『リュミエール』という雑誌名は、いうまでもなく、世界で初めてスクリーン形式の映画を上映した(1895年のことである)フランス人のリュミエール兄弟の名に由来する。また「リュミエール」という言葉は、フランス語で「光」を意味する。であるがゆえに、雑誌『リュミエール』は、映画の光に何よりも執着し、それに敏感であろうとする姿勢にこだわり、そのことを幾度も強調してきた。と同時に、一方、『リュミエール』は、影に対する感性も重視してきた。『リュミエール』第3号の特集「ハリウッド50年代」は、「影の歴史」をとらえようと試みた。「肝心なのは、影と陰りへの感性を回復することにある。人は、薄暗さの中に揺れる親しい人影を、幾人識別しうるだろうか。誰もが自分の五〇年代作家を隠し持っている。とりあえず数え始めることにしよう。ダグラス・サーク、ニコラス・レイ、サミュエル・フラーといったぐあいに・・・・・」このようにして、アメリカ映画の歴史が綴られることになるが、その後『リュミエール』第9号では五〇年代におけるハリウッドの崩壊とともに消滅するしかなかった「B級映画」の歴史性とその意義、そして第13号では50年代以降のアメリカ映画の歴史が論じられることになる。そしてそれらの論考は、『ハリウッド映画史講義』として1冊にまとめられる。この書物をまるまる論じることはとうてい不可能なので、「不況下で戦う中小企業」を描いた池井戸潤作品というか、あるいはかつてのNHKの人気番組『プロジェクトX~挑戦者たち~』的な側面にスポットをあてて紹介を試みることにする。
蓮實のこの書物は1930年代の左翼青年たち、具体的にはジョゼフ・ロージー、エリア・カザン、ニコラス・レイに注目することから始まる。彼らは、ニューヨークにおける演劇活動を政治と結びつける東部(ニューヨーク)の左翼的知識人であった。彼らのような戯曲家を中心とした演劇人が西部(ハリウッド)の映画人となるのは、映画が農民や労働者階級の啓蒙に最もふさわしいメディアだとアメリカ共産党が判断したからであった。第2次大戦後、このことは、彼らを嵐のような悲劇に巻き込むこととなる。
そしてまた、戦前においてアメリカ映画は経済的な状況からも危機にさらされる。1929年の大恐慌が映画産業に打撃を与えたのである。さらには、ラジオの興隆が映画に追い打ちをかける。この危機をアメリカ映画は、民主党政権による「合衆国憲法の精神」に違反した「産業復興法」に保護されるかたちで生き延びる。しかし、のちに「独占禁止法」が適用され、この保護は消滅することになるだろう。ハリウッドの撮影所システムが円滑に機能したのはほぼこの時期であり、「B級映画」が存在したと言えるのは、1932年から1947年までのほぼ15年間である。では、具体的に「B級映画」はどのようにして生まれたのか。
1930年代前半、不況によって観客動員数の減少に危機感を抱いた映画館オーナーたちは、それへの対応として「二本立て興行」を製作サイドに要請する(この現実的要望が「B級映画」の起源にある)。当時ハリウッドの撮影所にはメジャー系の会社と、それに比較すると資本力が圧倒的に恵まれていない「貧窮通り」と呼ばれる地域に事務所を構える群小プロダクションがあった。また、それとは別にメジャー系の諸会社の中にもA級映画を制作する「A地域」と、二本立て興行の添え物としてのB級映画を製作する「B地域」があった。不況期に映画産業を生き延びさせるために、低予算による短期間の撮影という悪条件を引き受けた「B級映画」は、このような時代状況を背景に生まれた。「貧窮通り」の群小プロダクションや「B地域」の低予算映画製作班たちの知恵と活力によって、B級映画は製作され、当時の映画産業を支えたのである。
「下町ロケット」な人びと
映画史に燦然とその名を残す作品に怪奇映画『フランケンシュタイン』(1931年)がある。一般的な映画史においては、その作品の監督はジェームズ・ホエールとされている。けれどもユニヴァーサル映画の利益の大半の部分に貢献したこの映画の真の生みの親は、まったく別の人間だった。その人物の名は、ヨーロッパからハリウッドに来たロバート・フローレーである。フローレーは、ユニヴァーサルのカール・レムレ社長に怪奇映画を作ってみたいと申し出て、承諾される。監督をするつもりで、シナリオと詳細なカット割りを提出しながらも、フローレーの斬新なアイディアはホエールの監督作品として製作され、フローレーの名前は、シナリオ・ライターとしてもクレジットされることはなかった。
フローレーはまた、ドイツ時代にラングやムルナウの撮影監督を務めたカール・フロイントとも仕事を一緒にしたが、フローレーとフロイントによって、「東欧的な暗さを合衆国西海岸のステージに造形してゆくという途方もない作業」がこの時代のハリウッドに導入され、「B級映画」の誕生に深く加担したのである。フローレーは50年代にはテレビの世界に仕事の場を移すこととなるが、それと同時期に「B級映画」もまた映画の歴史から消滅する。
ところで、じつは、フローレーと『フランケンシュタイン』の原作者メアリー・シェリーとの間には浅からぬ因縁がある。パリで生まれ、スイスで育ったフローレーの回想録にはしばしばレマン湖畔のウシーという土地が登場するのだが、このウシーこそがメアリー・シェリーが『フランケンシュタイン』の着想を得た場所なのである。
スイスで青少年時代を過ごしたロバート・フローレーは、このウシーの記憶とともにハリウッドに赴き、合衆国西海岸のまばゆい陽光にさらされつつ、陰りをおびた東欧の怪物どもを蘇生させたということになるだろう。
だがそれにしても、カール・レムレに統率されたユニヴァーサル社は、何という贅沢な使者をレマン湖畔のウシーから迎えたことだろう。しかもその使者は、名前を名乗ることさえせずに、『フランケンシュタイン』誕生の功績のいっさいをジェームズ・ホエールに譲っている。この楽天的な匿名性こそ、「B級映画」を支える精神にほかならない・・・・・
ロバート・フローレーのような特別な感性を持った人間を筆頭に、ほかにも有象無象の名もなき人びとが、ハリウッドの撮影所システムが崩壊する直前の一時期、絢爛豪華とはまるで異質の作品を作り続けて映画史の一角を担ったのであった。ウィーリー・ディクソンの『B級監督』に収録されている監督は350人に及ぶという。そうした作品群は、当然、箸にも棒にも掛からぬ駄作が並ぶことになるが、低予算、撮影期間の極端な短さといった否定的条件が、貧しさの側ではなく単純さへの側へと転化し、鈍い輝きを放ち始める瞬間があることもあると証明してみせた。
ステージに設けられたセット数の絶対的な少なさを、ロケーションによってカバーするといった撮り方によって、「A級映画」とは全く異質の時間と空間とをフィルムに導入するといった創意あふれる「B級映画」が確実に存在するのである。経済的・物理的水準での苛酷な条件が、作家的資質の例外性をきわだたせることになるという幸福な現象は、「B級映画」の黄金時代にのみ可能な映画的事件だったといえよう。
そしてまた、このような苛酷な条件を生きたのは、B級作家だけではない。ラオール・ウォルシュやアラン・ドワンのような「A級映画」を任される作家たちも「B級映画」の量産にすすんで手を貸した。「涼しい顔で『B班』撮影に出発したり、出来そこないの映画に手を加えて完成させながら、クレジットには監督の名前ひとつ載せようとはしなかった」。彼らはともに、「一流、二流といった区別がたんなる虚構にすぎないことを楽天的な大らかさで示してくれた貴重な作家なのである。ともに例外的な資質に恵まれていながら、いつでも、率先して匿名性に埋没してみせるところが彼らの素晴らしさなのである」。このようなまるでヒット・ドラマ『下町ロケット』の一場面を彷彿とさせるささやかな情景が映画史にはあった。その情景を担った「B級映画」は、歴史的な使命をとうに終えている。「撮影期間は十日間、予算は通常映画の十分の一、上映時間は八十分、という単純さが映画に思いもかけぬ不意打ちをくわせる時代」は完全に終わった。だからそれを懐かしみ、信仰の対象に仕立て上げようとする行為は、あきらかに間違っている。つけ加えて言うならば、一般に「B級映画」とみなされているものは、「二流監督の作った安易な発想にもとづく粗製濫造のプログラム・ピクチャー」といったものにすぎず、真の意味での「B級映画」とは別物である。
「B級映画」は50年代には歴史から姿を消した。「二本立て興行」という「B級映画」の条件が消滅したからだが、この時期、よく知られるように、「赤狩り」によって才能ある作家たちがハリウッドから去ることを余儀なくされた。さらにテレビの影響によって1年に500本くらい映画を作っていたハリウッドは200本まで製作本数を減らしてしまう。そしてまた、30年代にヨーロッパからハリウッドに亡命してアメリア映画に協力していた才能豊かな作家たちが、戦後になると落ち着きを取り戻した故郷に帰ってしまった。このようにしてアメリカ映画は、廃墟への道をたどることとなった。
ヘイズ・コードによる保護を失ったアメリカ映画
1930年代有名な「ヘイズ・コード」が映画の歴史に登場する。これは日本における「映倫」のようなものであり、反道徳的な性描写や過激な暴力シーンを禁じるものである。そのことによって、表現の自由はないがしろにされ、アメリカ映画の画一化という現象が懸念される一方、「ハリウッドの黄金時代はあくまでも『ヘイズ・コード』との共存によって特徴づけられ、ことによると『ヘイズ・コード』そのものが、ハリウッドをアメリカから保護する機能を演じていたのかもしれない」という視点を蓮實重彦は提示している。
たとえば、男と女の肉体的な愛を描けないという不自由な条件を逆手にとって、そこに至るまでの過程を面白おかしく描こうとする「スクリューボール・コメディー」というジャンルが生み出され、ハリウッド映画を活気づける。また暴力をスペクタクルとして視覚化することを禁じることによって、「視覚的な効果」よりも「物語の簡潔さ」を重視する古典的なハリウッド映画の美学が生まれた。
ヘイズ・コードは1968年に廃止されるが、その時アメリカ映画は大きな変容を蒙った。「サイレントからトーキーへの移行期に成立した物語の優位は、『ヘイズ・コード』によって助長され、30年代のアメリカ映画の黄金期」を支え、そのような条件においてシナリオの映画であり編集の映画でもあるというハリウッド映画の美学が成立したが、「『ヘイズ・コード』の消滅は、アメリカ映画からこうした物語の優位を奪い、見せることの至上権争いへと人を駆り立てる」。視覚的なスペクタクルばかりが強調され、映画はたんなる「見世物」へと変貌してしまう。
いわゆる『アメリカン・ニューシネマ』がその登録商標のごとくに濫用したスローモーションとズームとによって、『B級』的な発想の小品までが、無意味に上映時間を引き伸ばしてゆく。ラオール・ウォルシュならワン・ショットで片づけた活劇における犯罪者の姿を、『俺たちに明日はない』(67)のアーサー・ペンは何十秒もかけて撮ったのだし、ヒッチコックならたった一つの切り返しショットできわだたせただろうサスペンスを『キャリー』(73)のブライアン・デ・パルマが何十秒にも引き伸ばしたことが、その変化を雄弁に証拠だてていよう。その結果として、アメリカ映画は二つのジャンルを失う。サスペンス映画と西部劇である。
今現在の映画の状況でもあるが、私自身も、コンピューター技術を駆使した見世物映画よりも、「有効なショットの連鎖」に映画本来の運動を感じる。だから、次のような蓮実の言葉には完全に同意する。「最良の作家とは、瞳だけに働きかけるイメージのスペクタクル化の全盛期に、その風潮になじめず、物語の簡潔さに貢献するショットの可能性を確信しつつ、たんなるハリウッド映画のパロディとは異なる語り方を発見した人たちのことにほかならぬ」。そうした作家の筆頭として、蓮實が挙げるのが「73年の世代」のイーストウッドである。逆に『フルメタル・ジャケット』のキューブリックは評価しない。フランシス・コッポラに関しては、『ワン・フロム・ザ・ハート』や『ドラキュラ』は視覚優位の作品ゆえこれらを評価せず、語りの映画である『タッカー』は高く評価している。『タッカー』の主題は「メジャー対インディーズ」であり、なおかつ「ジェフ・ブリッジズの楽天的な笑顔にもかかわらず、ふとロバート・ロッセンやジョン・ヒューストンをさえ思わせる四〇年代後期の反逆的な英雄物語と、それにふさわしい簡潔な題材処理が行われており、まるで映画産業における『五〇年代作家』の戦いを描いているかのようにみえる」。「50年代」に視線を向けるという行為は、いまもなお有効であるかのようだ。私は『リュミエール』を通して歴史の見方を学んだが、映画のみならず思考を抽象化させずにおくためにも具体的な歴史を感受する姿勢はあらゆる領域で必要であるにちがいない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
