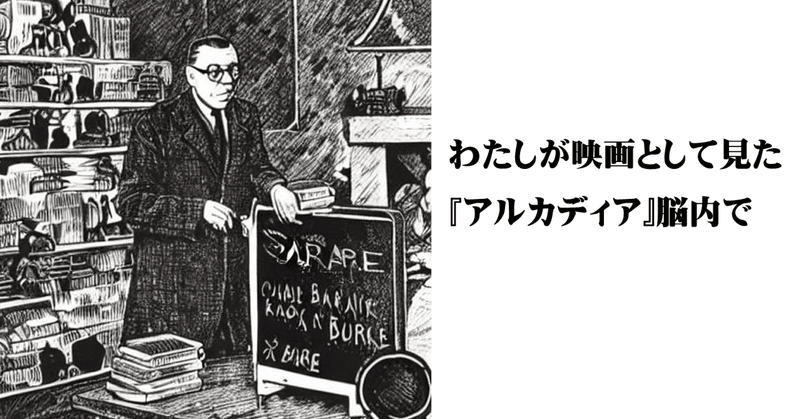
わたしが映画として見た『アルカディア』(脳内で)
2023年の1月が早くも31日を迎え、今年の12分の1が、あっという間に過ぎ去ろうとしている。noteアプリから、「このままだと8ヵ月連続投稿チャレンジが途絶えてしまうよ」と通知があったので、ファスプロ1時間チャレンジ。例のごとく、以下の内容は、何の事実にも基づかないただのデタラメである。
昨年末、日本の動画配信サービス「ダーニャ」が、"ネオ・マルチバース(Neo Multiverse)"と銘打ち、作品発表と同時に配信を開始して話題を呼んだ、「異なる監督と脚本家によって描かれる三部作」の第1作、それが今回ご紹介する『アルカディア』である。
本作の最大の特徴、それはなんといっても"わかりやすさ"だろう。本作でメガホンを取った劇団ひとりが、特別配信されているオーディオ・コメンタリーで語っているとおり、本作では、明確なテーマと明確な対立構造が実にわかりやすいかたちで描かれている。
さて、本編の内容はといえば、世界史の教科書でもお馴染み、ジャン=ポール・サルトルの引用に始まったり、主人公のひとりであるマリーが、劇中で彼の主著「存在と無」を読むシーンが描かれたりするなど、タイパを重視する昨今のニーズに大いに応えるかたちで、「これは"実存"をテーマにした作品ですよ!」というメッセージが、映像の手触りとは裏腹にケバケバしく喧伝されながら、内容的にも実に過不足なく作品はその展開をみせる。
歌うことで感じられる自分自身の存在を、「実存」の拠り所とするホリコミと、彼女が所属する組織が言うところの"修正"の名の下にテロ行為に加担し、他者を破壊することで「あるべき存在」を具現化しながら生きるマリー。フランスの地で、予定されたテロの犯行現場に向かうマリーが、ホリコミの運転する車をヒッチハイクする場面から物語は始まる。
海が目的地だとホリコミに告げたマリーは、道中に存在する、テロの対象となるいくつかの施設での停車を依頼しながら、粛々と爆弾の設置を完了させていく。そんなマリーを余所に、テロの片棒を担がされているとは露ほども思っていないホリコミは、相棒のホリコメと共に歌い、己の存在を噛みしめる。両者ともに、それぞれの目的を遂行していくのだが、胸の奥に潜む信念が正反対であることは、監督が名言しているとおりである。
劇中におけるホリコメの歌唱シーンでは、サウンドトラックからの音源が重ねらているのだが、その音楽の全体的な雰囲気は1990年代に「渋谷系」として日本で流行ったサウンドそのものであり、個人的には、表題曲となっている「アルカディア」という曲名は、その時代を中高生として過ごしたぼくに対しては、「サルトル」というキーワードと共に、高校生時代を思い出させてくれる仕掛けの一つとして機能してくれたように思う。「アルカディア」という固有名詞は、第二次大戦中に行われた、フランクリン・ルーズベルトとウィンストン・チャーチルによる米英会議のコードネームとして日本ではよく知られていると思うが、本来は、ペロポネソス半島の中央辺りを指す地名であり、「古代の楽園」の代名詞として後世に語り継がれている名称でもある。
敬虔なクリスチャンであったマリーは、無神論の立場をとるサルトルの思想に強烈な怒りを覚え、若い頃より、志を同じくするテロリスト集団に身を置くこととなった。本質、すなわち神の意思こそ存在に先立つとの考えを信念として、破壊活動によって世界をあるべき姿へと修正してきた若きテロリスト、マリー。彼女は、自らの存在を、まるで自由意思が赴くままに証明しているかのように歌い続けるホリコミの姿に、次第に心境の変化を強いられることとなる。物語が進むほどに、目の前で、実存の足場を固めるホリコミを眺めるマリーの脳裏に、次第に敵性思想の生みの親であるサルトルの声が蘇ってくるようになるのだが、この明瞭な演出が見ている者の理解を大いに助けてくれる。
そして物語の終盤では、自らが信念だと思っていたものに対して疑念を持ち始めたマリーの元に、当然のように、ホリコミとホリコメの殺害命令が組織から下される。自分の中に何か新しい存在を生み出そうとしていた二人を、"あるべき存在"として、命令通り始末したあとのマリーの表情が、まるで本作品を鑑賞した者に解釈の自由という名の罰を与えるかのように、大きなキャンバスが如く白い広がりを見せていたように見えたのは、ぼくの行き過ぎた解釈なのだろうか。
おしまい
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
