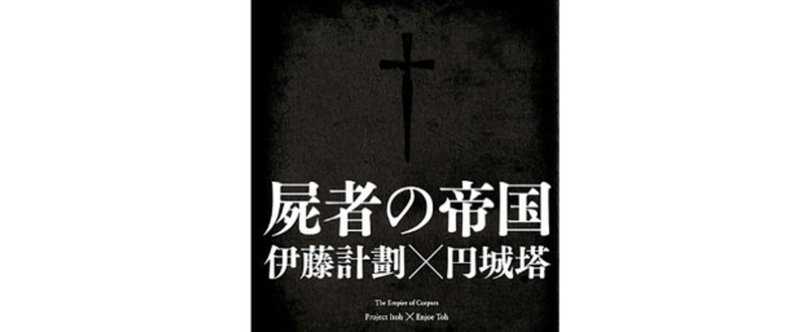
『屍者の帝国』伊藤計劃×円城塔 ◆SF100冊ノック#14◆
■1 あらすじ
19世紀大英帝国―死体に霊素を注入し、プラグインを読みこませることで、ロボットのように、あるいはコンピューターのように用いる技術の発達した、今とは異なる世界。医学部生ワトソンは、ある日英国の軍事探偵へとスカウトされる。最新の「屍者」フライデーを伴い、向かう先はアフガニスタン。追うのは、「屍者の王」とも呼ばれる革命家、アレクセイ・カラマーゾフ―
現実・虚構の人物・歴史が入り乱れる中で、ワトソンは「ザ・ワン」―フランケンシュタイン博士による最初の「屍者」の影を見る。明治時代の日本、さらにはアメリカへ。世界をめぐる旅の中で、次第に壮大な陰謀と思惑が明かされていく。
■2 設定の妙
と、あらすじを書いてみてもあまり伝わらないんですが、とにかく設定の素晴らしさに魅せられる。「19世紀」という過去を描きながらも、屍者技術が現代を超えるロボット技術、コンピューター技術のように働くことで、レトロさとSFが無理なく融合。「屍者」というテクノロジーを用いることで、歴史・社会がどのように変化したか、を描く手つきはまさにSF的想像力の歓び。
さらに、「屍者」は多くの意味を持たされる。既にプロローグの時点で、それは「フランケンシュタイン」の発明である―「人造人間」のイメージを持たされ、「プラグインを書き込む」という言葉でアンドロイドへ、後にはコンピューター的なイメージを持たされることで、「死」の持つ禍々しい、呪わしいイメージをテクノロジーに吸収する。「ゾンビ」の言葉は一度も出てこない(たぶん……)「屍者」の意味が幾重にも重なり、ずらされていく中で、様々なテーマを―例えば「哲学的ゾンビ」であるとか、「キリスト教の復活の奇跡の体現」としての屍者―語ることを可能にする。
着想の1つは、同様に過去の超テクノロジーを描いた『ディファレンス・エンジン』だと思うし、これまで読んだ中では、『ブラッド・ミュージック』の生理学的な描写や、『地球の長い午後』の脳に宿る菌類アミガサタケ、を思い出す。
この小説、とにかく様々な勢力が入り乱れて、また史実上の人物も次々登場し、彼らの思惑が似てたり絡まったり……というので非常にわかりにくい。意図的にそうしているという印象もあるのだが……読む前に、19世紀の世界史、特に各国の外交状況を確認したり、特に『フランケンシュタイン』や、本書最後に記されている参考文献をめくってみると良いと思う。また、読書中、特に各勢力の「目的」をメモしながら読むのがおすすめ。(そうでもしないと話を見失う)
僕は、以前に円城さんの本で挫折した経験が幾度かあり、その複雑で説明過剰な文体をあまり好きでは無かったのだけど……この小説で印象が大きく変わった。むしろ、複雑な世界を読み解いたり、その中で人間を想像していくこと。読み手により多くを求めるのだけど、一方で、決してそれは必須ではなく、楽しむことが出来るとも思う。再読もきっと楽しいだろう。
■3 伊藤計劃と「意識」
伊藤計劃がプロローグだけを書いて亡くなり、それを円城塔が引き継いで書いた作品。それが「屍者」をテーマにしている、というところからも色々語れそうだが、円城は、伊藤がこれまで書いてきた「言葉・言語」「生命」なにより「自我・意識」を本作のテーマとして織り込んでいる。
特に印象に残った場面は、ハダリーとの会話で、「屍者」がいわゆる「哲学的ゾンビ」として語られること、さらにそれが、全ての人間にまで敷衍されていくところ。テクノロジー、特に脳科学や人工知能技術が進む中で「意識」というか「自由意志」みたいなものが揺らいできてて、これまでも『攻殻機動隊』や、最近の『ユートロニカのこちら側』、もちろん伊藤の『ハーモニー』でも繰り返し描かれてきた。
これは読み込み過ぎかもしれないが、最後に「言葉」を上書きされたワトソンが、ホームズの「語り手」となるところにメタ的な解釈をしたくなる。そして、これまで受動的だった「筆記者」にして「屍者」フライデーが(それは、ロビンソン・クルーソーの中で「奴隷」すなわち自意識が許されない従属的な者の名だ)自ら、魂を宿して動き出す……「ワトソン」とはつまり、観察者にして作家のシンボルではないか。言葉によって世界を想像・創造することが魂の証明……という読みはロマン主義の懐古厨と言われてしまいそうだけど。
追記:(原作小説→小説『フランケンシュタイン』のこと)
■4 キーワード
パスティーシュ #スチームパンクSF #伊藤計劃 哲学的ゾンビ フランケンシュタイン 意識・認識 #屍者の帝国
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
