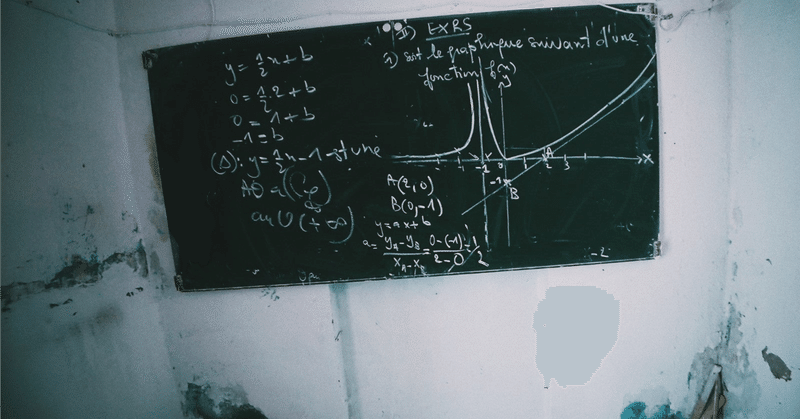
#131 私が自分のことを「先生」と呼ばない理由
先日、後輩教員と飲んでいる時に、
「先輩は自分のことを先生って呼ばないですよね?何でです?」
と、唐突かつナチュラルに問われた。後輩の人間観察力の鋭さに感嘆するとともに、そういえば何で俺はそうしようと思ったのだっけと、何杯目かの角ハイボールを流し込みながら、思考を巡らせた。
「感覚的な問題ではある。」
と、長芋のわさび和えを口に放り込みながら、後輩に答えた。
「どういうことです?」
「感覚的に嫌なのだよ、自分のことを先生と呼ぶのは。」
「ちょっと意味わかんないです。でもほとんどの先生は、自分のことを先生って呼びますよ。放送でも、〇〇先生からのお話ですと言うし。」
「だからそれも、その人の感覚的な問題であるわけよ。」
何の答えにもなっていないよなあと反芻しながら、タッチパネルを押し、角ハイボールをおかわりした。
「先生という名詞は、読んで字の如く、【先に生まれた人】を意味するわけだ。であれば、児童にとってその関係性は永続的だ。ただ、ある地点を境に、児童は我々を超えていく。もしかしたら、現時点で我々を超えてさえいるかもしれない。実際に、私はもう6段の台上前転はできない。」
「もうですか笑」
「笑うな、俺はもう四十を過ぎている。そうなると、先生という名詞はなんら意味をなさないものになってしまう。」
「つまり感覚的な部分はスキルと結びつくってことですか?」
ハイボールから日本酒に選手交代をして、思考を深めようと思った。
後輩はグイグイとバイタルエリアに切り込んでくる。
「弁護士や医者も、先生って呼ばれますよね。でも自分では先生とは言わないですよね?」
「彼らは私たちの悩みを抜本的に解決するスキルを持ち合わせている。だから尊敬の念を込めて、黙っていても皆から先生と呼ばれるだろう。我々はそれができないのだよ。言ってみれば農耕民族。そのあたりを埋めるために、自ら先生という呼称を使うのではないだろうか。」
「はあ。」
「そう、自信のなさの表れだよ。本当に自分に自信がある教員は、先生という呼称を用いずとも、児童を惹きつけることができる。だから、上下感をもたせる先生という呼称を用いないのだよ。」
結局、確固たる結論を見出せぬまま、酒だけが進み、いつもの如く泥酔してしまった。翌日、途切れ途切れの記憶の中、私は二日酔いと闘っていた。自分に自信がないから酒の力を借り、泥酔してしまうのだ。今日は休日。いつもより数時間遅い起床に、「先生はいいご身分で。」と家族に言われるのは目に見えているから、もう少しだけ寝て、やり過ごそうと布団の中で決意した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
