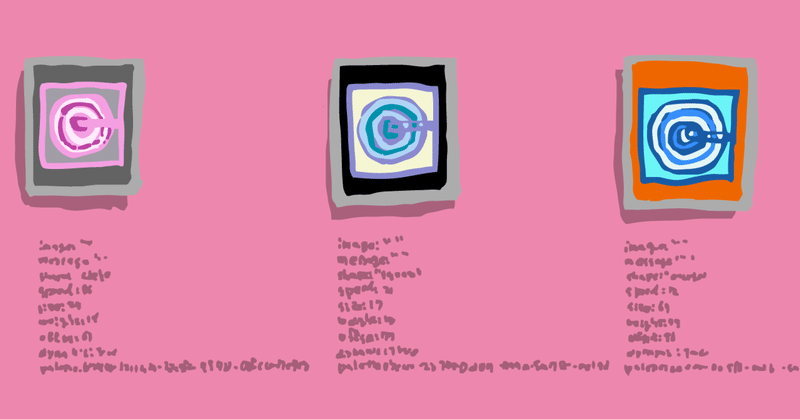
正気に返らせるもの―Made in Contract展評
「考えさせるもの」と「考えさせないもの」
「NFT」という言葉には、とにかく悪い印象しかない。NFT(Non-fungible token)の存在を知った当初は「デジタルデータの商取引を可能にする夢のような技術」という華やかな印象だったが、それが「価値の不確かなものが高額でやり取りされるアヤシゲなもの」という賭場的ないし詐欺的なイメージに塗り替えられるまでにはそう時間を要さなかった。そのためバブル絶頂の頃は警戒して遠くから観察するだけにとどめ極力関わらないようにしていたのだが、思うところあってバブルの波も鎮静化した去年の六月からジェネラティブアート専用のNFTのプラットフォームであるfxhashに作品を投稿するようになった。すると始めた途端にNFT絡みの詐欺的なメッセージが山のように来るようになり、あらためてその「治安の悪さ」に驚かされた。さらには知人が本格的に怪しい類のNFT(取引の場がオンラインではなくセミナー会場だったりするようなもの)の販売に加担して自分も巻き込まれそうになるという事件まで起きて、個人的にはもう「NFT」といえば詐欺の代名詞のような散々なイメージしか持っていないというのが実情なのである。
NFTが「うさんくさい」のには二つの理由があるように思われる。一つはその技術的な実体が複雑で理解しづらいこと。注目を集め始めた当初は大手メディアでさえ「デジタルデータの複製を防ぐ技術」などと大間違いの説明を平気でしていた。さすがに時間が経つにつれそれは修正されていったが、しかしだからと言って「では結局NFTとは何だったのか?」という質問にすんなり答えられるのは今でもNFTに精通した一部の人たちだけだろう。その実体が理解しづらく、にも関わらず誤ったイメージばかりが誇大広告気味に流布してしまっている。詐欺師の材料になるのに、これほどの好条件はまたとあるまい。
「うさんくさい」のもう一つは言うまでもなくその投機性だ。無価値に等しいデジタルデータが一夜にして天文学的な価格を付ける。バブル的な熱は沈静化したとはいえ、広く世界を見回してもここまで錬金術的に無から有の価値を生み出し、ここまで大幅にその価値を乱高下させるものも珍しいだろう。当然これも詐欺師にとっては絶好の商売ネタである。
そしてそれは当のNFT自身にとっても問題である。先に挙げた技術的な実体のわかりにくさと合わせて、一攫千金を狙える金融商品的なイメージがあたかも「NFT」の本体であるかのようになってしまっているからだ。もちろんそんな浮ついた風潮を尻目にNFTの技術を使って何が出来るかについての模索は着実に行われているのだろうし、そうしたニュースに接することもある。しかしそれらが普段目にしている価格の乱高下ばかりが話題になっている「NFT」とは全く別の技術なのではないかと疑うくらいにまでNFTの投機的側面は突出してしまっている。そして自分にとって何よりも腹立たしく感じるのは、そこで人々の欲望を煽り、投機の対象とされる主たる商品が「NFTアート」という、仮にも「アート」を名乗るものであることなのだ。
世の中には「立ち止まって思考することを促す」と「思考の機会を奪う(考える暇を与えない)」の二つのベクトルが存在する。後者は詐欺師の常套手段だが、同時に現在では経済全体を動かすための駆動力として広く活用されている。小売りのタイムセールも、株価の変動も、「今買わないと損をする(考える前に行動しろ!)」という暗黙のメッセージで我々を行動(多くの場合は消費)へと駆り立てる。いつでもどこでも価格やレートが一定した穏やかな世界に生きてみたいと願うが、それでは世の中が回っていかないということなのだろう。思考の機会を奪って「考えさせない」スキルは、考える前に行動しないと死んでしまうといった緊迫した状況に対処するために発達した生物としての人間の生存本能を利用したものなのだろうが、良くも悪くもそれで人々を行動させ、その動力によって動く経済によって我々の社会は成り立っているのである。
しかしそれが行き過ぎると困ったことが起こる。「考えさせないもの」は人を行動へと駆り立て、そのことが社会を動かすような大きなエネルギーを生み出しもするが、そのエネルギーが大きくなり過ぎると暴走が始まり制御ができなくなる。とりもなおさず「考えさせずに行動させる」ということは「人を狂わせる」と同義だからだ。生存本能を過度に刺激されて破滅した人間や熱狂状態に陥った集団がしでかした愚行の数は限りがない。
そこで重要になるのが「立ち止まって思考することを促すもの」の存在なのだ。つまり狂乱状態に陥った人間を「正気に返らせるもの」である。「考えさせないもの」に比べると立ち止まっての思考を促す「考えさせるもの」は、それ自体が経済全体を動かすような巨大なエネルギー源になることは難しい。しかしそれは暴走する熱を冷まし、そこで生まれた流れを適切な方向に向かわせる役割を果たすのだ。人をいやおうなく行動へと駆り立てる「考えさせないもの」とその暴走を抑制する「考えさせるもの」の二つのベクトルが釣り合って、人類ははじめて破滅へと到ることのない適切な発展が可能になるのだと言える。
自分は本来アートは「思考の機会を奪って行動させるもの」ではなく「立ち止まって考えさせるもの」のほうであるべきだと考えている。しかしNFTにおいて「アート」が果たしている役割はその反対だ。「NFTアート」と呼ばれるものの大半は、短期間に価格が大きく変動するNFTの「考える暇を与えずに行動(売り買い)させる」という熱狂発生システムの燃料となり、積極的にそれを加速させている。自分がNFTを「うさんくさい」と感じる最大の原因はこれかもしれない。
NFTを(で)考えさせる展覧会
しかしNFTに関わる人たちのなかにも真剣に「考えさせる」の方向へと向かおうとしている人たちが存在する。自分が見聞したなかでは、昨年の春に3331アーツ千代田で見たProof of X展などがその代表である。この展覧会を見たことでそれまでネガティブ一辺倒だったNFTのイメージが若干プラスの方向へと修正され、「NFTだから…」と躊躇っていたfxhashへの投稿を始めることへの後押しにもなった。
本稿で取り上げたいのは、そのProof of X展の出品作家でもあったNIINOMIが代表を務めるギャラリーNEORT++でつい先日まで開催されていたMade in Contract展である。この展覧会はProof of Xからの流れも感じさせるNFTについて「立ち止まって思考することを促す」企画だった。Proof of X展のときはまだ見えていなかったデジタルアートのフィジカル展示としての可能性も感じさせNFTをテーマにした展覧会としてはこれまでにない出色の出来だったように思われる。
Made in ContractはNFTの技術的な核である「スマートコントラクト」をテーマにした展覧会である。スマートコントラクトとはブロックチェーンに記録されたプログラムを実行する仕組みで、NFTをNFTたらしめている核心的な技術であるとも言える。とはいえ専門家でもない限りその重要性はなかなかすんなりとは理解できないだろう。しかし本展はその難解な技術要素をテーマにしつつも、展示自体は難解さを感じさせるものではなかった。むしろスマートコントラクトをテーマにすることで実態が掴みづらかった「NFT」本体の姿を明らかにするような場となっていたように思う。
本展のステートメントではスマートコントラクトを利用した作品を「Contract Art」という呼称で新しいアートとして定義しようとしているのだが、スマートコントラクトがNFT技術の核であることを考えれば素直に「NFTアート」でよさそうにも思える。そのほうが混乱も少ないし、一般にも受け入れられやすい。しかしそれにも関わらず主宰者が「Contract Art」という新語を捻出しなければならなかった背景には、前述した通り「NFTアート」の語が本来的な「アート」の文脈で使用されない状態で蔓延してしまっているという現状があるのだろう。同じNEORT++で昨年開催された高尾俊介の個展「Tiny Sketches」の関連トークでゲストの畠中実が「ビデオを使っている作品が全て“ビデオアート”ではないのと同じく、NFTの流通手段を使っているからといって“NFTアート”ではない」という趣旨の発言をしていたが、まったくその通りだと思う。本来ならば本展に出品されている作品のほうが真に「NFTアート」と呼ばれるべきものなのだ。
本展に関して特筆しておきたいのはそのインスタレーションの洗練度の高さである。Proof of X展は志の高い企画だったが展示自体はオーソドックスな体裁で「寄り合いによるグループ展」の感は否めなかった。それに対して本展は展覧会としての統一感があり、展示される作品はデジタルでもフィジカルな展示であるからこそ見えてくるものが多々ある複雑な造りになっていた。ここではとくにその展示の様相と効果を中心にして、具体的に本展の出品作品がどのようなものであったのかひとつひとつ見ていきたい。
各展示作品について
bouze 《Advertise》、《HODL》
展覧会を訪れる観客が最初に目にするのはギャラリーが入居するビルの入り口に設置された大型の縦型モニターである。そこに表示されているのは「広告」なのだ。これは本展の参加作家bouzeの作品《Advertise》で、投稿サイトにURLを送れば誰でも無検閲でそのURLが示すwebページをこのモニターに表示することができる。表示される権利はその時点で最高の金額を支払った者。次の投稿者が現れなければいつまでも同じ内容が表示され続けるが、支払った直後にそれを上回る金額の投稿があれば表示が誰の目にも留まらぬうちにすぐさま終了してしまう可能性もある。投稿のための金額は日本時間の0:00にリセットされる。現代社会の代名詞的な存在でもある広告とNFTでも盛んに使用されるオークションの仕組みが合体されることによってレンジが広い批評性を持つ作品になっている。
本展におけるこの作品の妙は、広告が表示されるモニターの設置状況にこそある。NEORT++が入居するまるかビルは廃ビル寸前の小さな建物で、大通りに面しているわけでもなく、しかも入り口前が駐車スペースになっていてギャラリーを目指してきた人ですら気付くのが難しいくらい目立たない場所にある。つまり通りがかった人が偶然目にする…といったシチュエーションはまず期待できないのだ。同じモニターが会場内にも設置されているが建物の外に設置されているモニターと目撃される確率はそんなに変わらないかもしれない。広告を掲示するのにこれほど不向きな場所もないというくらいの悪条件なのである。これを目にする者は本展を目当てにギャラリーを訪れた人ばかりとなるので、その特定層をターゲットにした広告ならばある程度の宣伝効果はあるのかもしれない。とはいえ規模としては知れたものだろう。宣伝効果を狙って投稿が殺到しインフレーションが起こる…といったことはまず起こりそうにない。
もちろんこの作品の面白さはそこにこそある。逆に広告スペースとしての価値が高く表示機会の奪い合いになるようでは作品の持つ意味合いが変わってしまうのである。タイムズスクエアに広告が表示される権利と馬喰町のまるかビルの入り口に表示される権利とではその意味合いが全然違うのだ。同じ「広告」と言っても費用対効果を厳密に計算して打ち出される一般の広告とはそもそもの種類が異なるのである。誰の目にも触れることなく終わるかもしれない本作での広告表示にわざわざ対価を支払って参加する人は、それが「粋な遊び」だとわかっているからこそ参加するのだ。この作品が本当に広告スペースとしての価値を増し、そのことによって巨額の利益を上げるようになったら、途端にそれは「野暮」になる。野暮になるイコール「批評性を失う」ということだ。
これは非常に重要な点である。コンテンポラリーアートの大物作家が既に何人かNFTを使った作品を発表しているが、それらに全く批評性が感じられないのは彼らの作品がNFTの文脈を相対化するようなコンセプトを謳いつつも、その実はNFTの錬金術的な熱狂システムの補強に加担しているだけだからなのだ。「考えさせる」素振りを装いながら、実際は人を「考えさせない」方向へと導いているのである。熱狂の最中にいながらその熱を冷まさせることはきわめて難しい。熱狂のシステムを利用しながらも、そこから適切な距離を取ることで初めて相対化は成る。人を狂わせるNFTの熱狂システムからの距離の取り方はこの作品の肝であり、本展の他のどの出品作品にも確認できる特徴である。
そしてそのことよりもなによりも、この作品が最高なのは廃ビルのような古びた建物の入り口におよそそれに似つかわしくないハイパーなデジタル広告が設置されているその違和感バリバリな光景なのである。この面白さは写真でもある程度確認できるので、公式アカウントや来場者の撮影した写真をSNSなどでぜひ探してみてほしい。
展示の二作目は同じbouzeによる作品《HODL》である。壁に二つの円形の光がビデオプロジェクターで投影されている。光はエッジの光彩を微妙に変化させながらわずかに揺らめている。一つの円は大きく、もう片方は小さい。この作品は当該のNFTを保有している期間に応じて円の大きさが拡大していくという作品である。NFTを売却したり、他のウォレットに転送したりすると大きさがリセットされる。盛んに転売が繰り返されることで値段が吊り上がり「価値が上がる」というNFTのシステムに対する批評性を持っている。
本展の展示の特徴として物理的なモニターによる表示とプロジェクターによる映写の使い分けの上手さが挙げられるのだが、この作品においてそれは特に顕著である。もしこの作品が先の《Advertise》と同じ液晶モニターで展示されていたら、そこに表示される円の大きさは画面のドット数で正確に計測することが可能になり、その絶対的なサイズはNFTが保有されている期間を示す数字以上の意味は持たなかっただろう。しかしビデオプロジェクションの場合は少し事情が異なる。プロジェクターを壁に近付ければ投映される円は小さくなるし、遠ざければ大きくなる。映写の場合は「絶対的な大きさ」という概念自体があやふやになるのだ。確かに二つの円のうち一つは大きいので保有期間が長いのだと理解できるが、それは隣の小さな円と比較しての「大きい」であって、もし円が一つだけならそれが大きいのか小さいのか、つまり保有期間が長いのか短いのか、その判断にすら困るだろう。
つまりナンセンスなのだ。そしてそのナンセンスはもともとこの作品自体に含有されていたものである。保有期間に応じて円が大きくなる。ナルホド。でもだからなんなんだ? 保有期間を数字で表示するのと円の大きさで表すのとでは何が違うんだ? もちろん何も違いやしない。ナンセンスなのである。しかしナンセンスだからこそ、この作品を見るものはNFTを「保有」することの意味について立ち止まって考えることを促される。NFTを短期間で転売して利ザヤを稼ぐ手段としてしか考えていない手合にはそんな考察は不用かもしれない。しかしそんな手合しか存在しないNFTに何の意味があるのか? 短期転売による価値の流動性は場を動かすエネルギーを生むが、しかし“それだけ”になってしまったらNFTの技術が持つ潜在的可能性が花開くときも訪れなくなってしまうだろう。この作品はナンセンスだが、そのナンセンス性が場を浄化する「考えさせるもの」としての機能を果たしているのである。
NIINOMI 《Memory Disc》
次の展示作品はNIINOMIの《Memory Disc》だ。正方形に近いやや縦長のモニターが壁に五つ等間隔で並ぶ。画面には色とりどりの模様が回転するレコード盤のような図柄が表示されている。この作品を目にしたものがまず感じるのは展示用のデバイスがカッコイイ!ということだろう。剥き出しのディスプレイが壁から浮いた感じに見えるよう工夫されたこの機器は、本作品のための特注なのか、デジタル作品の展示用ガジェットの試作もしているこの作者のことだからもしかしたら自作のものなのかもしれない。市販のモニターでただ映像を流すのとは段違いの、設置される壁面との比率も完璧なまさに「展示のためのデバイス」といった感がある。
しかし本作の肝はそこではない。重要なのはこの作品があくまで「スマートコントラクトをテーマにした展覧会」への出品作であることだろう。その証拠に各デバイスの下にはビデオプロジェクションでそれぞれの絵柄に対応するNFTのブロックチェーン上に記録されたattributesの文字情報が投影されている。その内容は図柄の色、形、サイズ、回転スピードなどだが、拍子抜けするほど単純かつ簡潔な情報である。それもそのはずで、そもそもNFTにおいて実際にブロックチェーン上に記録される情報の量は極めて小さい。記載量によってガス代(手数料)が決定されるので自ずとそのサイズは縮小せざるを得ないのだ。本作は記録媒体としてのCDをモチーフにしているとのことだが、今やすっかり時代遅れになった感のあるCDでも一枚のディスクで650~700MBぶんの情報が記録できる。しかしそれと同じだけの情報をNFTとしてブロックチェーン上に記録しようと思ったらいったいいくらかかるかわからない。ガス代の高いチェーンではKB単位の調整に奮闘しているのだというのだからまさに桁違いだ。
実はこのことはNFTの実態がわかりにくい要因の一つにもなっている。「NFTはブロックチェーンに記録されるから永続性が保証される!」とか「画像がオリジナルであることを証明できる!」とか喧伝されていたわりには、肝心の画像データはそこには保存されていなかったりする。ドット絵やコードだけで出来ているようなファイルサイズの小さいデータを除き、一般のjpeg画像を表示するような「NFTアート」の大半はブロックチェーン上には画像データの保存先のURLを記録しているだけのことのほうが普通なのだ。この《Memory Disc》でも、展示されている作品の一つはjpegデータ(作者NIINOMIのアイコン用画像)を使用したものだったが、attributesのimageの欄には画像の保存先であるIPFSのアドレスが記載してあるだけだった。
この作品で見るべきものは、NFTの中身であるattributesの文字情報のスカスカ感とフィジカルなデバイスで表示される作品のモノとしてのカッコよさとの落差である。確かに各作品の見た目を決定しているのはこのシンプルなattributesの値であり、NFTとしてこの作品を「保有」するものは、この値にこそ対価を支払っていることになる。しかしそれはその場で即座にメモしてしまえるくらいに簡素なものなのだ。もしこの作品をフィジカルな作品としてデバイスごと購入するとしたら、家のどこに飾ろうとか具体的なイメージがいろいろとわくだろう。しかしこのattributesの値を「保有」することへの具体的なイメージはわきにくい。いっぽうデバイス機器は大量生産も可能だし一つのモニターで違う絵を表示することもできる。その意味で言えば作品の「本体」は素っ気ない文字列のほうだと言える。しかしブロックチェーン上に記録された文字列と、今この場でメモ帳に書き写した文字列では何が違うんだ? それに見ていてときめくのは絶対デバイス表示のほうだし、attributesの値を見てときめく人間がいたらよっぽどの変態だろう。いったいデジタル作品の実体はどこにあるのか? 回転するディスクの図柄に合わせるかのように、見ているこちらの思考もぐるぐるぐるぐる回転する…。
NFTの「保有」については、それに慣れた人ならばもう当たり前の感覚になっているのかもしれないが、我々一般人の感覚ではまだまだ理解しがたいものである。しかし考えてみれば現代アートの映像作品の「所有」なども一昔前はなかなか理解が難しかったが、今ではすっかり当たり前になった感がある。NFTの「保有」の感覚や、デジタルアートにおいていったい何が「本体」であるかの認識もすぐに変化していくのかもしれない。本作の展示はモノとしての作品とブロックチェーン上に記録される情報の両方を対比させることで、新しい技術の登場によるその移行期の感覚の在り様を炙り出していた。通常ならばattributesの情報を紙に印字してパネルで展示してしまいがちなところを、ビデオプロジェクションで映し出しているのも効果的な演出である。そのことによってフィジカルな現実界(モノとしての展示用デバイス)と抽象的なオンチェーンの世界(投影される簡素な文字列)というレイヤーの違いを体感できるからだ。
0xhaiku《Receipt》、《Recycle bin》、《marquee shelter》
続く展示は本展三人目の出品者0xhaikuによる作品《Receipt》と《Recycle bin》である。前者は購入者が好きな金額でmintすることができるという作品。ただしその金額はまだ誰もmintしていない一意のものでなければならない。後者はNFTのBurn(廃棄)の仕組みを利用して、保有する任意のNFTをBurnすると代わりにRecycle Bin(ゴミ箱)のジェネラティブアートNFTが手に入れられるという作品。どちらもNFTの基本的なシステムを題材としたコンセプチュアルな作品だが、展示ではmintされた作品が実際に紙のレシートとして会場内に設置された機械から印字されゴミ箱に流れ込むというインスタレーションになっていた。
しかし展示の効果として自分が感心したのは0xhaikuのもう一つの作品《marquee shelter》のほうだ。この作品はHTMLの規格から廃止されたmarqueeタグのみを使用して作成されていて、ブラウザがフォローアップするのを止めたら表示ができなくなるこの旧規格をブロックチェーン上に「埋葬」することを企図している。展示ではアスキーアートで描かれた犬が左右に歩いている映像がビデオプロジェクションで壁一面に投影され、他にMDNのmarqueeの解説ページがプリントアウトされて飾られていた。
この作品においてもビデオプロジェクションによる映像の投映が効果している。というのも同じ映像をデバイスのブラウザ上で見ることもできるが、ブラウザで見る場合はmarqueeタグが既に廃止された規格であるとはいえまだ現行のブラウザでも再生できるので「廃止されていずれ見られなくなる旧規格」に思いを馳せるためには若干の努力が必要となるからだ(ブラウザのバージョンアップで見られなくなった場合は今度は「見られない」ことによって想像力を喚起するためのまた別の努力が必要となる)。しかし映写による展示ではそのハードルがスキップされる。映されているのがブラウザ上で動いている映像なのかその録画映像なのかはわからないが、再生デバイスに思いを致すことなくただ映像だけがそこに在るという状況はこの作品の展示には合っていたと思う。通常展示におけるビデオプロジェクションは映写環境が暗ければ暗いほど投映される映像が鮮明になってよいのだが、本作の展示の場合は光量の不足によるやや薄めの映像がむしろ「いずれ見られなくなる廃止されたHTML規格」というノスタルジー感と上手くマッチしていて、掲示された規格のプリントアウトと合わせてブロックチェーンを墓地に見立てたメモリアル感を絶妙に演出していた。
unknown artist《TODAY》
本展四人目の出品作家は匿名で、正確には存在しないと言ってもいいかもしれない。河原温の日付絵画を模したSNSのアカウントが展示権フリーで公開されていたために追加されたのだという。作品は会期中の当日の日付が日付絵画のフォーマットで表示されたフルオンチェーンのNFTがニューヨーク時間の0:00に1024eth(会期時のレートでだいたい2億円以上)からスタートして誰かがmintするまで1時間ごとに価格が半減していくという仕様。mintされなかった日付のNFTは廃棄される。
冒頭の《Advertise》が通常の値を吊り上げていくかたちのオークションだったのに対し、本作では高値からスタートして買い手が現れるまで値を下げ続けるというダッチオークションの手法が採られている。どちらの作品も天文学的な金額を上限としながらも高額な値段帯での取引を端から見込んでいないところに批評性があり、作品が成立するための条件となっている。人を「考えさせない」方向へと導く熱狂のシステムを利用しながら、熱狂自体からは距離を置き相対化を図るという姿勢は、展覧会の冒頭作から最後の作品である本作まで一貫している。
《Advertise》では広告の設置場所の「辺鄙さ」がその距離をつくるための手段となっていたが、この作品でそれに当たるのは本作と作品の元イメージの作者であるコンテンポラリーアートの巨匠河原温との繋がりのデタラメさだろう。というか、繋がりなど何もないのだ。河原の作品のフォーマットを模した投稿をしている匿名アカウント(これもおそらく河原との繋がりは何もなく、オリジナリティも特にない)が使用権を公開しているのに便乗して、さらに関係のない第三者がこれまた匿名で勝手に使用しているだけなのだから。しかしこの「無関係さ」こそが実は重要で、もしこれが某マンガの神様の遺族のように河原の作品の著作権を正式に継承した人間が出品する由緒正しいNFT作品だったなら本気で億単位の値段で競り落とされるかもしれず、そうなったらもはやそれは「アート作品」ではなく、ただの「下品」なのである。マンガの神様のNFTならばまだキャラクターグッズの延長として許されるのかもしれないが、さすがに河原温では無理だろう。本作ではそのギリギリのアナーキーなユーモアが欲望と無法の渦巻くNFTの現状に対する戯画となっていた。
本展の会場となったNEORT++はこじんまりとした小さなスペースで展示作品の数も多くない。しかしこれだけの数の作品からでも、NFTというシステムが持つさまざまな特徴を窺い知ることができる。《Advertise》と《TODAY》はNFTを通してやり取りされる価格の無根拠さや出品状況の無法ぶり、オークションシステムの狂乱さを露わにする。《HODL》はNFTを「保有」することの意味やその時間の「長さ」についてあらためて考えさせる。《Memory Disc》はNFTのブロックチェーン上に記載される情報の内実に目を向けさせ、NFTアートの「本体」とは何かについての考察を誘う。《Receipt》はNFTにおける「唯一性」について、《Recycle bin》はその「廃棄」の意味について問いかける。《marquee shelter》はNFTの特徴であるタイムスタンプ性と永続性によってそれが廃れ行く記憶の記録媒体として機能する可能性を示し、「消えていく技術や規格の埋葬地」というブロックチェーンの新しい利用方法を提案する。「NFTとはなにか?」「スマートコントラクトって何?」など説明だけ聞いてもなかなか理解しづらい抽象的な概念の実態が、展示を通してストンと腹に落ちたように体感できるのだ。
本展の出品作の大半はオンラインでも見ることができるのだが、面白いのは本来の居場所であるはずのオンラインで見たほうが展示会場で見たときに比べると作品の持つ批評性に気付きにくくなっているように感じたことである。オンラインはNFTの熱狂の中心(=取引の場)とダイレクトに繋がっているので展示会場で見るときよりはそれとの距離の取り方が難しく感じられるということも関係しているのかもしれないが、全般にフィジカルに体験する展示に比べるとオンラインでは作品の抽象度が高まりより観念的に感じられてしまうのである。この差はとても興味深く、デジタルとアナログの関係を考えるに当たって様々な示唆を孕んでいる気がする。良くも悪くも我々が今後生きていくのがデジタルと不可分な世界であることを考えると、本展は単にNFTという特定の狭い一分野だけでなく、もっと広く大きなものをも照射していたのかもれない。
*展示情報
「Made in Contract」
会期:2023年1月7日–22日
会場:NEORT++
住所:東京都中央区日本橋馬喰町2-2-14 maruka 3F
URL:https://two.neort.io/ja/exhibitions/made_in_contract
参考文献:hasaqui《NEORT++「Made in Contract」展評》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
