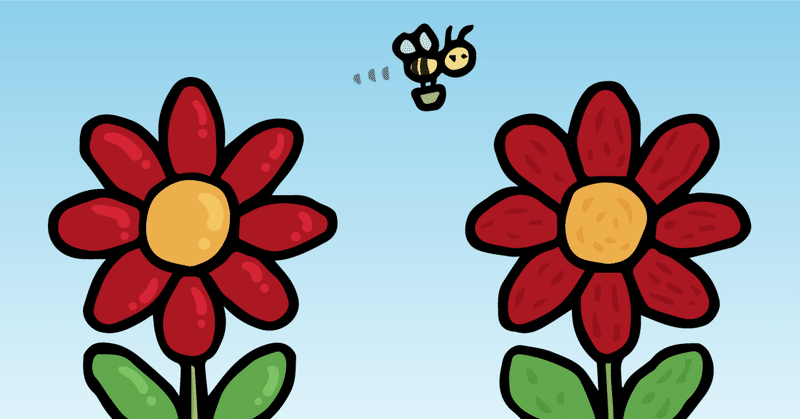
「作品」とはなにか?~生成AIと人間の違いから考える「作品」論
生成AIの登場による恩恵の一つに、AIと人間を比較することで様々な物事が明快になるという思考上の利点が挙げられる。AIにできること/できないことや、AIに任せてしまっていいもの/人間がすべきものについて考えることで、「人間」の本質が明らかになる。ここでは芸術分野における生成AIと人間による表現の違いを考えることによって、我々が持っている(いた?)「作品」という概念について考えてみたい。
絵画で時間を経験することの意味
先に自分が絵画の複時性について書いた記事をアップロードしたのとちょうど同じ日に、Tokyo Art Beatで美術家、美術批評家の石川卓磨氏による「画像生成AIに作れない作品とは何か——絵画は時間でできている」という記事が公開された。絵画の時間表現メディアとしての特性を画像生成AIの能力と比較しながら丁寧に論じる良記事でとても興味深く読んだ。絵画というメディアの特性と生成AIの能力の限界を考えるとき、「時間」に着目するのは必然的な帰結でもあるのだろう。
ただこの記事で画像生成AIにできないとされるもののなかには、技術的改善によって克服できるものも多く含まれているような気がする。たとえば石川氏は画像生成AIは未完成の作品を作れないと主張する。しかしそれは画像の完成図のみを生成する現在のアルゴリズムに基づく判断であって、たとえばここで彼が例に挙げるセザンヌの筆致の手順を学習させ、完成に至る前に中断するようにすれば、それは「未完成の作品」とはならないか? あるいは彼は手書きロボットは、ただ入力された情報を正確に書き出しているに過ぎないと言うが、それこそカメラと連結して既に描かれた色や形に反応して次の筆致を決定するようにプログラムしたり、あるいはここで例に挙げられている額田宣彦の制作のようにキャンバス地の肌理を触覚して線を引いていくようなロボットも可能になるかもしれない。つまりそれらは画像生成AIの本質的な限界というよりも、技術的に未発達な部分に過ぎないとも言えるのだ。
しかしこの話の論点は、むしろその先にこそあるのだと思う。技術の発達で画像生成AIや手書きロボットでも時間の要素を含んだ絵が描けるようになったとする。問題は、そのとき我々は人間が描いた絵と同じようにAIが描いた絵でも「時間を経験する」ことができるか?ということなのだ。なぜならば絵画で時間を経験することは、色や形を楽しむのとは次元の異なる体験だからだ。絵画における色や形は画面上に厳然として存在するものである。その色や形には作者の思考や感情、制作の軌跡などが籠められているのかもしれない。しかしその絵を見るものが鑑賞においてその次元まで想像力を深めているかどうかは「色や形を認識した」というレベルでは判断できない。それに対して時間は色や形のようには画面上に存在しない。それは鑑賞者が「経験する」ことによって初めてそこに現れる。しかも絵画の場合、その時間は鑑賞者が経験する以前に必ず一度その絵の作者によって経験されたものである。つまり鑑賞者は絵画で時間を経験することができている時点で、畢竟その絵を描いた作者の制作の次元にまで思いを馳せていることになる。
問題は、その作者が人間ではないAIやロボットの場合でも、人間が描いた絵と同じように自身の「経験」をシンクロさせることができるのか?ということだ。つまり絵画で「時間を経験する」という鑑賞体験は、結果的に「作品」における作者の持つ意味という問題を炙り出すのである。
「作品」を成立させるもの
図書館でいろいろな辞書を調べてみたが、「作品」の語の使用例としては明治を遡るものは発見できなかった。それに対して「作者」の語は万葉集にも載っている。つまり表現物を「作った人」という意味での「作者」の概念は古代からあっても、「作品」という概念は比較的歴史の浅いものであるということなのだろう。たとえば「柿本人麻呂の和歌の作者は人麻呂である」という文章に違和感はないが、「柿本人麻呂の和歌は人麻呂の作品である」だと、若干引っ掛かりを感じる向きも出てくるのではないか。それは現代における「作品」の概念を飛鳥時代の表現に適用することから生まれる齟齬なのである。
先の石川氏による記事でも、そこで示された時間を経験する絵画の鑑賞法は、東洋画の場合は少し事情が異なるが、西洋絵画の場合たとえばルネサンス期以前の絵にも有効だろうか?という疑問はわく。絵画における完成/未完成の問いも、それが重要な意味を持ち始めるのはセザンヌ以降だろう。少なくともそれらの絵が描かれた当時に「描かれた時間」の推測や「なぜ制作はここで止められたのか」という問いを抱きながら見る鑑賞法は稀であったに違いない。しかし現代において柿本人麻呂の和歌を「人麻呂の作品」として鑑賞することが不可能ではないように、「作品」の概念がなかった時代の絵画も、その制作に思いを馳せ、その絵のなかで時間を経験することは可能であると思われる。それは作品をめぐる様々な条件が異なっていても、現代に共通する要素がそこにあるからだろう(そうでなければ美術史などというものは成立し得ない)。そしてこの場合における最大の共通要素は、それを人間が描いているということなのである。
もちろんすべての作品が「作った人」への共鳴を誘うわけではない。デュシャンの《泉》を前にして、その便器を作った職工に思いを馳せる者はいないだろう。その意味では作品に内包された作者を識別することはとても重要である。なぜならば現在我々が持つ「作品」の概念は作者の存在と切り離すことができないからだ。作者の存在が作品の意味内容にまで影響を与えるようになったのは近代以降からである。ロラン・バルトなどはそうした作品外部に存在する作者の人格が作品解釈に影響を与えることを批判し、作者の存在を無視した受け手主導の鑑賞を提唱している(*1)。確かに自律性や自立性も「作品」の重要な成立要素の一つだろう。しかし現在我々が直面している作品の作者が人間か非人間かという問題は、これまで人類が経験してこなかったものである。それは必然的に「作品」の成立における作者が持つ意味への再考を促す。
ところが、生成AIの本格的な活躍を待つまでもなく(!)、作品の成立に深く結びついた「作者」の存在は、現在まさに危機に瀕しているのである。次はそのことを見ていく。
作品人格としての「作者」の危機
作品との関係性における「作者」の危機は、両極端の二つの方向で生じている。一つは作者の存在の過剰化であり、もう一つは希薄化である。
まずは過剰化のほうから見ていこう。1985年に刊行された『作品の哲学』のなかで佐々木健一は作者と作品の関係性において、作者の行為が作者の「歴史的な人格」を表すのに対し、作品は創造の主体としての人格を表現するのだと分別している(*2)。アンドレ・ブルトンが『ナジャ』のなかでヴィクトル・ユゴーの日常生活におけるエピソードが彼の作品以上にユゴーという人間をよく表し、感じとらせるものであるとして行為と作品を対比させているのに対し、そもそもその両者が表す人格の種類が異なるのだと反論するのである。行為が示す歴史的人格が「ありのままの私」であるのに対し、作品が表す創造の主体とはその私をも超えようとするものだとする。
この定義には自分も共感するのだが、しかし現実の作品受容の場において、事はそうすんなりとは片付かないだろう。作品が示す作品人格としての作者と行為が示す現実人格としての作者はどうしても混同され、混濁していく運命にある。まして現在はこの本が書かれた当時からは想像もできないほど、この二つの人格の関係が著しく均衡を欠く事態へと到っているのだ。言うまでもなくそれはSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)による実在作者の存在の露出の過剰化である。一昔前とは比べ物にならないくらい、作者の発言や生活に注目が集まるようになった結果、作者の行為によって示される人格が作品の示す人格を打ち消してしまうのだ。その究極の結果がキャンセル・カルチャーだろう。作者のたった一つの発言が、その作者が作り上げてきた全ての作品の価値を無効化してしまうまでの威力を持つ。このバランスの著しき不均衡は、作品人格としての「作者」の成立を阻害する。
次に、それとは反対に、作者の存在の希薄化について見ていこう。それは作品の「コンテンツ」化というかたちで起こっている。デジタルメディアの隆盛により、音楽、小説、映像、イラストなど様々な表現がデジタルデバイス上で受容されるようになった。本来ならば「作品」と呼ばれていたそれらの表現は、デジタルメディアで消費される際は、その多くが「コンテンツ」と呼ばれる。「コンテンツ」とは用途に適った機能を提供する情報内容のことだ。つまり音楽ならばそれを聴いて癒されたり、気分を盛り上げたりするもの。小説ならば読むことでストーリーや文章、世界観を楽しませるもの。さらにそれらのコンテンツを提供する業者の側からすれば「アクセス数を稼いで広告収入やサブスク料金を稼ぎ出してくれるもの」のことだろう。ある意味ではそれを「作品」とは呼ばず「コンテンツ」と表現するのは理に適っており、誠実な態度であるとも言える。合目的的な存在である「コンテンツ」では、作品が示す作品人格としての作者はその関心の内には入らない。「コンテンツ」における作者名は、内容傾向を示すタグ以上の意味を持たないのだ。
これらの事態は生成AIの活躍にとって好条件となる。作者の言動によって作品が棄損されることに嫌気がさせば、リスク管理の面からもその心配のない「AI作者」の株が上がるだろう。作者の存在が問題とされない「コンテンツ」の制作にAIが長けていることは言うまでもない。その結果として、作品人格としての「作者」の存在はますます忘却されていく。それは「作品」という概念自体の消滅の危機を意味する。それに抗うためにも「作品」における作者の持つ意味について明らかにしておく必要があるのだ。次はその本題となるべき人間が作る作品が意味するものについて考えてみたい。
作品に内在する「いのち」
現時点では未だ(辛うじて)我々は人間が作った表現物とAIが作った表現物のあいだに差を認めている。両者による表現の見分けがつくという「質の差」ではなく、むしろ受け手の心理的な意味合いのことをここでは言っている。作者が人間だと思って読んでいた小説がAIによるものだと知らされたら、なにか裏切られたような気持ちになるだろう。人間が描いたと思って見ていた絵画の作者がAIだと知ったとき、目の前にある絵の見え方が変わって、そこから何かが失われたような感覚を覚えるのではないか。その感覚にこそ、人間による表現とAIによる表現の違いの本質が隠されているのだと考える。
これに似た体験が他にないかと考えてみた結果、生きた本物の花だと思っていた花が、近寄ってよく見ると実は造花だったと知ったときの感覚に似ているのではないかと気が付いた。ということは、人間による作品にはあってAIによる表現にないものは「いのち」なのだろうか? もちろん生物である生花と無機物の造花では物質的な違いがあり、人間とAIによる表現の違いとは事情が異なる。しかし(にも関わらず)そこで感じる違和感に通じるものがあるという点にこそ注目したい。
この感覚をうまく説明してくれるものがないだろうかといろいろ探しているうちに、「いのちの哲学」と言われることもある西田幾多郎の哲学に行き当たった。哲学者の池田善昭は生命科学者の福岡伸一とのダイアローグのなかで西田の「逆限定」の理論を樹木の年輪を例に説明している(*3)。「逆限定」というのは生命は環境に包まれながら、逆に環境を包み返してもいるという理論で、西田自身の言葉で言えば「環境が個物を生み、個物が環境を変じて行くという個物と環境との関係は生命と考えられるものでなければならない」(「私と汝」*4)となる。池田の年輪の例だと樹木は育ちながら周囲の環境の状況を自らの内部(年輪)に克明に記録している。これは樹木が環境によって生育されながら環境の歴史を作っていることになり、両者が互いに「包み包まれる」または「作り作られる」という関係性を持つ。池田はこのことと福岡が説く生命科学の理論との相似性も指摘している。
牽強付会のそしりを免れないかもしれないが、自分はこの構図を「作品」の成立における作品と作者の関係に当てはめてみたい。その場合「環境」に当たるのが作者で「個物」が作品となる。作品は作者によって作られ、作者の作家的文脈の上に成立する。それと同時に作品は作られることで、作者の作家的人格を作っている。作者は自分の作った作品によって規定されることで「作者」となるのだ。つまり作品が作者の「作品」として成立するとき、作者と作品は相互に「作り作られる」または「包み包まれる」という関係性を持つ。そしてこの「作り作られる」という相互作用こそが、作品に内在する「いのち」の感覚を生むのではないか。
そう考えると、たとえばスタイルの固定してしまった作家が量産する似たり寄ったりの作品が生気を失い魅力が感じられなくなってしまうことや、義務的に作られた再制作の作品が「作品」ではなく「資料」に見えてしまうことの理由が説明できる。つまりそれらの制作においては、作者と作品の相互作用が働いていないのである。作品を作ることにおいて作者はなにも変化していない。故にそれらの作品は「死んでいる」ように見えるのだ。
この場合の「環境」を批評、シーン、制度、歴史といった作品を成立させる作者以外の要素に当てはめてみることも可能かもしれない。しかし相互に限定し合う作用の強さにおいては、作品と作者との繋がりには遥か及ばない。「限定」のベクトルは必ず双方向でなければならないのである。
そしてなによりも、この相互作用はAIにはできないものなのだ。生成AIが自身が生成した物から学習し自身を変化させるようにして、疑似的に相互作用の構図を作り出すことは可能かもしれない。しかしそれでは駄目なのだ。なぜならばここで作者と作品のあいだで起こっている相互作用は、互いの存在を賭けたものだからである。その存在の重みこそが「いのち」の感覚を生み出すのだ。そしてAIはこの存在の重みだけは絶対に持ち得ないのである。故に生成AIは「コンテンツ」は生み出せても「作品」を作ることはできないのだ。
「作品」の消滅した世界
観賞者が作品に「いのち」を見出すとき、そこで起こっていることはなにか。それは他者の発見ではないのか。同じ「この世界」に生きる私以外の他者の発見である。それは情緒的な共感ではない。存在への共鳴である。その自分以外の「いのち」の発見によって、私は自分が生きる「この世界」の拡がりを知るのだ。
ではこの「作品」という概念が消滅してしまった世界とは、どんな場所なのか? 思うに、それは我々の身の周りにある植物がすべて造花になってしまったような世界ではないのか。想像するだけで身の毛もよだつ気がするが、案外その世界に住んでいる住人にとっては普通のことなのかもしれない。「生きた花」という概念を持たない彼らにとって「花」とは、空間を彩り人の目を楽しませるものでしかない。その用途のためには生花よりも手入れの簡単な造花のほうがはるかに理に適っている。つまり「コスパがいい」のだ。色鮮やかな造花で彩られた世界に生きる住人たちは、それなりに華やかで楽しい生活を送っているのかもしれない。そこは周囲から「いのち」の気配の消えた閉塞した世界なのだが、彼らはそれに気付くことがないのである。
それはそれでゾッとするようなディストピアだろう。しかし「作品」の概念が希薄になり大量のコンテンツにまみれて暮らす我々は、ひょっとすると既にもうそんな世界へと足を踏み入れているのかもしれないのだ。
註
*1 ロラン・バルト「作者の死」「作品からテキストへ」(花輪光訳『物語の構造分析』 みすず書房 1979年)
*2 佐々木健一『作品の哲学』東京大学出版 1985年
*3 池田善昭、福岡伸一『福岡伸一、西田哲学を読む―生命をめぐる思索の旅』小学館新書 2020年
*4 小林敏明編『近代日本思想選 西田幾多郎』ちくま学芸文庫 2020年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
