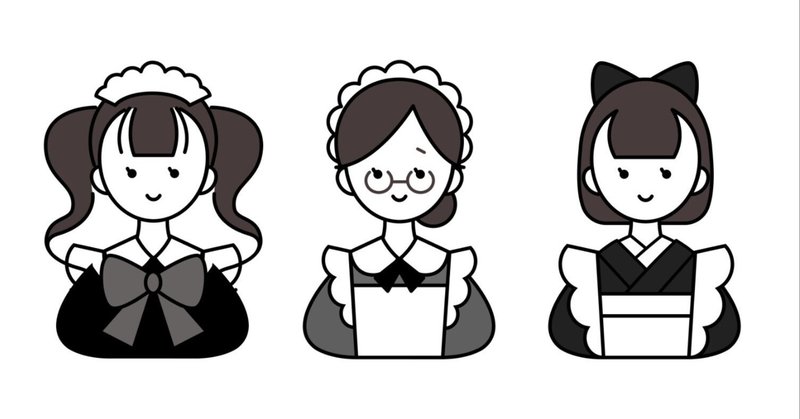
連続小説 カフェー・宝来屋(福が来た)第二話
第二話「患ったら一人前」
翌日から客を取り出した福だが何せ十五の小娘だ。痩せ干そっている上に、何処を触っても感じないから客も寄り付かないと女将は心配していた。だが、幼い顔で愛想が良いからか文士と呼ばれる先生方が代わる代わる通ってくる。なんと先生方は賭けをしていて誰が最初に福を感じさすかと競っているらしい。
そして一ヶ月がたった頃、数人で始めた福を感じさせる賭けは、一人抜け、二人抜けして今では二人の一騎討ちとなっておりました。一人は若き文壇の貴公子。もう一人は重鎮といわれる大御所。ある日、福からよがり声を出させたのは貴公子の方でございました。貴公子は高らかに笑い福の常連になりました。
女将は「よしよし福、良くやった。大御所先生には悪いけど老い先短い人はねぇ。ところでお前、少しは感じる様になったのかい」と福に尋ねた。福は顔を赤らめながら「なんか変な感じがしだしたと思ったら急にあっちこっち感じて来ちゃって」と言った。女将は頷き「それで良いんだよ」とニンマリ笑った。
二つ年上の紅葉は福の面倒を良くみている。女将に言われた訳でもないのに姉の様に世話をやいている。「福ちゃん、馬(生理)は有るのかい。そうかい、軽いのかい。良かったね。でも出る物の多い時は客に言っとくんだよ。そういうのが嫌いな奴もいるからね」ある日、福は紅葉の手の赤い斑点に気がついた。
紅葉の赤い斑点は日に日に大きくなってきた。福が自分の手を見つめているのに気がついた紅葉は「あぁこれ、楊梅(ようばい)さ。福ちゃんは来たばかりだから知らないだろうが、この商売をやってるとこれになるのが当たり前なのさ。痛くも痒くもないし直ぐ消えちまうよ。触ってもうつらないから安心しな」
そう言われても気味が悪く、福は紅葉が触った物には直接触らないでいました。紅葉の手の斑点は梅毒の症状です。この当時、サンバルサンという薬があって感染後早い段階で投薬すれば治るのですが、商売柄また感染するのです。吉原遊郭の女性の寿命が22才前後なのは性病と肺結核と自殺が原因だそうです。
ある日、福は唇の裏に赤い斑点を見つけた。夜に一つだったものが朝には六つに増えていて慌てて女将の所に行った。「ああ、罹っちまったねぇ」と言って医者に予約の電話を掛けた。「今から出ますので、一時間少々で着きます。はい、よろしくお願いします」と電話を切って「よし、出掛けるよ」と言った。
停留所からバスに乗り、揺られながら福は外の景色を眺めていた。震災から一年程がたち瓦礫の山となっていた東京は忽ち近代建築の展示場かと思うほど綺麗な洋式の建物が建ちだした。車内では白襟嬢と呼ばれる女の車掌さんがキリッとした姿勢で乗車賃の切符を切っている。こんな仕事もあるんだと思った。
バスを降りてから歩きながら女将と色々喋った。こんなに話をしたことが無かったから怖いと思ってた女将が優しい人だと分かった。それだけでも病気に罹ったかいはあった。「ここだよ」と言われたのは雑司が谷にある産婦人科の病院だった。「ご免下さい」女将が声をかけると待合室から女の子が出てきた。
「妙さん、ようお越し下さいました。どうぞお上がりください」と女の子は流暢に喋った。「ありがとう。いつも無理いって申し訳ないですね」と女将も丁寧に話してる。お医者の子は小さくても、そこいらのガキとは違うんだと福は感心した。「それが先ほど急患が有りましてお父様は出掛けてしまいました」
一通り用意が終わったらしく女の子は「お父様の代わりに小児科の医師がお注射を致します。呼んで参りますのでお待ちください」と言って部屋を出ていった。福は女将に「あの子が注射をするのかと思った」というと女将は笑って「あの子ならそれ位するだろうね。でも、お医者様でないと注射は出来ないよ」
一通り用意が終わったらしく女の子は「お父様の代わりに小児科の医師がお注射を致します。呼んで参りますのでお待ちください」と言って部屋を出ていった。福は女将に「あの子が注射をするのかと思った」というと女将は笑って「あの子ならそれ位するだろうね。でも、お医者様でないと注射は出来ないよ」
直ぐに女の子はもどり、その後ろから白衣を着た初老の男が入ってきた。「お待たせしました、こちらの先生が診察をします」と女の子は言った。「こんにちは、院長の代わりに私が拝見します。あなたが中野福さんですね、上の服を全部脱いでこちらへ掛けてください」と診察机の横の椅子を福に差し出した。
医師は胸と背中に聴診器を当てて二三問診をしてから左腕に注射を打った。福は初めての注射に泣き出しそうな顔で耐えた。女将と医院を出て振り返ると女の子が手を振っていた。福は笑顔で手を振り返した。「ちょっと寄り道するよ」女将はそう言って来た道とは違う方に歩きだした。福は後をついていった。
暫く歩いて着いたのは法明寺というお寺だった。本堂にお参りをして横手にある石像の前に行った。女将は買い求めてあった花を供えて一心に拝んだ。福は参道にある茶店の団子が食べたいと言ったが女将は駄目だと言って喫茶店でパフェを奢ってくれた。「あれは子授けの団子さ。あたしらには毒ってもんさ」
それから二三日経って、ご隠居と呼ばれる常連さんが客についた。あっちの方は駄目になっているのだが触ったり舐めたりして、こっちの反応を見て楽しんでいる。結構上手で何度もいった。するとご隠居が「この前、女将と医者へ行ったろ」と聞く。そうだと言うと「じゃあ、帰りは寺に寄ったな」と言った。
「あの雑司が谷の医者は堕ろすのが上手でな、腹ん中を痛めずに子を掻き落とすのさ。ヤブじゃあ死んじまうからな。そして寺は鬼子母神を祭っていて堕ろすした子の供養をしているんだ」ご隠居はそう言いながら福の中に入れた指を動かす。福は、ご隠居の役立たずを咥え喘ぎながらあの石像を思い浮かべた。
福は子が出来ることは知っていた。ここで生きていく為に。借金を返して堅気に戻るために必死になるあまり、そんなことを終ぞ考えてはいなかった。男と寝ること、それは子が出来ることなのだ。そして出来た子は堕ろさねばならない。女将があの医者と寺に連れて行ったのはそれに気づけということなのか。
女将に鬼子母神にお参りをしたいと言ったらあたしと行こうと言った。あの時は知らないから手も合わせずにいたと言ったら「あんたにはいないからね。必要無いかと思ったんだよ」と言った。改めて花を供えて手を合わせて仰ぎ見たら、なんだか女将に似ている様な気がした。子が出来ませんようにと願った。
「福ちゃん、楊梅に罹っちまったって」女将の所へ紅葉が来て嬉しそうにそう言った。「なにを笑ってるんだい。あんた達仲が良いんだろ。少しは心配しておやり」女将は紅葉を窘めた。紅葉は膨れっ面になり「どのみち罹っちまうんだから早い方が良いんですよ。『患ったら一人前』って言うじゃないですか」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
