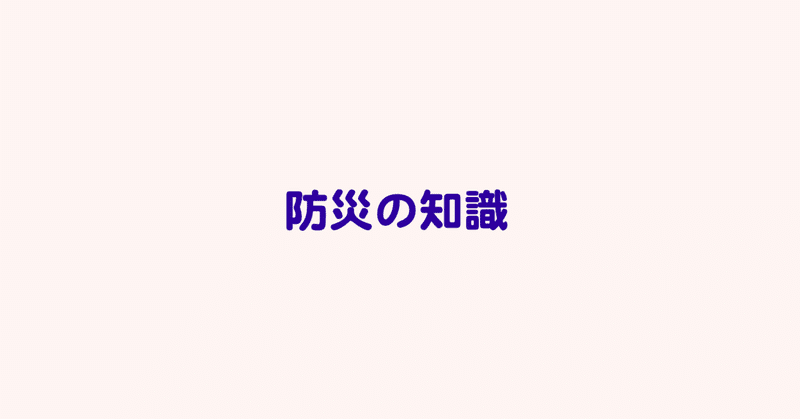
火災について
震災における火災の特徴
阪神大震災と阪神淡路大震災の火災について比較した表がある。阪神淡路大震災では、関東大震災と比較して、出火率はほぼ等しく、 延焼面積は1/50、延焼速度は1/10となっている。
$$
\begin{array}{ l c c}
& 関東大震災(1923) & 阪神淡路大震災(1995) \\ \hline
比較対象地域 & 東京市 & 阪神7都市^* \\ \hline
面積 & 約600\, \mathrm{km^2} & 約600\,\mathrm{km^2} \\ \hline
人口 & 約250万人 & 約280万人 \\ \hline
全半壊数 & 約3万棟 & 約20万棟 \\ \hline
出火件数 & 約100件 & 約200件 \\ \hline
焼失面積 & 約3,800\, \mathrm{ha} & 約70\, \mathrm{ha} \\ \hline
延焼速度 & 約200〜300\, \mathrm{m/ha} & 約20〜40\, \mathrm{m/ha} \\ \hline
\end{array}
\\
\scriptsize{(^*尼崎市から神戸市の7市のうち六甲山より被害の少なかった北の地域を除く)}
$$
関東大震災において地震の発生は、ちょうど昼時でこんろなどを使用していたこと、木造家屋が多かったため火災が多かったといわれる。阪神淡路大震災は早朝5:46に地震が発生したにもかかわらず、同時多発的に出火している。停電復旧後にガスや家財に着火した通電火災が原因といわれる。同時多発的に出火すると通常の消防力では対応できなくなる。
防災・減災対策による被害軽減効果
電気による出火の低減策として感震ブレーカーの設置を8.3%から25%にし、付近の住民による初期消化率を36.6%から60%にすると、死者数が約7割減少する。
感震ブレーカーの設置率を50%にし、初期消化率を90%にできれば、死者数がさらに6割減少する。
復電による出火の抑制、初期消化が被害軽減には重要となる。

不燃化について
災害に強い都市構造を作るために、道路、河川、鉄道、公園や大家建築物により延焼遮断帯を形成することが重要となる。延焼遮断帯は、震災時においては避難経路、救援活動時の輸送経路でもあるため、道路の拡幅整備や沿道建築物の耐震化が必要となる。延焼遮断帯の内部であっても、木造住宅密集地域などにおいては、延焼のリスクが高いため、不燃領域を広げる整備が必要となる。万一、延焼による大規模火災発生時には広域避難場所への避難が必要となる。避難場所までのルートの確保が重要となる。広域避難場所は火災の輻射熱から身体を守るため10ha以上が必要だとされている。
引用文献
阪神・淡路大震災における 阪神・淡路大震災における 火災からの教訓
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/senmon/shutochokkajishinsenmon/7/pdf/shiryou1.pdf
首都直下地震等による東京の被害想定(令和4年5月25日公表)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1000902/1021571.html
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
