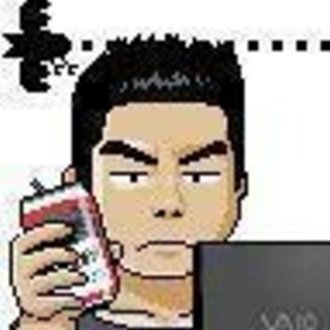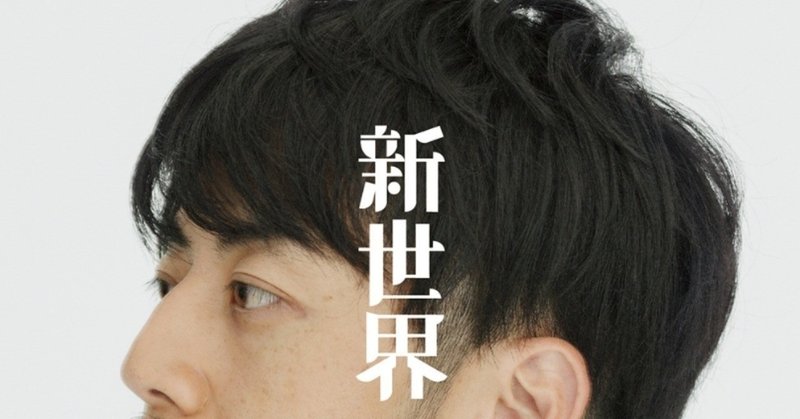
キミに守りたいものがあるなら、「お金」の話から逃げるな。
ようこそ「新世界」の世界へ。
この記事はお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんの著書「新世界」をその章立てごとに読み解くことで、より「新世界」という作品をあんたに楽しんでもらうための記事だ。
今回は3回目。「キミに守りたいものがあるなら、「お金」の話から逃げるな。」の章を読み解いていこう。
目次はこちらね。
えんとつ町のプペルをサイコーにする方法
「えんとつ町のプペル」ってあんたは知っているかい?
まあ、この「新世界」を読んでいるくらいのあんたなら知っているかもしれないな。
「えんとつ町のプペル」は西野亮廣さんが様々な工夫のもと作り上げた絵本だ。
まあ、この絵を見てあんたはどう思う?
「ほほう、キングコング西野すげぇ書き込んだ絵を書くんだな」かい?
そこに西野亮廣さんの工夫があらわれている。
この絵本。実は西野亮廣さん一人で作ってはいない。
っていうか、絵を伴う書籍の中で一人で作成されることが普通の世界って絵本くらいしか無いんだよな。
なに?絵本がどう作られるんだって?
絵本は、一般的には一人で描く。
お話のネタを集め、お話を形にして、そのお話のテーマを伝わりやすいページ割を考え、そのページ割にあった絵を描き、文字の配置を考え、めくったときの触覚を想定しながら紙を決めて、誰に届けたいかを考えながら表紙のレイアウトを決める。
それらの作業を一人でやるわけだ。
絵本ってのは、書籍の中でも特殊なもので、売れる絵本は普通の書籍に比べて長く売れる傾向にある。
コレには理由があって、絵本ってやつは、例外を除けばほとんどのケースで親が選ぶ。これがどういうことを意味するのか?
普通の書籍であれば、「この本は面白そうだ」という読む人の判断で購入につながる。ところが、絵本の場合は読む人ではなく、読んでほしい人が買うわけだ。
そうなると、読んでほしい人は何を基準に買うのか?
子供の頃に買ってもらって内容を知っているものを買うわけだ。いまだにぐりとぐらが売れ続けているからくりがここにある。
だが、ここに一つの落とし穴がある。
売れ線の絵本はずっと売れ続ける。
下手すれば作者が亡くなってからも売れ続ける。出版社にとっては没後50年で著作権が切れるから、そこから先は売れただけ利益に直結する。
そうなると、出版社としては、旨味が強いからより販促をかけてその本を売り続ける。
そして、絵本全体の売上は横ばい傾向だ。ここ数年はちょっと盛り返しているけどね。

出展:http://www.garbagenews.net/archives/2101334.html
こんな状況で同じ絵本だけが売れ続けていればどうなるか?
当然、新しい絵本を売り出しても売れるかどうかわからないから、部数を出すことが出来ない。
絵本作家には印税の形で報酬が支払われるが、部数が出ないものだから、当然収入が少ない。
収入が少ないから、人を雇ってコンテンツを作り込むなんてことは出来ない。だから一人で制作をするしか無いわけだ。
でもそこで、西野亮廣さんは考えた。
それぞれのプロフェッショナルが集まって、映画のように分業制で作ってしまえば、世界の誰も見たことがない絵本が作れるのでは?
出展:新世界
そこから「えんとつ町のプペル」という作品は始まったんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?