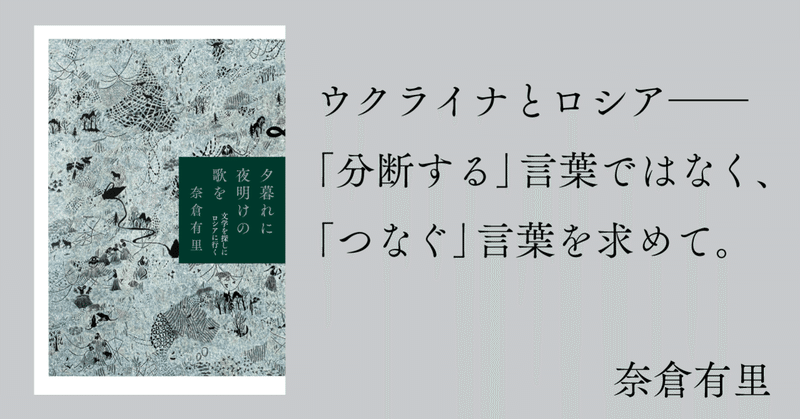
ウクライナとロシア──「分断する」言葉ではなく、「つなぐ」言葉を求めて。 奈倉有里
2021年10月にイースト・プレスから刊行された奈倉有里『夕暮れに夜明けの歌を』は、高校卒業後、2002年から2008年の間、単身ロシアに渡り、日本人として初めてロシア国立ゴーリキー文学大学を卒業した筆者が、テロ・貧富・宗教により分断が進み、状況が激変していくロシアを活写したエッセイです。本書の中には、現在のロシアによるウクライナ侵略の背景にあった出来事が、ミハイル・シーシキン(ウクライナ人の母とロシア人の父の間に生まれモスクワで育った作家。1961年~)と、アンドレイ・クルコフ(ウクライナの作家。1961年~)らの言葉とともに描かれています。筆者の許可を得て、重要な「27章 言葉と断絶」と「29章 灰色にもさまざまな色がある」を全文公開します。(編集部)
27章 言葉と断絶
人と人を分断するような言葉には注意しなさい。
──レフ・トルストイ
大学時代の私やマーシャに「ロシアとウクライナが戦争をする」などと言っても、私たちは笑い飛ばしていただろう。ウクライナ東部に祖父母のいる友人マルーシャもいたし、ウクライナ人の学生もいた。そもそもロシアにとってウクライナやベラルーシは「外国」というより「家族」といった感じで、あえていうなら、たとえばベラルーシならオーリャの故郷をはじめ多くの地域で日常的にロシア語を話していたのに対し、ウクライナではどんどんウクライナ語教育が進められていたから、それなりに独自の発展をしていくのだろうという感覚はあったが、戦争が起こるなどとは到底思えなかった。
しかし最終学年のころには、ウクライナとロシアの不穏な溝を感じる出来事が起こるようになっていた。そこで問題になるのはやはり言語だった。あるとき、文学史の教授が講義でウクライナ出身の作家を何人か挙げ、「ゴーゴリはウクライナ語もできたのに、結局はロシア語で書くことに落ち着くわけで、やはりウクライナ語よりロシア語のほうが優れているというか、文学的で、文学作品に適しているんでしょうね。ほかのウクライナ出身の作家も多くがロシア語で書くようになっていますし」という、ありえない発言をした。両言語の歴史をめぐる考察もなにも一切抜きにして(いや、たとえそれがあったとしても)言語を比較してどちらかを優れているだとか文学的だとかいう主張には、むろん根拠も学術性も皆無である。講義で教授が堂々とそういう発言ができるというのは、社会にそれを許すだけの風潮が広まってきていたということでもある。ただこのときは、普段はおとなしいマルーシャが即座に「じゃあシェフチェンコのウクライナ語作品はどう説明するんですか!」と大声で反論したのがせめてもの救いだった。だがそれにしても、なぜ教授があのような発言をするに至ったのだろう。
ミハイル・シーシキンもまた、ウクライナ人の母とロシア人の父のあいだに生まれモスクワで育った作家であり、一九九〇年代以降はスイスに暮らしている。ウクライナ、ロシア、ヨーロッパをそれぞれ身近に知るシーシキンは、ウクライナ問題が勃発してすぐにその経緯を鋭く考察し、現状を批判した──
ロシアとウクライナは、ほんとうの意味での兄弟だ。私自身、母はウクライナ人、父はロシア人の家に生まれているし、似たような家庭はロシアにもウクライナにも数限りなく存在する。その二国を争わせ、分かつことなど、本来できるはずがない。ゴーゴリを──共に誇る偉大な作家を、どちらかの国に属する作家と定めるのだろうか。共に経験してきた恐ろしい歴史を──恥を、苦しみを、分断するというのだろうか。〔…〕
プーチン政権下のロシア。連日ニュース番組で流されるのは、ウクライナの反戦運動を凶悪な暴動のように捉えたプロパガンダ的な視点の特集ばかりだ。しかもそこへ、昔から小話に登場するような、ウクライナ人を小馬鹿にしたようなイメージが加わるのだからたちが悪い。つまり、狡くて欲張りで少し頭が足りないウクライナ人、豚脂のためならヨーロッパにだって悪魔にだって魂を売ってしまうウクライナ人……といったイメージだ。国営テレビが先頭に立ってそういった番組を放送しているのだから恐ろしくなる。〔…〕
ウクライナ東部やクリミアの住民の混乱も無理もない。人々は「ウクライナ化」政策に対する戸惑いを隠せなかった〔東部にはロシア語話者が多い〕。考えてもみてほしい、スイスで同じようなことが起こったらどうなるだろう──ベルンの連邦議事堂において、多数派のドイツ語系議員によって「ロマンディ地方〔スイス西部のフランス語圏〕におけるフランス語の使用を禁ずる」という法律が採択されたとしたら?
その困難な状況において一般の人々をさらに混乱させたのは、ソチオリンピックを悪用した偽りの「勝者」、つまり愛国意識を煽り「国家は国民を守らなければならない」と声高に叫ぶ者たちだった。いかなるイデオロギーのもとにおいても──一九世紀の正教であれ、共産主義であれ、現代に復活した正教であれ、体制は常に愛国心を利用して国民を操ってきた。それは今でも変わらない。この数週間というもの、ロシアのテレビではひっきりなしに、「祖国を守れ」と訴えている。「クリミアおよびウクライナ東部のロシア系住民を、ウクライナの暴徒から守れ」と。〔…〕
長い歴史のなかで崇められてきた「愛国心」という聖者は、人間の権利も個人の尊重も、粉々に嚙み砕いて飲み込んでしまった。
幼なじみがアフガニスタンで戦死したとき──あのときも彼らは、「戦地で祖国を守っている」ことになっていた──私は幾度か彼の両親のもとを訪ねた。彼の母親は、「祖国ってなに?ねえ、祖国ってなんなの?」と繰り返し問い続けていた。その問いに、返せる言葉はなかった。
チェチェンで戦争がはじまったときもそうだった。あるドキュメンタリーで見た、まだあどけない少年が「僕はここで、祖国を守ってるんだ」と語っていた姿が目に焼きついている。
そして今、ロシア人の少年とウクライナ人の少年に求められているのが、互いに対立し「祖国を守る」ことだという。〔…〕
二〇〇八年にも政府はグルジアとの間に戦争を起こし、それまで培ってきた友好関係をいとも簡単に切り捨てた。あの戦争が生んだ溝は決して浅くない。同じことが今、ウクライナとの間に繰り返されようとしている。〔…〕
気の遠くなるような人類の歴史のなかで、いったい、「国を愛せ」という呼びかけの末に、どれほどの命が犠牲になっただろう。そして今、ロシア人が、ウクライナ人が、同じ犠牲のもとに立たされようとしている。兄弟は共にその苦しみを味わい、いつの日か共に未来を取り戻そうとするだろう。(ミハイル・シーシキン『ウクライナとロシアの未来』拙訳、集英社『すばる』二〇一四年六月号より抜粋)
政府が意図的に言語を分断させるという行為──それは、両言語の話者を故意に対立させる暴挙にひとしい。加えてロシアでは、それまでにもウクライナに対する「弟」的な見方が根強くあった。兄弟とはいえあくまでも「兄」はロシアで、ウクライナは「弟」である(ベラルーシに対しても似たような見方がある)。楽天家で陽気なウクライナという弟は、愛嬌はあるが欲張りで間抜けで少し頭が足りないとか、お兄ちゃんほどは立派になれないとか、そういったイメージにつなげられていく──ロシアの国営テレビが先頭をきって、そういった番組を放送するのである。
しかしこういった現象は、突如として現れるわけではない。二〇〇八年の講義で文学史の教授が「ロシア語のほうがウクライナ語より文学的で優れている」と言ってしまったあの瞬間を、私は二〇一四年以降に幾度も苦々しい気持ちで思い返した。仮にも言葉を教える大学である。ある大教室の壁には、レフ・トルストイの言葉が掲げられていた──「言葉は偉大だ。なぜなら言葉は人と人をつなぐこともできれば、人と人を分断することもできるからだ。言葉は愛のためにも使え、敵意と憎しみのためにも使えるからだ。人と人を分断するような言葉には注意しなさい」。その教えは私たちにとって指標であり規範であった。現代文学のゼミで差別主義的な思想を含む小説を扱ったときに、発表をした学生がトルストイのこの言葉を引用し、「これは隣の教室に書かれているトルストイの言葉で言うなら『分断』を招く作品ではないのか」と批判していたのを覚えている。それなのに、教授が先陣を切ってあんなことを言うなんて。
マルーシャやシーシキンや、そのほか数え切れないほどのウクライナとロシアの両方に出自を持った人々にとって、両国の紛争やクリミア併合は人と人どころではない、自らの身体を引き裂かれるかのような痛みだった。それだけではない。ロシアでもウクライナでも、それまで親しかった人々が、「クリミアはロシアのものか、ウクライナのものか」というたったひとつの争点により、まっぷたつに分断されていった。
信教の問題にせよ紛争にせよ、国家は内面の自由という概念が存在しないかのように強引に市民を巻き込み、白か黒かの選択を迫る──そのことによってさらなる分断が生まれるのをわかっていながら。けれどもクリミアの歴史を考えるなら、クリミアほど「どこのものでもない」場所はない。そんなことは、ずっと昔から言われていたのに。少なくとも四〇年前にアクショーノフが『クリミア島』を書いたころから。
*1…一九六一〜。モスクワ生まれの作家。邦訳は『手紙』拙訳、新潮社、二〇一二。
29章 灰色にもさまざまな色がある
どこか遠くで、大砲が轟いた。
──『灰色のミツバチ』アンドレイ・クルコフ
二〇一四年やそれ以降しばらくは日本のニュースでもウクライナについての報道を多くしていたから、当時のことを覚えている人もいるだろう。しかし次第に報道は減り、ウクライナの現状がどうなっているのかを詳しく知る人はあまりいないかもしれない。どの地域についてでもそうだが、とりわけ普段はあまり注目されないような国や地域についてのニュースというのは、いっときさかんに報道されても、激しい衝突がなくなるとぱたりと情報が途絶えてしまう。しかし当然ながら現地では生活が続いており、紛争や衝突は突然なくなっているわけではない。むしろ大きな出来事のあと、世界に注目されなくなったときにこそ、新たな不幸が口をあけていることも多い。そこにはひとりひとりの暮らしを詳細に知らなければ伝えようのない真実というものがあり、それを描きとる可能性を持つのが文学でもある。
アンドレイ・クルコフはウクライナ育ちの作家で、これまでもウクライナを舞台にした作品を描いてきたが、二〇一八年に発表された『灰色のミツバチ』という作品は、世界から急速に忘れ去られていったある村を舞台とした長編だ。
主人公の養蜂家セルゲイ・セルゲーィチはウクライナ東部に暮らしている。ドンバスでの紛争が続くなか、いわゆる「グレーゾーン」に留まり続ける数少ない住人である。住み慣れたスタログラドフカ村は、ウクライナ側も親ロシア派側も統括できずにいる地域だ。激戦区ではないにせよ、すでに多くの住民が村をあとにしている。いまだに村に留まっているのは彼と、幼なじみのけんか友達パーシカだけだ。セルゲイの妻は紛争がはじまるより前に娘を連れて出ていってしまい、彼はミツバチとともに村に取り残されていた。そうして、グレーゾーンで暮らす数年の年月が過ぎた。過ぎゆく日々はいつも似通っていて、遠く響く銃声さえもがスタログラドフカ村の静寂の一部になっていた。
セルゲイは紛争の対立には関与したくない。名前をもじって「灰色」と呼ばれている彼は、その名のとおり白にも黒にもなりたくないのだ。しかしときに世の中は「灰色」のままでいることを拒む。幼なじみのパーシカとの関係は、社会が平穏なうちはほほえましい「けんか友達」だった。しかしひとたび紛争の対立が介入すれば、二人のあいだに修復し難い亀裂が生まれる。
村の電気は三年前から止まっており、セルゲイは薪ストーブで暖をとり、湯を沸かして生活している。新鮮な食料や卵はなかなか手に入らない。あるときからウクライナの兵士がセルゲイのところにやってきて、食料をくれたり、携帯電話を充電してきてくれたりするようになる。だがその後、パーシカがウォッカを手土産にロシア陣営の兵士を連れてセルゲイの家に遊びにきたのをきっかけに、セルゲイとパーシカは大喧嘩をしてしまう。それまでぼんやりとしていた紛争の対立が、より身近なものになっていく。
セルゲイは暖かい季節を選んで村を去る決意をする。車の後方にミツバチの巣を積んだ荷台をとりつけて牽引し、道中、検問所を通るたびに、「ミツバチが銃撃戦を怖がるから、安全な場所で休ませる」と説明しながら南を目指す。もしあの村でミツバチが銃の音を怖がって逃げてしまっても、ミツバチは五キロ以上の距離を飛べない。ミツバチを紛争から逃れさせ、アカシアの花咲く地へと連れていかなければならないのだ。紛争地帯を抜けたセルゲイは、青年のころに戻ったような自由と清々しさを感じた。
主人公は旅をする──ザポロージエのちいさな村、そしてクリミアへ。テントを張り寝袋で寝て、身体が痛むときはミツバチの巣箱の上に寝て回復する(なんと実際にこういう健康法があるらしい)。セルゲイの世界はミツバチを中心に回っているが、その心は閉ざされてはいない。ミツバチとともに飛び回りながら、ロシア人ともウクライナ人ともクリミアタタールの人々とも軽々と交流し、多くの人から好感を持たれる。ところが、どこにでも「灰色」に無関心ではいられない人がいる。そういった人々にとってセルゲイは常に余所者であり、彼らに警戒されたり疎まれたりするのを敏感に察知するセルゲイは、どこへ行っても結局は居場所を見つけられずに、ついには故郷のグレーゾーンへと帰っていく。
いつもミツバチのことばかり考えている主人公はほほえましい人柄だが、この話の内容自体は作者クルコフが実際にグレーゾーンへと何度も足を運び、取材をして書いたもので、作中には現実のウクライナ東部の問題を鋭く描き出す描写も多い。
これは、私にとっても身近な話だった。大学の友人マルーシャの祖父母もウクライナ東部に住んでいる。激戦区からは少し離れていたが、紛争が激しさを増していた二〇一四年からはモスクワ郊外にあるマルーシャの実家に疎開してきていた。ところがしばらくして以前よりは危険ではなくなると、二人は住み慣れたウクライナへと帰っていった。その後もときには銃声が響くけれども、そんなことも日常となっていったという。
かろうじて自分が即座に標的になるわけではないとはいえ、どれほどかかわるまいとしてもすぐ近くで争いが起きている限り危険なことに間違いはない地域に、彼らはどうして帰っていくのか。しかし紛争は、紛争地域だけで起きているわけではない。モスクワにいても、ただでさえそこに暮らす人々は「白か黒か」を迫られ、分断を余儀なくされている。そこへグレーゾーンの人々がくれば、紛争に対しなにかしらの立場を主張する人にとっては容易に争いの種になりかねない。『灰色のミツバチ』の主人公セルゲイがどこにいてもいたたまれなくなったのも、やはりそのためだった。その苦しさが、果たしてどのくらい伝わるだろうか──出身地を理由に、自分という存在が、つい最近まで親しかった人々の争いを誘発させてしまうつらさが。
二〇一九年、ドンバスのローカルニュースで一枚の写真が紹介されていた。激戦区から少し離れた居住区の外壁に、大きくこんな文字が書かれている──「ここには人が住んでいます」。文字はたったそれだけだが、そこには「だからどうかここで射撃や強奪や破壊行為をしないでください」という切実なメッセージが込められている。現地の集落の多くはいまだに「グレーゾーン」のままだ。インフラが崩壊し、地方自治体も機能せず、電気も病院もない地域だが、そこを離れられない人々がいる。高齢者や体の不自由な人も多い。
世界のニュースが報じなくなった灰色の世界で、ただ日々を生きようとする人々。その灰色はしかし、単純なひとつの色ではない。白か黒かを迫らずにそれぞれの灰色に目を凝らすことなくしては、対立は終わらないのだろう。
*2…一九六一〜。ペテルブルグ近郊に生まれるが、幼少期にウクライナに移住。邦訳は『ペンギンの憂鬱』沼野恭子訳、二〇〇四年、『大統領の最後の恋』前田和泉訳、二〇〇六年。ともに新潮社。
奈倉有里(なぐら・ゆり)
1982年東京生まれ。ロシア国立ゴーリキー文学大学卒業。東京大学大学院博士課程満期退学。博士(文学)。著書に『夕暮れに夜明けの歌を』(イースト・プレス)、『アレクサンドル・ブローク 詩学と生涯』(未知谷)、訳書にミハイル・シーシキン『手紙』、リュドミラ・ウリツカヤ『陽気なお葬式』(以上新潮クレスト・ブックス)、ボリス・アクーニン『トルコ捨駒スパイ事件』(岩波書店)、サーシャ・フィリペンコ『理不尽ゲーム』『赤い十字』(集英社)など。
奈倉有里さん翻訳の他の記事はこちら▼
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
