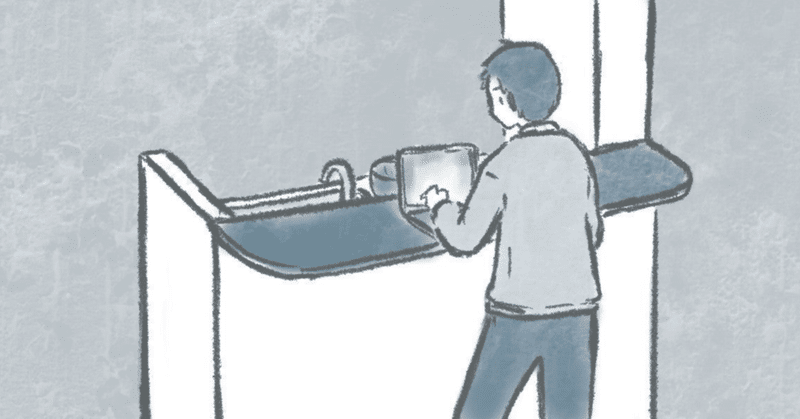
知らないうちにNGの叱り方をしていないか?~誰も注意してくれない~
書店に行くと、今もなお、ほめ方、叱り方に関する本が多く並んでいます。院生や若手の先生の話を聞くと、この手の本はかなり需要があるということです。子どもをどのようにほめたらいいか、叱ったらいいかだけではなく、ほめられない、叱れないことで悩んでいる先生方も多いと聞きます。
ほめる・叱るについては、様々な情報が出尽くしている感がありますが、、NGであるものの、学校現場において、まだまだ見受けられ、なかなか改善が図られていない「叱る」について考えてみました。
【叱る依存が止まらない(村中直人著)】にもありますが、日本人は「叱る」行為を過大評価する傾向があります。叱ることで「期待した方向に向かう、よりよい変容を促す」と思いがちですが、深く考えず叱るだけであれば、それほど効果はありません。
それどころか、叱られた子どもの人生を左右するマイナスの影響を与えることがあります。学校において教師という影響力のある存在から「叱られ」、学校に行けなくなった子ども、やる気をそがれた子どもたちも、深く傷ついた子どももたくさん見てきました。
私は、叱ること自体を否定しませんが、以下の叱り方はNGと考えています。しかし、学校ではよく見受けられるものです。時には「自分はそのような叱り方をしていないか」と改めて振り返ることが大切です。
①人格否定
先日、教師の体罰のニュースが報道されていました。複数のメディアで詳細をみてみますと、一連の指導?の中で教師が子どもに「お前なんかいらん」という言葉を発したようです。
このような叱り方は人格否定にあたります。
存在も含め人格そのものを否定する叱り方になります。影響力のある人に人格否定をされると、子どもたちはもう何もできません。中には、自分の存在の必要性を考える子どもも出てきます。
「何もいいところないね。」
「何のために生きているの?」
「何回言ってもできないね。」
「あなたの存在意義は?」
「何をしてもできないね。」なども人格否定につながる言葉です。
➁見捨てる
子どもにとって、頼みの綱、影響力ある存在から、見捨てられるような言葉をもらうと、非常に厳しいです。
例えば、
「もう何もしなくていいよ。」
「あなたのような人はもうクラスにはいりません。」
「クラスから出ていきなさい。」
「どうせろくな人間にならない。」
「先生はあなたのために、もう何もしません。」
これらは子どもの可能性を否定する言葉であり、教師との信頼関係を根底から崩すものです。子どもが先生から「見捨てられたと思われたら致命傷」になることが多く。このような言葉で叱っても、子どもたちではなく、教師にとってもプラスになることは何もありません。
➂ついでに「あれこれ」
忘れ物をしたことについて叱っている最中、それ以外のことも持ち出し、あれこれ叱ってしまうこともNGです。
叱ると気分が高ぶるといいます。叱る依存がはじまり、過去の様々な過ちを引き合いに出して叱る先生がいますがよくないです。子どもからは反発心が生まれやすくにり、教師の話を聞く耳をもたなくなります。
また、そのような叱り方をしても、ほとんどの場合、子どもの頭の中は思考停止状態です。「早く話が終わらないかな」とよそ見をすることもあるでしょう。「よそ見」をしたことを叱るというサイクルになれば、負のループに陥ることになります。
学校現場で出ると、叱るという行為について「指導」される機会は、そう多くはありません。多忙な現場では、不適切な叱り方をしている同僚を目にしても、スルーしてしまうことさえあります。しかし、以上の叱り方は、子どもを傷つけ、教師を疲弊させるだけで何も生みません。
だからこそ、手遅れになる前に、NGの叱り方になってないか、定期的に確認する必要があります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
