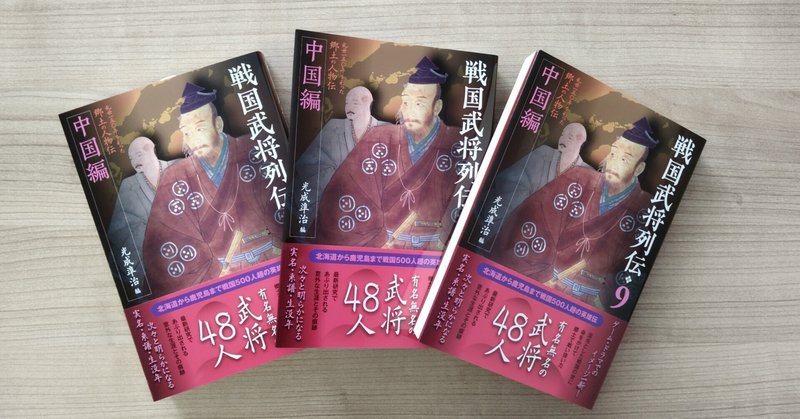
光成準治編『戦国武将列伝9 中国編』を刊行します
8月の新刊、光成準治編『戦国武将列伝9 中国編』が刷り上がってきました。昨年より刊行が始まった「戦国武将列伝」シリーズの7弾目になります。
https://www.ebisukosyo.co.jp/item/694/
刊行に先駆けて、下記に本書の「はしがき」をアップしました。編者の光成先生による戦国期中国地方の研究状況や編集方針、本書の読みどころ等がまとめられていますので、ぜひご覧ください。
はしがき
中国地域における戦国大名といえば、多くの人が毛利元就を思い浮かべるであろう。しかし、元就が一国衆の地位からの脱却を図ったのは天文二十三年(一五五四)であり、仮に戦国期の始期を応仁・文明の乱が勃発した応仁元年(一四六七)、終期を毛利氏と羽柴秀吉方との国境が画定した天正十三年(一五八五)初頭とすると、戦国大名毛利氏の登場以後よりもそれ以前の期間のほうがはるかに長い。にもかかわらず、毛利氏以外の大名や国衆は脇役的にとりあげられるケースが多かった。
例えば、大内氏は守護大名の典型とされてきたため、戦国大名毛利氏に取って代わられ滅亡した古いタイプの権力とみなされることも少なくなかった。しかし、戦国大名領国とは、守護権ではなく自らの公儀性に基づいて広域的な支配を行う地域国家と定義でき、守護職を獲得していない安芸国や備後国においても多くの国人領主層を従属下に置いていた大内氏は戦国大名といってもよかろう。大内氏は応仁・文明の乱勃発以前の康正三年(一四五七)に安芸武田氏領へ進攻しており、その時点で戦国大名化への道が始まっていたと捉えることもできる。大内氏の滅亡は弘治三年(一五五七)。戦国期の中国地域西部に影響力を及ぼした期間は毛利氏よりも大内氏のほうが長い。
毛利氏と並ぶ中国地域における代表的な戦国大名尼子氏についても、天文十年(一五四一)の郡山城合戦での敗退や、永禄九年(一五六六)の富田開城、山中幸盛らの再興活動の失敗といった対毛利氏戦の敗北が広く知られたエピソードだが、郡山城敗退後も尼子晴久が死没する以前においては、尼子氏が大きく衰退したわけではない。
さらに、因幡国・伯耆国・備前国・美作国・備中国においては、守護山名氏・細川氏の退潮の中から武田高信、南条宗勝、浦上宗景、宇喜多直家、三
村元親・家親といった地域領主が台頭している。けれども、これらの武将も毛利氏との関係に注目が集まり、地域領主としての面は広く知られていない。安芸国や備後国の国衆は本来毛利氏と同格の存在であり、毛利氏が戦国大名化した後も同盟関係的側面は残されていたが、毛利氏家臣としての活動のみに注目が集まってきた。
このような毛利氏中心史観は、江戸期に成立した軍記類(『陰徳太平記』など)の影響が現代にも色濃く残っていたためである。このため、本書では、軍記類の叙述に基づく虚像を排して実像を描き出すことに努めた。
中国地域の戦国期史料については、『大日本古文書』『萩藩閥閲録』など従来から活用されてきた毛利氏関係文書に加え、近年、『山口県史』『新鳥取県史』といった県史編纂における史料編や『出雲尼子氏史料集』『戦国遺文大内氏編』などの大名別史料集が刊行されたほか、『新修倉敷市史』『久世町史』『松江市史』といった自治体史においても充実した史料編纂が行われている。本書はそれらの成果を踏まえ、最新の研究動向を盛り込み各武将の実像に迫ったものである。
中国地域においては、他の地域と異なり、守護あるいは守護代層に出自をもつ家が大名として織豊期まで存続することができなかった。そのような特殊性は毛利元就や宇喜多直家といった武将の知勇によって、守護・守護代層が滅亡・衰退に追い込まれたことのみを要因にするとは考えられない。その謎を解き明かすためには、滅亡・衰退していった家の武将や国衆を研究対象とすることも有効であろう。本書は単に武将の一生を追うだけでなく、マクロな視点で中世から近世へと移行する時期の中国地域史を見直そうとしたものである。
右記のように比較的史料に恵まれた当地域であるが、未解明の史実も少なくない。本書の刊行を契機にさらなる研究の深化に加え、埋もれた史料の発掘につながることにも期待したい。
二〇二三年七月
光成準治
試し読み
なお、下記リンク先より、本書の「試し読み」ページをご覧いただけます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
