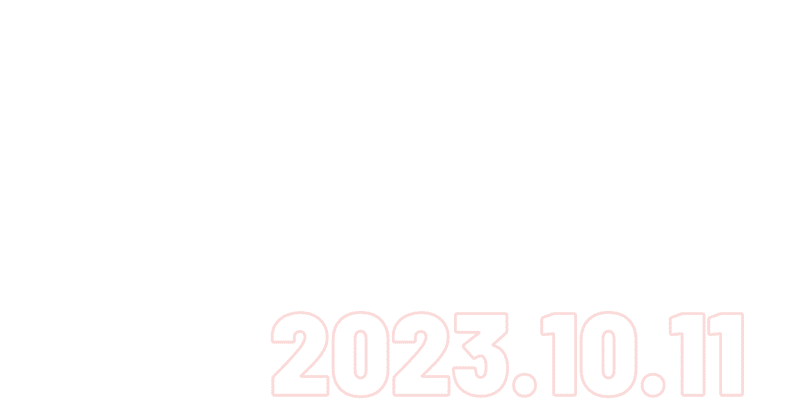
ボタンを買いたかった私のはなし
ヘンリーネックベストの襟元に付けるボタンが欲しくて、商店街の中程にある毛糸屋に来た。
1.5mmのやつが、4ついる。
一生続くかと思われた夏の厳しい暑さは、まるで最初から存在していなかったかのように音もなく姿を消してしまった。
秋のはいりくちは、いつも急だ。
去年パーツを編むだけ編んで、ほったらかしにしておいたベストを、私は急いで仕上げる必要があった。
その毛糸屋の前は、何度も通ったことがある。
商店街はまっすぐ街中まで伸びていて、コンビニやスーパーに行くのに必ず使う道だから。
広さは10畳あるかないかの小さな店。
だけど、商店街の店の半分はシャッターを降ろしているこんな田舎で、毛糸を専門に扱っているところがあるのはほとんど奇跡だ。
中に入って毛糸を眺めてみたい、でも本当に買うか分からないのに、ただの冷やかしになるのはなんだか決まりが悪い。
それで、ずっと中に入るのを躊躇っていた。
でも今は、「自分で編んだベストに付けるボタンを買う」という、店に入るには立派すぎる理由がある。
ガラス戸を、用心深げにそろっと引く。
「こんにちは」と声の調子を上げて挨拶をすると、華奢なおばあさんが店の奥から出てきた。
年のころは80過ぎといったところか。
真っ白い髪を堂々と短くまとめている。
「いらっしゃい」
はっきりと意思のある声質。
しゃんと伸びた背筋が、本当の年齢を分からなくさせている。
淡い黄色の薄手のニットに、白のチノパンという何気ない装いだが、唇にはちゃんと薄桃色の口紅が塗られている。
意志のある人だ、と私は思った。
「なにか?」
おばあさんは、初めてやってきた私に向かって簡潔に問う。
まっすぐこちらに向かってくる眼差しに、なぜか慌ててしまう私。
無駄なく答えなきゃ。
「ベストに付けるボタンが欲しくて来ました」
「ボタン?どんなボタン?ボタンは服の顔だから、ミリで違ってくるのよ。あなた、編んだものは今日持ってきてる?ボタンは実際に編み地に置いてみないと出来上がりの雰囲気がわからないからね。ボタンの厚みによってボタンホールの通り具合も変わってくるし」
私は気圧された。
思い切り抱きつけばポキンと簡単に折れてしまいそうな細い体で、どうやってこれだけのことを息継ぎもせず捲し立てられるのだろう。
なんだか怒られているような心持ちがして、私はすっかり縮んでしまった。
「あの、編んだやつは、持って来てないんですけど・・・」
「あらそう、自分で編んだの?」
「はい」
「なら、なおさら、いい加減じゃなくちゃんと決めなくちゃ」
いい加減、という言葉にくらっとする。
私はもう、すっかり自分のことが、恥ずかしい。
「今日じゃなくても、また別に日に編んだものを持ってきて選びなさいな」
ほとんど消え入りそうな声で、私は「はい」と返事する。
おばあさんの顔が見れない。
2年間、ずっと中に入ってみたくて念願叶ってやってきた。
お店に辿り着くまでの私の足取りは気忙しく、それでいて少しだけ宙に浮いていた。
間近でいろんな毛糸が見られる。
どんなボタンがあるのだろう。
店員さんと、編みもののはなしで盛り上がれるかもしれない。
ほんの2分前まで、お小遣いを握りしめて駄菓子屋に駆けていく子どものような心持ちだったのが信じられない。
おばあさんに「それじゃ」と結びの言葉を言われてしまったので、私は「じゃあ、また編んだものを持って来ます」と言うしかなかった。
すごすごと店を後にしようとする、丸まった私の背中におばあさんは声を掛けた。
「それ、あなたが自分で編んだの?」
私はこの日、レース編みの白いショールを肩にさげていた。
北風があんまり強くて薄手のシャツでは心許なく、出がけに慌てて肩に引っ掛けてきたもの。
「はい」
私が早口にそう答えると、おばあさんの口角がぴくりとほんの少し上向いたのが分かった。
私は、自分の編んだものをこの賢いおばあさんに見られたくなかった。
編みものは独学したから、棒針の持ち方や始末のやり方が我流になってしまっている。
きっと、おばあさんなら一目見ただけで私のショールのまずいところを的確に探り当ててしまうだろう。
見てほしくない。見ないで。
「ありがとうございました〜」
別れの言葉だけ、なんとか声を張った。
おばあさんは「はい」とだけ返事をして、作業台の上に置いてある老眼鏡をかけた。
ガラス戸を閉めてから、私はもう一度おばあさんにぺこりと頭を下げた。
おばあさんはもう、私の来訪があったことなどすっかり忘れてしまったかのように、自分の編みかけの作品に向き直っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
