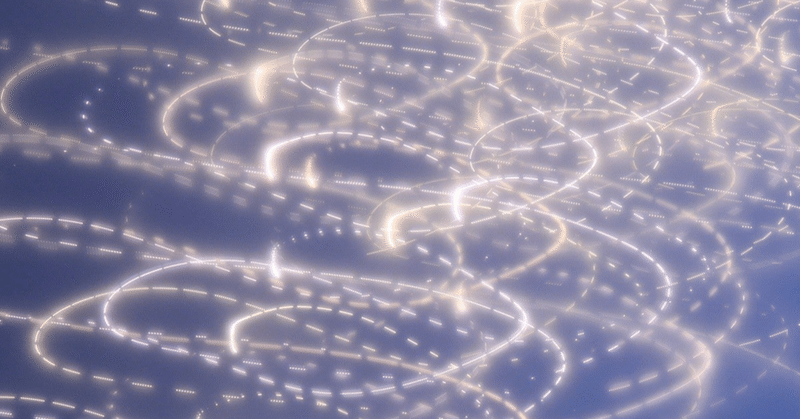
浮髪
今日、告白をした。予想に反して、返事はオーケーだった。
男手一つで育てられた僕は、女子とは縁のない、いわゆる青春が無い生活を送っていた。姉はいるが、母親に引き取られた。だから彼女がどこにいるかも分からない。唯一の記憶は、両親が離婚した十二年前、僕が五歳の時既に小学校高学年だったという事だけだ。
話は戻って、僕は高校に入学して、一人の女性に恋をした。
一年生の時、来年も同じクラスだったら、勇気を出して告白してみようと思っていた。そして二年生になり、また同じクラスになってしまった。自分の中で変な予定を立てていたせいで、同じクラスになったのは少し嫌だった。そこまで仲が良いわけではない。だけど、せめて想いだけでも伝えてみようと思えたのは、一年生の時に習った、与謝野晶子の『みだれ髪』のせいだ。
真っ直ぐな愛を訴え続けた与謝野晶子に胸を打たれた。今の世の中で、ましてや自分は男に生まれて、少しばかりでも勇気を出して恋心を伝えるべきなのではと、新しい自分になるための第一歩でもあった。
僕は小さい頃から髪の毛が綺麗な女性が好きだ。男は無意識に女性の胸や尻や脚等を見ているなど聞いたことがあるが、僕はまず、髪の毛を見てしまっている気がする。もし自分が女性だったら、僕は普通の男よりもさらに気持ち悪いだろう。
そう、彼女は髪の毛が綺麗だ。油気が無く、風が吹くとその髪の毛はすらすらとひとつひとつが波打つように宙を鯉のぼりの様に舞う。
付き合い始めて数日、僕の住んでいる地域は、秋雨がよく降るようになった。
湿気は髪の毛の調子が悪くなる。天然パーマの友人は、髪の毛がものすごく膨らみ、頭が心なしか何回りか大きく見えた。彼もそれを悩んでいた。
彼女の髪の毛は相変わらず綺麗な髪の毛をしていた。その髪の毛は重そうには見えない。
今日は珍しく、曇りだ。彼女とは毎日一緒に下校している。今日は久しぶりに、傘をささずに下校することができる。距離が少しでも縮まる機会になると思う。そうなって欲しい。でも、雨が降って来ることで、何か起きるのではないか、という淡い期待も、心のどこかにある。
学校から駅まで歩く。特に当たり障りのない会話をする。毎日この繰り返しだ。今日もそうだ。一限目の教師のメガネが新しくなっていたこと、三限目には空腹からお腹が大きな音でなってしまい、先生に注意されたこと、今日は久しぶりに雨が降っていないこと。体の中からつらつらと、当たり障りのない言葉たちが出てくる。駅までは十五分。電車の方向は逆方向だ。
「雨だ」
と、彼女が不意に呟いた瞬間に雨が、止められているシャワーから垂れる水程垂れてきた。
急いでスマホを開き、天気予報を調べる。青く映った雨雲が僕らの上空にいる。さらに雨は強くなる。雨は僕らを早足で歩かせる。制服のシャツは雨を吸い、肌に吸い付く。僕は学校指定のカバンを頭にかざしながら、土砂降りの中をゆく。あまり速く走りすぎると、彼女を置いていってしまう。
もう少し歩いたところにはコインランドリーがある。そこで雨宿りをすることにした。
雨宿りをしている僕と彼女の髪は濡れていた。その姿を見て、僕は何も思わなかった。不思議だ。あれだけ美しいと思っていた彼女に、何の感情も覚えない。僕は無言になった。コインランドリーの中は居心地の悪い湿気に包まれ、薄い窓の外からは雨音が聞こえる。彼女の小さい声は、雨の音に消されてしまう。
「雨が降るなんて、驚いたね」と、話しかける彼女の顔を見ず、
「うん」
と窓の外に通る車たちを目で追いながら頷いた。
あれから数十分経っただろうか。雨はすっかり止んで、雨が降り出す前のグレーの空に戻ろうとしている。僕は彼女がびしょ濡れになっているのを見て、学校に一度戻り、体操着で帰ろうと提案した。彼女はそれを快諾した。僕は彼女に学ランを貸し、それを羽織らせ、学校まで十数分もう一度歩くことにした。学ランはカバンの中に入れていたからか、あまり濡れていなかった。僕がワイシャツ一枚になり、寒いのではないかと心配してくれたが、僕は大丈夫だと彼女を諭した。
彼女は歩きながら、放課後なのだから、青春がしたいと話を始めた。文化祭で青春の思い出を作ればいいじゃないかと僕は言った。
それに対して彼女は、青春というのは、特別な日に限ったことじゃない。青春とはなんたるかを僕の横で熱弁している。僕にはそれは漫画や小説の世界での出来事でしかないと思ってしまう寂しい脳みそしか無い。
彼女の熱弁を聞きながら、いつの間にか学校に着いた。すると彼女は、
「せっかくびしょ濡れなんだからさ、このままプールに行かない?」
と僕を誘った。僕は「せっかく」の意味は分からなかった。もう十月で、今日は少し曇っている。
「いいよ」
断る理由は見つからなかった。誰もいないプールに忍び込んでみるのは、悪くないと思った。
学校には誰もいなかった。あれだけ雨が降っていたのに。僕等以外は雨に濡れずに帰ることができたのだろうか。
今日は偶然職員会議の日だ。だから部活動は禁止されている。いつもならこの時間は、水泳部が意気揚々と泳いでいる。
「キイ」
とドアが鳴り、静まり返ったプールサイドを歩く。空と似た色をしたプールには、枯れ葉が数枚だけ浮かんでいる。毎年春頃掃除するプールと同じとは思えない程に綺麗な状態を保っている。
また当たり障りのない会話をする。今回はさっきの雨の話だ。朝家を出るときには振る予定はなかったとか、口にたくさん雨が入って、喉が潤ったとか、でも雨は神様のおしっこと言われているとか、そんなことを話していた。
彼女が深く息を吸ったのと同時に、急に会話が止まった。変なことを言ってしまったのかと、少し戸惑った。
その瞬間、彼女は僕の手を引いて、水の中に飛び込んだ。
水深が一メートルと少しとは思えないほど深く感じた。音はしばらく聞こえなく、ゴウゴウという水音だけが聞こえる。驚いて何かを叫んでいる僕の声は彼女には届いていないが、確かに僕は叫んだ。僕は腕と脚を振ったが、横にしか進めなかった。だいぶ深く落ちているようで、服の重みのせいで上に中々上がれなかった。
そういえば、彼女はどこに行ったのだろう。霞む景色の中で彼女を探した。手の少し届かない程先に彼女が見えた。
雨で濡れた髪を見た時の不思議な感情は、今目の前で美しく、被帛のように舞っている彼女の美しさに淘汰され、僕は足搔くのをやめ、その姿を見つめた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
