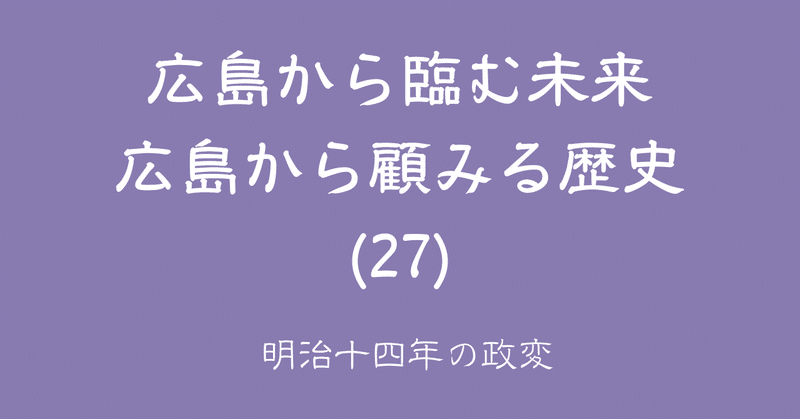
広島から臨む未来、広島から顧みる歴史(27)
明治十四年の政変
明治十四(1881)年四月、『会社条例』草案が脱稿、同月、太政官が商法典編纂を決し、太政官法制部主管山田顕義は、ドイツ人ヘルマン・レースラーに商法草案の起草を委嘱する。
会社法についての続きだが、明治十年までの『会社条例』草案に関わる動きまで見てきた。その後、明治十年には西南戦争が、そして明治十一年には紀尾井坂の変があり、西郷、大久保という薩摩の両巨頭が相次いで世を去った。
地租改正に伴う混乱
個人的な感覚では、この時期には、まず地租改正に伴う全国的な混乱の気配があったことは否めないと思うが、それに伴って征韓論で最過激派であったとも言える板垣退助が自由民権運動の旗手のような存在として各地で動き回っていたということがありそう。ただ、各地とはいっても、いったい中央政府の力がどこまで及んでいたのか、というのは十分に考える必要がある。先の述べた佐賀の乱などの西南戦争に至るまでのいわゆる不平士族の反乱というのは、維新のお膝元とも言える西国で起きていたのであり、お膝元でそれなのに、他の地域に地租改正などの革命的な制度変更を押し付けられるとは到底思えない。つまり、この時期の中央政府の力は西国においてもせいぜい長州に届くかどうか、東国に至っては、これまで書いてきたことを含めて、それでもこの時期に都が京都にあったのだという想定を受け入れたにしても、まさにその山城が精一杯で、近江、特にいわゆる旧幕府の勢力範囲の色彩が強くなる湖東地方にはまずその力は及んでいなかったのではないかと考えられる。
地方自治に関わる動き
そこで、地方自治についての動きを見てみると、明治八年の『立憲政体の詔書』によって地方官会議の設置が決まり、翌明治九年には地租改正に関わり「各区町村金穀公借共有物取扱土木起功規則」を公布して、会社法がないためにまだ法人とは認められない地方自治体の共有財産の取り扱いを定めた。これが地租改正と関わって出されたというところに日本の土地問題を複雑化させた原因があると思われ、というのは、地租は土地の私有権を前提にそこに租税を課すということであるが、伝統的村落共同体で大きな地位を占めていたのが入会地と呼ばれる共有地であり、土地についてはこの規則のタイトルである金穀公借共有物には含まれないと見られ、それゆえに共有財産であるべき入会地を個人財産に分割する必要が出てきて、それによって争う必要もないところに争いが引き起こされたのだと考えられる。この規則の正確な内容はまだ確認できていないが、金殻公借共有物取扱などの財政行為の実施には、不動産所有者の60%以上の賛成が必要と定められているようだ(湖南市立石部南小学校 | 郷土の歴史)。そうなると、不動産を多く確保することで公有物の財政行為に影響力を持てるということになり、土地の争奪が激しくなることは十分に予想できる。翌年のいわゆる西南戦争と呼ばれるものの原因として、このような土地争いがあったのではないかという想定は十分に成り立ちうるのではないだろうか。
貨幣経済化の推進と土地に関わる争い
この時期には、納税の金納化や国立銀行の設置なども睨み、貨幣の入手というのが大きな関心事となっていた。そんな時に、金穀の共有が認められながら土地はそうではないということになると、共有地での共同労働から貨幣を得るというモデルが成立し得なくなり、土地を私有化してそこから商品作物の販売を通じて貨幣を得なければならない、という、争いと競争がビルトインされたような”現代的”社会制度が確立することになったと言える。そしてそれが共有物の財政行為の決定権にも関わるとなると、土地をめぐる権利争いはますます激しくなる。そのような、わざわざ地域社会に争いを持ち込むような規則を導入するということの問題の大きさには留意すべきなのだろう。
異質な日本の近代
のちの日本で共産主義が受け入れられやすい土壌があったのは、西洋における革命によって土地を王侯貴族から取り戻すというイメージよりも、もともと共有地であったものをその状態に戻す、という意味合いが強く、その意味で明治維新とは革命でもなんでもなく、むしろ一部の成金、それは徳川を代表とした大名として名を残しているものが多いと言えるが、そういったものどもがあたかも江戸時代から継続的な支配者であったかのように歴史を書き換えながら土地の収奪を行なったプロセスであるといえ、その意味で日本は近代になってから封建制がかなりの完成度で成立した西洋から見ると異質な国、文化であるのだといえよう。
歴史記述の歪み
そしてその上で、日本史を西洋史の時代区分に合わせて記述しようという無理なやり方をしたために歴史記述自体がかなりおかしなことになったのだと言えそう。そうして書かれた歴史記述はなんであれ創作的な部分が多くなり、そのために中近世を中心に都合の良い記述をしたもの勝ち、のようなことになって、歴史的な嘘が多く混ざり込む、というか、歴史記述にほとんど真実が含まれていないという、かなり悲劇的な状態になってしまったのだと言える。その意味で、そのような歴史を戦争、というよりも敗戦によって清算するというのはある種の必然であったと言えそうで、明治維新以来の歴史記述のあり方が八十年を経て一旦リセットがなされたのだと言えそう。しかし、そのせっかくのリセットも、またその段階でもっと大きな嘘が混じり込んだために、今度こそはもはや選択肢を見出し難いような袋小路に完全に迷い込んでしまってその戦後からの八十年を迎えようとしているのではないだろうか。
地方自治制度の展開
少し話が飛躍しすぎたが、そのようなリセットで無理に無理を重ねたのが明治一桁年代だといえ、それが西南戦争と紀尾井坂の変で一度話を整理したのだと言えそう。その紀尾井坂の変があった明治十一年には、地方自治に関するいわゆる三新法、すなわち「郡区町村編制法」、「府県会規則」、そして「地方税規則」が公布され、評判の良くなかった大小区制から町村制に戻り、府県と郡が国の行政区画とされた。この時に府県が郡の上に置かれたことで、国・郡・町村の体制が国・府県・郡・町村となり、そして議事機関は府県に府県会が置かれるとなったことで、法的には最新参の府県が地方自治においては大きな権限を持つようになり、一方で区町村会が任意設置となったことで、基礎自治体の意志決定能力というのが最初の段階からかなり低く設定されたのだった。このように地方自治の出発段階で府県に強い力を与え、区町村の力を抑えたことが、現在に至るまで地方分権の動きを難しくしているように見える。自由民権運動の高まりで、これに対して不満が噴出したか、明治十三年四月には「区町村会法」が公布されることになった。この自由民権運動の状況というのは、おそらく各地に置いてさまざまな様相を見せたと思われ、それによって「民主的に」明治新政府に参加するか否か、ということが決まっていったのではないかと思われる。この時点までに新政府の威光がどこまで広まっていたのか、というのはさらに調査が必要になりそう。
明治十四年の政変
さて、地方の状況がこのようになっている中、中央政府でも国会開設運動が活発になりだしていた。そしてそれが明治十四年の政変に至ることになる。一般見解の評価のためには、Wikipediaの引用とそれに対する評価が効果的ではないかと思うので、多少長くなるが明治十四年の政変から抜粋引用したい。
明治12年(1879年)、国会開設運動が興隆し、政府内でも憲法制定や国会開設について議論が開始されていた。明治9年(1876年)からは元老院において憲法草案の作成が進められていた。明治12年12月に参議山縣有朋が立憲政体に関する意見書を提出したことにより、太政大臣三条実美と岩倉は参議から立憲政体に関する意見を天皇に提出させることとした。翌明治13年2月には黒田清隆、7月には井上、12月には伊藤が提出した。このうち黒田は立憲政体は時期尚早であると述べ、山縣と井上はヨーロッパの知識を盛り込んだだけのものであった。
伊藤は井上毅の協力を得て意見書を作成した。その内容は「国会創設は望ましいことではあるが、大事を急いで行うのは望ましくない」「国会を作る場合は上下両院を作り、均衡を保つべきである」「上院を作成する準備のため、現在の元老院を拡張し、華族・士族から公選された代表者に法律を作成させる」「下院の準備として府県会議員から公選の会計検査を行う検査員を選出する」というものであった。しかし大隈は意見書を出そうとはせず、明治14年を迎えた。
明治14年1月から2月にかけ、伊藤は熱海の旅館に大隈・井上・黒田を招き、立憲政体等について語り合ったが、合意は行われなかった。またこの会議の中では開拓使の廃止問題が取り上げられた。黒田は開拓使の継続が必要であると主張したが、大隈は財政上の問題で継続は困難であるとした。官有物払下げの方針が定まり、五代友厚が引き受け手として名乗りを上げた。
3月になると、未だ意見書を提出していなかった大隈に対し、左大臣有栖川宮熾仁親王から督促が行われた。大隈は有栖川宮に対し、他の参議・大臣に見せないことを条件に意見書を提出した。大隈の意見書は「早急に欽定憲法を制定し、2年後に国会を開く」「イギリス型の立憲政治を導入し、政党内閣を組織させる」など、あまりにも急進的なものであった。有栖川宮は意見書を三条と岩倉に見せており、岩倉は伊藤が大隈の意見書について知らないということを察知した。意見書の内容があまりにも過激であると考えた岩倉は、伊藤に知られる前に大隈と話そうという手紙を書いている。しかし大隈は伊藤と意見を交換しようとはしなかった。
7月30日より天皇は北海道を含む地方行幸に赴き、閣員のうち有栖川宮・大隈・黒田・大木喬任はこれに同行していた。一方で東京に残った伊藤・井上・山縣有朋・山田顕義・西郷らは大隈の排除に向けて動き出し、三条や当時京都で病気療養中だった右大臣岩倉具視の説得を開始した。また佐々木ら非薩長系の政府重臣、井上毅による薩摩系参議への根回しも開始された。この頃佐々木高行・土方久元・吉井友実ら天皇親政を目指す旧侍補グループや谷干城・鳥尾小弥太ら非薩長系の軍人、そして金子堅太郎や三好退蔵といった中堅官僚は「中正党」と呼ばれるグループを形成し、払下げに反対して薩長勢力に対抗しようとしていた。
10月8日までに東京政府のメンバー内では、大隈の罷免、憲法制定と9年後の国会開設、そして払下げの中止が合意された。帰京した岩倉は払下げ中止には否定的であり大隈罷免にも消極的であったが、伊藤や黒田が大隈罷免と払下げ中止を強く迫ったことによって、大隈罷免に同意し、開拓使問題については明治天皇の裁下を仰ぐこととなった。
天皇が10月11日に帰京すると、岩倉は千住駅で拝謁し、大隈の謀略によって払下げ問題が批判を受けているため、早急に御前会議を開いて払下げを再考するべきであると上奏した。その後三条・岩倉の二大臣、伊藤・黒田・山縣・西郷・井上・山田の六参議は有栖川宮左大臣と密談し、大隈罷免について合意した。これに続いて大隈以外の大臣・参議が大隈罷免を上奏した。明治天皇は大隈排除が薩長による陰謀ではないかと疑ったが、薩長以外の参議も大隈排除に同意していたことから、大隈排除に同意した。
同日中に伊藤と西郷によって大隈はこのことを知り、辞職した。10月12日に払下げの中止と国会開設が公表され(国会開設の詔)、事件は終息した。しかし農商務卿河野敏鎌や、矢野文雄・小野梓といった大隈系官僚が大量に辞職した。
と、さまざまな要素が入り混じった、非常にわかりにくい政変となっている。直接的には官有物払い下げの問題がきっかけになっているが、立憲政体、憲法、そして国会開設に関わる問題がベースであったのは明らかであろう。その複雑な問題を官有物払い下げ問題で政局化し、議論のレベルを下げるという、今の時代にも通じるような手法がとられていることがよくわかる。
日本で憲法改正の議論がしにくいのは、そもそも最初の憲法ができた時に、このような泥に塗れたような議論でレベルが下がり、結局地方分権について全く触れられないという非常に程度の低い憲法ができてしまったという反省が強く残っているのではないかと考えられる。これを他山の石とし、憲法議論は落ち着いて、かつハードルが上がりすぎないような、もっと身近なものにする必要があるだろう。
意見書提出
それはともかく、この政変の経緯を追ってみたい。まず注目したいのは、立憲政体の意見書の提出が、山縣有朋という非常に反動的な政治家から出されたという、議論の出発点だ。これによって参議から立憲政体に関する意見を天皇に提出させるということが定まり、この時点で欽定憲法になるという道筋がほぼ決まったのだと言える。しかも、天皇に提出してしまった意見書というのは、なかなか訂正が難しいということで、議論に大きな枷が嵌められることになる。そのなかで、最初に提出した山縣はヨーロッパの知識を盛り込んだだけという、非常に無責任とも言える態度で議論の口火を切ったことになる。ついで、官有物払い下げに積極的な黒田と井上が提出するが、黒田は時期尚早、井上は山縣と同じくヨーロッパのコピペということで、時間を稼ぎながら、そのうちに払い下げをどんどん進めたいという意向が読み取れそう。伊藤も基本的には時期尚早だとするが、それまでに行うべきことを具体的に列挙した現実的な案だと評価できそう。
開拓使の取り扱い
ついで熱海で行われた会議では、開拓使の議論が出たという。黒田は開拓使を継続してもっと財政を注ぎ込んでから安く払い下げを目指すという路線であったとみられる。それに対して大隈が反対し、その結果として払い下げの方針が決まったという。つまり、財政の追加負担を避けるために早期の払い下げを主張したのが大隈であるということになる。
大隈の意見書
この段階ではまだ意見書を提出していなかった大隈だが、有栖川宮からの督促を得て非公開を条件に急進的な意見書を提出したという。まず、上記開拓使の話を考えると、時間をかければかけるほどに民意によるチェックのない財政支出が拡大するということで、早く憲法を定めたいというのが基本的な立場であったと言える。その背景には、板垣を中心として過激化する自由民権運動というものがあり、前年に集会条例を出して過激化を抑えようとはしていたものの、いつどのように暴発するかはなんとも言えない、というリスクをはらんでいたと言える。その中で有栖川宮に対して欽定憲法で2年後の国会開設という意見書であれば、天皇に対して直接ではないのでそれを根拠に突っ走るということも防げるので、天皇の負担を軽くできる、という見通しがあったのではないか。条件として大臣に見せないという項目が本当に入っていたかはわからないが、反動派の狙っていた天皇に乗せて一気に走らせるという路線が宮への欽定憲法の早期公布という意見書によって難しくなり、三条だけでも処理できず、岩倉まで行くだろうことは想定内だったのではないだろうか。太政官の制度上では、左大臣である宮よりも太政大臣の三条の方が上になるわけで、職制上上司への報告というのは問題とはならないだろう。その上でその報告を受けた三条が右大臣の岩倉に相談、という手続き論になるのではないか。
大隈の身を挺した政治正常化
このように、大隈は、いわば人身御供として欽定憲法、国会開設、官有物払い下げというトリレンマとも言える状態を最小の被害で乗り越えようとしたのだと言えそう。そうして、払い下げを中止させながら、ある程度の期間をおいた国会開設、憲法制定が決まり、それと引き換えに大隈は罷免されたが、大隈派というよりも払い下げ推進派とも言える河野敏鎌を中心とした勢力を道連れにしたのだと言えそう。
商法典編纂の背景の一部
こんな政変の半年前に、冒頭の商法についての動きがあったことになる。例によって『日本会社立法の歴史的展開』から抜粋したものだが、最初の「会社条例」草案が脱稿する、というのはなんのことだか調べてみてもよくわからなかったので、そのまま書き写しただけに止める。その後の内容は、要するに、太政官が商法典の編纂を決めて、ドイツ人レースラー(ロエスレル)にその草案起草を委嘱したということだが、この時期にその動きがあった背景には、やはり払い下げの問題があり、公的資産の払い下げに法的裏付けのない法人に対してそれを行うことができるのか、という法理論上の問題が出てきたことは十分に考えられる。その前月三月に大隈が意見書を宮に提出しており、それで動き出してしまわないように、なんらかの歯止めをかけておくために法人の扱いが決まっていない、という理屈を準備したのではないか。結局それが決定打となり、払い下げを引き止めることができるようになったのかもしれない。
誰かが読んで、評価をしてくれた、ということはとても大きな励みになります。サポート、本当にありがとうございます。
