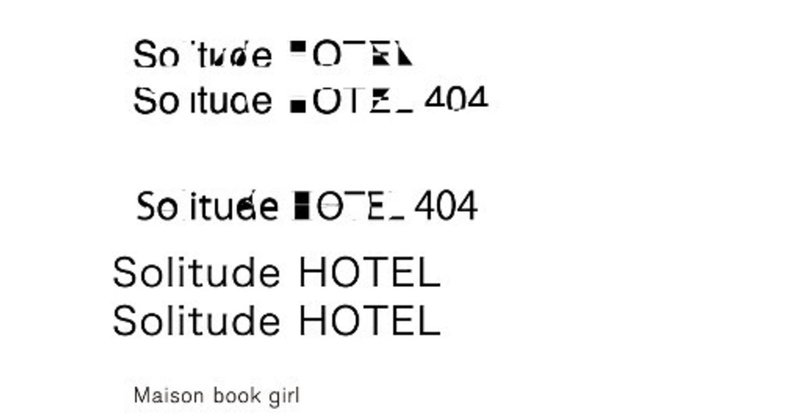
「孤独」に 1
2021年4月2日。

ワンマンライヴの告知に、悪寒がした。
階数表記の無いホテルの名前の横には、「404」の文字があった。
今まで色んな場面でこの数字を見てきた。大好きだったフラッシュ倉庫、はるか昔のニュース記事、消えていったバンドのホームページ。
僕はその3桁の数字を、今までそこに在ったはずのものを無慈悲に消し去ることのできる恐ろしい数字として認識していた。
崖の前に立たされたその不安な背中を、笑いながら何度も小突かれるかのように、彼女たちのホームページは日を追うごとに歪み、削れ、壊れていった。
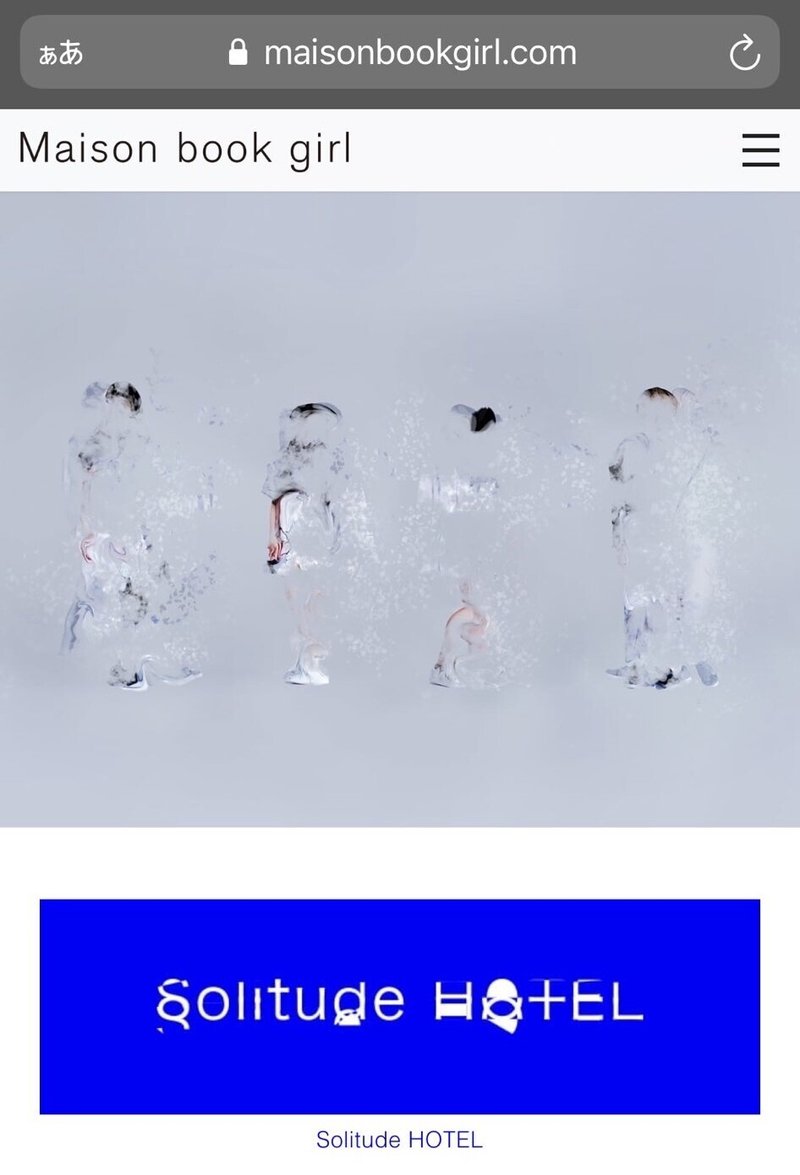
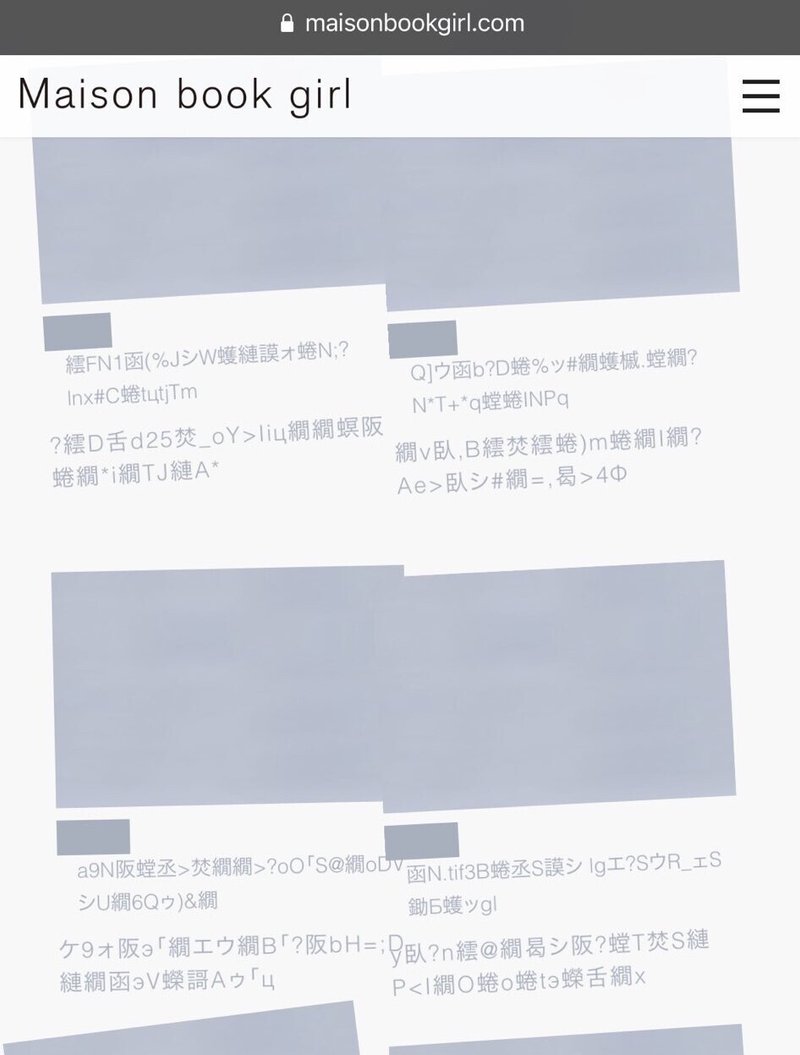
―――――――――
かつて僕は、アイドルが好きではなかった。
厳密にはアイドル界隈における、”女性性を食い物にして金を稼ぐ”という汚いシステム(今は当然そんなことを思ってはいないのだが、当時は本当にそう思っている節があった)が嫌いだったと思う。口には出さないものの、僕はアイドル界隈をどこか冷めた目で見ていた。
その価値観の中にいた僕にさえ、6年半ほど前に見た彼女たちの姿はとても印象に残ってしまった。忘れもしない2015年12月11日、名古屋は栄TIGHT ROPE。大好きなRINGO DEATHSTARRのオープニング・アクト。
僕はそこで、思春期の頃憧れ続けたバンド達と同等、ややもするとそれ以上の熱に成長する温度に、初めて触れることとなった。
「煙だ。」
僕が彼女たちに興味を持ってから、初めて発表されたMVを見てそう感じた。
担当カラーがあるわけでもなく、白くて、掴めなさそうで、無機質で。
だからこそ、これから何にでもなれそうだと思った。
僕はこのMVを見てから、彼女たちの虜になった。
友達がでんぱ組 Inc.にドハマりするのをどこか嘲笑していた節もあった僕が、「現場」に行くほどアイドルを好きになることなんて、無いと思っていた。
人は変わる。既存の価値観をはるかに凌ぐ存在によって。
初めて「現場」に訪れ、かつて小馬鹿にしていた「チェキ」の列に並んだ。初めて面と向かって話をした。
眼鏡をかけた彼女は、Twitterで他ファンとも触れ合わず、ひとり愛をつぶやき続けていた僕のことを知っていた。とても嬉しかった。
彼女たちは、僕を見つけてくれていた。
彼女たちが彼女たちで在り続けるためなら、自身のできるサポートは何でもしてあげたい、と思った。
彼女たちは、とても優しい人たちだった。
2020年、音楽好きの誰もが絶望した1年だったと思う。たくさんのアーティストが自身の存在意義と向き合った結果活動を停止し、多くのライヴハウスやクラブがあっという間に消えていった。そんな中にあっても、彼女たちは常にファンである僕たちを支えようとしてくれていた。
自身でYouTubeライヴを企画したり、オフの姿を積極的に見せたり。何よりも嬉しかったのは、生のライヴに必ず劣ると思われていただろう配信のライヴで、他アーティスト達よりも先に新たな可能性を見いだしていたことだ。
「孤独な箱で」と題されたその配信ライヴは、彼女たちの舞台表現の到達点のひとつだと思っている。
配信ライヴ「6irthday」で、リンドウの蕾を使ったパフォーマンスが行われた。花言葉は、「あなたの悲しみに寄り添う」。
「Ghost」と題された楽曲でリンドウの蕾を手にした彼女は以前、「ファンの皆の影のような存在になりたい」と言っていた。
その言葉通り、彼女たちはやさしい影のように、衣服に麝香を残す煙のように、ずっと僕たちを見守っていた。
その煙に包まれながら、僕たちはこのホテルの中に棲んでいた。
この世界を作っていたプロデューサーが、質問を募集していた。
「彼女たちの新曲の発表はいつですか?楽しみにしています。」
返事は無かった。僕の質問だけでなく、彼女たちに関する質問に彼は何一つ答えなかった。
ここから、ひとつの「予感」が形を持ち始めた。
公演の14日前から、彼女たちのことを考えない日は一日も無かった。
―――――――――
2021年5月30日。真っ白な朝が来た。
家族連れやカップルで賑わうワンダーランドの側にある、ノーワンダーランドに向かう。
物販に並ぶ。「予感」がひとつの「確信」に近づいた。
積み上げられた段ボールには、本公演でのグッズ以外に、過去のツアーで売られていたグッズ達の姿もあった。
今まで当たり前のように存在していると思っていたものの中身が、実は錆び付き今にも崩れそうなさまであるのを見たような気分だった。
会場入りし、席に着いた僕はもう、気が気では無かった。
「全部持ってってね、ありがとう」
最後のような彼女の言葉を見て、僕はiPhoneの電源をそっと落とした。
―――――――――
平穏が途切れ、「last scene」が流れ出した。
彼女たちの声のしない、地鳴りのような低音に包まれたそのいびつな音は、これが最期である「確信」を得るには充分すぎるものだった。
ペストマスクの男が、ステージ中央に置いていた青い紙を拾い上げる。

突然、「Solitude HOTEL 4F」のオープニングムービーが流れ出した。まさか肉眼でこのムービーが見られるとは。
2017年12月28日に行われたこの公演後のレポートを見て、僕は鳥肌が止まらなかったのを覚えている。あまりにも練られたステージ構成、ダークな世界観。観られなかったことをとても悔やんだ公演だった。
そんな公演のオープニングムービーが、眼前に流れている。
僕たちは過去を観ていた。今日はきっと、今までの「Solitude HOTEL」の総括だ。きっとそうに違いない。
舞台から出てきた彼女たちは、照明が暗くてはっきり見えない。やたらと低音が強く、大きいオケに対して歌声が埋もれてしまっている。彼女たちは、本当に「消えそうな」状態だった。
楽曲は、「sin morning」に始まり、「rooms__」「lost AGE_」と続いた。「4F」の再現でありながらも、そこには確かにベストアルバム「Fiction」を経た彼女たちの「今」があった。
昔の音源よりもよほど歌唱表現がずば抜けて成長した彼女たちは、全曲公演である「9F」にて、特殊な演出が無くとも自らの存在を誇示することに成功した。あの公演は、歴代の彼女たちの活動の総括であった。
……総括?
「総括」なら、「9F」で終わっていたのだ。「cotoeri」の衣装を身に纏い歌い踊る彼女たちは、そのために居るのではないと考え直した。
曲目は「end of Summer dream」「veranda」「bed」と続き、MCに入った。今日はMCをしないと思っていたのに。
しかし、その内容はまるで「4F」のMCのデジャヴのようだった。メンバーも僕たちも、まるで「此処にいる気がしない」。
そう思った瞬間、メンバーの姿がほんの一瞬歪んで見えた。たしかに寝不足だったが、よほど疲れているのだろうかと思った。
USBメモリの抜ける音が聞こえた。トラブルなのか演出なのかさっぱり見当がつかない。そのとき、またしても彼女たちの姿が歪んだ。
僕たちは今、いったい何を見ているんだろう。
「それでは次の曲聴いてください、”cloudy irony"」
笑顔の彼女が放ったその一言とは裏腹に、始まったのは「karma」だった。彼女たちは、それが「cloudy irony」であると信じて歌い踊っている。
やがて「karma」が「cloudy irony」を取り込んで「river」になり、見る見るうちに彼女たちは大きなモザイクノイズで覆われた。
遂にその歌声さえも、チープで無機質な電子音へと変わり、もう「過去となった」彼女たちはモザイクの海に消えてしまった。
数日前に録画されたであろう"過去の彼女たち"の10mほど前にあった中央ステージは、いつの間にかもくもくと白い煙に包まれていた。
煙草やシーシャが苦手な僕の、大好きな煙。
僕が世界で最も愛しく想うその煙は、サイレンの音を引き連れ、壊れそうな「Solitude HOTEL」のロゴと共に、実体の伴う彼女たちを映し出した。
最期なんだね、Maison book girl。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
