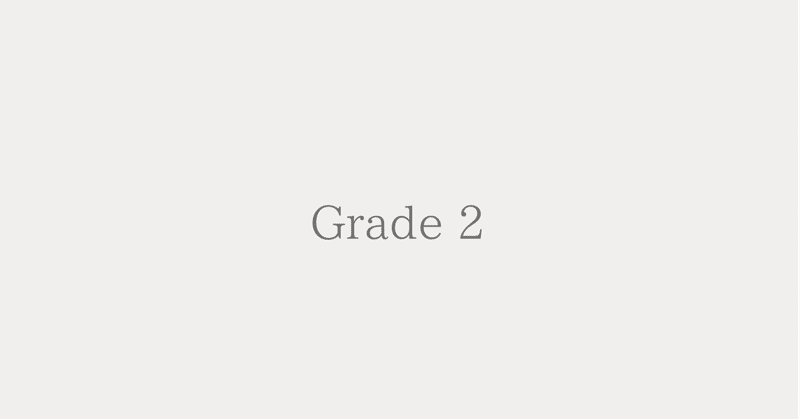
渋渋・渋幕 田村哲夫先生
来年度からのスケジュール変化に向けて、更なる日常の効率化のための部屋の改造も終わりが見えてきたと共に、
娘の教育についても頭が整理され始め、もう根本から考え抜く時間は必要なさそう。
後は頑張る娘を応援しつつ、とにかく好きなことを一つでも多く見つけて、心が動く瞬間を体験してほしいと願うのみ。それらが人生を豊かにしてくれるはずだから。
年末の旅の途中で降ってきた言葉が「福澤諭吉をアップデートする」。
(教育業界の「中の人たち」がどう感じるのかはわかりませんが)この本を読んで少なくとも私は田村先生は福澤諭吉をアップデートしている方のように感じました。
私自身が「知」の端っこに触れたような気がする、、と初めて感じた瞬間はsenior(学部4年)。そのときのことは今でも覚えていて、
私にとってはその瞬間のためにリベラルアーツは不可欠だったし、でももっと複雑で、
今なら言語化できるけれどあえてしたくないと感じる部分。
この本の「伝説の」というタイトルはあまり好みではない、、、というのは、以前も書いたけれど日本の風潮として「あの人すごい」が好きで、「あの人はすごいからできた」の空気を作りがち。
それは、「=自分にはできない」であり、誰かを神格化するばかりでチャレンジする人が出てこない構造に繋がっていると個人的には思っていて、
私が年に何度かは仕事で海外に出るようにしているのは、この空気に慣れないようにするため。(日本は個人でも組織でも、進める力よりも進めない力が強すぎる。冷静で客観的であることが「賢さ」だと考えすぎてる(悪く言えば勘違いしている)気がする。)
私立だから本自体が学校の宣伝でもあるからそういうタイトルになるのも理解できますが、中身が良かったからこそ、、!!
個人的には田村先生の志の部分が読めてよかったと感じています。
誰かの志を読むのは大好きだけど、こういうのも日本だと自分語りだとか、話はいいから行動しろ、とみんながテキトーに使っている言葉に潰されがち。
でも、こういう人や本との出会いは人生を変える機会になる、というのは、高校の、英語CDが並ぶ棚の中に何の脈絡もなく置かれていたたった1冊の留学の本が私の人生の進む方向を変えたことから。
昨年、○○○ちゃんのママこんなお仕事してるの!?と私の仕事風景を見た娘のお友達が、それに影響されたのか土日もそれに関連した習い事をしていると先日伺い、
自分が日々向き合っていることが誰かにとっての機会になりうる、自分自身が「機会」になることもできるんだよな、、と考えつつ、
とりあえず部屋の片付けを完遂したい気持ちと娘を外遊びに連れて行きたい気持ち、ちょっとだけ仕事をしたい気持ちと眠気に折り合いをつけて1日を遂行することが目下の現実です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
